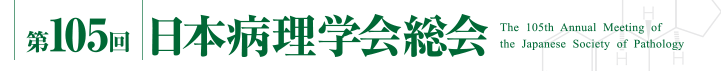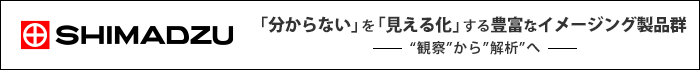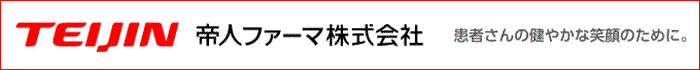骨髄病変の診断は、通常、骨髄血スメアおよび骨髄病理標本の両者によりなされる。しかし、骨髄血スメアは血液内科もしくは臨床検査科で評価され、病理医は骨髄血スメアを日常鏡検しないことが多く、骨髄病理標本の診断そのものを苦手としている病理医は多い。今回は骨髄病理に親しんで貰うことを目的として、骨髄病理診断の基本的な見方と特徴的な症例を紹介する。血液病理のExpertに、MDSの診断、症例からみた骨髄疾患の特徴、リンパ腫の診断について、日常みられる疾患をcompatible with 〇〇〇と安易に診断しないよう、診断のこつとピットフォールを解説いただく。
コンパニオンミーティング
- 全て開く
- 全て閉じる
骨髄病理標本の見方
5月12日(木) 19:30~21:00 B会場(仙台国際センター(会議棟)2階 橘)
日本血液病理研究会
オーガナイザーの言葉
オーガナイザー/座長:中村 直哉(東海大学医学部基盤診療学系病理診断学)
座長:伊藤 雅文(名古屋第一赤十字病院病理部)
CM1-1 骨髄異形成症候群の病理組織診断:実践的アプローチ
演者:茅野 秀一(埼玉医大・医・病理)
CM1-2 市中病院での骨髄病理診断の実際-異形成と骨髄増殖像を示す症例-CMML,MDS 5q-
演者:谷岡 書彦(磐田市立総合病院病理診断科)
CM1-3 骨髄におけるリンパ腫の見方
演者:大島 孝一(久留米大学医学部 病理学教室)
小児胚細胞腫瘍の臨床的および病理学的特徴
5月12日(木) 19:30~21:00 C会場(仙台国際センター(会議棟)2階 萩)
日本小児病理研究会
オーガナイザーの言葉
胚細胞腫瘍は、小児から成人まで幅広い年齢層に発生し、成人では性腺での発症がほとんどですが、小児では性腺以外に仙尾部・後腹膜・前縦隔・頭蓋内など様々な部位でみられます。また、その組織像も多彩で成熟奇形腫・未熟奇形腫・悪性胚細胞腫瘍に分類されます。さらに、悪性胚細胞腫瘍は未分化胚細胞腫/胚細胞腫/セミノーマ・胎児性癌・多胎芽腫・卵黄嚢腫瘍・絨毛癌に分類され、これらの複合組織型もみられます。今回、日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会から「小児腫瘍組織カラーアトラス第7巻 胚細胞性腫瘍およびその他の腫瘍(仮題)」が発刊されることになりました。そこで、比較的多く遭遇する腫瘍について組織診断の要点の解説と診断に密接な関係のある分子病理学的知見について、さらに、小児・若年者の卵巣胚細胞腫瘍の臨床的特徴と治療に関してご専門家の先生方にご講演いただけることになりました。多数の皆様にご参加をいただき、小児胚細胞腫瘍に関して理解を深めたいと思います。
オーガナイザー:岸本 宏志(埼玉県立小児医療センター 病理診断科)
| 座長: | 田中 祐吉(神奈川県立こども医療センター 病理診断科) 柳井 広之(岡山大学病院 病理診断科) |
CM2-1 小児胚細胞腫瘍の臨床病理学的特徴
演者:井上 健(大阪市立総合医療センター・病理診断科)
CM2-2 小児胚細胞腫瘍の発症機序
演者:岩淵 英人(国立成育医療研究センター)
CM2-3 悪性卵巣胚細胞腫瘍の臨床的取扱いについて
演者:宮城 悦子(横浜市立大学附属病院・産婦)
医療事故調査制度における病理解剖とAi
5月12日(木) 19:30~21:00 G会場(仙台国際センター(展示棟)1階 会議室1)
病理解剖と死亡時画像診断(Ai)研究会
オーガナイザーの言葉
医療法の改正に伴い2015年10月より新しい医療事故調査制度が施行された。この制度は医療の安全を確保するため再発防止が目的である。そのためには何が起こったか、死因はなにかを明らかにする必要があり、医療機関が医療事故調査を行うこととなった。この医療事故調査方法には、病理解剖と死亡時画像診断(Ai)が含まれている。このうち承諾の得やすいAiはほぼ必須になると思われるので、病理医にとって病理解剖の前にAiが撮影されていることになり、否応なく病理医もAiに関係しなければならなくなると思われる。そこで、今回のコンパニオンミーティングでは、「医療事故調査制度における病理解剖とAi」のテーマで、この医療事故調査制度のモデル事業の段階から関与されてきた野口先生、医療事故などのAi画像の読影をされている山本先生、法医学の立場から竹下先生そしてAiと病理解剖を経験してきた小上先生らにご発表いただき、利点や問題点などを共有できたらと思い企画した。
オーガナイザー:法木 左近(福井大学医学部 腫瘍病理学)
オーガナイザー/座長:丸山 理留敬(島根大学・医学部・病理学)
座長:桂 義久(社会保険横浜中央病院)
CM3-1 医療事故調査制度、茨城県における取り組み
演者:野口 雅之(筑波大学医学医療系診断病理学)
CM3-2 医療事故調査制度におけるAiの役割
演者:山本 正二(Ai情報センター)
| CM3-3 | 島根大学法医解剖における医療行為関連事案紹介および今後の医療事故調査制度へのAiや病理解剖施行について |
演者:木村 かおり(島根大・医・法医)
CM3-4 病理解剖とAiを施行した予期せぬ2死亡例
演者:小上 瑛也(福井大・医・病理診断科)
~日常診療で気をつけたい、newly emerging syndromesの診断:
腎腫瘍を中心として~
5月12日(木) 19:30~21:00 H会場(仙台国際センター(展示棟)1階 会議室2)
Birt-Hogg-Dubé 症候群診療情報ネット (BHDネット)
オーガナイザーの言葉
日常の病理診断で「No malignancy」「Benign neoplasm」で片づけてしまう良性病変のなかにも、主治医が気づかない系統的疾患の可能性を、病理医のほうが最初に気づくことがあるかもしれません。今回のコンパニオンミーティングでは、比較的近年に概念が確立された系統的疾患の中から遺伝性腎腫瘍の可能性を示唆するいくつかの症例を呈示し、2016年に発行される腎腫瘍の新WHO分類にあわせて、病理診断時の実際や問題点などを紹介します。各診療科と横断的に対話できる病理医ならではの利点を生かして、BHD症候群やフォン・ヒッペル・リンドウ病などの系統的疾患の診断に役立つ知見や、家族性腫瘍の診断時に気をつけてほしいこと、病理医参加型の包括診療への取り組みなどを議論したいと思います。Key lectureを高知赤十字病院の黒田直人が行い、4名の病理医が経験症例を提示する予定です。
オーガナイザー/座長:中谷 行雄(千葉大学大学院医学研究院診断病理学)
座長:長嶋 洋治(東京女子医科大学病院・病理診断科)
CM4-1 腎腫瘍の新WHO分類と遺伝性疾患・系統的疾患
演者:黒田 直人(高知赤十字病院・病理診断科部)
CM4-2 von Hippel-Lindau (VHL) 病に発生した病変の自験例(腎癌を中心に)
演者:澤住 知枝(横浜市大・病院・病理部)
| CM4-3 | Brit-Hogg-Dubé症候群(BHDS)の2症例(症候群を構成する皮膚病変・肺嚢胞・腎腫瘍の適切な診断に向けて) |
演者:白瀬 智之(大津赤十字・病理)
CM4-4 SDH変異が示唆された両側腎癌・褐色細胞腫の合併例
演者:長瀬 真実子(島根大・医・器官病理)
CM4-5 血管筋脂肪腫;結節性硬化症との関連を中心に
演者:畑中 佳奈子(北海道大病院 病理診断科)
脳腫瘍病理診断の基礎 ―新WHO2016分類への対応―
5月12日(木) 19:30~21:00 D会場(仙台国際センター(会議棟)2階 桜1)
日本脳腫瘍病理学会
オーガナイザーの言葉
脳腫瘍の病理診断が大きく変わる。近年、1p/19q共欠失やIDH mutationを始めとする重要な分子マーカーの発見により、脳腫瘍発生機序や悪性度進展の新知見が明らかになった。今まで組織形態に頼っていた病理分類や悪性度評価或は各腫瘍の発生母地までもが再考を余儀なくされてきている。また、MGMT promoter methylationに代表される、各種分子マーカーの治療予後予測因子としての有用性により、今まで一辺倒であった脳腫瘍治療が、個別化・層別化へと一気に移行する可能性が示唆されている。このセッションを通して、新たな脳腫瘍WHO分類第改訂4版(2016)で必須とされる分子病理診断の方向性が見えてくる。
| オーガナイザー/座長: | 若林 俊彦(名古屋大学脳神経外科) 澁谷 誠(東京医大八王子医療センター中央検査部) |
CM5-1 脳神経外科医が脳腫瘍の病理診断に期待すること
演者:園田 順彦(山形大学・医・脳外)
CM5-2 新WHO分類に関連する脳腫瘍の分子診断の基礎
演者:田中 伸哉(北大・医・腫瘍病理)
CM5-3 脳腫瘍WHO分類の変更点-1:成人のびまん性神経膠腫
演者:廣瀬 隆則(兵庫県立がんセンター・病理)
CM5-4 脳腫瘍WHO分類の変更点-2:小児悪性神経上皮性腫瘍、特に上衣腫と胎児性腫瘍について
演者:小森 隆司(都立神経・検査科病理)
膵胆道系の生検診断と細胞診 ―診断へのアプローチと鑑別方法ー
5月12日(木) 19:30~21:00 E会場(仙台国際センター(会議棟)2階 桜2)
日本膵臓病理研究会
オーガナイザーの言葉
膵胆道系の生検・細胞診は、全体像を把握することが難しく、微小検体であることや変性などにより診断に難渋することが多々ある。また、生検・細胞診の診断は手術・化学療法等の治療方針を決定する重要な因子であり、侵襲性の高い治療法を左右する生検・細胞診は病理医にとってプレッシャーとなることがある。本ミーティングでは、膵管・胆管生検/膵液・胆汁細胞診、膵胆道EUS-FNA生検・細胞診を対象として、診断のアプローチ方法と免疫組織・細胞化学を含む鑑別方法について解説する。また、症例検討を通して意見交換を行う。
| オーガナイザー/座長: | 相島 慎一(佐賀大学医学部病因病態科学診断病理学分野) 平林 健一(東海大学医学部基盤診療学系病理診断学) |
CM6-1 膵液・胆汁細胞診/膵管・胆管生検
演者:内藤 嘉紀(久留米大学・医・病理)
CM6-2 膵胆道EUS-FNAの細胞・組織診断
演者:能登原 憲司(倉敷中央病院・病理)
CM6-3 膵胆道系の生検と細胞診:症例検討
演者:平林 健一(東海大学・医・病理)
卵巣癌 ~形態と発癌メカニズム~
5月13日(金) 17:40~19:10 B会場(仙台国際センター(会議棟)2階 橘)
日本婦人科病理学会
オーガナイザーの言葉
2014年にWHOの卵巣腫瘍分類が刊行され、卵巣癌は高異型度漿液性癌、低異型度漿液性癌、類内膜癌、粘液性癌、明細胞癌、漿液粘液性癌に亜型分類された。各亜型はその遺伝子異常によっても特徴づけられ、この分類の妥当性を示している。近年の網羅的遺伝子解析結果から、さらに詳細な卵巣癌の分子学的特徴が明らかにされつつある。高異型度漿液性癌のTP53変異、低異型度漿液性癌のKRAS/BRAF変異、類内膜癌、明細胞癌のARID1a、PIK3CA変異、粘液性癌のKRAS変異、HER2増幅が知られている。一方で、発生母地、前駆病変として高異型度漿液性癌の漿液性卵管上皮内癌(STIC)、低異型度漿液性癌、粘液性癌の境界悪性腫瘍、類内膜癌、明細胞癌、漿液粘液性癌の子宮内膜症が広く知られている。また明細胞癌では間質の硝子化が形態的特徴の一つであり、その形成機序と意義についての研究も進んでいる。今回は卵巣癌の形態と発癌メカニズムを整理して理解できる機会となることを意図した。
オーガナイザー:三上 芳喜(熊本大学医学部附属病院 病理診断科(病理部))
| 座長: | 寺戸 雄一(杏林大学 病理学教室) 大石 善丈(九州大学 形態機能病理) |
CM7-1 ポストゲノム時代の卵巣癌の病理
演者:前田 大地(秋田大学大学院医学系研究科器官病態学講座)
CM7-2 卵巣明細胞癌 ー病理形態と関連分子ー
演者:加藤 哲子(弘前大・医・病理診断学)
CM7-3 子宮内膜症を背景とする粘液漿液性腫瘍と類内膜腫瘍
演者:和仁 洋治(姫路赤十字病院病理診断科)
1)食道癌取扱い規約の変更点の解説と上皮内癌の診断
2)知っていると見えてくる、案外遭遇頻度の高い消化管病変集
5月13日(金) 17:40~19:10 C会場(仙台国際センター(会議棟)2階 萩)
消化管病理医の会
オーガナイザーの言葉
今回の消化管コンパニオンミーティングは2本立てである。前半は昨年10月の規約改定を受けた食道癌の話題である。今回の改定で病理に関わる点は何が変わったのか、改定のポイントを規約作成に携わった新井先生に整理していただく。特に上皮内腫瘍の呼称が変更になったことは多くの病理医の関心事と思われる。河内先生には、どのように癌、squamous intraepithelial neoplasia、atypical epitheliumを使い分けるのかを、経過観察症例の供覧を中心に実践的な解説をお願いした。後半は「知っていると見えてくる、案外遭遇頻度の高い消化管病変集」と題して三つの病態を紹介する。「知っていると見えてくる」が裏を返せば「知らないと見えてこない」であることはH.pyloriで思い知らされた。明日からの診断業務に必ず役立つ知識をお持ち帰りいただけるものと思う。
オーガナイザー:八尾 隆史(順天堂大学大学院医学研究科・人体病理病態学)
| 座長: | 菅井 有(岩手医科大学病理診断学講座) 根本 哲生(東邦大学医療センター大森病院病理診断科) |
CM8-1 「食道癌取扱い規約第11版」の病理診断に関わる改訂点
演者:新井 冨生(東京都健康長寿医療センター・病理診断科)
CM8-2 食道扁平上皮内腫瘍・扁平上皮癌の病理組織像
演者:河内 洋(がん研有明病院・病理)
CM8-3 腸管スピロヘータ症の臨床病理学的特徴について
演者:立石 陽子(横浜市大・医・病理)
CM8-4 胃粘膜におけるランタン沈着
演者:伴 慎一(獨協医大越谷病院・病理診断科)
CM8-5 プロトンポンプ阻害薬(PPI)による胃粘膜変化: PPIポリープ、胃底腺ポリープ様病変と除菌後胃粘膜
演者:九嶋 亮治(滋賀医大・医・臨床検査)
乳腺腫瘍分類の新しい展開
5月13日(金) 17:40~19:10 D会場(仙台国際センター(会議棟)2階 桜1)
乳癌基礎研究会
オーガナイザーの言葉
本セッションでは、日常遭遇する整理しておくべきいくつかの特殊型乳腺腫瘍、腫瘍様病変の新しい分類をとりあげ解説する。腺様嚢胞癌、神経内分泌癌、lobular neoplasiaである。宮居先生には腺様嚢胞癌について、その基本的な病理組織学からtriple negative乳癌としての性格や近年のt(6; 9) (q22-23; p23-24) 転座などについて解説していただく予定である。川崎先生には神経内分泌癌に関して新しいWHO分類に沿って体系だって解説していただき、その組織発生に関しても触れていただく予定である。山口先生にはわが国規約では触れていないlobular neoplasiaに関して、関連病変や遺伝子異常、前癌的性格に関して講演していただき、鑑別診断やその臨床病理学的意味、マネジメントにも触れていただく予定である。いずれも、最新の知見を取り入れながら、実地の診療にも役立つ内容となっている。
オーガナイザー/座長:小山 徹也(群馬大学大学院病理診断学・病理診断科)
座長:市原 周(独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 病理診断科)
CM9-1 腺様嚢胞癌
演者:宮居 弘輔(防衛医大・医・病態病理)
CM9-2 神経内分泌形質を有する乳癌
演者:川崎 朋範(岩手医大・医・病理)
CM9-3 小葉新生物
演者:山口 倫(久留米大学医学部附属医療センター 病理診断科)
病理医と泌尿器科医の対話 -依頼書及び報告書の向こう側に何があるのか―
5月13日(金) 17:40~19:10 E会場(仙台国際センター(会議棟)2階 桜2)
日本泌尿器病理研究会
オーガナイザーの言葉
病理診断に際し、診断依頼書の記載内容及びその解釈が重要です。しかし、泌尿器科医から病理医に正確に真意が伝わる記載方法はほとんど討議されたことがないと思います。また、依頼内容の趣旨を病理医が十分に理解できてないこともあると思います。逆に泌尿器科医側からも、病理診断書に関しても同様のことが言えると思います。患者にとって必要な事項が十分盛り込まれていない、あるいは意図するものが通じない報告書が作成されていることが憂慮されます。
本コンパニオンミーティングでは泌尿器科学会の腫瘍部門で指導的立場にある泌尿器科医2名をお招きし、実際の病理依頼書に書かれた意図を解説して頂きます。これに対し若手病理医3名が病理診断書を作成し、参加者にお示ししたいと思います。泌尿器側に報告書の内容評価をして頂き、改善点があればコメントをして頂きます。双方向の意見交換からより良い病理診断報告書の見本をお見せしたいと考えています。会場からの参考意見も大歓迎です。
オーガナイザー/座長:都築 豊徳(名古屋第二赤十字病院 病理診断科)
座長:長嶋 洋治(東京女子医科大学病院 病理診断科)
CM10-1
演者:荒井 陽一(東北大学医学部 泌尿器科)
CM10-2
演者:賀本 敏行(宮崎大学医学部 泌尿器科)
CM10-3
演者:渡邊 麗子(国立がん研究センター 中央病院 病理部)
CM10-4
演者:小島 史好(和歌山県立医科大学 人体病理学)
CM10-5
演者:内田 克典(三重大学医学部 腫瘍病理学)
唾液腺導管上皮系悪性腫瘍の病理診断の問題点と展望
5月13日(金) 17:40~19:10 F-1会場(仙台国際センター(会議棟)3階 白橿1)
唾液腺腫瘍病理研究会
オーガナイザーの言葉
現行の唾液腺腫瘍WHO分類(2005)が登場してから10年以上が経過し,この間,いくつかの組織型に関して,疾患概念や診断基準についての再考の必要性も指摘されるようになってきた.そこで,今回は筋上皮細胞の関与しない導管上皮系の悪性腫瘍に焦点を絞って問題点を討論することにした.すなわち,1)唾液腺導管癌,特にバリエーションの範囲と他の腫瘍型との鑑別,2)腺癌NOS,特に診断名の使用範囲や腫瘍型としての独立性,3)脱分化型癌,特に診断基準や混成癌との区別,4)非浸潤癌,その実例や種類,分類上の将来展望,という4つのテーマを選んだ.いずれも施設や病理医間の診断基準の統一,診断の再現性の向上が必要な重要事項と考えられる.4演者によるプレゼンテーションと活発な討論により,理解をより深めたい.
オーガナイザー/座長:森永 正二郎(北里研究所病院病理診断科)
座長:小川 郁子 (広島大学病院口腔検査センター)
CM11-1 唾液腺導管癌の病理組織学的鑑別診断
演者:矢田 直美(九州歯科大学健康増進学講座口腔病態病理学分野)
CM11-2 腺癌NOS ~その診断名と臨床病理学的意義~
演者:島尾 義也(県立宮崎病院・病理診断科)
CM11-3 唾液腺“脱分化癌”の概念と組織像 ~自験例に文献的考察を加えて~
演者:吉田 真希(東京医大・人体病理)
CM11-4 唾液腺の非浸潤癌
演者:山元 英崇(九州大・病院・病理診断科)
造血器異常と腎疾患:病理と臨床の接点を確認しよう
5月13日(金) 17:40~19:10 G会場(仙台国際センター(展示棟)1階 会議室1)
日本腎病理協会
オーガナイザーの言葉
近年、単クローン性γグロブリン血症(monoclonal gammopathy: MG)にともなう腎障害が注目されている。その疾患の広がりは、糸球体沈着症に基づくネフローゼ症候群のみならず、円柱腎症による腎機能不全、そして、近位尿細管への軽鎖沈着に基づくFanconi症候群に及ぶ。病理診断には、MGを証明する免疫診断と電顕診断が必須である。そして、病理診断を受けた臨床医は、MGの背景となる骨髄での形質細胞異常症に対する治療法に関して血液臨床医の意識を変えつつある。すなわち、MG with unde termined significance (MGUS) として積極治療を見送っていた従来の考え方から、MG with renal significance (MGRS)として積極的治療する時代となった。今回は、腎臓病理、造血器病理、腎臓臨床医、血液臨床医が一同に介して、その接点を確認することを目的としている。
オーガナイザー/座長:城 謙輔(東北大学大学院・医科学専攻・病理病態学講座)
座長:山口 裕(山口病理組織研究所)
CM12-1 造血器疾患関連腎疾患の臨床
演者:相馬 淳(岩手県立中央病院腎臓内科)
CM12-2 Renal diseases with monoclonal immunoglobulin depositionに含まれる疾患群
演者:清水 章(日本医科大学 解析人体病理学)
CM12-3 腎疾患に関連する造血器異常:骨髄腫の病理
演者:定平 吉都(川崎医科大学 病理学1)
CM12-4 悪性リンパ腫と腎疾患(悪性リンパ腫関連腎障害)
演者:前田 邦彦(山形県立保健医療大学)
CM12-5 骨髄腫とMGUS -量から質へ-
演者:石澤 賢一(山形大学・医・血液・細胞治療内科学)
肺病理学の最近のトピック
5月13日(金) 17:40~19:10 H会場(仙台国際センター(展示棟)1階 会議室2)
日本肺病理学会ミーティング
オーガナイザーの言葉
胸部腫瘍の分野では、肺および胸腺腫瘍のWHO分類が改訂された。肺腫瘍の改訂点については、昨年の病理学会のコンパニオンミーティングや他の学会でも何度か取り上げられている。本ミーティングでは、胸腺腫瘍の改訂点について、実例に則して解説が行われる。また、肺癌学会を中心にして、WHO分類の改定に関連した病理「目合わせ会」が開かれる予定であり、その報告がある。一方、非腫瘍性肺病理の分野では、強皮症との関連で注目される、抗ARS抗体症候群に関連した間質性肺炎に焦点を絞って、入門者にも判るような解説をして頂く予定である。
オーガナイザー:石川 雄一(がん研究会がん研究所病理部)
| 座長: | 福岡 順也(長崎大学) 南 優子(国立病院機構茨城東病院 胸部疾患・療育医療センター) |
CM13-1 胸腺腫の病理‐WHO分類改訂をめぐって
演者:立山 尚(春日井市民病院・病理)
CM13-2 抗ARS抗体症候群における間質性肺炎および関連肺疾患の病理
演者:田中 伴典(近畿大学医学部病理学講座)
CM13-3 肺癌診断の病理医目合わせ会の報告
演者:大林 千穂(奈良県立医科大学病理診断学講座)
混合型肝癌の病理診断に関するコンセンサスを目指して
5月13日(金) 17:40~19:10 I会場(仙台国際センター(展示棟)1階 会議室3)
肝腫瘍病理懇談会
オーガナイザーの言葉
近年、各病理医間で混合型肝癌に関する診断基準にばらつきがみられ、臨床医も含めその対応に混乱が生じている。このような状況の中、まず各病理医間での混合型肝癌に対する診断基準のコンセンサスが要望されている。本ミーティングでは肝腫瘍を専門とする施設病理医の混合型肝癌に対する考え方の意見交換により問題点の抽出と診断基準に関するコンセンサスを得るための第1回目の会合をコンパニオンンミーティングとして企画した(肝腫瘍病理懇談会)。次の5項目の観点などを含めて検討したい。① 混合型肝癌の定義、分類や名称について(原発性肝癌取扱い規約やWHO分類との異同)② 中間型(亜分類)や多分化能(肝幹細胞や癌幹細胞の概念)を示す病理形態について③ 末梢型肝内胆管癌、細胆管癌、混合型肝癌の関連性について④ 肝細胞癌の発育や脱分化に伴う形質転換や多様性について⑤ 免疫組織学的検討や新たなマーカーによる分類、識別などについて
オーガナイザー/座長:中島 収(久留米大学病院 臨床検査部)
座長:坂元 亨宇(慶應義塾大学医学部 病理学教室)
CM14-1 混合型肝癌を含む原発性肝癌の妥当な組織分類を構築するにあたっての基礎知見
演者:柴原 純二(東京大学・医・人体病理)
CM14-2 混合型肝癌の病理診断の諸問題に関する見解
演者:近藤 福雄(帝京大学・医・病理診断科/帝京大学・医・病理学講座)
CM14-3 私の混合型肝癌の診断方法と鑑別点
演者:相島 慎一(佐賀大・医・病因病態科学)
CM14-4 混合型肝癌中間型の組織形態および免疫形質に関する検討
演者:秋葉 純(久留米大学病院病理診断科・病理部)
CM14-5 混合型肝癌・細胆管癌の病理診断:コンセンサスを目指して
演者:佐々木 素子(金沢大学・医・形態機能病理学)