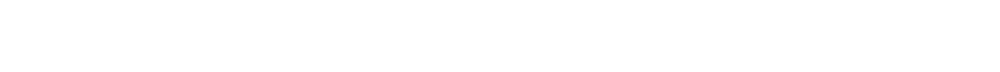主催事務局
近畿大学医学部整形外科学教室
運営事務局
株式会社コングレ内
〒530-0005
大阪市北区中之島4-3-51
Nakanoshima Qross
未来医療R&Dセンター
E-mail:jsha2026@m.congre.co.jp
会長挨拶

第21回日本股関節鏡研究会
会長 後藤 公志
(近畿大学医学部整形外科学教室 主任教授)
この度、第 21 回日本股関節鏡研究会を、2026年 9 月 5 日(土)、大阪市中央公会堂において開催する運びとなりました。日本股関節鏡研究会は、2009 年に股関節鏡フォーラムとして発足後、他の研究会と合同となって、 2015 年に日本股関節鏡研究会へ名称変更され、大阪での開催は今回で2度目となります。会場となる大阪市中央公会堂は大正時代のネオ・ルネッサンス様式を基調とした国の重要文化財で、その歴史的な建造物が醸し出す壮大な雰囲気の中で活発な議論がなされることを期待しております。
今回のテーマは「明鏡止水~股関節鏡のすすめ~」とさせて頂きました。股関節鏡手術は、膝や肩関節の関節鏡手術と異なり、関節内に視野を確保するだけでも困難な症例に遭遇することがあります。牽引台を含めて準備に労力がかかる上にうまく手術を進めることが出来ない経験をすると、敢えて再挑戦しようと思わないのが股関節鏡手術ではないかと思います。しかし、落ち着いた明鏡止水の気構えで基本に忠実に手術に臨めば、視野の確保が不可能な症例はありません。視野が確保出来れば、スコープを通じて画像検査では把握しづらい関節内病変を発見でき、病態の理解が格段に高まります。
著書「学問のすゝめ」の中で、福沢諭吉は明治維新後の変化のダイナミズムの中で学問の大切さを説いています。股関節外科の世界では、近年の人工股関節置換術の進歩によってその患者満足度が非常に高まり、術後のリハビリ期間も短縮している一方で、相対的にリハビリに要する期間や治療効果にばらつきのある股関節鏡手術に対しては、積極的に取り組みにくい現状があります。しかし、保存治療か人工股関節の二択では股関節外科の発展は望めません。もう一度原点に立ち返り、骨温存手術としての股関節鏡手術の魅力、そしてその医学と医療への貢献という視点から股関節鏡手術を議論し、股関節鏡に馴染みのない若手整形外科医が股関節鏡手術にチャレンジしたいと感じて頂ける研究会にしたいと考えております。そして、看護師、理学療法士を含む、治療に関わる全てのメディカルスタッフにも積極的に参加して頂いて、医療スタッフ全体で股関節鏡手術に対する理解を深める会にしたいと考えております。
活気に満ち溢れた『食い倒れの街』、『天下の台所』である大阪のど真ん中の中之島で、皆々様方のご参加を心よりお待ちいたしております。