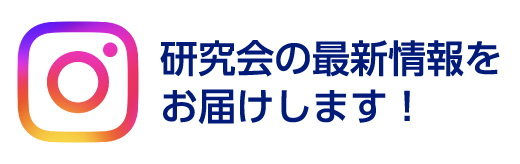ご挨拶
名古屋医療センター 院長

臨床研修について少なくとも過去数年は貢献しているとは思えない私が、第42回臨床研修研究会を2026年4月18日に名古屋市でお世話させていただくことになり、大変恐縮しております。名古屋医療センターで臨床研修に関わる飯田浩充統括部長、同門である名古屋大学卒後臨床研修・キャリア形成支援センターの高見秀樹講師の絶大な支援を受けながら準備を進めてまいりました。
私の母校である名古屋大学の附属病院は自大学出身の初期研修医数がわが国で最も少ないことで知られており、古くから私自身を含む多くの卒業生がいわゆる関連病院で初期研修を受けております。とは言え大学病院に一旦は戻るのが通例ですが、戻るまでの年数は診療科によって異なります。私は卒後7年目に戻っており、それまでの研修内容は今日の研修プログラムと比較すれば定型的とは言えません。そうした研修を受けたことについては良い点も悪い点もあったのだろうと思いますが、どうやら臨床医としては何とか「育った」ものと推察されますし、それ以上に「地域を支える」病院で初期研修医、後期研修医としてそれなりの労働量をこなした自負はあります。その意味で私が受けさせていただいた研修は、今にして思えば今回のテーマである「人を育て、地域を支える臨床研修」の範疇であったのかもしれません。
現在の卒後研修制度になってから初期研修医が大学を離れたことにより様々な弊害が出ているとの見方もあります。一方、それまでは卒業した学生の多くがそのまま大学に残って研修していたとすれば、果たしてそれが臨床医としての鍛錬に適していたのかという疑問もあります。また、研修医は教育を受けるだけの立場ではなく、病院にとって様々な局面で極めて貴重な戦力でもあります。卒後研修に熱意を持つ数多くの病院で研修医が臨床能力を磨くとともにその地の医療を支えてくれればという思いでシンポジウムI「地域医療を守る臨床研修」を中心に据えました。もちろん、その後には大学にも籍を置き、ある人はそこでの医療や教育を担い、またある人はわが国の医学研究に大きな貢献をするというのが理想です。一方で医療の質・患者安全が根付き、働き方改革が始まるなど近年は医師を取り巻く環境が大きく変化しています。AIやICT技術などの技術の発達も目覚ましく、そうした新しいテクノロジーを使うことでこの変動の時代を乗り越えることも必要と考え、シンポジウムII「テクノロジーを活かし現場をつなぐ臨床研修」で進化した卒後研修を提案いたします。
名古屋はお越しになる場合の利便性だけが取り柄のあまり人気がない町かもしれません。ゆえに、会場には名古屋市随一の繁華街である栄の新たなランドマークとされる中日ビルを選びました。本研究会の前後には眼下に広がる歓楽街を満喫いただければと思います。そして万が一体調不良となられた場合のことですが、実はこの界隈はガッチリと名古屋医療センターの診療圏となっております。安心して受診され、私どもの自慢の研修医達の活躍ぶりも御視察いただければと思っております。