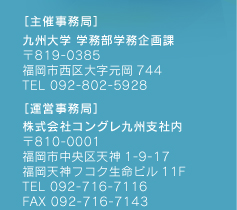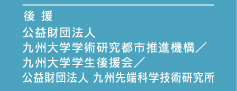| ▼成果報告 ▼パネルディスカッション |
 |
|
 |
 |
 |
大学院は何のためにあるのか
〜大学院教育の将来展望〜 |
 |
 |
 |
| 日本学術振興会理事長 |
 |
| 安西 祐一郎 氏 |
|
|
 |
| 講演者略歴 |
 |
1974年慶應義塾大学大学院博士課程修了。
カーネギーメロン大学客員助教授、北海道大学文学部助教授、慶應義塾大学理工学部教授、93年〜2001年同理工学部長、01〜09年慶應義塾長。
現在、独立行政法人日本学術振興会理事長、人工知能技術戦略会議議長、日本ユネスコ国内委員会会長等。
中央教育審議会会長、環太平洋大学協会会長、情報処理学会会長、日本認知科学会会長、日本学術会議会員等を歴任。
専攻は情報科学、認知科学。 |
|
|
 |
| 講演では以下の点についてお話しします。 |
 |
| 1) |
日本の大学院教育はなぜ世界の潮流に立ち遅れてしまうのか。 |
 |
| 2) |
大学院教育と学部教育の関係をしっかり構築できないのはなぜか。 |
 |
| 3) |
日本の社会は大学院修了者に何を求めているのか。 |
 |
| 4) |
博士課程で学ぶことに何の意味があるのか。 |
 |
| 5) |
博士課程教育リーディングプログラム事業にどんな意味があるのか。 |
 |
| 6) |
日本の大学院教育は今後どうすればよいか。 |
|
 |
| ただし、以上は総論であって特定の大学についての議論ではありません。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
九州大学における大学院教育の最前線
〜博士課程教育リーディングプログラム等の教育を通じて〜 |
|
 |
|
 |
| 超学際科学 (transdisciplinary science) としての決断科学 |
 |
九州大学大学院
理学研究院教授・持続可能な社会のための決断科学センター長 |
 |
| 矢原 徹一 氏 |
|
|
|
 |
|
 |
| 産官学連携による次世代を担う人財養成 |
 |
分子システムデバイス国際研究リーダー養成および
国際教育研究拠点形成 副プログラムコーディネーター |
 |
| 久枝 良雄 氏 |
| |
|
|
|
 |
|
 |
| グリーンアジア国際戦略プログラムによる人材育成 |
 |
九州大学大学院総合理工学研究院,
グリーンアジア国際リーダー教育センター
教授;副研究院長,センター長 |
 |
| 谷本 潤 氏 |
|
|
|
 |
|
 |
| 九州大学エネルギー研究教育機構の取組と大学院教育への貢献 |
 |
| 九州大学副学長 (産学連携担当) |
 |
| 佐々木 一成 氏 |
|
|
|
 |
 |
 |
九州大学における大学院教育の成果
〜博士課程教育リーディングプログラム修了生からの報告〜 |
|
 |
|
 |
| リーディング大学院での活動紹介 |
 |
工学府建設システム工学専攻
博士後期課程3年 日本学術振興会特別研究員 |
 |
| 本田 博之 氏 |
|
|
|
 |
|
 |
| コースで高めた人間力 |
 |
| 九州大学 工学府 材料物性工学専攻 片山研究室 博士課程3年 |
 |
| 登 貴信 氏 |
|
|
|
 |
|
 |
| リーディングプログラム1期生として |
 |
オーエスジー株式会社
R&D室 開発グループ新素材開発チーム |
 |
| 儀間 弘樹 氏 |
|
|
|
 |
| page top |
 |
|
 |
 |
 |
 |
〜社会が求める課題解決型人材とは〜 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
九州大学副学長
(産学連携担当) |
 |
| 佐々木 一成 氏 |
|
|
 |
 |
文部科学省
高等教育局大学振興課
大学改革推進室 室長 |
 |
| 井上 睦子 氏 |
|
|
 |
 |
株式会社三菱総合研究所
オープンイノベーション
センター長 |
 |
| 小野 由理 氏 |
|
 |
 |
 |
千代田化工建設株式会社
技術本部 技術本部長 |
 |
| 石川 正男 氏 |
|
|
 |
 |
九州大学大学院総合理工学研究院,グリーンアジア国際リーダー教育センター
教授;副研究院長,センター長 |
 |
| 谷本 潤 氏 |
|
|
 |
 |
工学府建設システム工学専攻
博士後期課程3年
日本学術振興会特別研究員 |
 |
| 本田 博之 氏 |
|
 |
 |
 |
九州大学
工学府 材料物性工学専攻
片山研究室
博士課程3年 |
 |
| 登 貴信 氏 |
|
 |
 |
 |
オーエスジー株式会社
R&D室
開発グループ新素材開発チーム |
 |
| 儀間 弘樹 氏 |
|
 |
|
|
|
 |
| page top |
 |