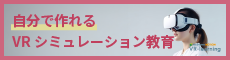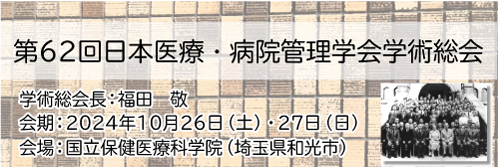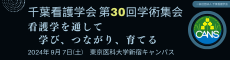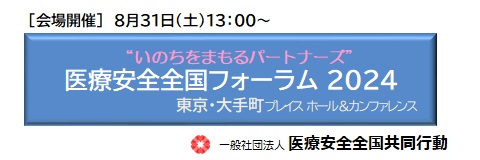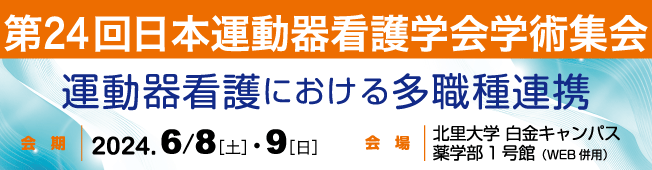ご挨拶
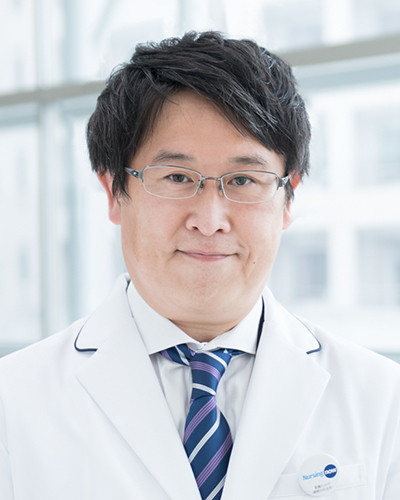
- 第28回日本看護管理学会学術集会
- 学術集会長 秋山 智弥
名古屋大学医学部附属病院 - 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター
看護キャリア支援室 室長・教授
第28回日本看護管理学会学術集会ホームページへようこそお越しくださいました。
第28回学術集会は、2024年8月23日(金)~24日(土)、名古屋国際会議場で開催いたします。名古屋では初の開催となります。テーマは『看護のルネサンス』です。コロナ後の世界を、ペスト流行後に中世ヨーロッパで花開いたルネサンス運動になぞらえ、本学術集会のテーマとしました。
ペストは、14世紀には『黒死病』として恐れられ、ヨーロッパでは 人口の3分の2以上に相当する5,000 万人以上もの命が奪われたと推計されています1)。神に祈りを捧げ、天国への道を信じて禁欲的に生きていた中世ヨーロッパの人々にとって、ペストによる無惨で孤独な死の数々は、死生観をも揺るがすほどの大惨事だったと考えられます。危機に直面したことで、人々は内省し、かつての古代ギリシャ時代のように、現世的な幸福や本質的な思考を重視するに至ったのではないでしょうか。
そして現在、私たちはコロナ禍を経験しました。私は、コロナ禍を通して3つの価値を学んだように思います。一つ目は『健康』の価値です。医学が進歩し、ともすれば手放しで得られるかのような錯覚さえ覚えていた『健康』というものが、やはり自らの手でも守るべきものである、ということに気づかされました。二つ目は『家族』の価値です。移動や面会が制限される中、『家族』でなければ埋められない社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)があることにも気づかされました。そして、三つ目は『看護』の価値です。治療法や予防法が確立されるまでの間、頼りになるのは患者自身の免疫力であり、その内なる治癒力を最大限引き出すことができたのは他ならぬ『看護』そのものだったと思います。
COVID-19の患者や陽性者が次々と隔離されていく中、看護師は最後の砦として、孤立を余儀なくされた方々へ、シールド越しにほほ笑みかけ、マスク越しに声をかけ、触れることができずとも人々の心へ直に浸透しようと努力を重ねました。2021年4月、ブラジルのある看護師が面会のできない重症患者のために、ぬるま湯を入れた医療用手袋を結び合わせて患者の手を包み込み、あたかも家族に手を握られているかのようなケアを実践している、というニュースがSNSで話題になりました。WHOのテドロス事務局長もそのニュースに感銘を受け、「神の手」と題してリツイートされたことでも有名になりました2)。
医療安全元年とも呼ばれる2000年以降のこの20年、医療の安全性を向上させるためのシステムアプローチや医療の質を担保するための治療・ケアの標準化が強力に推し進められてきました。システム化と標準化の進展は、医療の質と安全を向上させるための不可欠な取り組みであったことは言うまでもありません。しかし、その一方で、行き過ぎた標準化の波は、前述したブラジルのナースのような、看護師ひとり一人の考える力や創意工夫する力を奪ってきたようにも感じています。医療の質と安全性を向上させつつも、ひとり一人異なる患者への対応に、ひとり一人異なる看護師の人間的なアプローチがあって然るべきです。「どこを標準化し、どこに自由度や裁量を与えるのか」-人工知能が実社会に浸透し始めた今だからこそ、あらためて「人間らしさ」を追求し、看護の専門性とそのあるべき姿について議論すべき時期に来ているのではないでしょうか。
コロナ禍では様々なシステムが機能不全に陥りました。平時を想定して創られたシステムが有事には役に立たない、ということも数多く経験してきました。システムが機能しなくなった時、私たちは看護師としてどうあるべきか、ひとり一人が自分の頭で考え、行動しなければなりません。
- 限られた資源の中で行える最善のケアは何か?
- 医療の安全と倫理の狭間で患者の尊厳をいかに護るのか?
- めざましく進化するAIやICTをどのように活用していくのか?
看護管理者として、またひとりの看護師として、看護の原点と看護をとりまく現状とをしっかりと見極めながら、より自由に、より人間らしく発想し、看護という目に見えない営みを皆さんとともに描き出したいと思います。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
1) WHO:Fact Sheets
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/plague
2) 朝日新聞デジタル:コロナ患者の手握る「神の手」 ブラジル発のケアに注目
https://www.asahi.com/articles/ASP4K3RC9P4KUHBI00M.html