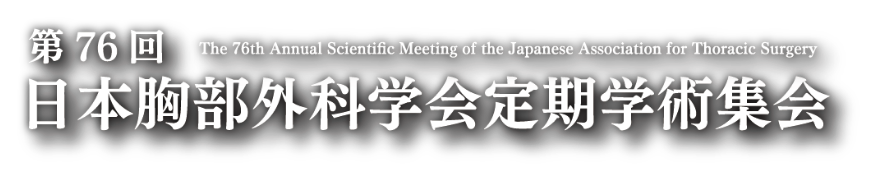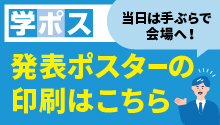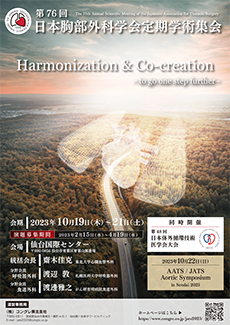プログラム
領域横断
1)Pros & Cons; 4 Rounds「フレイルティと向き合う」(指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:耐術能に直結するフレイルティの本質は何か?
CQ2:フレイルティを修飾し周術期成績を改善し得るのか?
●概要
多様な外科手術治療成績に関わる術前リスク因子については長年にわたり解析が進み、いわゆるリスク・カリキュレーターが使用されている領域もある。その一方で、日常診療において外科医の経験に基づくeyeballによる患者状態の評価も重要であることが認識されている。その具体的な”指標”としてフレイルティのインパクトが増している。そしてフレイルティの評価指標も多岐に及んでいる。しかしながら、フレイルティを術前リスク因子として定量化した上での科学的検討は未だ深められていない。この企画では各領域からフレイルティの本質を捉える視点での臨床研究解析結果を供覧していただき、3領域を横断する視座でフレイルティの本質を解き明かして頂きたい。
2)パネルディスカッション
「反回神経麻痺ゼロを目指したベストアプローチ」(指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:反回神経障害併発の現実的シナリオとは?
CQ2:反回神経障害を100%回避できる術はあるか?
●概要
胸部外科手術の中で3領域のいずれにおいても反回神経と関わる場面がある。しかし、手術視野展開における反回神経の見え方はそれぞれ異なり、それに伴って温存の仕方も自ずと異なっている可能性がある。3領域の外科医は、反回神経機能温存をどのように位置づけているのであろうか?反回神経障害の捉え方を相互に共有することにより理解がさらに深まることを期待する。
3)JaSECTとの共同セッション
「胸部外科領域における術中モニタリングの深化と未来像」(指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:臓器機能や止血機能の迅速な術中モニタリングは胸部外科手術の低侵襲化に貢献するか
●概要
開心術の成績は向上しているものの、未だ体外循環中の臓器機能や止血機能異常によって死亡または重篤合併症を来すリスクがある。体外循環中の脳脊髄虚血、腹部臓器虚血、高血糖などを迅速に検知したり、術中または周術期の凝固線溶系や血小板機能を正確に評価できるモニタリングデバイスについて、最近の装置の信頼性や使用効果を含めて討論する。最終的に低侵襲化に資する最も有効な術中モニタリング法を模索する。
4)シンポジウム
「領域を横断して応用可能な医療機器と派生する新治療法の可能性」(公募)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:今、手中にある手術器具、手術支援装置、エナジーデバイスがベストか?
●概要
手術の精度と効率は、外科医が手にする手術器具によって大きく変わる。近代的なエナジーデバイスや光や粒子を用いた医療機器を組み合わせ使用することで、手術難度と安全度、および、効率が変化していると思われるが、それぞれの領域に限定され応用されている側面もあるかもしれない。領域ごとに応用が拡大している実践的な医療器具、あるいは、開発段階にある医療機器等についての情報共有を期待したい。(例、Microwave scissors、Pulsed water jet dissector、Phototherapy(?) combined with medical agent、 Nano-particle、Near-infrared radiation)
5)シンポジウム
「働き方改革2024に備えて:ここまで実践しています!
~JaSECT合同セッション~」(指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:どこまで対応すれば、働き方改革水準を満たしたと言えるのか?
●概要
病院長が語る働き方改革。3 領域の大学病院や市中病院の病院長に登壇いただき現状等を発表いただきたい。
6)ワークショップ
「新たなチャレンジとしての低侵襲治療教育」(指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:血管内治療による低侵襲治療に加え、open repairも出来る二刀流医師を育成することを目指すのは理想に過ぎないのか?
CQ2:若手に低侵襲性治療を指導する際のプログラム構築に当たって重要なことは何か?
●概要
例として、TEVARは胸部大血管領域おいて不可欠な治療方法になって久しいが、必ずしもopen repairとは並行して教育が進んでいない現状がある。Open conversion等の対応も考慮するとopen repairも出来る二刀流の医師の育成を目指すのが理想であるが、TEVARに特化した胸部外科医も存在する。適切なTEVAR施行医を教育するためのロールモデル考えるべく、各施設の現状、教育方針、U-40の医師がどのような教育修練を望むか議論が必要である。呼吸器外科と食道外科領域において相同性のある課題を挙げて頂き、並列で議論いただく。
心臓分野
1)ワークショップ
「LVAD装着患者の右心不全の全貌を明らかにする」(公募・一部指定)
※同じセッションテーマの会長要望演題を企画検討中
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:右心不全の発症をどれだけ予測できるようになったか
CQ2:右心不全発症後、改善までのメカニズムは
●概要
LVAD後の右心不全のコントロールの如何は,患者のQOL,予後を大きく左右する。その発症メカニズムに関する全貌は未だ不明であり,定義,予測,管理も曖昧な点が多い。右心不全に対する外科的対策である三尖弁形成,右心補助,右心バイパス術の適応は議論の余地を残している。新たなLVADが導入された後の右心不全に対する影響も重要な課題である。既成概念にとらわれずに各施設の経験をもとに議論していただきたい。
2)パネルディスカッション
「MCSにおける脳合併症を本気で考える」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:脳神経合併症発症のリスクと予防法は何か、植込手術時・周術期管理の工夫は何か?
CQ2:脳合併症(脳出血)を起こした症例の開頭の正しい基準とは?
●概要
PCPS, Impella, VADなどのMCS(Mechanical Circulatery Support)は重症例を救命する上で欠かせないものとなっている。 MCS治療戦略において脳合併症予防は大きな課題の一つであり,患者のQOL,予後,介護者に与える社会的活動に影響する最も深刻な合併症である。脳合併症を予防するための手技,管理の工夫,発症時の血管内治療,開頭術を含めた対策,治療後の抗凝固療法,後遺症の対応と様々な問題点がある。特に重度の後遺症を併発した患者に関しては,受け入れ施設,リビングウィルへの対処等、未解決の問題がある。長期在宅補助人工心臓治療DTが広がると同時により重要になる課題である。VADのみならず全ての補助循環装置に発生した脳合併症の活発な議論を求める。また、脳出血を発症した症例の開頭の基準については、それぞれの施設の脳神経外科医の見解を含めて議論いただきたい。
3)シンポジウム「FFR guided CABGの真髄」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:FFR-guided CABGはgraft patecyを改善するか
CQ2:FFR-guided CABGは予後を改善するか
●概要
今日の冠動脈血行再建において虚血の評価方法としてFFRが重要視されているが、CABGに対する術前FFR測定の意義について議論の余地は多い。FFR測定を考慮したバイパスターゲットやグラフトの選択がグラフト開存率や生命予後にどのような効果があるのか議論していただきたい。
4)シンポジウム
「知り尽くされていない感染性心内膜炎」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:IE手術において自己組織・同種組織を使用するメリットはあるのか
CQ2:適切な治療介入のタイミングは?(疣贅サイズ、感染源、合併症併発時など)
●概要
感染性心内膜炎に対する手術方法の選択や合併症併発時の外科的治療介入のタイミングについては、明確な見解がなくいまだ多くの議論がなされている。自己心膜を使う形成術、同種組織の使用と人工弁置換で感染再発率に違いはあるのか、具体的な手術手技を議論するのではなく、再発予防の観点から工夫している手術方法について議論していただきたい。また、疣贅の大きさ、起炎菌の種類、脳出血等の合併症発症時など手術介入のタイミングについても現在明確な基準がなく、内科・外科・他科(感染症科・併診科)によって意見が分かれるところである。適切な外科的手術介入の根拠となる兆候や指標について議論を深め、感染性心膜炎に対する理解を本シンポジウムにて深めたい。
5)シンポジウム
「IMH 2023: Beyond the Guideline」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:ガイドラインを越えたIMHの本態に迫れるか?
●概要
IMHの定義、病態カテゴリーおよび手術適応はガイドラインで規定されているが、実際の治療戦略は施設毎に異なっているのが現状である。IMHを様々な側面から学び直すとともにガイドラインを越えた本態に迫り、従来の基準以外の新たな指標を見出したい。セッション前半では、外科医のみならず、循環器内科医、放射線診断医、病理医等それぞれの観点からIMHを語って頂き、定義の共有と知識の整理を図りたい。セッション後半では各施設におけるIMH病態のカテゴライズ、手術適応基準、上行大動脈径、偽腔径以外の指標等をお示しいただき、手術症例、保存的加療の症例、保存的加療から手術へconversionとなった症例などについて論じていただきたい。全体としてIMH本態への理解を深めるとともに、conversion症例を中心とした理学的、画像診断的な特徴を炙り出すことで、ガイドラインを越えた新たな治療基準を見出すことを目指す。
6)パネルディスカッション
「胸腹部大動脈瘤治療における脊髄保護戦略の今」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:最新の胸腹部大動脈瘤手術における脊髄保護戦略は?
●概要
胸腹部大動脈瘤における完全な脊髄保護法の確立はいまだ大動脈外科の未踏峰である。各施設の戦略下での手術成績を発表いただき、最新最良の戦略をupdateするとともに、解決すべき新たな課題を明るみにしたい。大動脈解離のみならず動脈硬化性の病因にも注目した脊髄保護戦略の包括的な議論を深めたい。
7)パネルディスカッション
「B型大動脈解離の全体像から見た治療介入プロセス」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:B型大動脈解離の発症時からどのように内科医・外科医が関わり連携すべきか?
CQ2:B型解離に対する長期的展望に立った治療の肝とは?
●概要
人口動態統計による大動脈瘤および解離による死亡者数は、胸部大動脈瘤および解離の術後在院死亡数(日本胸部外科学会統計)の約10倍と推測される。とりわけ、B型解離は内科医や救急医が管理することが少なくないため、病院到着前の死亡や急性期入院中の死亡、転院後の死亡例など、外科医が管理している時期以外の予後の全体像は明らかではない。ここでは、B型解離全体の予後を示していただき、初期治療のあり方、best medical treatmentの有効性、外科的治療介入の決定プロセス、病院間連携など「あるべきB型解離の管理のあり方」について議論いただく。
8)パネルディスカッション
「弓部大動脈領域のTEVARにおける限界を探る」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:遠隔期の再介入態様で浮き彫りになる初回弓部TEVAR時の鉄則とは?
●概要
大動脈瘤や大動脈解離に対する弓部TEVARでは、デブランチ型ハイブリッド治療に加え、分枝型デバイスの臨床治験も開始されている。一方で本邦の弓部置換術の成績は良好であるため、弓部TEVARにおいても遠隔期耐用性が求められる。ここでは、弓部TEVARにおける遠隔期成績を示していただき、良好な遠隔期耐用性を得るための解剖学的条件、デバイス選択、留置方法などについて議論し、遠隔期の再介入様式から初回TEVAR時の鉄則となるようなtake home messageを提供したい。
9)パネルディスカッション
「左心低形成症候群におけるFontan手術未到達例及びFailed Fontanからの考察」
(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:良好な遠隔期成績のための左心低形成症候群の治療戦略は何か?
●概要
左心低形成症候群においては、両側肺動脈絞扼術の採用、段階的治療戦略における適切な肺血流制御と共に三尖弁への手術介入など治療成績の向上が認められました。しかしながら、Fontan手術未到達例や、Failed Fontanとして治療に難渋している症例も散見されます。今回はこれらの症例を提示していただき、左心低形成症候群の更なる治療向上のための治療戦略さらには、Fontan手術の適応に関しても議論を深めたい。
10)シンポジウム
「心臓血管外科における未来医療を目指して:予測医学・シミュレーションを用いたPrecision medicine」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:ガイドラインのみに依存しない外科治療のPrecision medicineは可能か?
●概要
近年、心臓血管外科では基本的にガイドラインを軸とする標準医療がなされているが、心不全や大動脈瘤の発生・進展のように病因解明や予後予測に基づく治療が不十分な病態が未だ存在し新たなブレイクスルーが望まれる。最近は人工知能等を用いた予測医学・シミュレーションによる個別医療の可能性が視野に入り、外科治療に関しても個々の患者の予測精度の向上が重要な課題となると考えられる。新技術を用いた心臓血管外科の個別医療の未来について討論したい。
11)パネルディスカッション 「次世代の外科治療:外科医による新しい治療機器の開発を見てみよう!」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:次世代の外科治療のための医工連携(産学連携)とは
●概要
新しい外科治療機器の開発は、未解決の疾患に対する医療ニーズ(アンメットニーズ)や困難な状況に対する外科医の着想から始まるが、実現に向けては医工連携によるプロトタイプ作製に加え、医療機器メーカーとの産学連携による製品化開発が必須である。このプロセスは手術経験からのニーズとのマッチングが求められ、外科医の果たす役割は大きい。これまでの外科医の取り組みについての情報交換し、次世代の外科治療について議論したい。
12)会長要望演題 複雑化するMCSを迷わない(公募)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:非VAD・非Impella施設における重症急性心不全治療の現状と認定施設への搬送タイミングは?
CQ2:MI合併症に対するMCS治療戦略(VSP、LV rupture)
CQ3:体外設置型左室補助人工心臓の今後の使い道とは?
●趣旨
劇症型心筋炎,急性心筋梗塞等,心原性ショックに陥った症例に対するMCS治療はIMPELLAの導入に加えて各施設の方針もあり,その戦略は多岐にわたり複雑化している。特に心室中隔穿孔,心室破裂を伴う心筋梗塞後症例に対する最適な治療戦略は不明である。IMPELLAと体外設置型補助人工心臓の適応,使い分けも様々である。これらの状況を踏まえ,補助人工心臓,IMPELLA導入の困難な施設が,実施施設への搬送を考慮するタイミングの指針になる議論を求める。
13)会長要望演題 TRを科学する(公募)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:TR再発のメカニズム・危険因子は何か?
CQ2:弁輪縫縮の方法でアウトカムは変わるか?
●趣旨
現行での三尖弁閉鎖不全症に対する手術治療法は、弁輪形成が主体となっている。しかしながら、弁輪縫縮の方法には多くのバリエーションがあり、また、人工弁輪の素材や形態もさまざまである。それらの違いによって術後早期ならびに遠隔期の遺残TRの動態に変化が生じるか否かについては必ずしも明らかになっていない。また、近年、弁下組織に何らかの矯正手技を追加した三尖弁輪形成術によって、三尖弁形成の適応に変化が見られる可能性がある。さらには小児における三尖弁形成で右室形成が追加されることもある。
14)会長要望演題 大動脈緊急症に対する診療体制: 各地域の現状と課題(公募)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:大動脈緊急症に対する診療システム構築は進んでいるか?
●趣旨
循環器対策基本法施行下に大動脈疾患の救急搬送体制や病院間連携システムの構築が各都道府県で進められている。各地域の実情に応じた独自の対応が求められており、先進的システムが機能している地域がある一方、問題が山積している地域もある。各地方の実情(大動脈緊急症ネットワークを含めた救急医療体制、ICT、画像共有システムなど)と現在の取り組み、さらに今後の課題に関して発表いただき、社会的背景として、働き方改革、人的医療資源の効率的活用、施設集約化の問題も包括的に議論する場としたい。
15)会長要望演題 無症候性PAUに対する対峙の仕方(公募)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:無症候性PAUは病態としてbenignかmalignantか?
●趣旨
痛みなどの症候性PAU、また、CT画像上で大動脈周囲の浸出液や胸水の貯留をきたしているPAUに対しては、TEVARや人工血管置換術の適応となる場合が多い。しかしながら、無症候性のPAUを偶然見出した場合には、それぞれの施設や対処する医師によって対応策が異なっている可能性がある。各施設で蓄積された経験例に基づいて現行での方針を提示し議論を深めて頂きたい。
16)会長要望演題 中期遠隔期成績からみた小児三尖弁形成及び右側房室弁手術の工夫(cone手術除く)(公募)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:より複雑な三尖弁形成手技により三尖弁手術の遠隔成績は改善したのか?
●趣旨
成人領域では三尖弁手術介入の重要性が再認識されているが,先天性領域でも従来からの三尖弁輪縫縮や交連縫合に加え,最近ではcone手術の多くの治験も蓄積され,広範な弁尖補填や弁下組織に対するより積極的な介入も行われるようにもなってきた.しかしその遠隔期の成績についての検証は十分ではなく,今回は主にEbstein以外の症例について各施設の経験を発表していただき,遠隔期も含めた外科的介入の妥当性について議論したい。
17)会長要望演題 最新の画像診断・イメージング技術が導く心臓血管外科の未来:新たなエビデンス構築を目指して(公募)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:最新の画像診断・イメージング技術を用いることで、疾患の予後予測はどこまで可能か?
●趣旨
近年の画像診断用モダリティーの発達によってイメージング技術は著しく進歩し、病態の理解が深まるとともに新しい治療手技が考案されつつある。より高い解像度や時間分解能によって心臓血管の形態や血流動態の変化が詳細に描出可能となり、大動脈手術(置換範囲、脊髄灌流)、弁膜手術(人工腱索長・大動脈基部再建)、冠動脈手術(目標血管選択、至適バイパス長)等に大きく貢献している。画像解析エキスパートと外科医による多角的な討論を期待する。
呼吸器分野
1)シンポジウム「非小細胞肺癌に対する縮小手術の適応」(指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:縮小手術の適応はどこまでか
●概要
近年、肺がん診断精度の向上とともに手術症例においても小型病変の占める割合が増加している。小型肺がんにおける区域切除の優位性を示したJCOG0802試験の結果からも、今後縮小切除の増加が予想される。施設間によって手術手技も多様であり、縮小手術の適応も様々である。また、高齢者では縮小手術のほうが全生存率が良好とする報告もある。年齢因子、臓器機能によって部分切除・区域切除はどこまで許容されるのか、また、2cm以下でもhypermetabolic pure solid tumorは本当に縮小手術で良いのか。さらに、亜区域切除の妥当性はあるか。非解剖学的切除時のサージカルマージンはどのように設定すべきか、などを議論していただきたい。
2)ワークショップ
「肺癌の治療戦略-組織型別の治療方針-」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:肺癌の組織型によって治療戦略はかえるべきか
●概要
肺癌は他臓器癌と比べて組織型が多彩で種類が多いことが知られている。肺癌の組織分類は1999年WHO分類第3版において大きく変化した。各組織型の生物学的特性が明らかになってくることによって、従来の小細胞癌、非小細胞癌という大きなくくりから、非小細胞癌においては例えば小型でlepidic 主体の腺癌は縮小手術が検討され、micropapillary/肺胞腔内腫瘍散布像(STAS)/EGFR遺伝子変異を伴う腺癌、大細胞神経内分泌癌(LCNEC)や多形癌は標準術式に加えて術後補助療法、再発時の治療方針を考慮するなど、組織型によって手術を中心とした治療戦略が大きく変化してきている。現状において、どの様な方針の下に治療を行っているのか、各施設1組織型に絞って提示していただきたい。
3)パネルディスカッション
「区域切除におけるリンパ節郭清」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:区域切除でのリンパ節郭清はどうあるべきか
●概要
早期肺癌に対する区域切除術がさらに増加している。区域切除を行う際はリンパ節転移陰性が前提となるが、側方へのリンパ流による転移も考えるとどのリンパ節を迅速診断するべきか、積極的区域切除での肺門縦隔リンパ節郭清は根治術式としてありうるかが重要となってくる。現在、日本では症例に応じて系統的あるいは選択的リンパ節郭清を選択することが主流となっているが、すりガラス成分主体の早期肺癌ではリンパ節転移の可能性がほぼ皆無であることが判明しており郭清の個別化や縮小化も進んでいる。区域切除が普及するにつれ、葉間/肺門リンパ節の郭清範囲についてもさらなる検討が必要であり、術前の精査によりリンパ節転移の有無の検討を行い、症例に応じた最適な郭清様式の選択について議論していただきたい。
4)ワークショップ
「呼吸器外科学における医工連携」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●概要
昨今,医学の進歩には科学技術の革新とその応用が不可欠となっている.呼吸器外科分野においては,手術支援用ロボットが新たな手術法として本邦でも認可を受け既に大きな実績を残している。その他、新たな手術支援用ロボット/手術支援システム、手術トレーニングソフトウェア、術中ナビゲーション技術の開発など,医工連携の重要性は増していると言える.さらに,第5世代移動通信システム(5G)やAIといった最新技術が今後,どのように呼吸器外科学と融合していくのか大変興味深い.一方で,この分野の競争は国際的にも大変厳しく,スピード感を持った医学系と工学系の連携が必要となっている.本セッションでは,医工連携の最新知見と展望について発表いただきたい.
5)パネルディスカッション
「ドナー因子と肺移植成績」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:ドナー因子は肺移植成績にどのように影響しているのだろうか?
●概要
肺移植を必要とされている患者数に比べ臓器提供数は不足しているため、移植成績を悪化させない範囲でできるだけ多数のドナー肺を移植に用いるための医学的知見の集積は重要である。ドナーの医学的な諸因子(年齢、性別、体格、喫煙歴、脳死原因、喀痰培養検査結果、HLAタイピング、血液ガス、X線所見など)が移植成績に及ぼす影響については多数の報告があるが、日本からの報告はまだ少ない。近年、日本臓器移植ネットーワーク内に倫理委員会が設置され、ドナー情報の研究利用の枠組みが確立されたことから、日本においてもこのテーマについての知見を共有していただきたい。また、ドナー因子に関する基礎的な研究も報告されており、ドナー因子が肺移植成績に及ぼす影響について議論していただきたい。
6)パネルディスカッション
「縦隔炎の外科治療update」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:縦隔炎に対して手術に踏み切るタイミングは?
CQ2:縦隔炎に対する外科的アプローチ法の選択とは?
●概要
急性縦隔炎はまれな病態であるが、時に致命的な結果を招きうる重篤な感染症のひとつであり、食道穿孔、胸骨正中切開後の感染、膿胸からの波及や他臓器の感染巣からの血行性波及によって生じる。さらに、降下性壊死性縦隔炎は歯科的疾患や、扁桃周囲膿瘍や後咽頭および周囲膿瘍、頚部外傷などによって起こる致死的で緊急を要する病態である。また、化膿性胸鎖関節炎は広範囲な胸壁膿瘍や縦隔炎の原因になる。重症な縦隔炎の患者を救命するためには、補液や抗菌薬投与などの全身管理に加えて、積極的な頚部や縦隔の外科的ドレナージが必要である。本セッションでは、さまざまな縦隔炎に対する術前評価、手術適応、アプローチ、ドレナージの経路や範囲、手技について議論していただきたい。
7)ビデオワークショップ
「低侵襲呼吸器外科手術のベストプラクティス
~Do&Don’tを知り尽くす~」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:低侵襲呼吸器外科手術の禁忌手技は何か?
CQ2:低侵襲呼吸器外科手術で守るべき手技は何か?
●概要
低侵襲呼吸器外科手術の発展に伴い、その中でも胸腔鏡手術や単孔式手術、ロボット手術と多彩なアプローチ法が考え出され、現在多くの施設で普及してきている。しかし、新しいアプローチを導入および実践するにあたって、確かな根治性と安全性が担保できなければ、低侵襲手術の意義が失われてしまうだろう。そのために我々は、アプローチごとの特徴を正確に理解したうえで、守るべき基本事項と破ってはいけない注意事項を心得ておく必要がある。本セッションでは、根治性と安全性を両立した、最善の低侵襲呼吸器外科手術を行うために各アプローチ法におけるDoとDon’tを提示していただきたい。また、各アプローチ法が持つメリット、デメリットを比較、共有し、低侵襲呼吸器外科手術のベストプラクティスについて議論していただきたい。
8)ビデオワークショップ
「低侵襲呼吸器外科手術の限界を理解しよう」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:低侵襲呼吸器外科手術の禁忌適応は何か?
CQ2:低侵襲呼吸器外科手術で避けるべき手技は何か?
●概要
低侵襲外科手術には各種のアプローチ法があり、その特徴を十分理解することが必要である。その上で、手術適応、守るべき基本事項と避けるべき事項を熟知する必要がある。低侵襲手術のキーとなるエネルギーデバイスについては、個々のデバイスの特性を十分に理解した上で使用する必要があり、不適切な使用は重大な合併症を招くリスクがある。ロボット手術については症例数が増大している中で、ロボット手術特有の合併症、トラブルシューティング、ピットフォールについての情報の共有が肝要である。根治性と安全性を両立した低侵襲呼吸器外科手術を最善に行うための適応限界と術中禁忌手技に関して議論していただきたい。
9)パネルディスカッション
「ICI時代の悪性胸膜中皮腫の集学的治療」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:悪性胸膜中皮腫に対してICIを用いた集学的治療は勧められるか?
●概要
外科治療に化学療法や放射線治療を加える集学的治療によって悪性胸膜中皮腫の治療成績は向上してきたが、いまだ予後不良の疾患である。近年、悪性胸膜中皮腫に対するImmune Checkpoint Inhibitor(ICI)の有効性が注目され、ICIが治療戦略に加わって早4年が経つ。「切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫症例」に対するICI使用が適応となっているが、ICI投与の至適時期や外科治療を含めた他の治療との組み合わせについてのコンセンサスはまだなく、各施設で様々な試みがなされている。本セッションでは、ICIが悪性胸膜中皮腫に対する集学的治療の成績に寄与できているかどうかを検証し、集学的治療におけるICIの今後の位置づけについて議論していただきたい。
10)会長要望演題
「間質性肺炎合併肺癌に対する手術適応」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:間質性肺炎合併肺癌に対する手術適応や術式はどう選択すべきか
●概要
間質性肺炎合併肺癌に対する薬物療法は限られた薬物の使用にとどまり、そのエビデンスは乏しい。血管新生阻害薬や免疫チェックポイント阻害剤の有効性や安全性の情報も乏しく、外科治療が期待されている領域である。しかしながら、周術期の間質性肺炎急性増悪はいまだ肺癌手術死亡の上位を占めており克服しなければならない喫緊の課題である。小型非小細胞がんに対する縮小手術のプレゼンスが増大してきている昨今、間質性肺炎合併肺癌に対する術式や手術適応をどのように選択すべきか?間質性肺炎の特性や重症度、バイオマーカーなどをふまえ、短期・長期予後、合併症の観点から議論頂きたい。
11)会長要望演題
「胸腺上皮性腫瘍に対する標準術式」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:進行胸腺上皮性腫瘍に対する低侵襲アプローチは勧められるか?
CQ2:胸腺上皮性腫瘍に対してリンパ節郭清を行うべきか?
●概要
早期の胸腺腫に対する低侵襲アプローチは標準治療として受け入れられつつあるものの、進行胸腺腫や胸腺癌に対する低侵襲手術は一定の見解は得られていない。さらに、進行胸腺上皮性腫瘍に対するリンパ節郭清の必要性やその範囲についてまとまった報告はない。一方で、薬物や放射線治療の進歩に伴って集学的治療も変化する可能性があり、本セッションでは補助療法を含む進行胸腺上皮性腫瘍に対する治療方針を議論したい。
食道分野
1)ビデオシンポジウム ※英語セッション
「cT3br、cT4局所進行食道癌に対する低侵襲手術の妥当性」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:局所進行食道癌に対して低侵襲食道癌手術は安全に施行できるか
CQ2:局所進行食道癌に対して低侵襲食道癌手術は開胸手術と同等の根治性を担保できるか
●概要
高度局所進行食道癌(cT3b、cT4)に対する術前補助療法後の手術やコンバージョン手術、サルベージ手術は、従来開胸手術が標準であった。近年、胸腔鏡下手術やロボット支援下手術などの低侵襲手術の普及に伴い、一部の施設においては高度局所進行癌に対しても低侵襲手術が積極的に適応されるようになった。しかし、高度局所進行癌に対して低侵襲手術の安全性が担保されるか、開胸手術への移行を想定したプランニングが必要か、開胸手術と同等の根治性が担保されているかということについては未だ明らかではない。本セッションでは、ビデオを供覧しつつ、高度局所進行食道癌に対する低侵襲手術の妥当性について、安全性と根治性の観点から、開胸手術と比較して議論していただきたい。
2)パネルディスカッション
「食道癌術後再建法と長期的なアウトカム」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:再建方法の違いは消化管生理や栄養状態に影響するか
CQ2:長期QOLや栄養状態の観点から栄養瘻は必要か
●概要
食道癌術後の消化管再建については、これまで短期合併症の軽減を目指した様々な工夫がなされ、安全性の向上が図られてきた。一方、食道癌術後の摂食機能低下や栄養障害は長期におよぶため、食道癌治療成績の向上に伴って、術後のQOLや消化管運動生理、栄養状態をいかに改善するかが注目されるようになっている。本セッションでは、胃管の形状や再建経路、吻合位置など、基本的な胃管再建の工夫に加え、Roux-en-Yを付加した延長胃管、胃温存結腸再建等の特殊な再建方法が術後長期のQOL、消化管運動生理や栄養状態にどのような影響を与えるかデータを提示いただいて議論いただきたい。また、早期経管栄養は術後短期成績を改善することが示されているが、長期的に見た場合の栄養瘻の功罪については明らかにされていない。長期QOLや栄養状態の観点から、栄養瘻の必要性と作成方法の工夫についても議論していただきたい。
3)ワークショップ「術野内再発を考える」(公募)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:なぜ術野内再発が起こるのか
CQ2:術野内再発に対して局所治療は有効か
●概要
食道癌の再発形式としてはリンパ節再発が最も頻度が高く、食道癌に対する根治手術には確実なリンパ節郭清が重要である。近年、術前補助療法の有効性が明らかとなり、DCF療法や術前化学放射線療法など、局所治療効果の高い術前治療が一般化している。また、胸腔鏡やロボット支援下手術の進歩により、拡大視効果に基づいた緻密なリンパ節郭清を行えるようになってきている。しかしながら、確実に切除したと考えられる症例においても術野内再発をきたす症例は未だ少なくない。本セッションでは、なぜ術野内再発が起こるのか、術野内再発に対して局所治療は有効か、局所治療の選択は手術か化学放射線療法か、再発部位によってその選択は変わり得るのか等々、術野内再発をめぐる様々な問題に関して多面的な議論を期待したい。
4)ワークショップ「食道癌手術の周術期管理を考える」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:周術期管理チームは食道癌の術後合併症の軽減に有効か
CQ2:周術期管理チームの有用性をエビデンスとするには何が必要か
●概要
食道癌に対する根治手術は最も侵襲の大きな手術のひとつであり、術後合併症の発生は未だ多く、高度な周術期管理が求められる。近年、周術期の栄養管理、口腔ケア、薬物管理、リハビリ介入、術後回復期のサポートなど、多職種のチームによる周術期管理の有用性が注目されている。しかしながら、チームによる周術期管理が術後合併症の軽減や長期予後改善につながるというエビデンスは乏しく、保険診療における加算の実現に向けてのハードルとなっている。本セッションでは、周術期管理チームの導入が術後合併症の軽減や長期予後の改善につながるか、これから導入する施設に対するアドバイス、エビデンスを創出するための方法論等、周術期管理をめぐる問題点について議論していただきたい。
5)ディベート
「サルベージ手術におけるリンパ節郭清;郭清は必要か」(公募・一部指定)
- Clinical Question/企画概要
-
●Clinical Questions
CQ1:サルベージ手術に予防的リンパ節郭清は有効か
CQ2:郭清省略はサルベージ食道切除の安全性向上に寄与するか
●概要
サルベージ手術は根治的化学放射線療法後の遺残・再燃に対して根治を期待しうる治療選択肢である。一方、サルベージ手術は術後合併症や在院死亡リスクの高い手術であり、リンパ節郭清の意義については一定の見解は得られていない。サルベージ手術においても通常の食道癌手術と同様のリンパ節郭清を行うという施設もある一方で、サルベージ手術においては選択的にリンパ節郭清を省略する施設も存在する。本セッションでは、サルベージ手術において予防的リンパ節郭清は必要か、治療開始前にリンパ節転移を有する場合と認めない場合、あるいは遺残と再燃でその意義は異なるのかなど、サルベージ手術におけるリンパ節郭清の意義について、徹底郭清派と郭清省略派の間で議論していただき、一定の結論に導くことを期待したい。