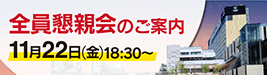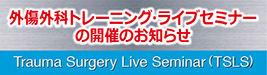演題登録(公募)
演題募集期間
多数のご応募をいただきありがとう
ございました。
- 2024年4月1日(月)正午~
- 5月24日(金)正午
6月7日(金)正午まで延長いたしました。
6月13日(木)正午まで延長いたしました。
6月20日(木)正午まで延長いたしました。
※これ以降の再延長はございませんので
ご注意ください。
応募資格
日本国内の施設に所属している方については、共同演者を含む全員が本学会会員であることが必要です。
非会員の方は演題登録時までに必ず日本臨床外科学会へ入会してください。
ただし、「研修医セッション」の筆頭演者は必ずしも本学会員に限りません。
※共同演者は本学会会員であることが必要です。
入会および会費納入に必要な書類は日本臨床外科学会事務局にお問い合わせください。
オンラインでの入会登録は以下のボタンから行ってください。
(入会申請中のときは「会員番号」欄に999999と入力してください)
※会員番号が6桁に満たない場合は、先頭(左)に「0」を追加し6桁で入力ください。
【お問い合わせ先】
日本臨床外科学会事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-6-9 ロックフィールドビル8階
TEL:03-3262-1555 FAX:03-3221-0390
応募方法
演題登録はホームページからのオンライン登録による応募のみとなります。事前に登録システム利用上の注意をご確認ください。
UMINオンライン演題登録システムでは、【Firefox】【Google Chrome】【Microsoft Edge】【Safari】以外のブラウザで演題登録はできません。それ以外のブラウザでは、ご利用にならないよう、お願いいたします。
※各ブラウザは、最新バージョンの使用を前提としております。
募集カテゴリー
募集カテゴリーについては下記をご参照ください。
※趣旨をクリックすると詳細をご覧いただけます。
01 地域に外科を
(1)へき地医療における外科医療の実践と技術修練

(1)へき地医療における外科医療の実践と技術修練
近年、外科手術の集約化が、技術面、安全性からも勧められている。しかしながら、全国へき地には、ある一定の割合で、外科手術や、外科的手技が必要とされ、その為に症例の少ない地域へ単身あるいは経験豊富な上級医がいない状態で若手外科医が派遣される事になる。外科専門医取得後の中堅外科医がへき地医療に携わるとき、安全性も考慮し、どの程度までの手術手技が標準的に必要か、について議論していただきたい。また、各施設あるいは派遣元施設(大学医局など)が、症例の少ない地域で外科医としてのモチベーションを保つ為に、どのような取り組みをされているか、遠隔指導なども含め、今後どのような取り組みが必要か論じていただきたい。
02 地域に外科を
(2) 地域医療を支えるGeneral Surgeonの自負

(2) 地域医療を支えるGeneral Surgeonの自負
地域で活動されている外科医の多くは、General Surgeonとして活躍されており、往診やコロナなどの専門以外の疾病に対応することも頻繁にあるに違いない。その日常を写真・映像などを用いて解りやすく発表していただき、幅広い経験に基づいた医療全般に対する熱い思いを若い外科医に伝えていただきたい。
03 地域に外科を
(3)医療情報を地域に届けるために

(3)医療情報を地域に届けるために
近年の外科診療は日進月歩で、いかに確度の高い最新の医療情報を得るかは日常臨床では重要な課題である。インターネットが普及した2000年前後から四半世紀が経過し、最近は生成AIの登場、医療DXの概念など、医療情報の提供方法、活用方法は新たなフェイズに入った感がある。また2020年以降の新型コロナウイルス感染症パンデミックにより、WEB会議のインフラが急速に整備され、多くの学会・研究会へWEB参加出来るようになり、診療を中断することなく情報を得ることが可能になった。今後の医療の在り方は、情報をいかに取得し活用するかに大きく依存していると考えられる。外科診療の均霑化を実現するためには、情報過疎地、情報弱者をなくすためのインフラ整備が重要で、今後10-20年を見据えた医療情報提供方法、活用方法についての提案、事例報告を広く募集する。
04 そして、世界へ(Prof. Alan Lefor Memorial Seminar)
(1)世界の中で『医療の谷間に灯をともす』
”Brighten the World in Your Corner”

(1)世界の中で『医療の谷間に灯をともす』
”Brighten the World in Your Corner”
自治医大の建学の精神である「医療の谷間に灯をともす」をグローバルレベルで実践していただいている先生方に登壇していただき、海外での医療援助活動の内容、人道危機の状況、医療行為の実際(特に資源が限られる現場において)、やりがい(目指したきっかけなど)、海外の人道援助現場で求められる資質(技術)は何か、どのようにして取得したか?さらには家族の理解や医療者としての内面の変化などについて語っていただき、世界を舞台にした臨床活動を志す若手外科医へのメッセージとしたい。
05 そして、世界へ(Prof. Alan Lefor Memorial Seminar)
(2)世界を舞台に先端医療を
”Advanced Medical care on a global stage"

(2)世界を舞台に先端医療を
”Advanced Medical care on a global stage"
第一線の外科医療を経験された後に、海外における様々な最先端医療の分野で活躍されてきた先生方に、海外に出られたきっかけや現在の活動状況、それを維持するモチベーションなどについて語ってもらい、“海外で働いてみたい”と考えているがそのロールモデルがないと悩んでいる若手外科医に対するエールを送っていただきたい。
06 働き方改革の導入から新時代の外科へ
(1)タスクシフティング、チーム医療の観点から
(2)ワークライフバランスの観点から
(3)デジタル技術の導入と労働環境の観点から
(4)若手医師の教育の観点から
(5)医療安全の観点から
(6)医療連携、地域医療の観点から
(7)外科研究の観点から

(1)タスクシフティング、チーム医療の観点から
(2)ワークライフバランスの観点から
(3)デジタル技術の導入と労働環境の観点から
(4)若手医師の教育の観点から
(5)医療安全の観点から
(6)医療連携、地域医療の観点から
(7)外科研究の観点から
本年4月の働き方改革の導入に伴い、外科の臨床現場では様々な変化が起こってきつつあると思われる。その現状について、若手医師、指導医、女性医師、大学病院、地域病院、開業医などの異なる立場の方から、良かった点、困った点などを含めた現場の「生の声」を発表していただき、より良い外科医療を実現するための今後の課題とそれに対する具体的な対応策を考えてみたい。具体的なテーマとして、タスクシフティング、ワークライフバランス、若手医師の教育、医療連携と地域医療、医療安全、外科研究などの観点から複数のワークショップ形式のセッションを設けて討論していただきたい。
07 明日の外科を魅力あるものに
~若手医師が求める外科社会とは~

~若手医師が求める外科社会とは~
外科医不足の問題が顕在化して久しい。外科を志す若手医師を増やすために各学会は様々な対策を講じているが、外科医志望者減少に歯止めがかからない状況である。学会の意思決定層と若手医師との価値観に大きな乖離があり、有効なアプローチが出来ていない可能性がある。したがって、今後は、外科という職業が若者にとって真に魅力のある仕事になるためには、外科社会はどうかわっていくべきなのか?という視点からこの問題を考えていく必要があると思われる。 本セッションでは、働き方改革、男女共同参画、教育体制、管理職育成など、多角的な観点から若手医師が求める外科社会になるための方策を論じていただきたい。特に若手外科医からの提案に期待する。
08 外科教育を再考する
「外科医の技術と知識の未来:教育の革新への挑戦」

「外科医の技術と知識の未来:教育の革新への挑戦」
外科教育は、外科医の高齢化、若手外科医の減少、「医師の働き方改革」の施行により、急速な革新を求められている。過去、外科教育は手術室や病棟でのオンザジョブトレーニングによるスキルアップが重視されてきた。しかしながら新型コロナ感染症蔓延後から対面での教育訓練が困難になり、抜本的な外科教育改革が必須となった。現代の技術革新により、シミュレーションやバーチャルリアリティを活用した教育手法が台頭し、SNSやweb会議システムの普及がさらに拍車をかけた。これらのツールの利用は安全で場所を問わない訓練を可能にした。また、AI(人工知能)やデータ解析を活用した個別化された教育プログラムを組み合わせることで、学習者の実際のスキルや知識レベルに基づいてカスタマイズされた教育を提供することが可能である。伝統的な外科教育手法を鑑み、未来の外科医を育成する手法について論じていただきたい。
09 外科医のためのエルゴノミクス:快適性と効率の追求

外科医を取り巻く現状は、鏡視下・ロボット支援手術などの低侵襲手術の隆盛や人工知能や仮想現実などの最新技術の導入により大きく変化している。医師の働き方改革が本年4月から施行され、外科医の働き方にも改善が求められている。しかしながら手術室における外科医の労働環境に大きな変化はなく、腰痛や肩こりなどの筋骨格系の異常を来す外科医も多い。本セッションでは人間工学の専門家の知見を鑑み、働き方改革に即した外科医の労働環境の構築と改善について論じていただきたい。
10 手術のビジュアル化:
イラストレーションによるオペレコの革新

イラストレーションによるオペレコの革新
手術記録には、公的な文書としての役割と外科医のスキル向上の一環としての役割がある。特に、若手外科医にとっては、後者としての役割が大きい。近年、デジタルイラストレーションの普及により、外科医自身が綺麗なイラストを容易に作成することが可能になってきた。一方で、これが業務の負担となっている現状もある。また、鏡視下手術が増加し、手術全体がデジタルデータとして保存されることも増えてきており、新しい手術記録のあり方が模索されている。本企画では、イラストを含めた手術記録の本質的な目的について論じる同時に、近年利用が進んでいるデジタルイラストレーションの活用によって、手術記録の目的達成と業務の効率化について議論を深めていただきたい。
11 AIが描く外科の未来:テクノロジーが導く医療の進化

近年、ディープラーニングによる画像認識やプロンプトに応答してメディアを生成することができる生成AI(人工知能)などのAIは進化が著しい。外科領域では、手術診断の迅速化、手術ナビゲーションによる精度向上、手術ロボットによる手術の自動化、ヒトとロボットとのハイブリッド手術支援など、テクノロジーが外科診療にもたらす恩恵は計り知れない。また通信技術の発達はTelemedicineを普及させ、地域医療の格差解消に貢献すると考えられる。さらに、画像診断や生体情報の解析におけるAIの活用は、早期診断、オーダーメード治療の精度向上が期待される。対してこれらの技術革新には、個人情報保護や医療倫理、医療安全など、多くの解決すべき課題がある。こうした技術革新がもたらす可能性と共に、外科の進化が人々の健康と医療へのアクセスにどのような影響を与えるのかを考える必要がある。AIとの共存共栄の時代を迎え、AIと外科との関係性や未来の外科について幅広く論じていただきたい。
12 外科医をとりまく医療機器開発 up to date

外科は手術を主たる業務とすることから、手術成績を向上させることに余念がない。すなわち手術の歴史は医療機器開発の歴史と関係性が深い。我が国の外科医は診断から手術、術後経過まで広く診療を行うため、多くの開発ニーズを持つ。多くの医療機器が外科医の開発ニーズから生まれ、日常診療に利用されている。近年では、手術用鉗子や開創器などの鋼製小物に加え、術中リアルタイム診断支援、患者の画像情報をもとにして作成された精緻な臓器モデル、ロボット支援手術システム、手術動画解析による診断・治療支援など、より高度化した医療機器や医療技術開発に外科医が参画している。忙しい日常診療の合間を縫って、工学部、産業界と連携し医療機器を開発してきた経験について本セッションで論じていただきたい。
13 救急医療における外科医の役割

救命救急領域における外科医の役割について、多方面から論じていただく。一般外科医がどのように外傷治療に参画するか、外傷外科医をどのように育てるか、など。特に、地域には人口減少、都市部への距離、限られた医師数、専門医の偏在など多数の問題が存在し、かつ、各地域の特有の問題を抱えています。効率的な外科緊急医療を住民に提供するための工夫、方向性を紹介していただきたい。
14 男性外科医の「仕事と育児の両立」ー理想と現実ー

近年、男女共同参画の焦点は女性の両立支援から働き方改革や男性の家庭参画へと推移している。国も働き方改革関連法や男性の育児休業の取得を促進するための制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」を創設するなど積極的に後押ししている。しかしながら育休取得を阻む雰囲気・収入減・キャリア形成の遅れに対する心配等から男性育休の取得率は未だ17%と限定的である。また、男性が経済的大黒柱でありながら育児も相応に分担することになると、ワーク・ライフ・バランスは、想像以上に厳しいものかもしれない。本セッションでは、男性外科医の「仕事と育児の両立」の理想と現実、また男性の両立支援について討論していただきたい。
15 女性外科医が指導者として活躍するためには?

外科に占める女性医師の割合は年々増加してきている一方で、指導的地位に就いている女性外科医は少ない。今後、女性が指導者として活躍するためには、どんなことが必要であろうか。女性が指導者として活躍する際の問題点、目標となる指導者や理想の指導者像などについて、様々な立場から意見を述べていただき、将来の外科をリードしていける若手女性外科医を増やす方策について考える機会としたい。
16 コーチングによる組織マネジメントの新潮流

近年、様々な病院において、幹部に対する医療コーチングプログラムを導入することで医療スタッフ間のコミュニケーションが良好になり、経営改善にも繋がっている事実が報告されてきている。本セッションでは、各施設において、具体的にどのような形でコーチングを導入し、どのような影響があったのかを発表していただき、病院内の良好な職場環境を構築するための方法論に関する議論を深めていただきたい。
17 外科医にとって臨床試験とは?

現代医学において、RCTに代表される高レベルのエビデンスを創出するための臨床試験は必須のものである。外科の分野でもこれまでに多くの臨床試験が施行されてきたが、その過程で外科に特有の問題点がいくつも指摘されてきている。また、実際の外科臨床の現場においては、純粋なエビデンス以外の要素で治療を行わなければいけないケースも多い。本セッションでは、外科業務と同時に積極的に臨床試験に関わってこられた先生方に、その経験、今後の課題などについて語っていただき、第一線で働く外科医にとって「臨床試験にどうコミットし、そこで得られた情報を賢く活用するにはどうすればいいのか?」について議論を深めていただきたい。
18 外傷外科トレーニング・ライブセミナー

外傷治療の経験が少ない外科医や外科専攻医を対象とし、外傷外科の基本的な知識と手技を学ぶことを目的としたセミナーです。宇都宮の学会会場と自治医科大学先端医療技術開発センター手術室をつないで、大型動物を用いた外傷トレーニングをライブ中継いたします。日本の外傷治療のトップ指導者による手技を解説付きでご覧いただける貴重な機会です。手術室と会場をリアルタイムでつなぎ、会場とのやりとりを通じて、参加者がより多くの学びを得られるプログラムとなっています。なお、本セミナーは日本専門医機構 外科専門研修における外傷研修として、2ポイントが付与されます。
19 減量・代謝改善手術の進化と展望

減量・代謝改善手術は、高度肥満症や肥満2型糖尿病に対する有効な治療法として認められている。現在、腹腔鏡下スリーブ状胃切除術が保険適用となっているが代謝の改善や減量効果が高いとされるスリーブバイパス術などの他の術式も含め、手術の効果と安全性の最新のエビデンス、手術後の管理とフォローアップ、多職種チームによる統合的な肥満症治療等について論じていただきたい。
20 胃癌腹膜播種治療における最新の進歩と課題(English session)

腹膜播種は胃癌を扱う消化器外科医にとって最大の難敵である。胃癌腹膜播種に対する治療戦略、全身化学療法、腹腔内局所治療(HIPEC、PIPACを含めた)およびConversion surgeryに関する最新の知見について発表していただき、外科医の視点から見た今後の胃癌腹膜播種治療の方向性について議論していただきたい。
21 直腸癌に対するロボット支援手術の有用性のエビデンス

直腸癌に対するロボット支援手術は、診療報酬上は腹腔鏡手術と同等であり、ロボット加算が認められていない。しかし最近、腹腔鏡手術とロボット支援手術を比較した臨床研究では少しずつロボット支援手術の有用性が示されてきている。自施設あるいは多施設共同研究の結果から直腸癌に対するロボット支援手術の有用性のエビデンスを示していただきたい。
22 便失禁診療・研究の進歩と課題

便失禁に対する外科治療として仙骨神経刺激療法が2014年に保険収載され、便失禁診療ガイドラインが2017年に発行され、難治性排便障害に対して経肛門的洗腸療法が2018年に保険収載されるなど、便失禁診療が進歩している。また2021年には、臨床検査技師が直腸肛門機能検査を独立して施行できるように法整備がなされ、便失禁診療における多職種協働が進みつつある。さらに、本学会開催までには、便失禁診療ガイドラインが改訂される予定である。このように便失禁診療・研究を取り巻く環境が大きく変わっている状況を踏まえて、便失禁診療・研究がどこまで進歩しているか、そして今後更に進歩するためには、どのような課題を解決するべきかを話し合うことは有意義と考える。
23 クローン病における肛門部病変の治療戦略

クローン病は全消化管に狭窄や瘻孔などの病変を生じうる炎症性腸疾患であるが、難治性痔瘻などの肛門部病変の治療に難渋することも多い。シートン法などで膿瘍腔をドレナージした上で、クローン病に対する内科的治療を行うことで瘻孔に対処するのが原則であるが、近年、ダルバドストロセルによる再生医療も行われている。また、シートン法にも様々な方法や工夫がみられる。そこで、痔瘻に限らずクローン病における肛門部病変に対する各施設での対応方法や治療戦略を発表・議論していただくことで、クローン病の肛門部病変に悩む患者さんに資したい。
24 進行胆嚢癌の治療戦略 集学的治療と切除適応

深達度がT1a(m)、T1b(mp)の胆嚢癌は、リンパ節転移の頻度は極めて低く予後良好であることから腹腔鏡下手術の適応である。またT2(ss)胆嚢癌も外科的切除断端陰性が確保できれば系統的切除に拘らない術式が許容される。一方、T2以上の進行胆嚢癌は、技術的に切除可能でも予後は極めて不良であり、手術先行では予後改善は期待できない。術前化学療法を含めた各施設の戦略を示していただき、今後のT2以上の進行胆嚢癌の集学的治療と外科手術の役割について議論していただきたい。
25 心臓血管外科手術のハイリスク症例に対する術前評価と
周術期多臓器合併症の予防策

周術期多臓器合併症の予防策
近年、心臓血管外科手術の対象となる患者は、高齢者あるいは多臓器疾患合併などリスクを抱えた症例が多くなっている。手術前のリスクアセスメントとリスクに沿った対応をすることが合併症回避につながると考えられているが、本セッションでは周術期合併症に対する、各施設における工夫をもとに討論をしていただくことを期待する。
26 肺癌周術期治療の現状と展望

近年、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬の術後補助療法としての有用性が報告されいている。また術前治療に免疫チェックポイント阻害薬を用いる臨床試験も進められている。新規薬剤が肺癌の術後成績の向上に寄与することが期待されている一方、有害事象や長期成績についてはまだ課題が残されている。肺癌周術期治療の選択肢が広がりつつあるが、現状と展望についての議論を期待したい。
27 本邦における脳死移植の現状と展望

臓器移植法が制定されてから、本邦でも脳死移植は増加傾向にあるが、まだまだ十分な提供数には達していないのが現状である。この原因としては、手続きの複雑さや適切な情報提供の不足、さらには臓器提供の意思表示が不足していることから有効なドナーが見過ごされていることなどがある。現在の脳死移植の問題点や課題を取り上げ、今後の展望を議論していただきたい。
28 外科医が行う緩和医療の実情と課題

本邦では緩和医療の多くを外科医が担っている現状がある。地域医療の現場で癌の診断から治療、看取りまで携わっている外科医の取り組みを発表していただきたい。出血、狭窄などの切迫した症状に緩和手術、疼痛管理、精神面も含めた緩和ケア領域での様々な工夫やその有用性や限界について最新の知見を発表していただきたい。
29 外科医が行うがん薬物療法の実情と課題

近年のがん領域の医学の急速な発展に伴い、がん薬物療法は多岐にわたり、かつ複雑化している。米国のように、腫瘍内科医ががん薬物療法を担当するのが理想であるが、我が国の多くの施設では外科医が消化器癌の薬物療法を担当しているのが実情である。最新の知見やガイドラインを習得するための研修機会を利用してがん薬物療法に関する専門性を高めることに加えて、診察に十分時間をとって患者の心理的サポートをしながら、多職種との連携をしてがん薬物療法を行うことが重要である。しかし、手術や術後管理に時間をとられ十分な時間が取れないのが現状であると思われる。一方で、高額の薬剤や材料費は、患者個人の金銭的負担のみならず医療経済全体を圧迫しつつあり、何らかの対応策が必要になると思われる。本セッションでは各施設において外科医が行っているがん薬物療法の実際と、今後の課題解決にむけた工夫等について発表いただきたい。
30 外科医が行う基礎研究と臨床応用

外科医は患者の肉体に傷をつけることを介して、その手で病変を直接触知するという極めて特殊な経験を有している。したがって、侵襲をどれだけ軽減し、最大の治療効果を引き出すためにはどんな工夫が必要か?を考えることが外科研究の根本的な目的であると言える。本セッションでは、その「手」の感覚に基づく外科医独自の視点から得られた基礎研究の成果とその臨床応用の取り組みについて発表していただき、外科研究の課題と将来展望について議論していただきたい。
31 腹腔鏡下Sleeve状胃切除の手技の工夫と治療成績

高度肥満症に対する腹腔鏡下Sleeve状胃切除(LSG)は、食事制限と代謝改善を目的としたシンプルな術式であるが、胃縫合線のリークや出血など重篤な合併症の他、ねじれ・狭窄や逆流性食道炎でも治療に難渋する場合がある。各施設での、LSGの技術的な工夫についてビデオにて供覧いただき、あわせてLSGの長期的な成績や合併症の発生率、再手術の必要性等について発表いただきたい。
32 腹腔鏡下肝切除:技術認定を目指して

日本内視鏡外科学会の技術認定医合格のためには、術者だけではなく、助手、カメラマンも含めたチーム力が重要である。さらに、正確な術前シミュレーションと術式の流れに沿った、安全なアプローチが必要である。本セッションでは、腹腔鏡下肝切除の“キモ”とは何かについて合格ビデオ、さらには不合格ビデオを共有し、安全確実な手術を行える内視鏡外科医の育成を目指したい。
33 腹腔鏡下膵切除:技術認定を目指して

日本内視鏡外科学会の技術認定医取得は、腹腔鏡手術を行う外科医の1つの目標となっている。膵臓領域では2012年度から膵体尾部切除術の技術認定が始まり、2022年度までに188名が申請し57名が合格(合格率30%)している。本セッションでは、ロボット支援膵体尾部切除術を見据え、腹腔鏡下膵体尾部切除術をどのように標準化し、技術認定をクリアしていくか、使用デバイス、術野展開、手術手順等の観点から議論していただきたい。
34 肝癌ナビゲーション手術の工夫

肝臓の立体構造の把握は、肝臓外科医にとって不可欠なものとなった。手術計画を立てる際、肝臓の立体イメージの共有がより安全な手術につながるが、近年の治療支援画像の技術進歩により、立体イメージの共有が容易になり、3次元画像をもとに議論し治療計画を立てることが可能になった。さらに、画像支援システムは進化をとげ、肝切除症例におけるシミュレーションからナビゲーションへと普及しつつある。本セッションでは肝切除のナビゲーションを中心とした治療支援画像のアイデアと共に、各施設における工夫やこれまでの成果を共有することにより、さらなる発展を目指したい。
35 心臓血管外科手術の領域における鏡視下手術のpitfallとbailout

外科一般の領域ではすでに通常の診療として取り入れられている鏡視下手術(ロボット手術・右開胸鏡視下手術)が心臓血管外科の領域でも遅ればせながら普及しつつある。本学会では、鏡視下手術の導入に際し陥りやすいpitfallとそれに対するbailoutの方法など、エキスパートからビデオを用いて詳細な発表をしていただきたい。
36 食道胃接合部癌に対する再建手術の最適化と工夫

食道胃接合部癌の切除後再建方法には、空腸間置、上川法、SOFY法などの様々な吻合法が試みられているが、胃の切除範囲や郭清度に応じてどの再建方法が最適なのかについては一定の見解は得られていない。各施設での経験や治療成績をもとに、再建方法の選択基準や手術技術の工夫、術後管理のポイントなどについて議論いただきたい。
37 食道亜全摘後、胃管以外による食道再建:
空腸再建か大腸再建か?

空腸再建か大腸再建か?
食道亜全摘後の食道再建には、胃管が使用できない場合、小腸や大腸を再建臓器として用いる。しかし、これらの再建方法の長期的な有効性や安全性については、まだ十分に検証されていない。各施設における、食道亜全摘後に小腸再建あるいは大腸再建を行った症例の臨床データから、再建方法による術後合併症発生率や栄養状態、食事摂取量、体重変化、QOL、消化管運動器脳等の違いに基づき、胃管以外の選択肢として、大腸再建あるいは小腸再建のどちらが望ましいのか議論いただきたい。
38 進行胃癌に対する術前化学療法のUp to date

進行胃癌に対する術前補助化学療法は、根治的手術を目指す重要な治療選択肢だが、現在のエビデンスは限定的であり、特に大型3型・4型胃癌やbulky N2胃癌において有効性が示唆されているに留まる。一方、手術による根治性向上がほぼ限界に達している状況において、化学療法による腫瘍縮小後に根治切除を目指すConversion手術は新たな治療戦略として期待されている。各施設での術前補助化学療法やConversion手術の治療成績をご発表いただき、進行胃癌に対する術前化学療法の現状と展望について議論いただきたい。
39 食道癌に対する集学的アプローチ:食道癌治療の最前線

食道癌治療における集学的アプローチにより予後改善と生活の質の向上が得られている。最新のガイドラインでは、cStageII、III食道癌に対してDCF3剤併用術前化学療法が強く推奨されており、手術後には免疫チェックポイント阻害薬による術後補助療法が推奨されている。また、FP療法と放射線照射を組み合わせた化学放射線療法も食道がん治療の重要な役割を果たす。これらの集学的アプローチは食道癌の治療戦略において今後のさらなる進展が期待されている。各施設より食道癌に対する集学的アプローチによる臨床データをご発表いただき、最前線の食道癌治療について議論いただきたい。
40 大腸癌肝/肺転移例の治療戦略

多発肝転移and/or肺転移症例を有する大腸癌に対しては、Up front surgeryか抗癌剤治療後に手術か、一期的切除か二期的切除か、未だに議論があるところである。そこで、各施設の最新のデータを元に適切な治療戦略を議論していただきたい。
41 結腸癌に対するロボット支援手術と腹腔鏡手術の今後

ロボット支援手術の保険適用が、結腸癌にも拡大され、すべての大腸癌患者に対してロボット手術が行われるようになった。今後、ロボット支援結腸切除は腹腔鏡手術を超えていくのか?すべての大腸外科医にその技術は必要か?各施設のデータを示し、議論していただきたい。
42 下部進行直腸癌に対する術前治療と術前治療奏功例に
対する治療方針について

対する治療方針について
近年、下部進行直腸癌に対して欧米に準じた術前治療を行う施設が増加している。術前治療の内容は各施設様々であり、また術前治療奏功例に対し根治手術を行うか、手術を行わず経過観察するかといった治療方針も様々である。各施設の治療成績から、術前治療の工夫と術前治療奏功例に対する治療方針について報告していただきたい。
43 下部直腸腫瘍に対する術式選択
―肛門温存術か直腸切断術か?―

―肛門温存術か直腸切断術か?―
下部直腸腫瘍に対する術式には、低位前方切除術やISRなどの肛門温存術と直腸切断術がある。肛門温存術では、永久ストーマを回避することができるが、低位前方切除後症候群と呼ばれる排便障害を生じることが多く、それによるQOLの低下が問題である。そこで、ISRを積極的に行っている施設と、直腸切断術が比較的多い施設に、自施設での直腸腫瘍全体に対する各術式の割合、その術式の選択方法、肛門温存術後患者の低位前方切除後症候群の頻度、重症度、QOL及び直腸切断術後患者のストーマ関連合併症の頻度、重症度、QOL等を発表していただいた上で、どのような患者にどちらの術式を勧め、それをどのように決定するべきなのかを議論していただきたい。
44 大腸癌腹膜播種に対する治療戦略

ステージIV大腸癌において腹膜播種を有する患者の予後は他の転移様式と比べて悪い傾向にある。この病態に対し、欧米では古くからcytoreductive surgery (CRS)+ hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) が施行されており、本邦でも切除可能な大腸癌腹膜播種に対して積極的切除が推奨されている。しかし、他の治療法との比較試験は少なく、外科的切除の有用性に関する明確なエビデンスは存在しない。本セッションでは、大腸癌腹膜播種に対する治療の現状を整理し、今後の方向性について議論していただきたい。
45 鼠径ヘルニアに対する術式の選択と術後成績

鼠径ヘルニアに対する術式は数多く存在し施設によって、施設や術者によって標準術式が異なっているのが現状である。また、ロボット支援ヘルニア修復術も保険適用が検討されている。そこで、鼠径ヘルニアに対する各施設の標準術式と成績を映像等を用いて示していただき、安全で再発の少ない術式について議論していただきたい。
46 肝門部領域胆管癌手術における断端評価

肝門部領域胆管癌はR0切除が唯一の根治的治療法であり、胆管断端の癌遺残は予後不良因子である。断端陰性確保するため、これまで広範囲肝切除、血管合併切除、膵頭十二指腸切除併施など侵襲度の高い術式が選択されてきたが、現在は根治性と安全性のバランスを考えた術式選択が行われている。癌の水平方向進展度を正しく評価することは、切除範囲の決定や予後を予測する上で依然として重要なテーマである。本セッションでは、術前の断端評価における各種画像診断の役割と最適な組み合わせ、Mapping生検、術中迅速病理診断の結果を実際の手術現場でどう反映させるかに関して総合的に議論していただきたい。
47 切除境界胆道癌を定義する

膵臓癌、肝細胞癌では既に切除可能性分類が行われ、治療成績向上をめざした取り組みが行われているが、膵臓と肝臓に挟まれてた胆道では、その取り組みはまだ道半ばである。胆道癌(胆管癌、胆嚢癌)では、切除可能性を評価するための因子が多数存在するため、切除可能・不可能の境界は施設毎に異なっているのが現状である。本セッションでは、切除可能性を分類するための因子(肝予備能、動脈浸潤など)を明らかにし、各施設の切除可能と切除不能胆道癌の共通項を明らかにすることで切除境界胆道癌を考えていきたい。
48 大動脈瘤に対するステントグラフト治療の現状と展望

大動脈瘤患者に対する血管内治療はその低侵襲性から増加の一途をたどっているが、合併症や長期成績、再治療介入などの問題点も残っている。本セッションでは胸部・腹部大動脈瘤に対するステントグラフト治療の最新の動向、教育面での課題、今後の展望について議論していただきたい。
49 難治性気胸の治療戦略

高齢化とともに、間質性肺炎やCOPDなどに合併した難治の気胸を経験することが多くなった。手術時の肺瘻制御の工夫、胸膜癒着術や気管支塞栓療法など難治性気胸の治療戦略について議論していただきたい。
50 小児内視鏡手術の功罪ー中・長期成績からみた課題

近年、小児外科領域でも内視鏡手術が広く行われ、短期的には、非侵襲的で回復期間が短く、入院期間が縮小されるなど、多くの利点が報告されている。しかし、中・長期の成績に関しては、手術後のフォローアップが不十分であることもあり、十分な検討がなされていないと思われる。このセッションでは、中・長期の成績を踏まえて小児内視鏡手術の功罪を総合的に検討していただきたい。
51 生体ドナーの術後合併症と長期予後

生体移植実施にはドナーの存在は不可避であるが、健常人にメスを入れるという特殊な医療形態をとるため、生体ドナーの安全性の確保は生体移植において最優先事項である。しかしながら、その術後合併症や長期予後についての報告は少ない。そこで、各施設の経験や長期的なフォローアップデータを基にして、安全性の高い生体ドナー管理について議論していただきたい。
52 神経内分泌腫瘍肝転移の新しい治療戦略

NENの肝転移は高率に再発ことが知られている。エベロリムス、スニチニブ、ストレプトゾシン、ランレオチド、放射性核種標識ペプチド治療と様々な治療薬の登場により、肝切除の役割はこれまでと大きく変化している。セッションでは、今後の肝切除の役割に関して議論していただきたい。
53 根治切除不能消化器癌への挑戦
ー薬物療法と手術療法のベストコラボレーションとは?ー

ー薬物療法と手術療法のベストコラボレーションとは?ー
近年、奏効性の高い新規抗腫瘍薬の登場によって、元来、根治切除不能であった進行癌症例に対してConversion surgeryが施行され、良好な治療成績が得られるようになってきている。しかし、その適応、手術方法、さらには目的そのものが、原発の癌種や転移様式、臓器によって多様であるのが実情である。本セッションでは、様々な消化器癌におけるいわゆる”Conversion surgery”の現状と成績を検討し、その概念を整理するとともに、転移を有する高度進行消化器癌に対する薬物療法と手術療法の最善の組み合わせについて臓器横断的な観点から改めて考えていただきたい。
54 癌に対する外科的治療において
リンパ節郭清はどこまで必要なのか?

リンパ節郭清はどこまで必要なのか?
一定の割合でリンパ節転移の可能性のある癌に対しては、clinical N0でも定型的リンパ節郭清を伴う根治手術を行うことが長い間外科の常識として考えられてきた。しかし、乳癌における腋窩郭清や口腔癌における頸部郭清などに代表されるように、長期予後やQOLの観点から予防的リンパ節郭清は省略されるケースも増えてきつつある。また、近年、リンパ節の切除ががんに対する免疫応答を低下させ、宿主には悪影響を与える可能性があるという基礎的データも報告されてきている。これらのことを踏まえて、様々ながん種における定型的リンパ節郭清の臨床的意義について再検討していただきたい。
55 GIST克服に向けた最新の治療戦略

GIST診療ガイドライン第4版およびWeb改訂版では、外科領域では大型GISTに対するイマチニブによる術前補助療法について、内科領域では新たに承認されたHSP90阻害剤ピミテスピブの4次治療としての位置づけについて、病理診断領域では遺伝子型の分類や鑑別診断の方法についてそれぞれ明記された。これら新しい知見に基づき、各施設でGISTに対してどのような治療戦略をとっているのか、またその治療成績について論じていただきたい。
56 鏡視下結腸切除における体腔内吻合の工夫

鏡視下結腸切除における体腔内吻合を行う施設が増加している。一言に体腔内吻合と言ってもデルタ吻合、機能的端端吻合、オーバーラップ法など施設により吻合法が異なっている。各施設の吻合の工夫と術後短期成績を提示していただき体腔外吻合に対する体腔内吻合の有用性を示していただきたい。
57 ロボット支援肝臓切除術の展望

肝胆膵外科領域のロボット支援手術は、膵臓領域が先行し、肝臓領域は実施施設がまだ少ない。肝離断法は、今のところClamp crush法に留まる。肝離断では、切離面に沿って断続的に微妙なTensionをかけて離断を進めることが重要だが、開腹手術や腹腔鏡手術で術者と助手が織りなす術野展開と比較するとまだ不十分である。コストの問題も不透明である。今後、術野展開の工夫、デバイスの開発・革新が期待されるが、ロボット支援肝切除の真のメリットはどこにあるのか?現況と問題点を明らかにし、今後の展望などに関して広く議論したい。
58 ロボット支援膵切除術の展望

ロボット支援膵切除は手術時間が長く、出血量が少ないところに特徴がある。リアルワールドデータを持ちより、手術時間、出血量、術後膵液瘻、手術コスト等を比較し、ロボット支援膵切除の立ち位置を明らかにしたい。ロボット支援膵切除の普及を考えるうえで、コストに見合ったメリットが何処にあるのか?開腹、腹腔鏡、ロボットはどのように使い分けるのか?術者養成のための教育体制は?等を議論したい。
59 乳癌オンコプラスティックサージャリーの工夫

乳癌手術において根治性と整容性を追求するオンコプラスティックサージャリーの重要性は益々増加しつつある。再建術の時期や方法なども含めて、各施設での工夫、ピットフォールなどについてビデオを用いて発表していただき、その内容について討議していただきたい。
60 進行胃癌における審査腹腔鏡手技と評価法の工夫

進行胃癌の術前診断における審査腹腔鏡の有用性は認められているが、手技や術前画像診断との一致性にはばらつきがある。診断率を高めるためには、手技の標準化や新しい技術やアイデアの導入が必要である。各施設における漿膜浸潤胃癌に対する播種評価の精度を高めるための手技や工夫、術前画像診断との一致性向上に向けた取り組み等について発表いただきたい。
61 食道癌ロボット支援手術の現在と今後の展望

食道癌に対するロボット支援手術は2018年4月より保険適用となり、手術数が急速に増加している。ロボット支援手術は、従来の胸腔鏡下手術に比べて、より精密で低侵襲な手術が可能となり、術後の合併症の減少に寄与する可能性が示唆されている。しかし、ロボット支援手術の普及にはコストや術者の訓練などの課題もある。各施設における食道癌ロボット支援手術の治療成績を示していただき、さらなる普及と手術成績の向上を得るための今後の課題についても論じていただきたい。
62 若年大腸癌に対する診断と治療

欧米での報告では結腸癌、直腸癌共に39歳以下で増加傾向を示している。本邦でも同様な傾向にあるのか?各施設で診断治療を行った39歳以下の若年大腸癌の治療成績を提示していただき、本邦の若年大腸癌の特徴について議論していただきたい。
63 腹壁瘢痕ヘルニアに対する術式の選択と術後成績

近年、腹壁瘢痕ヘルニアに対する根治手術においても腹腔鏡下での修復術が普及し、ロボットプラットフォームの導入も行われてきつつある。しかし、その適応や手技に関しては症例ごとに大きく異なっており、一定の見解は得られていないのが現状である。そこで、腹壁ヘルニアに対する各施設の術式と長期成績を用いて示していただき、安全で再発の少ない修復術の在り方について議論していただきたい。
64 切除不能膵癌に対する新規治療法の試み

切除不能膵癌(Unresectable; UR)には局所進行(LA)と遠隔転移(M)がある。UR膵癌は全身病であり化学療法を中心とした全身的な治療が必須である。UR-LA膵癌では、ときに局所制御のために放射線療法を加えConversion surgeryへ持ち込む症例もある。一方、UR-M膵癌では、適切なタイミングで遺伝子検査を行い治療介入できるようにすることが特に重要である。また、腹膜播種を伴うUR-M膵癌では、腹膜治療が新たな選択肢として注目されている。本セッションでは、UR膵癌に対する新規治療法や治療戦略に関して広く議論を行いたい。
65 肝胆膵外科の術後合併症にどう対処するか

肝胆膵外科手術において、術後合併症の予防や治療法は重要である。近年の患者高齢化に伴い、周術期管理に難渋するケースも増えてきた。肝胆膵外科術後合併症にどう対処すべきか、その予防法や治療法について最新のデータを発表いただきたい。
66 遺伝性乳癌に対する取り組み

遺伝性乳癌に対する治療戦略や検査システムの最新動向、患者と家族への情報提供やカウンセリングの役割などを発表していただき、異なる専門家や関係者が交流できるプラットフォームを提供していただきたい。
67 AYA世代乳癌患者について考える

AYA世代の乳癌患者は、がん治療に伴う妊孕性の低下、家庭や仕事を含む社会生活の問題に加え、遺伝的素因なども含めた長期的な健康管理に対応する必要があり、専門的なアプローチと支援の連携が求められる。各施設での取り組みについて発表し、患者と家族が包括的かつ効果的なケアを受けられるような具体策を考えていただきたい。
68 内視鏡下甲状腺手術の工夫

整容性に優れた内視鏡下甲状腺手術(VANS法)が保険適用になってから数年が経過し、希望する患者や導入する施設が増えてきている。また、海外では口腔内からの操作で手術を行う経口法内視鏡下甲状腺手術(TOETVA法)が普及してきている。内視鏡下の甲状腺手術に関する各施設での取り組みや教育面での配慮について発表していただきたい。
69 Frozen elephant trunkの現状と未来

人工血管とステントグラフトを組み合わせたハイブリッド型のデバイスを用いた血管内治療は、弓部大動脈瘤や解離に対して低侵襲かつより短時間で治療できるという点から本邦でも普及しつつある。Frozen elephant trunkに関する各施設での治療経験と課題を発表し、今後の展望について議論していただきたい。
70 肺癌に対するロボット支援手術と胸腔鏡下手術

肺癌に対する低侵襲手術としてロボット支援手術や単孔式胸腔鏡下手術など新たな術式が近年急速に普及している。各施設における手術の工夫や安全確保のための方策について議論していただきたい。
71 小児移植の現状と今後の展望

小児移植は生命を救う重要な治療法であるが、ドナーの確保が困難で、臓器の適合性に伴う供給不足が問題である。また、移植後の免疫抑制療法による感染症や副作用のリスク、患者の成長に伴う移植臓器の適合性や機能の維持も大きな課題である。これらの問題を克服するためには、臨床、倫理、法的側面を含む多角的なアプローチが必要となる。小児移植の発展に向けた具体的な対策について議論していただきたい。
72 悪性腹水に対するCARTの実用性

癌性腹膜炎に伴う悪性腹水はPSの低下による化学療法の中止を余儀なくされ、患者予後の悪化に直結する。大量腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法(CART)は本邦発の治療法であり、症状緩和に有用とされているが、近年、腹水が制御できたケースに積極的治療を導入することで癌性腹膜炎患者の予後向上にもつながることが示唆されてきている。癌性腹水に対する各施設でのCARTの経験を発表して、その臨床的意義を検討していただきたい。
73 外科診療における運動と栄養の意義

周術期栄養管理は創傷治癒の促進や免疫機能の維持に寄与し、運動療法は心肺機能の維持や術後ADLの回復が期待される。推奨される栄養療法や運動療法は、患者の低栄養はサルコペニア、フレイルなど患者ごとに考慮する必要があるが、術後合併症の軽減や入院期間短縮に寄与することが知られている。エビデンスに基づいた周術期管理法を集学的に行うERASも本邦独自の発展も遂げており、患者の術後回復促進につながるプレリハビリテーションを中心に施設において取り組まれている周術期管理について討論していただきたい。
74 高齢患者に対する周術期管理

本邦は超高齢社会に突入し、外科診療においても絶大な影響を及ぼしている。高齢者診療においては多様な併存症、サルコペニア・フレイルによる身体機能低下や低栄養、さらには家庭環境も考慮する必要がある。高齢者に対する外科診療は多職種による統合的なアプローチが必要で、かつテイラーメイドな周術期管理が重要と考えられる。本セッションでは、高齢者に対して行なっている周術期管理の取り組みについて、各領域から広くご発表いただきたい。
75 外科領域におけるLiquid Biopsy の臨床応用

CTC、ctDNA、exosome、miRNAなどを対象としたリキッドバイオプシーは、非侵襲かつがんのダイナミクスを良好に反映するため、がん患者の早期発見や治療のモニタリング、補助療法の適応判断などの分野で臨床応用が進んできている。外科領域におけるリキッドバイオプシーの最新のトピックや臨床応用の実際について発表していただきたい。
76 非開胸縦郭アプローチによる食道癌手術の展開

食道癌治療における最新の進歩として、非開胸縦郭アプローチが注目されている。この術式は、従来の開胸手術に比べて患者の身体的負担を軽減し、回復期間の短縮が期待されている。各施設での非開胸縦郭アプローチを用いた食道がん手術手技を中心にビデオで供覧していただき、あわせて適応基準や治療成績、患者QOLへの影響、その臨床的有効性等について発表いただきたい。
77 ロボット支援胃切除術のトラブルシューティング

ロボット支援手術は、精密さと効率性を高めることで、外科医療の新たな地平を切り開いている。ロボット支援胃切除術は、その有効性が期待されている一方で、腹腔鏡手術とは異なるトラブルの発生も指摘されている。ロボット支援胃切除術における具体的なトラブル事例を共有し、それらに対する効果的なトラブルシューティング方法を示していただきたい。また、手術手技の安全性を向上させるための工夫や、ロボット支援胃切除術の今後の展望についても論じていただきたい。
78 急性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除の工夫

急性虫垂炎に対しても腹腔鏡手術が標準治療となりつつある。腹腔鏡下虫垂切除といってもその手技は施設によって様々である。各施設の手技と成績を供覧いただき、安全で安価で若手医師が会得しやすい手技について議論していただきたい。
79 呼吸器外科における再手術の工夫

区域切除の増加に伴い、同一肺葉の再発や第二癌に対する手術の増加が見込まれる。また、薬物療法や放射線治療が困難または奏功しない症例に対して残肺全摘が必要になることもある。これらの手術は高度な癒着に難渋することも多く、中枢の血管や気管支の処理などについて議論していただきたい。
80 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術(LPEC)の現状と課題

小児鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術(LPEC法)は、安全性が高く腹腔内の観察や処置が容易であることなどの利点から、現在、標準手術として全国の施設で取り入れられてきている。一般病院での経験や問題点を発表していただき、適応年齢や他疾患への適応も含めてLPEC法の今後の方向性を討論していただきたい。
要望演題(口演)
- 安全な食道切除・再建の工夫
- 胃がん肝転移に対する治療選択
- CY1胃がんの治療戦略
- 残胃がんの治療戦略
- 食道良性疾患に対する低侵襲手術
- 胃・食道がんに対する免疫チェックポイント阻害剤の治療成績
- 低侵襲胃がん手術のトラブルシューティング
- 高度肥満症に対する外科手術の工夫
- 虫垂炎治療:待機手術vs早期手術
- 大腸がんに対するステント治療の有用性
- 遺伝性大腸がんに対する診療上の問題点
- 消化管手術における最適な人工肛門
- NOMIの診断と治療
- 広範囲小腸切除後の短腸症候群に対する治療・管理での工夫
- 潰瘍性大腸炎に対する手術手技
- クローン病に対する手術手技
- 低位前方切除後症候群の現状と対策
- 排便障害の診断と治療
- 腹膜偽粘液腫の治療
- 安全性を追求した急性胆嚢炎に対する治療ストラテジー
- 肝胆膵外科手術における術中超音波検査の有用性
- 地域医療を支える肝胆膵外科:少ない医療資源でどこまで対応すべきか?
- 重症急性膵炎における外科的ドレナージ・ネクロゼクトミーの成績
- 慢性膵炎に対する外科治療の適応と成績
- 膵がんの遠隔転移に対する外科治療
- 進行がん合併例における心臓血管外科手術
- 急性大動脈症候群の治療成績向上に向けての提言
- 肺がんに対する区域切除の工夫と課題
- 呼吸器外科領域におけるロボット支援手術のトラブルシューティング
- 縦隔腫瘍に対するロボット支援及び胸腔鏡下手術の現状と課題
- 異時性及び同時性多発肺がんに対する治療戦略
- He2陽性に対する乳がん治療
- BRCA異常にまつわる基礎と臨床
- 高齢乳がん患者への治療マネジメント
- 乳腺領域における地域医療体制
- 乳がん術後局所合併症(感染、血腫など)のマネジメント
- 甲状腺がんにおけるプレシジョンメディシン
- 重症心身障碍者の外科治療
- 小児外科疾患の成人移行支援
- 稀な内ヘルニアの治療経験
- 鼠径部嵌頓ヘルニアに対する治療戦略
- 超高齢者の外科治療
- 各領域におけるSSI対策
- 経済面からみたロボット手術
- 周術期口腔ケアの意義
- 外科領域における院内感染チーム(AST)の活躍
- 移植術後管理におけるポイント
- 消化器手術におけるERAS
- 日帰り手術の適応と問題点
- 外傷診療における克服すべき課題
- 外科医が行う外来化学療法の問題点
- 外科医が関与する緩和医療の問題点
- 医師の働き方改革:自己研鑽とは何か?
- 医師の働き方改革:ICTの活用
- 医師の働き方改革:タスクシフティングの工夫
- 医師の働き方改革:ワークライフバランスの変化
- 医師の働き方改革:医療安全上の工夫
- 医師の働き方改革:研究環境はどう変化したか?
- 地域医療を支える外科医の確保に何が必要か
- クリニカルパスと地域連携パスの進展
- 内視鏡外科手術教育への取り組み
上部消化管
下部消化管
肝・胆・膵
心臓血管
呼吸器
乳腺内分泌
小児
ヘルニア
領域横断
働き方改革
その他
要望演題(ビデオ)
- 噴門側胃切除後の再建法の工夫
- 大動脈食道瘻、大動脈十二指腸瘻の治療の工夫
- 難治性痔瘻に対する治療のアプローチ
- 直腸脱の手術手技
- ロボット支援直腸がんに対する側方郭清
- 胆嚢がんに対する腹腔鏡下手術:適応と手術手技
- 肝細胞がんに対するコンバージョンサージェリー
- 腹腔鏡下(ロボット支援)膵切除術におけるpitfallと対処法
- 腹腔鏡下(ロボット支援)肝切除術におけるpitfallと対処法
- 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の私の工夫
上部消化管
下部消化管
肝・胆・膵
ヘルニア
一般演題(口演・ポスター)
カテゴリーA(臓器別等分類)、カテゴリーB(分野別分類)、カテゴリーC(症例報告か否か)よりそれぞれ該当するものを選択してください。
研修医セッション・学生セッション ※Awardあり
本セッションの趣旨は、若手医師(初期臨床研修医)の発表修練の場とすることです。
初期臨床研修医の皆様が学んだ症例、研究成果について積極的に発表・討論を行っていただく機会を与えるとともに、優秀な演題について表彰を行うことにより、さらに外科への興味をもっていただくことを目的に、本学術集会ではこのセッションを重要視しています。
基礎はもとより臨床研究を含め、結果には至らない中間報告、経験報告でも結構ですので、多くの応募を期待します。
【研修医セッション・学生セッション 応募資格】
応募時点で医学生もしくは医師免許取得後2年目以内の初期臨床研修医であれば、日本臨床外科学会会員でなくても応募可能です。
「研修医セッション」を選択いただいた場合には、医師免許取得年をご記入いただきます。
医学生の場合は「000000」とご記入ください。
その他、演題登録に関する規定等は下記、演題募集要項をご参照ください。
文字数制限
演題名:全角換算90文字以内
抄録本文(日本語):全角換算600文字以内
※上記の文字数を超えると登録できません。
共同演者・所属機関の登録
共同演者ならびに所属機関は筆頭演者を含めて15件まで登録できます。
利益相反状態(COI)の自己申告
演題登録時、UMINオンライン演題登録システムにて、演者全員(筆頭、共著)の利益相反状態(COI)について申告していただきます。
自己申告が必要な期間は、演題登録日からさかのぼって3年間となります。
また、学術集会での発表時にも、演題登録日の3年前から発表日までの期間について、自己申告が必要となります。
利益相反状態(COI)の自己申告についての詳細はこちらをご確認ください。
受領通知
演題登録完了後、入力した電子メールアドレス宛に確認のメールが自動配信されますので、必ず内容をご確認ください。
はがき等での通知は行いませんので、ご了承ください。
確認のメールが届かない場合は、電子メールアドレスが間違って入力されている可能性がありますので、確認・修正画面から正しく登録されているかをご確認ください。
※Gmailなどのフリーメールでご登録いただいた際には、演題登録完了後の自動返信メールが届かない場合がございます。必ず、登録時に表示される演題番号を手元に控えるようお願いします。
演題採否
演題採否は第86回日本臨床外科学会学術集会事務局により決定いたします。
演題申込の分野などに関しましては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
演題採否ならびに発表日時・会場は、9月上旬頃にご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。
登録画面
◎暗号通信
◎平文通信
※暗号通信が使えない場合にのみ以下をご利用ください。
演題登録に関するお問合せ
第86回日本臨床外科学会学術集会 運営事務局
jsa2024-abs@congre.co.jp