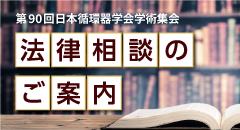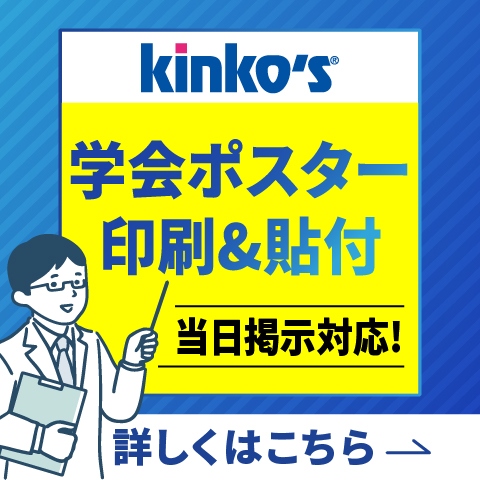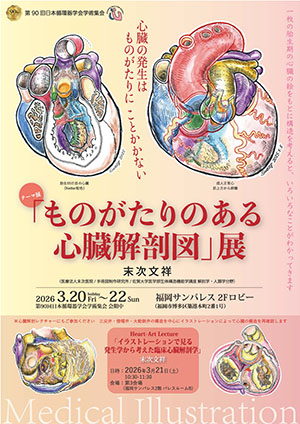|
| |
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~14:25 第5会場(福岡国際会議場3Fメインホール) |
|
| Statin Pleiotropy: from Endothelial Function to Immune Modulation |
|
|
|
| 演 者: |
James K. Liao
| ( |
University of Arizona, College of Medicine, USA) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)14:20~15:05 第5会場(福岡国際会議場3Fメインホール) |
|
| Pioneering the Future of Medicine through the Expansion of Physical AI into the Medical Field |
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:10 第5会場(福岡国際会議場3Fメインホール) |
|
| Chuichi Kawai MD: Distinguished Global Leader in Cardiovascular Disease |
|
|
|
| 演 者: |
Sidney C. Smith
| ( |
University of North Carolina, USA) |
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:40~9:10 第1会場(福岡サンパレス2F大ホール) |
|
| 日本循環器学会はどのようにあるべきか |
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)14:30~15:10 第5会場(福岡国際会議場3Fメインホール) |
|
| 社会を拓く新循環器学 |
|
| 座 長: |
堀 正二
| ( |
大阪国際がんセンター名誉総長、大阪大学 名誉教授) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:20~10:05 第1会場(福岡サンパレス2F大ホール) |
|
|
|
| Healthcare infrastructure in the AX era |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)10:10~11:10 第1会場(福岡サンパレス 2F大ホール) |
|
|
|
| 夢みる力が「気」をつくる~ななつ星への道~ |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:25 第1会場(福岡サンパレス 2F大ホール) |
|
|
|
| 再生心筋細胞移植による重症心不全治療(LAPiS試験)の成績と今後の心不全治療の方向性 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
福田 恵一
| ( |
慶應義塾大学 名誉教授 / Heartseed株式会社 代表取締役社長) |
|
|
|
| ディスカッサント: |
波多野 将
| ( |
東京大学医学部附属病院 高度心不全治療センター) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)14:35~15:20 第1会場(福岡サンパレス 2F大ホール) |
|
|
|
| Mitochondrial Dynamics in Protecting Cellular and Tissue Functions |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~18:10 第5会場(福岡国際会議場3Fメインホール) |
|
|
|
| AI × 脳科学からみる近未来 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)11:00~12:00 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
| Dynamics of Function and Regulation of the Endoplasmic Reticulum |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Brigham and Women’s Global Peer Session, The Cutting Edge of Cardiology Research (Part1) |
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~11:30 第5会場(福岡国際会議場3Fメインホール) |
|
|
|
| Clonal hematopoiesis of indeterminate potential, a recently recognized cardiovascular risk factor |
|
|
|
| 演 者: |
Peter Libby
| ( |
Heart and Vascular Institute, Mass General Brigham Hospital, USA) |
|
|
|
|
|
|
Brigham and Women’s Global Peer Session, The Cutting Edge of Cardiology Research (Part2) |
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| 座 長: |
Peter Libby
| ( |
Heart and Vascular Institute, Mass General Brigham Hospital, USA) |
|
|
| |
福本 義弘
| ( |
久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
Raffaele De Caterina
| ( |
University of Pisa, Italy) |
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~11:30 第3会場(福岡サンパレス 2F パレスルーム B) |
|
|
|
| イラストレーションで見る 発生学から考えた臨床心臓解剖学 |
|
|
|
| 演 者: |
末次 文祥
| ( |
末次医院 循環器内科・心臓血管外科 / 佐賀大学生体構造機能学解剖学・人類学講座分野) |
|
|
|
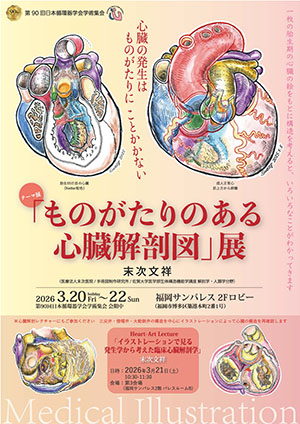 |
|
| ※ |
会期中、原画展も開催いたします。 |
| 【 |
特別企画 心臓イラストレーション原画展】
『ものがたりのある心臓解剖図』展 ~心臓の発生はものがたりにことかかない~
[作成者]末次 文祥 [展示期間]3月20日(金・祝)~22日(日)
[展示場所]福岡サンパレス 2 階ロビー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40-11:10 第9会場(福岡国際会議場 2F 204) |
|
|
|
冠微小循環障害
Coronary Microvascular Dysfunction |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Filippo Crea
| ( |
Gemelli Isola Hospital, Italy) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
Filippo Crea
| ( |
Gemelli Isola Hospital, Italy) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
心室不整脈アブレーション新時代
Future Perspective for Catheter Ablation for Ventricular Arrhythmia |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Pramesh Kovoor
| ( |
Westmead Hospital, University of Sydney, Australia) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
Pramesh Kovoor
| ( |
Westmead Hospital, University of Sydney, Australia) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
HFpEFの基礎研究と治療開発の最前線
Frontiers in Basic Research and Therapeutic Development for HFpEF |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Gabriele G. Schiattarella
| ( |
Charité-Universitätsmedizin Berlin & Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Germany) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
Gabriele G. Schiattarella
| ( |
Charité-Universitätsmedizin Berlin & Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Germany) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
佐藤 迪夫
| ( |
熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝・循環医学分野 分子遺伝学講座) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
血管炎の診断・治療の最前線
Advances in the Diagnosis and Treatment of Vasculitis |
|
| 座 長: |
前嶋 康浩
| ( |
獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
浅野遼太郎
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 血管生理学部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
岩倉 具宏
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 心臓血管外科) |
|
|
| |
新井真理奈
| ( |
東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
EFのカットオフ値再考―3学会合同ステートメントからひもとく次世代の心不全治療
Reconsidering EF Cutoff Values: The Next Generation of Heart Failure Treatment Unraveled from the Joint Statement of Three Academic Societies |
|
| 座 長: |
|
|
| |
John R. Teerlink
| ( |
School of Medicine, University of California San Francisco, USA) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
John R. Teerlink
| ( |
School of Medicine, University of California San Francisco, USA) |
|
|
|
| 演 者: |
坂田 泰彦
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 臨床研究開発部・心臓血管内科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
右心不全の基礎から臨床
From Basics to Clinical Practice in Right Heart Failure |
|
| 座 長: |
|
|
| |
福本 義弘
| ( |
久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
中岡 良和
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター研究所 血管生理学部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
Lp(a)研究の最前線
Frontiers in Lp(a) Research |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Kausik K Ray
| ( |
School of Public Health, Imperial College London, UK) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
Kausik K Ray
| ( |
School of Public Health, Imperial College London, UK) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
吉田 雅幸
| ( |
東京科学大学大学院 先進倫理医科学分野・遺伝子診療科) |
|
|
| |
木庭 新治
| ( |
昭和医科大学医学部 内科学講座・循環器内科学部門) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
Pulsed Field Ablation (PFA) が切り拓く新時代の心房細動治療
Pulsed Field Ablation: Ushering in a New Era of Atrial Fibrillation Therapy |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Boris Schmidt
| ( |
Cardioangiologisches Centrum Bethanien, Germany) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
Boris Schmidt
| ( |
Cardioangiologisches Centrum Bethanien, Germany) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
循環器病学におけるAIの進化と生成技術の活用
Advances in AI and the Use of Generative Technology in Cardiology |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Chia-Ti Tsai
| ( |
Internal Medicine, National Taiwan University Hospital, Taiwan) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
Chia-Ti Tsai
| ( |
Internal Medicine, National Taiwan University Hospital, Taiwan) |
|
|
|
| 演 者: |
塚田(哲翁)弥生
| ( |
日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科) |
|
|
| |
佐橋 勇紀
| ( |
Department of Cardiology, Cedars-Sinai Medical Center, USA) |
|
|
| |
岸 拓弥
| ( |
国際医療福祉大学 大学院医学研究科循環器内科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
冠動脈の石灰化病変(石灰化結節)に対する対応
Management of Coronary Calcified Lesions: Focus on Calcified Nodules |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
籔本 直也
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科) |
|
|
| |
|
|
| |
邑井 洸太
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科) |
|
|
| |
藤野 明子
| ( |
独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 循環器内科) |
|
|
| |
田中 穣
| ( |
医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 循環器内科) |
|
|
| |
中原 嘉則
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 心臓血管外科) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10-17:40 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
Low-risk ASに対するSAVRとTAVRの現在地
Current Perspectives on SAVR and TAVR for Low-Risk Aortic Stenosis |
|
|
|
| 演 者: |
谷口 智彦
| ( |
神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科) |
|
|
| |
岡田 厚
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門) |
|
|
| |
樋口 亮介
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科) |
|
|
| |
山本 真功
| ( |
医療法人澄心会豊橋ハートセンター 循環器内科) |
|
|
| |
平岡 有努
| ( |
社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 心臓血管外科) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
Fontan術後遠隔期の肝臓病変を考える
Fontan Circulation: Current Understanding and Management of FALD |
|
| 座 長: |
大内 秀雄
| ( |
国立循環器病研究センター 成人先天性心疾患センター) |
|
|
| |
考藤 達哉
| ( |
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 肝炎・免疫研究センター) |
|
|
|
| 演 者: |
岩切 泰子
| ( |
Department of Internal Medicine, Section of Digestive Diseases, Yale School of Medicine, USA) |
|
|
| |
大内 秀雄
| ( |
国立循環器病研究センター 成人先天性心疾患センター) |
|
|
| |
考藤 達哉
| ( |
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 肝炎・免疫研究センター) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
心血管系における細胞間コミュニケーションとマルチオミックス
Multiomics View of Cardiovascular Cellular Communication in Health and Disease |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Cameron S. McAlpine
| ( |
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
Cameron S. McAlpine
| ( |
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
江本 拓央
| ( |
神戸大学医学部 内科学講座 循環器内科学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
大石 由美子
| ( |
東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 病態代謝解析学(生化学)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
循環器疾患管理と遠隔診療
Cardiovascular Disease Management and Telemedicine |
|
| 座 長: |
|
|
| |
三浦 弘之
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
本田 怜史
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科) |
|
|
| |
|
|
| |
中山 敦子
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科) |
|
|
| |
三浦 弘之
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
新時代を迎えたcardiac replacement therapy ―心臓移植とDTの未来
Cardiac Replacement Therapy in the New Era- What Will We See in Heart Transplantation and Destination Therapy? |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Nir Uriel
| ( |
Columbia University, USA) |
|
|
|
| State-of-the-art: |
Nir Uriel
| ( |
Columbia University, USA) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
竹中 秀
| ( |
北海道大学大学院医学研究院 循環器内科学教室) |
|
|
| |
塚本 泰正
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 移植医療部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
心臓CTの新時代 -AI診断と次世代技術の未来を探る―
A New Era of Cardiac CT: Exploring the Future of AI Diagnosis and Next-Generation Technologies |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第2会場(福岡サンパレス 2F パレスルーム A) |
|
|
|
三尖弁閉鎖不全を多角的に検討する。~いつ、どのように治療するのがベストか?~
Multidisciplinary review of tricuspid insufficiency: When and how best to treat? |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
前川原慧則
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科) |
|
|
| |
北村 光信
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第3会場(福岡サンパレス 2F パレスルーム B) |
|
|
|
心筋症診療の新展開
New Developments in the Diagnosis and Treatments of Cardiomyopathy |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
金岡幸嗣朗
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 情報利用促進部) |
|
|
| |
|
|
| |
吉田 善紀
| ( |
京都大学iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第7会場(福岡国際会議場 2F 202) |
|
|
|
急性期脳梗塞救急診療の最新の進歩を多角的に解析する
Analyzing the Latest Advances in Emergency Treatment for Acute Ischemic Stroke |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
原 正彦
| ( |
島根大学大学院医学系研究科 地域包括ケア教育研究センター) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第9会場(福岡国際会議場 2F 204) |
|
|
|
ウェアラブル心電計、AIを用いた不整脈診療の最前線
Latest advancements of arrhythmia diagnosis and treatment using wearable ECG devices and AI technology |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
伊藤 知宏
| ( |
東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第15会場(福岡国際会議場5F 501) |
|
|
|
Fallot四徴症のライフロングマネジメント
Life-long Management of Tetralogy of Fallot |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Jamil A. Aboulhosn
| ( |
UCLA Adult Congenital Heart Disease Center, USA) |
|
|
|
| Keynote Lecture: |
Jamil A. Aboulhosn
| ( |
UCLA Adult Congenital Heart Disease Center, USA) |
|
|
|
| 演 者: |
小谷 恭弘
| ( |
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 心臓血管外科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
木島 康文
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第21会場(マリンメッセ福岡B 1F アリーナ) |
|
|
|
一次性MRに対する治療戦略:低侵襲医療を踏まえたハートチームの意思決定と展望
Strategic Approaches to Primary MR: Heart Team Decision-Making and Future Directions in the Era of Minimally Invasive Therapy |
|
|
|
| 演 者: |
泉 佑樹
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科) |
|
|
| |
大野 暢久
| ( |
一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 心臓血管外科) |
|
|
| |
|
|
| |
坂本 知浩
| ( |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 循環器内科) |
|
|
| |
倉島 真一
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室1) |
|
|
|
心筋症診断の最前線
Cutting edge of cardiomyopathy managements |
|
|
|
| 演 者: |
大滝 裕香
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 放射線科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
天野 雅史
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部 心不全科) |
|
|
| |
|
|
| |
河合 冬星
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室1) |
|
|
|
| <日本臨床腫瘍学会ジョイント> |
|
がん治療に関連する心血管毒性アップデート -Onco-Cardiologyガイドラインより-
Update of cardiovascular toxicity related to cancer therapy |
|
| 座 長: |
赤澤 宏
| ( |
金沢医科大学総合医学研究所 戦略的研究部分子心血管研究分野) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
舟越 俊介
| ( |
京都大学iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室1) |
|
|
|
心臓アミロイドーシス治療の最前線
Cutting Edge of Clinical Practice for Cardiac Amyloidosis |
|
| 座 長: |
|
|
| |
山野 哲弘
| ( |
京都府立医科大学 感染制御・検査医学 / 循環器内科学) |
|
|
|
| 演 者: |
泉家 康宏
| ( |
熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学) |
|
|
| |
藤本 直紀
| ( |
三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学) |
|
|
| |
|
|
| |
近藤 秀和
| ( |
大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座) |
|
|
| |
奥村 貴裕
| ( |
名古屋大学大学院医学系研究科 先進循環器治療学) |
|
|
| |
谷口 泰代
| ( |
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 総合内科、循環器内科) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
心不全は本当に予防できるのか? ―ステージA・Bからの介入戦略を再考する
Can we really prevent heart failure? – Rethinking approaches to Stage A and B heart failure |
|
|
|
| 演 者: |
中尾(舛方)葉子
| ( |
京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 薬剤疫学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
藤木 伸也
| ( |
新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
JSH2025で循環器診療はどのように変わるのか
How does JSH2025 change cardiovascular medicine? |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
山本 浩一
| ( |
大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学) |
|
|
| |
|
|
| |
甲斐 久史
| ( |
社会医療法人弘恵会 ヨコクラ病院 総合診療部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第2会場(福岡サンパレス 2F パレスルーム A) |
|
|
|
5年目を迎えた脳卒中・心臓病等総合支援センターの活動内容と課題
Five Years of the Nōsotchū / Shinzōbyō-tō Sōgō Shien Sentā: Achievements and Challenges |
|
| 座 長: |
|
|
| |
前村 浩二
| ( |
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学) |
|
|
|
| 演 者: |
西村 邦宏
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 予防医学疫学情報部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
磯部 光章
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第3会場(福岡サンパレス 2F パレスルーム B) |
|
|
|
循環器領域における性差医療
Gender-specific medicine in the field of cardiovascular medicine |
|
| 座 長: |
|
|
| |
落合 由恵
| ( |
地域医療機能推進機構 九州病院 小児心臓血管外科) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
原田 栄作
| ( |
社会医療法人 寿量会 熊本機能病院 循環器内科) |
|
|
| |
|
|
| |
佐藤加代子
| ( |
東京家政大学 栄養学部栄養学科 臨床病態学研究室) |
|
|
| |
永吉 靖央
| ( |
一般社団法人 天草郡市医師会立 天草地域医療センター 循環器内科) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第5会場(福岡国際会議場 3F メインホール) |
|
|
|
心不全療養指導士の活動と今後の展望
Achievements and Future Prospects of Certified Heart Failure Educator |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
大舘 祐佳
| ( |
公益財団法人 日産厚生会玉川病院 医療技術部薬剤科) |
|
|
| |
皆川 健太
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院) |
|
|
| |
笠井 健一
| ( |
パナソニック健康保険組合松下記念病院 診療技術部リハビリテーション療法室) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第15会場(福岡国際会議場 5F 501) |
|
|
|
JRC蘇生ガイドライン2025の主な改訂点は?
What are the major updates in the JRC Resuscitation Guidelines 2025? |
|
| 座 長: |
田原 良雄
| ( |
国立循環器病研究センター 心臓血管内科/救急部) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
西山 知佳
| ( |
京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 先端中核看護科学講座 クリティカルケア看護学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
船崎 俊一
| ( |
川口きゅうぽらリハビリテーション病院 循環器内科) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F 会議室1) |
|
|
|
| <日本集中治療医学会ジョイント> |
|
循環器救急におけるプレホスピタル心電図の現状と展望
Prehospital Electrocardiography in Cardiovascular Emergencies: Current Status and Prospects |
|
| 座 長: |
藤田 英雄
| ( |
自治医大学附属さいたま医療センター 循環器内科) |
|
|
| |
竹内 一郎
| ( |
横浜市立大学 救急医学/高度救命救急センター) |
|
|
|
| 演 者: |
齋藤 研
| ( |
大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター 救命救急科) |
|
|
| |
|
|
| |
小橋 啓一
| ( |
医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 循環器内科) |
|
|
| |
佐藤 弘樹
| ( |
大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座) |
|
|
| |
岡田 興造
| ( |
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第5会場(福岡国際会議場3F メインホール) |
|
|
|
| <ダイバーシティ推進委員会(特定行為看護師養成促進部会)企画> |
|
看護師特定行為研修修了生が施設にもたらすメリット
~~外来、入院、在宅まで継続的な循環器チーム医療、タスクシフトの推進~~
Benefits that graduates of specific nurse practice training bring to facilities.
~~Continuous cardiovascular team medical care from outpatient, inpatient, and home care, and promotion of task shifting~~ |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
高橋 素子
| ( |
社会医療法人社団 正志会 平成立石病院 看護部) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
血管機能評価をどう生かすか?
How can we utilize the vascular functional assessment? |
|
|
|
| 演 者: |
米津 圭佑
| ( |
大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座) |
|
|
| |
|
|
| |
三好 亨
| ( |
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第7会場(福岡国際会議場2F 202) |
|
|
|
AIを虚血性心疾患診療に活かす―AIの今と未来を見据えて―
Applying AI in the Treatment of Ischemic Heart Disease — Looking at the Present and Future of AI — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
保険診療の持続可能性と医療イノベーションの相克
The Conflict Between the Sustainability of Insurance-Based Medical Care and Recent Medical Innovation |
|
|
|
| 演 者: |
出島 徹
| ( |
独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ヶ谷中央病院 循環器内科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第9会場(福岡国際会議場2F 204) |
|
|
|
冠動脈不安定プラークの診断・治療のフロンティア
Frontier of Theranostics for Coronary Vulnerable Plaques |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
浅海 泰栄
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第15会場(福岡国際会議場5F 501) |
|
|
|
老化のメカニズムから加齢変容を探る
Exploring Age-Related Transformation through the Mechanisms of Aging |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Stefanie Dimmeler
| ( |
Goethe-University, Germany) |
|
|
|
|
| Keynote Lecture: |
Stefanie Dimmeler
| ( |
Goethe-University, Germany) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F大会議室) |
|
|
|
| <開業医 + 保険診療委員会企画> |
|
外来診療における循環器標準的予防治療の実践: 2024年診療報酬改定後の現状と未来
Implementation of Standard Preventive Cardiovascular Care in Outpatient Practice: Current Status and Future Outlook Following the 2024 Medical Fee Revision |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
肥後 太基
| ( |
ゆみのハートクリニック渋谷 わかばハートクリニック) |
|
|
| |
西 真宏
| ( |
京都府立医科大学 大学院医学研究科循環器内科学) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
進化する不整脈デバイス治療
Evolution and innovation of implantable cardiac devices for treating cardiac arrhythmias |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
茶谷 龍己
| ( |
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 循環器内科) |
|
|
| |
|
|
| |
河田 宏
| ( |
Peacehealth Sacred Heart Medical Center, USA) |
|
|
| |
岡 怜史
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門 不整脈科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F 会議室1) |
|
|
|
イメージングをHFpEF診療に活かす
Utilizing Imaging in the Management of HFpEF |
|
|
|
| 演 者: |
青山 里恵
| ( |
船橋市立医療センター 心臓血管センター 循環器内科) |
|
|
| |
阿部亜里紗
| ( |
愛媛大学大学院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座) |
|
|
| |
|
|
| |
藤田 文香
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~14:40 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
| ますます困っている高齢者心不全にどう立ち向かうか? |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
北井 豪
| ( |
国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部) |
|
|
|
| 2. |
高齢心不全患者への対応:リハビリテーションについて |
|
|
| 演 者: |
小幡 裕明
| ( |
新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科 地域連携のための内部障害リハビリテーション学講座) |
|
|
|
| 3. |
高齢心不全患者への対応 -地域連携について- |
|
|
| 演 者: |
衣笠 良治
| ( |
鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科学分野) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)14:40~15:40 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
| ステントグラフトの最前線と限界 |
|
|
|
| 1. |
EVARの限界 -EVAR後の持続性Type II エンドリーク- |
|
|
| 演 者: |
|
|
| 2. |
EVARの限界を突破する -Type II エンドリーク制御- |
|
|
| 演 者: |
|
|
|
|
| 演 者: |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:00~11:00 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
| 超高齢社会に求められる不整脈診療 |
|
| 座 長: |
夛田 浩
| ( |
福井大学医学部 病態制御医学講座 循環器内科学) |
|
|
| |
|
|
|
| 1. |
高齢者心房細動に対するカテーテルアブレーション~役割と課題 |
|
|
| 演 者: |
向井 靖
| ( |
福岡赤十字病院 循環器内科/九州大学医学部循環器内科学) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
西井 伸洋
| ( |
岡山大学学術研究院医歯薬学域 先端循環器治療学講座) |
|
|
|
| 3. |
持続可能な医療を目指して ~医療経済の側面からみたこれからの不整脈診療~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)11:00~12:00 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
| 安定冠動脈疾患のマネージメント |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
治療の前に考えること:ガイドライン改訂を踏まえてどう現場は変わったか? |
|
|
| 演 者: |
池村 修寛
| ( |
国家公務員共済組合連合会 立川病院/慶應義塾大学病院 循環器内科) |
|
|
|
| 3. |
安定冠動脈疾患のマネージメント ~ Bypass Surgeonの立場から ~ |
|
|
|
|
| 4. |
カテーテル治療の現在地と世界での安定冠動脈疾患の捉え方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:00 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
| 今後我が国で臨床研究をどのように進めていくか |
|
|
|
| 1. |
「多施設」臨床研究のチカラ ~U-40心不全ネットワークの実例とともに~ |
|
|
| 演 者: |
末永 祐哉
| ( |
順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学講座) |
|
|
|
| 2. |
Academic Research Organizationに所属する循環器内科医の立場からの臨床研究の推進について |
|
|
| 演 者: |
後岡 広太郎
| ( |
東北大学病院 臨床研究パートナー部門/東北大学病院 循環器内科) |
|
|
|
| 3. |
CLIDAS研究が拓く医療Society 5.0 臨床情報プラットフォームと持続可能な産学連携 |
|
|
| 演 者: |
甲谷 友幸
| ( |
自治医科大学内科学講座 循環器内科学・成人先天性心疾患センター) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)9:00~10:00 第1会場(福岡サンパレス 2F 大ホール) |
|
|
|
| ACHDガイドライン2025を読み解く |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| 禁煙ファーストを目指して |
|
| 座 長: |
梅津 努
| ( |
坂根Mクリニック/筑波大学医学医療エリア支援室) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
和泉 真実
| ( |
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 救急救命センター) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
|
|
| 座 長: |
塚田(哲翁)弥生
| ( |
日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| サイコカーディオロジーを知ろう! |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
庵地 雄太
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| メディカルスタッフが知っておきたい弁膜症の画像診断 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
柳 善樹
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 臨床検査部) |
|
|
| |
田中 良一
| ( |
岩手医科大学附属病院 口腔顎顔面再建学講座 歯科放射線学分野) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| 下肢動脈閉塞性疾患の診断から血管内治療まで |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| 最新のリハビリテーション ―急性期から慢性期までー |
|
|
|
| 演 者: |
吉田 陽亮
| ( |
地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター リハビリテーション部) |
|
|
| |
平川功太郎
| ( |
公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 リハビリテーション科) |
|
|
| |
山岸 純也
| ( |
岐阜大学医学部附属病院 リハビリテーション部 心臓血管リハビリテーション室) |
|
|
| |
|
|
| |
岡田 理佳
| ( |
医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 外来看護科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| 循環器診療におけるタスク・シフト/シェアを考える |
|
|
|
| 演 者: |
杉田 翔哉
| ( |
地方独立行政法人 山口県立病院機構 山口県立総合医療センター 臨床工学部) |
|
|
| |
平川 大輔
| ( |
医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 薬剤科) |
|
|
| |
小林 大祐
| ( |
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 リハビリテーション科) |
|
|
| |
小川 浩司
| ( |
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 臨床工学部) |
|
|
| |
小田切菜穂子
| ( |
医療法人社団ゆみの わかばハートクリニック 看護部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| 心不全患者をみる ―退院調整から在宅支援までー |
|
| 座 長: |
|
|
| |
櫻田 弘治
| ( |
心臓血管研究所付属病院 リハビリテーション室) |
|
|
|
| 演 者: |
上坂 建太
| ( |
公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 リハビリテーション科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
兒玉 吏弘
| ( |
大分大学医学部附属病院 リハビリテーション部) |
|
|
| |
比嘉 洋子
| ( |
北里大学大学院看護学研究科 基盤開発看護学専攻) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| <日本放射線技術学会ジョイント> |
|
| 低侵襲画像診断による虚血性心疾患評価の最前線 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
梁川 範幸
| ( |
つくば国際大学 医療保健学部 診療放射線学科) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
加藤 真吾
| ( |
横浜市立大学大学院医学系研究科 放射線診断学教室) |
|
|
| |
|
|
| |
梶浦 涼
| ( |
医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 放射線科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
| <日本臨床薬理学会ジョイント> |
|
| いま知っておきたい、心筋症治療薬 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
岸 拓弥
| ( |
国際医療福祉大学大学院医学研究科 循環器内科) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
矢野 俊之
| ( |
札幌医科大学医学部 内科学講座 循環動態内科学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| Precision Medicine in Heart Failure |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Manesh Patel
| ( |
AHA President-Elect; Duke Medical University, USA) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
Manesh Patel
| ( |
AHA President-Elect; Duke Medical University, USA) |
|
|
| |
Ambarish Pandey
| ( |
UT Southwestern Medical Center, USA) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| Tailoring Revascularization Strategies: Risk Stratification and Shared Decision Making |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Franz Weidinger
| ( |
Landstrasse Clinic, Austria) |
|
|
|
| 演 者: |
福井 寿啓
| ( |
熊本大学大学院生命科学研究部 心臓血管外科学) |
|
|
| |
|
|
| |
Franz Weidinger
| ( |
Landstrasse Clinic, Austria) |
|
|
| |
Jolanda Kluin
| ( |
Erasmus MC Rotterdam, Netherlands) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| Targeting Cardio-Metabolic Pathways in Obese Patients with Heart Failure |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Seok-Min Kang
| ( |
Yonsei University, Korea) |
|
|
|
| 演 者: |
古橋 眞人
| ( |
札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座) |
|
|
| |
佐野 元昭
| ( |
山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学講座) |
|
|
| |
Chan Joo Lee
| ( |
Yonsei University, Korea) |
|
|
| |
Jin Joo Park
| ( |
Seoul National University, Korea) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| Stroke prevention in Atrial Fibrillation |
|
| 座 長: |
野上 昭彦
| ( |
東京心臓不整脈病院難治性不整脈治療研究センター) |
|
|
| |
Yihong Sun
| ( |
Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, China) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
Chao Jiang
| ( |
Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, China) |
|
|
| |
Yiheng Yang
| ( |
Dalian Medical University Cardiovascular Hospital, China) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| Current Status and Future Perspective of Sudden Cardiac Death in Asia |
|
| 座 長: |
庄田 守男
| ( |
東京女子医科大学循環器内科先進電気的心臓制御研究部門) |
|
|
| |
Jiunn-Lee Lin
| ( |
President of Asian Pacific Society of Cardiology, Taiwan) |
|
|
|
| 演 者: |
藤生 克仁
| ( |
東京大学大学院医学系研究科 先進循環器病学 ) |
|
|
| |
石橋 耕平
| ( |
国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門不整脈科) |
|
|
| |
Chin-Sheng Lin
| ( |
National Defense Medical University, Taiwan) |
|
|
| |
Seung-Jung Park
| ( |
Division of Cardiology, Heart Stroke and Vascular Institute, Korea) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| Recent Advances in Cardiac Imaging |
|
|
| 座 長: |
新家 俊郎
| ( |
昭和医科大学医学部内科学講座循環器内科学部門) |
|
|
| |
海外座長未定 |
|
|
| 演 者: |
宇都宮裕人
| ( |
広島大学 大学院医系科学研究科 循環器内科学) |
|
|
| |
松本 英成
| ( |
昭和医科大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門) |
|
|
| |
海外演者未定 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
第90回特別企画:
日本学術会議「循環器・腎・代謝内分泌分科会」との合同企画セッション |
|
|
|
|
2026年3月20日(金・祝)16:30~18:30 第5会場(福岡国際会議場3F メインホール)
後援:日本学術会議 |
|
|
|
| 心腎代謝症候群(Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome)を本邦でどう考え、どう展開するのか |
|
| 座 長: |
|
|
| |
金子 英弘
| ( |
東京大学医学部循環器内科/先進循環器病学講座) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
山内 敏正
| ( |
東京大学大学院医学系研究科 代謝・栄養病態学) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
鶴田 真也
| ( |
厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課) |
|
|
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:
日本医療研究開発機構(AMED)ヘルスケア社会実装基盤整備事業合同セッション |
|
|
|
|
2026年3月21日(土)10:30~12:00 第7会場(福岡国際会議場2F 202)
後援:国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED) |
|
|
|
| 循環器病におけるヘルスケアサービス指針について |
|
| 座 長: |
|
|
| |
里見 智美
| ( |
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED) 医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
古賀 政利
| ( |
国立研究開発法人国立循環器病研究センター 脳血管内科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
第90回特別企画:
日本学術会議「生活習慣病対策分科会」との合同企画セッション |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第9会場(福岡国際会議場2F 204) |
|
|
|
| 「生活習慣病」のこれからを考える |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
郡山 千早
| ( |
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学・予防医学) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:
日本医療研究開発機構(AMED) 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 合同セッション |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)11:00~12:00 第21会場(マリンメッセ福岡B館 1Fアリーナ) |
|
|
|
| 循環器病の発展を支えるAMED研究 |
|
|
|
| 演 者: |
田中 桜
| ( |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)) |
|
|
| |
津村 和大
| ( |
川崎市立川崎病院 病態栄養治療部 / 日本医療研究開発機構(AMED)) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology1 |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 熊本大学Presents「腎神経デナベーションの未来─基礎から実践へ─」 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
坂倉 建一
| ( |
自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科・心血管治療部) |
|
|
| |
草山 隆志
| ( |
金沢大学 医薬保健研究域医学系 救急・災害医学分野) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 2 |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 長崎大学Presents「Destination therapyの現状と将来展望」 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
渡邉 琢也
| ( |
国立循環器病研究センター 心不全・移植科 移植医療部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
肥後 太基
| ( |
医療法人社団ゆみの ゆみのハートクリニック渋谷) |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 3 |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 琉球大学Presents「Island Innovation in Cardiovascular Medicine」 |
|
| 座 長: |
佐田 政隆
| ( |
徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
宮城 文音
| ( |
琉球大学病院 第3内科 循環器・腎臓・神経内科学) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 4 |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 鹿児島大学Presents「予防に勝る治療なし」 |
|
| 座 長: |
大石 充
| ( |
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
猪又 孝元
| ( |
新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学) |
|
|
| |
神田 大輔
| ( |
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学) |
|
|
| |
|
|
| |
窪薗 琢郎
| ( |
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学) |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 5 |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 宮崎大学Presents「MINOCA/INOCA診療における最新エビデンスと今後の課題」 |
|
| 座 長: |
海北 幸一
| ( |
宮崎大学医学部内科学講座 循環器・腎臓内科学分野) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
石井 正将
| ( |
熊本大学病院 医療情報経営企画部/循環器内科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 6 |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 大分大学Presents「心外膜脂肪は心血管疾患の治療標的になり得るか?」 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
髙橋 尚彦
| ( |
⼤分⼤学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
中森 史朗
| ( |
三重⼤学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学) |
|
|
| |
佐田 政隆
| ( |
徳島⼤学大学院医歯薬学研究部循環器内科学分野) |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 7 |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 九州大学Presents「DT時代のLVAD治療~遠隔期を見据えた課題と対策」 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
波多野 将
| ( |
東京大学医学部附属病院 高度心不全治療センター) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
佐藤 琢真
| ( |
国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 移植医療部) |
|
|
| |
當間裕一郎
| ( |
琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座) |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 8 |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 福岡大学Presents「防げ、心血管イベント!高血圧治療の最前線から」 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 9 |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 久留米大学Presents「震災時における診療について:南海トラフ地震に備えて」 |
|
| 座 長: |
福本 義弘
| ( |
久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
海北 幸一
| ( |
宮崎大学医学部内科学講座 循環器腎臓内科学分野) |
|
|
|
|
|
|
第90回特別企画:Frontline of Cardiology 10 |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第18会場(マリンメッセ福岡A 2F 大会議室) |
|
|
|
| 産業医科大学Presents「今こそ深掘りしたい、心力学理論と循環生理」 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
杉本 匡史
| ( |
名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院 循環器内科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
血管不全を生化学から診断する
~Inflammation and Cardiovascular Disease: 2025 ACC Scientific Statementを読み解く~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第15会場(福岡国際会議場 5F 501) |
|
|
|
| 日本の循環器研究を世界に向けて発信するために |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
坂東 泰子
| ( |
三重大学医学部 基礎医学系講座/分子生理学分野) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第19会場(マリンメッセ福岡A 2F 会議室2) |
|
|
|
| Learnings from Recent Clinical Trials |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Dan Atar
| ( |
Oslo University Hospital, Norway) |
|
|
|
| 演 者: |
Dan Atar
| ( |
Oslo University Hospital, Norway) |
|
|
| |
|
|
| |
Dan Atar
| ( |
Oslo University Hospital, Norway) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第3会場(福岡サンパレス2F パレスルーム B) |
|
|
|
| PAD/LEAD診療における脂質管理の現在と未来 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
| トランスレーショナル研究で加速する循環器疾患のイノベーション |
|
| 座 長: |
的場 聖明
| ( |
京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科) |
|
|
| |
中岡 良和
| ( |
国立循環器病研究センター研究所 血管生理学部) |
|
|
|
| 演 者: |
木谷 友哉
| ( |
京都府立医科大学大学院 医学研究科 循環器内科学) |
|
|
| |
勝海 悟郎
| ( |
順天堂大学医学部内科学教室 循環器内科学講座) |
|
|
| |
|
|
| |
中岡 良和
| ( |
国立循環器病研究センター研究所 血管生理学部) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第15会場(福岡国際会議場 5F 501) |
|
|
|
Onco-Hypertensionの現在と未来
がん治療と循環器の新たな連携に向けて |
|
|
|
| 演 者: |
高橋 雅信
| ( |
山形大学大学院医学系研究科第二講座 臨床腫瘍学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
金子 英弘
| ( |
東京大学医学部 循環器内科/先進循環器病学講座) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第19会場(マリンメッセ福岡A 2F 会議室2) |
|
|
|
| 和温療法の現状と今後の展開 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
藤見 幹太
| ( |
福岡大学病院 リハビリテーション部・循環器内科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)11:00~12:00 第21会場(マリンメッセ福岡B 1Fアリーナ) |
|
|
|
AIが循環器医療の常識を変える
─若手循循環器医師起業家たちの挑戦― |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第1会場(福岡サンパレス2F 大ホール) |
|
|
|
クリニックでのガイドラインの使い方
─地域医療でどう実践に活かすか─ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
| Molecular Pathogenesis and Precision Medicine in Cardiomyopathy: From Biomarkers to Therapeutic Targets |
|
| 座 長: |
岡﨑 敦子
| ( |
順天堂大学大学院医学研究科 難治性疾患診断・治療学) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
Jin Han
| ( |
Inje University, Korea) |
|
|
| |
|
|
| |
木谷 友哉
| ( |
京都府立医科大学大学院 医学研究科 循環器内科学) |
|
|
| |
|
|
| |
佐藤 迪夫
| ( |
熊本大学大学院 生命科学研究部 分子遺伝学講座) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
| Novel Frontiers in Heart Failure Research: Metabolism, Epigenetics, and Cardiac Reprogramming |
|
|
|
| 演 者: |
Linda Peterson
| ( |
Washington University School of Medicine, USA) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
| 心房細動と心房心筋症 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 前期安全性治験が終了した人工血液(HbV)は蘇生医学・循環器救急治療のゲームチェンジャーとなる可能性はあるか?:大量出血性ショック治療のブレイクスルーから学ぶ |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
佐藤 智彦
| ( |
東京慈恵会医科大学附属病院 輸血・細胞治療部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
| 致死性不整脈・心臓突然死へのアプローチ~リスク評価と治療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F, 会議室1) |
|
|
|
| 尿酸に関する最新の知見から、心血管疾患の新たな治療の可能性を検討する |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
桑原 政成
| ( |
自治医科大学 地域医療学センター公衆衛生学 兼 循環器内科学) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F会議室2) |
|
|
|
循環器集中治療体制の現状と今後の目指すべきCICUについて
ー心原性ショックに対する対応も含めてー |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
桑原 政成
| ( |
自治医科大学 地域医療学センター公衆衛生学 兼 循環器内科学) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
| 心不全に対する新たな人工心臓 |
|
|
|
| 演 者: |
増澤 徹
| ( |
茨木大学学術研究院 応用理工学野 機械システム工学領域) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
深町 清孝
| ( |
九州大学大学院医学研究院 心臓外科 重症心肺不全講座) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| 若年者の大動脈弁治療 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
曽我 欣治
| ( |
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管外科学) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第7会場(福岡国際会議場2F 202) |
|
|
|
| 医療過疎地の大血管緊急症をいかに救うか |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| MICS / ロボット心臓外科手術の現在と展望 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
伊藤 敏明
| ( |
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 心臓血管外科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
PCI後の抗血栓療法アップデート2026
-Evidence-Based Medicine の行方- |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
渡部 宏俊
| ( |
国家公務員共済組合連合会 枚⽅公済病院 循環器内科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
| 不安定プラークの診断と治療の最前線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 炎症性心筋疾患に対する治療戦略~リアルワールドでの戦い方~ |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
奥村 貴裕
| ( |
名古屋大学大学院医学系研究科 先進循環器治療学/循環器内科学) |
|
|
| |
當間裕一郎
| ( |
琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
IMPELLA導入による急性期虚血性心疾患治療の変革
-内科と外科の融合アプローチ |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
高木 数実
| ( |
久留米大学医学部外科学講座 心臓血管外科部門) |
|
|
| |
本田賢太朗
| ( |
和歌山県立医科大学 外科学第一講座 心臓血管外科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
Ischemiaから5年、残された現場での課題は何か?
─百人会議を用いたインタラクティブセッション─ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
| 負荷心エコー図検査を診療に活かす~動的診断から治療戦略へ~ |
|
| 座 長: |
山田 博胤
| ( |
徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域循環器内科学) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 糖尿病患者における循環器病の診断・予防・治療に関するコンセンサスステートメントの改訂へ向けて |
|
|
|
| 演 者: |
池田 香織
| ( |
京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構 臨床研究推進部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
石井 秀樹
| ( |
群馬大学大学院医学系研究科内科学講座 循環器内科学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
佐田 政隆
| ( |
徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野) |
|
|
| |
杉山 雄大
| ( |
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 糖尿病情報センター) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
TAVIデバイス3機種の選択指針と臨床的考察
─自施設における弁選択のこだわり─ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第7会場(福岡国際会議場2F 202) |
|
|
|
| ACSに対するPCIを再考する |
|
|
|
| 演 者: |
石井 秀樹
| ( |
群馬大学大学院医学系研究科内科学講座 循環器内科学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
鈴木 孝英
| ( |
旭川厚生病院 心臓血管カテーテル治療センター) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| Toward a Comprehensive Understanding of Atrial Fibrillation: From Basic Models to Genomics, Multi-Omics, Pathology, Sex Differences, and CHIP |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
沢見 康輔
| ( |
東京大学医学部附属病院 先端循環器医科学講座) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Hyo-Jeong Ahn
| ( |
Seoul National University, Korea) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
| 循環器集中治療におけるACPの実践 |
|
| 第1部:特別講演1:循環器集中治療と終末期医療について |
|
|
| 第2部:特別講演2:集中治療の差し控え・中止において医療者が知っておくべき法律知識 |
|
|
| 第3部:症例検討:循環器集中治療を開始した後,終末期と判定された症例 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第9会場(福岡国際会議場2F 204) |
|
|
|
| 収縮性心膜炎と類縁疾患の診断と治療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第9会場(福岡国際会議場2F 204) |
|
|
|
U40世界戦~海外若手研究者とディスカッション~
U40-HF Network Presents: Clinical Research in Heart Failure – Next Generation Perspectives |
|
| 座 長: |
松本 新吾
| ( |
東邦大学医療センター大森病院、Glasgow大学) |
|
|
| |
夜久 英憲
| ( |
国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部、Northwestern大学) |
|
|
|
| 演 者: |
Marco Metra
| ( |
Vita-Salute San Raffaele University, IRCCS San Raffaele hospital, Milan, Italy) |
|
|
| |
Mingming Yang
| ( |
Department of Cardiology, Zhongda Hospital, School of Medicine, Southeast University, China) |
|
|
| |
Jawad Haider Butt
| ( |
Department of Cardiology, Herlev and Gentofte University Hospital, Denmark) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第9会場(福岡国際会議場2F 204) |
|
|
|
| U40世代の臨床研究の実践を深掘りする |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第9会場(福岡国際会議場2F 204) |
|
|
|
| 炎症性筋疾患の心合併症─ 抗ミトコンドリア抗体陽性例から学ぶ |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
九山 直人
| ( |
熊本大学病院 循環器予防医学先端医療寄附講座) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第1会場(福岡サンパレス2F 大ホール) |
|
|
|
心不全薬物療法の過去・現在・未来
Pharmacological Therapy for Heart Failure: Past, Present, and Future |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Marco Metra
| ( |
Vita-Salute San Raffaele University, IRCCS San Raffaele hospital, Milan, Italy) |
|
|
|
| 演 者: |
Marco Metra
| ( |
Vita-Salute San Raffaele University, IRCCS San Raffaele hospital, Milan, Italy) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
| Comprehensive Perspectives in Interventional Cardiology: The Swiss‒Japanese Experience |
|
| 座 長: |
Stephan Windecker
| ( |
Bern University Hospital, Inselspital, Switzerland) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Stephan Windecker
| ( |
Bern University Hospital, Inselspital, Switzerland) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第15会場(福岡国際会議場5F 501) |
|
|
|
心臓突然死の新たなリスク層別化とその実践
New Approaches to Risk Stratification for Sudden Cardiac Death and Clinical Implementation |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Johann Bauersachs
| ( |
Hannover Medical School, Germany) |
|
|
|
| 演 者: |
Johann Bauersachs
| ( |
Hannover Medical School, Germany) |
|
|
| |
近藤 秀和
| ( |
大分大学 医学部 循環器内科・臨床検査診断学) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
野村 章洋
| ( |
金沢大学大学院 新学術創成研究科 / 循環器内科) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第15会場(福岡国際会議場5F 501) |
|
|
|
| 肥大心の診断と治療を再考する |
|
| 座 長: |
|
|
| |
中森 史朗
| ( |
三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
| 新時代の肺高血圧症を深掘りする |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
下川原裕人
| ( |
国立病院機構 岡山医療センター 循環器内科・肺高血圧症センター) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
| ACHDの心不全療法の進歩 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
宮﨑 文
| ( |
聖隷浜松病院 成人先天性心疾患・小児循環器科) |
|
|
| |
佐地 真育
| ( |
東邦大学医学部 内科学講座 循環器内科学分野) |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第20会場(マリンメッセ福岡A 3Fサブアリーナ) |
|
|
|
| ショックを伴ったACSへ多職種で立ち向かおう! |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第23会場(マリンメッセ福岡B 2F 会議室2) |
|
|
|
| 心原性ショックにおけるMCS管理のピットフォール |
|
| 座 長: |
市場 晋吾
| ( |
日本大学医学部附属板橋病院 麻酔科・集中治療室) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
清水 敬樹
| ( |
東京都立多摩総合医療センター 救命・集中治療科) |
|
|
| |
|
|
| |
市場 晋吾
| ( |
日本大学医学部附属板橋病院 麻酔科・集中治療室) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第3会場(福岡サンパレス2F パレスルーム B) |
|
|
|
| 循環器疾患におけるAI革命 |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
牧元 久樹
| ( |
自治医科大学 循環器内科 / データサイエンスセンター) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~9:30 第7会場(福岡国際会議場2F 202) |
|
|
|
| 心房細動関連脳梗塞を徹底的に科学する |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第9会場(福岡国際会議場2F 204) |
|
|
|
| 右室機能評価Update |
|
| 座 長: |
土肥 薫
| ( |
三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学) |
|
|
| |
|
|
|
| 演 者: |
杉本 匡史
| ( |
名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院 循環器内科) |
|
|
| |
山本 篤志
| ( |
東京女子医科大学 循環器内科、画像診断・核医学科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第15会場(福岡国際会議場5F 501) |
|
|
|
| 下肢急性動脈閉塞治療の最前線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第5会場(福岡国際会議場3F メインホール) |
|
|
|
| 循環器診療のゲームチェンジャー:革新的心臓リハビリ時代の幕開け、その後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00~9:30 第6会場(福岡国際会議場2F 201) |
|
|
|
| 急性大動脈解離の病因はなにか? |
|
|
|
| 演 者: |
清家 愛幹
| ( |
国⽴循環器病研究センター ⼼臓⾎管外科部門(⾎管外科)) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)8:00~9:30 第3会場(福岡サンパレス2F パレスルーム B) |
|
|
|
| 感染性心内膜炎Up-to-date:脳合併症を伴う場合の治療戦略 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
岡田 健次
| ( |
神戸大学大学院医学研究科 外科学講座 心臓血管外科分野) |
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
大原 貴裕
| ( |
東北医科薬科大学 老年・地域医療学/総合診療科) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第2会場(福岡サンパレス2F, パレスルーム A) |
|
|
|
| 脳卒中・心臓病支援の次なるステージ:全国整備から地域連携の実装へ |
|
|
| 第1部 講演「 |
脳卒中・心臓病等総合支援センター 全国整備の成果と課題─脳卒中・心臓病支援の実装に向けて」 |
|
|
| 第2部 パネルディスカッション「 |
支援をつなぎ、連携をひろげる─地域に根ざした患者サポートの実現へ」 |
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)14:10~15:40 第7会場(福岡国際会議場2F 202) |
|
|
|
| 循環器とスポーツ医学の融合と未来 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
深尾 宏祐
| ( |
順天堂大学 スポーツ健康科学部スポーツ科学科) |
|
|
| |
福島 理文
| ( |
順天堂大学医学部 臨床検査医学講座・循環器内科学講座・スポーツ医学研究室) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
YIA審査講演会(Clinical research) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~10:00 第16会場(福岡国際会議場5F 502) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
今岡 拓郎
| ( |
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 循環器科) |
|
|
| |
桑原 直也
| ( |
神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 循環器内科学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:10~11:10 第12会場(福岡国際会議場4F 411) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
The 1st Asian Award(渉外委員会(国際)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:25 第16会場(福岡国際会議場5F 502) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
Jiaxi Guo
| ( |
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China) |
|
|
| |
Tzong Shyuan Lee
| ( |
National Taiwan University, Taiwan) |
|
|
| |
Pham Phuoc Long Doan
| ( |
University of Medicine and Pharmacy, Hue University, Viet Nam) |
|
|
| |
WeiHsin Chung
| ( |
China Medical University Hospital, Taiwan) |
|
|
| |
Bao Quoc Vu
| ( |
University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Viet Nam) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
APSC Leadership Session(渉外委員会(国際)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~15:25 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
| Coronary Artery Disease and Heart Failure in Asia: Current Landscape and Future Directions |
|
| Opening Remarks: |
|
|
|
| Part 1: Coronary Artery Disease (CAD) |
|
|
|
|
|
| Keynote Lecture Title: |
State-of-the-Art / the optimal antiplatelet therapy after PCI for Asians considering bleeding risk and procedural complexity |
|
|
|
|
| Discussions: |
CAD chairpersons and speakers |
|
|
| + |
|
|
|
| Part 2:Heart Failure (HF) |
|
|
|
|
|
| Keynote Lecture Title: |
The Burden and Unmet Needs of Heart Failure in Asia-Pacific Region |
|
|
| Young Speakers: |
|
|
| |
Primasitha Maharany Harsoyo Putri
|
|
| |
|
|
|
| Discussions: |
HF chairpersons and speakers |
|
|
| + |
|
|
|
| Photo Session |
|
|
| |
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~15:25 第16会場(福岡国際会議場5F 502) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
Novia Nurul Faizah
| ( |
Cardiovascular Medicine, Kobe University, Kobe/Laboratory of Clinical Pharmaceutical Science, Kobe Pharmaceutical University) |
|
|
| |
ChiehLun Hsiao
| ( |
Department of Cardiovascular Biology and Medicine, Juntendo University) |
|
|
| |
Congcong Sun
| ( |
Department of Cardiovascular Medicine, The University of Osaka Graduate School of Medicine) |
|
|
| |
Lifu Sun
| ( |
Department of Cardiovascular Surgery, Graduate School of Medicine, The University of Osaka) |
|
|
| |
Wondwossen Wale Tesega
| ( |
Shiga University of Medical Science) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
Asian Pacific Grants for Innovative Research Plans Award (Clinical/Basic) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)8:00-10:00 第16会場(福岡国際会議場5F 502) |
|
|
|
|
|
| -Clinical Research Section- |
|
| 演 者: |
Tu Nguyen Tran
| ( |
Department of Cardiology, Cardiovascular Center, Hue Central Hospital, Hue, Viet Nam/Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Chung Ang University, Korea) |
|
|
| |
Hao-Chih Chang
| ( |
Division of Cardiology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taiwan) |
|
|
| |
Jung-Chi Hsu
| ( |
Cardiology, Department of Internal Medicine, National Taiwan University Hospital Jinshan Branch, Taiwan) |
|
|
| |
Wei-Ting Liu
| ( |
Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical University, Taiwan) |
|
|
|
| -Basic Research Section- |
|
| 演 者: |
Yu Lan Liu
| ( |
Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Tri-Service General Hospital, National Defense Medical University, Taiwan) |
|
|
| |
Tse-Wei Chen
| ( |
Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, National Cheng Kung University Hospital, Taiwan) |
|
|
| |
Yongjae Lee
| ( |
Graduate School of Medical Science and Engineering (GSMSE), Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea) |
|
|
| |
Hanestya Oky Hermawan
| ( |
Doctoral Program of Medical Science, Universitas Airlangga, Indonesia) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
メディカルスタッフ賞審査講演会【検査・治療部門】1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
| 座 長: |
|
|
| |
梁川 範幸
| ( |
つくば国際大学 医療保健学部 診療放射線学科) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
鳥居 裕太
| ( |
神戸市立医療センター中央市民病院 臨床検査技術部門) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
メディカルスタッフ賞審査講演会【看護・薬剤・リハ部門】2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:00 第14会場(福岡国際会議場4F 413+414) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
三木 康寛
| ( |
社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 リハビリテーション科) |
|
|
| |
坂本 翔太
| ( |
医療法人社団幸正会 岩槻南病院 心臓リハビリテーション科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:25 第5会場(福岡国際会議場 3F メインホール) |
|
|
|
| 医療AIの研究開発・実践に伴う倫理的・法的・社会的課題について |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)14:25~15:25 第5会場(福岡国際会議場 3F メインホール) |
|
|
|
| 循環器経カテーテル治療における医療安全:チームワークとしての取り組み(仮) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
大石 充
| ( |
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~17:30 第7会場(福岡国際会議場2F 202) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心血管インターベンション治療学会」 |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~17:30 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| Primary PCIの現状と問題点~働き方改革をいかに乗り切るか~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本不整脈心電学会」 |
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)17:30~18:30 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 遺伝性不整脈の診断と治療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本血管外科学会」 |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)9:55~10:55 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 血管外科:最近の話題 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心臓病学会」 |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)11:00~12:00 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| いまさら聞けない循環器ゲノム |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本小児循環器学会」 |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:25 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 基本法と医療DXの時代の学校心臓検診の近未来 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心エコー図学会」 |
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)14:30~15:30 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 心エコー図で右心系を診る |
|
|
|
| 演 者: |
天野 雅史
| ( |
国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部 心不全科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心不全学会」 |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:05~16:05 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 心臓サルコイドーシス revisited |
|
|
|
|
|
|
|
|
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心臓リハビリテーション学会」 |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)16:10~17:10 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 心臓リハビリテーションの未来像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本脳卒中学会・日本循環器学会ジョイントシンポジウム
(基本法・5カ年計画検討委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
| 循環器病対策の進捗評価と今後の対策と展望 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
鶴田 真也
| ( |
厚生労働省 健康・保健衛生局 がん・疾病対策課) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
飯原 弘二
| ( |
国立循環器病研究センター 循環器病対策情報センター) |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本循環器協会・日本循環器学会ジョイントシンポジウム
(渉外(国内)交流委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第8会場(福岡国際会議場2F 203) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本整形外科学会・日本循環器学会ジョイントシンポジウム
(渉外(国内)交流委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:25~14:55 第7会場(福岡国際会議場2F 202) |
|
|
|
| 人生100年時代の循環器と運動器の連携 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
酒井 良忠
| ( |
神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本機械学会・日本循環器学会ジョイントシンポジウム
(渉外委員会(国内)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第2会場(福岡サンパレス2F パレスルーム A) |
|
|
|
| 循環器疾患の診療向上に向けての医工連携 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
板谷 慶一
| ( |
名古屋市立大学 心臓血管外科, Cardio Flow Design Inc.) |
|
|
| |
中島 雄太
| ( |
熊本大学大学院先端科学研究部 産業ナノマテリアル研究所) |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
蘇生科学シンポジウム(教育研修 / 集中救急委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:40 第15会場(福岡国際会議場5F 501) |
|
|
|
Evolution of Critical Care Cardiology: Global Insights into Team Structure, Clinical Practice, and Research
— A Joint Session by AHA and JCS |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Dhruv Kazi
| ( |
Beth Israel Deaconess Medical Center, USA) |
|
|
| 演 者: |
Dhruv Kazi
| ( |
Beth Israel Deaconess Medical Center, USA) |
|
|
| |
Demetri Yannopoulos
| ( |
University of Minesota, USA) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
CJ/EHJ Joint Session(編集委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第15会場(福岡国際会議場5F 501) |
|
|
|
| 座 長: |
|
|
| |
Filippo Crea
| ( |
Catholic University of the Sacred Heart, Italy) |
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
Johann Bauersachs
| ( |
Hannover Medical School, Germany) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
ガイドライン症例セッション(学術集会プログラム部会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~11:30 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F 会議室1) |
|
|
|
| 2026年改訂版血管炎症候群の診療ガイドライン |
|
| 座 長: |
中岡 良和
| ( |
国立循環器病研究センター研究所 血管生理学部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:25 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F 会議室1) |
|
|
|
| 2026年改訂版感染性心内膜炎診療ガイドライン |
|
| 座 長: |
泉 知里
| ( |
国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門心不全科) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)14:25~15:25 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F 会議室1) |
|
|
|
| 2026年フォーカスアップデート版心疾患患者の妊娠・出産の適応、管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~17:10 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F 会議室1) |
|
|
|
| 2026年改訂版遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン |
|
|
|
| 演 者: |
山﨑 大央
| ( |
大分大学医学部附属病院 循環器内科・臨床検査診断学講座) |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本循環器学会 委員会セッション(ガイドライン部会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~14:40 第17会場(マリンメッセ福岡A1F アリーナ) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
泉 知里
| ( |
国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門心不全科) |
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)14:40~15:40 第17会場(マリンメッセ福岡A1F アリーナ) |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
中岡 良和
| ( |
国立循環器病研究センター研究所 血管生理学部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
海外留学ネットワーキングセミナー
(渉外委員会(国際)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:40~18:10 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
|
|
| アドバイザー: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
長坂 崇司
| ( |
群馬大学大学院医学系研究科内科学講座 循環器内科学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
酒井孝志郎
| ( |
昭和医科大学医学部内科学講座 循環器内科部門) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
河田 宏
| ( |
Peacehealth Sacred Heart Medical Center) |
|
|
| |
|
|
| |
中須賀公亮
| ( |
国立循環器病研究センター・名古屋市立大学大学院医学研究科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
佐橋 勇紀
| ( |
Cedars-Sinai Medical Center) |
|
|
| |
永井 道明
| ( |
安佐医師会病院 総合内科・広島大学大学院循環器内科学研究員) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
松下 絢介
| ( |
横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター内科) |
|
|
| |
夜久 英憲
| ( |
国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
梅井 正彦
| ( |
Royal Brompton Hospital, Imperial College London) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第16会場(福岡国際会議場5F 502) |
|
|
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
John G.F. Cleland
| ( |
University of Glasgow, UK) |
|
|
| |
Jae-Won Lee
| ( |
Asan Medical Center, Korea) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
JIYCオリジナルセッション(渉外委員会(国際)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第19会場(マリンメッセ福岡A 2F 会議室2) |
|
|
|
| JIYC Global Structural Heart Forum - Turning Evidence into Action |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Davide Margonato
| ( |
San Raffaele Hospital, Italy) |
|
|
| 演 者: |
Davide Margonato
| ( |
San Raffaele Hospital, Italy) |
|
|
| |
Jonathan Yap
| ( |
National Heart Centre Singapore, Singapore) |
|
|
| |
Jee‒hoon Kang
| ( |
Seoul National University Hospital, Korea) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
心不全療養指導士セッション
(心不全療養指導士療養指導士統括部会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)10:30~12:00 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
| 心不全療養指導士の挑戦~誕生から5年、今何に取り組んでいますか?~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
| 低栄養を呈する心不全患者への介入~スクリーニングだけで終わっていませんか?~ |
|
|
|
| 演 者: |
川瀨 文哉
| ( |
東北大学大学院医工学研究科 スポーツ健康科学分野) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
角屋 桜雪
| ( |
医療法人社団ユニメディコ サンライズファミリークリニック) |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
心不全療養指導士Cafe
(心不全療養指導士療養指導士統括部会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)16:10~18:10 第20会場(マリンメッセ福岡A 3F サブアリーナ) |
|
|
|
| 『原点回帰からの挑戦』 ~心不全療養支援を、多職種で繋ぐ~ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本循環器学会 委員会セッション
(JCS-JJC部会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月21日(土)13:25~14:55 第19会場(マリンメッセ福岡A 2F 会議室2) |
|
|
|
| 日本中の循環器ダイバーシティを繫ぐ |
|
| 座 長: |
|
|
| |
福江 宣子
| ( |
山口大学 教育・学生支援機構 健康科学センター) |
|
|
|
| ディスカッサント: |
高山 亜美
| ( |
新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科科) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
大野 聡子
| ( |
久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本循環器学会 委員会セッション
(専門医制度委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第3会場(福岡サンパレス2F パレスルーム B) |
|
|
|
| 循環器領域専門医制度と地域医療 |
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
椎谷 紀彦
| ( |
国立病院機構 函館医療センター 心臓血管外科) |
|
|
| |
星合美奈子
| ( |
三多摩医療生活協同組合 くにたち南口診療所)※共著者:増谷 聡(埼玉医科大学総合医療センター) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本循環器学会 委員会セッション
(IT/Database部会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)9:40~11:10 第19会場(マリンメッセ福岡A 2F 会議室2) |
|
|
|
JROAD研究のこれまでとこれから
〜リアルワールドデータからみる我が国の循環器病診療実態: JROAD研究に参加しよう!〜 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本循環器学会 委員会セッション
(集中・救急医療部会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第1会場(福岡サンパレス2F 大ホール) |
|
|
|
| 4学会合同終末期ガイドライン改訂版をどう活かすか |
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
伊藤 香
| ( |
帝京大学医学部外科学講座Acute Care Surgery部門) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
日本循環器学会 委員会セッション
(基本法・5ヵ年計画検討委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)13:40~15:10 第16会場(福岡国際会議場5F 502) |
|
|
|
| 脳卒中と循環器病克服第三次5カ年計画の主なポイント |
|
| 座 長: |
|
|
| |
前村 浩二
| ( |
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学) |
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
福本 義弘
| ( |
久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門) |
|
|
| |
塚田(哲翁)弥生
| ( |
日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科) |
|
|
| |
前村 浩二
| ( |
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
JCS EARLY CAREER CHAMPIONSHIP
(Next Generation部会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)16:30~18:30 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 詳細はこちら |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
血圧測ろうぜ!全国薬局啓発選手権(P-1 グランプリ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)15:40~17:10 第17会場(マリンメッセ福岡A 1F アリーナ) |
|
|
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
小川 温子
| ( |
株式会社メディカルシステムネットワーク・北海道心不全医療連携アカデミー・h-PDD) |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)10:10~11:10 第16会場(福岡国際会議場5F 502) |
|
|
|
| 医薬品の適正使用/実装に向けた産官学の連携 |
|
|
|
| パネリスト: |
|
|
| |
竹本 信也
| ( |
中外製薬株式会社 セイフティサイエンス第二部) |
|
|
|
|
| |
|
|
| 2026年3月22日(日)10:30~12:00 第9会場(福岡国際会議場2F 204) |
|
|
|
| 禁煙推進の次のステップ ~政策・課題・そして世界との協働へ~ |
|
| 座 長: |
|
|
| |
|
|
| 演 者: |
藤田 英雄
| ( |
自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科) |
|
|
| |
中村 正和
| ( |
公益社団法人地域医療振興協会 地域医療研究所 へき地医療研究センター) |
|
|
| |
田淵 貴大
| ( |
東北大学大学院 医学系研究科 学専攻公衆衛生学分野) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)14:00~16:00 第22会場(マリンメッセ福岡B 2F, 会議室1) |
|
|
|
| 「命の大切さを考える」~心肺蘇生法(コールアンドプッシュ)を学ぼう~ |
|
| 詳細はこちら |
|
|
|
|
SUWAN QUEST(健康ハートフェス in 福岡) |
|
|
|
|
| 2026年3月22日(日)13:00~17:00 第2・3会場(福岡サンパレス 2FパレスルームA・B) |
|
| 詳細はこちら |
|
|
|
| |
|
|
| オンデマンド配信セッション(現地開催なし) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
2024年度医師臨床研究助成報告会
(学術委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2024年度メディカルスタッフ研究助成報告会
(学術委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
Circulation Journal Award Session
(編集委員会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 演 者: |
|
|
| |
|
|
| |
小島 淳
| ( |
桜十字八代リハビリテーション病院 / 熊本大学) |
|
|
| |
David Hong
| ( |
Division of Cardiology, Department of Medicine, Heart Vascular Stroke Institute, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Korea) |
|
|
| |
Jiexin Li
| ( |
Department of Cardiology, Guangdong Province Key Laboratory of Arrhythmia and Electrophysiology, Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University, China) |
|
|
| |
大河 秀行
| ( |
名古屋大学 心臓外科 / 中京病院 心臓血管外科) |
|
|
| |
Woo Jin Jang
| ( |
Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Chung-Ang University Hospital, Chung-Ang University College of Medicine, Korea) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
ESC-JCS Young Joint Symposium
(渉外委員会(国際)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年3月20日(金・祝)8:00~10:00 第16会場(福岡国際会議場5F 502) |
|
|
|
| Management of Acute Coronary Syndrome with Large Thrombus Burden |
|
| 座 長: |
|
|
| |
Aleksandra Gasecka
| ( |
Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland) |
|
|
|
| 演 者: |
Aleksandra Gasecka
| ( |
Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland) |
|
|
| |
Dario Bongiovanni
| ( |
University Hospital Augsburg, Augsburg, Germany) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|