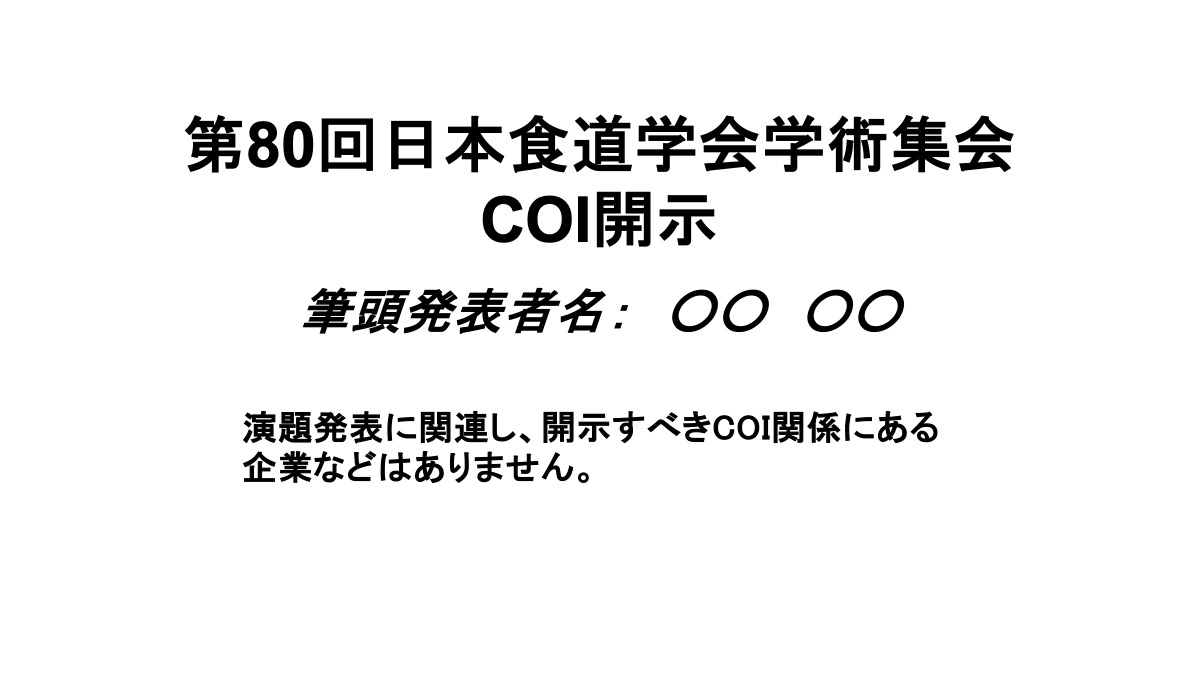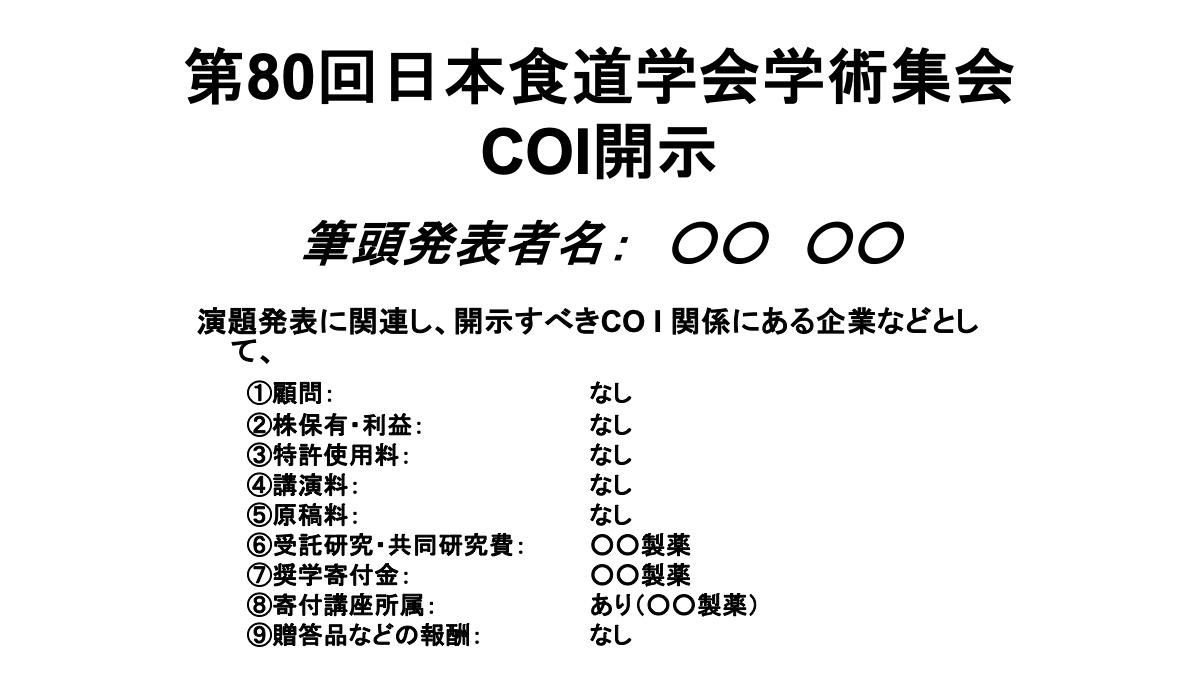演題募集
応募規定
-
筆頭演者は日本食道学会員に限ります。
応募時点で筆頭演者が非会員の場合は、会員番号欄に「999999」を入力し、筆頭演者に限り2026年4月20日(月)までに入会手続きを済ませてください。
会員でない場合には発表をお断りすることがあります。※看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、薬剤師などの準会員も同様です。医学部学生の演題応募に際しては学会の入会義務はありません。
※準会員の初年度の会費および学術集会参加費が免除されます。
詳細は、日本食道学会ホームページのお知らせをご確認ください。
https://www.esophagus.jp/private/information/news_20241018.html- ● 入会に関するお問い合わせ
-
特定非営利活動法人 日本食道学会 事務局
〒130-0012 東京都墨田区太平2-3-13 廣瀬ビルディング4階
TEL:03-6456-1339
FAX:03-6658-4233
E-mail:office@esophagus.jp
- 年会費納入者であること
筆頭演者は、年会費は演題登録年度と、発表年度の2年度分の納入が必要になります。
2026年4月20日(月)までに年会費納入手続きを済ませてください。
会費未納者は、発表ができませんのでご注意ください。 - 倫理審査の要/不要について
日本食道学会の演題応募に際しては、倫理審査が不要な発表以外は、必ず所属施設または関連の大学病院・関連学会(学会に研究倫理審査機能がある場合)・医師会等の倫理審査制度を利用し承認を得たうえで演題登録を行ってください。
倫理審査委員会の審査状況については、応募画面内にチェックリストを設けておりますので、ご回答をお願いいたします。チェックリストは応募者に臨床研究を行う上で、順守すべき倫理指針を再認識していただくことを目的としています。選択された内容について、査読委員から異議があった演題は、第80回学術集会プログラム委員会にて検証を行い、倫理的に問題があると判定された場合は、不採用となりますのでご注意ください。
なお、倫理審査委員会の承認番号は不要です。
発表内容がどの項目に該当するかについては、下記をご確認ください。 - 演題応募時には利益相反についての開示申告が必要です。
- 「主題演題」にご応募され、採択されなかった演題に関しましては、「一般演題」として採択審査を行います。
演題募集期間
| 2025年11月10日(月)正午~ | 2025年12月18日(木)正午 |
| 2026年1月8日(木)正午 | |
| 2026年1月22日(木)正午 | |
| 演題募集を締め切りました。 多数のご応募ありがとうございました。 |
演題カテゴリー
- 会長特別企画
-
歴代理事長が語る 第80回日本食道学会
- 特別企画
-
日本胃癌学会との合同企画
「EGJ腫瘍の診断と治療」食道胃接合部癌は本邦でも増加傾向であり、食道外科領域においてもその治療法の確立は重要な課題となっている。術前化学療法の上乗せ効果を検証するランダム化比較試験が進行中であるが、治療の標準的戦略は確立されていない。特に手術のアプローチ法(経裂孔的アプローチ、胸腔アプローチなど)や再建方法などは統一されておらず、根治性と術後QOLを両立させた手術の工夫が求められる。本合同セッションでは、食道外科医と胃外科医のそれぞれの立場から最新データと各施設の治療成績を提示いただき、薬物療法を含めた集学的治療の現状と課題、至適治療戦略を議論したい。
-
日本放射線腫瘍学会との合同企画
「放射線治療の高精度化による治療の適応拡大」放射線治療の高精度化により、単に有害事象が減少するだけでなく、リスク臓器(OAR)や既照射部位への照射、他治療との併用が容易になりました。さらに、線量増加や治療の寡分割化が可能となったことから、これまで放射線治療が困難な患者、制御が難しかった病態の患者、などに対しても放射線治療の選択肢が広がりました。食道癌においても、強度変調放射線治療(IMRT)、体幹部定位放射線治療(SBRT)、といった高精度放射線治療が一定の条件下に保険適用となっています。また、粒子線治療(陽子・重粒子)も先進医療として行われています。そこで本セッションでは、「放射線治療の高精度化による治療の適応拡大」というテーマで最新の知見と今後の展望について議論したいと思います。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
-
日本リハビリテーション医学会との合同企画
「食道癌治療におけるリハビリテーション治療とチーム医療」食道癌の集学的治療が進展する中、リハビリテーション治療と多職種連携によるチーム医療の重要性が高まっており、各施設で様々な取り組みをされていることと思う。本セッションでは治療前から退院後までの包括的なリハビリテーション治療の重要性を再確認する。こうした取り組みにおいて他職種連携によるチーム医療の実践が重要であり、医師、看護師、理学療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、栄養士といった他職種での関わりが望まれる。多職種間の情報共有の在り方やシームレスな連携体制構築のためのヒントを共有することで、各施設でのチーム医療の向上に寄与することを期待している。リハビリテーション治療の重要性を示す新知見や各施設の取り組み等をご発表いただきたい。
-
日本外科代謝栄養学会との合同企画
「食道癌周術期における栄養管理のState of the art」食道癌手術は消化器外科領域において最も侵襲の大きい術式の一つであり、術前から低栄養や嚥下機能低下を伴う患者も少なくなく、周術期の栄養管理は合併症予防や術後回復に直結する極めて重要な要素である。近年、サルコペニアやフレイルの概念が広く浸透し、栄養介入の意義が改めて注目されている。一方で、栄養管理の導入や評価法には施設ごとにばらつきがあり、さらなる標準化と実臨床への普及が課題となっている。本セッションは日本外科代謝栄養学会との合同企画として、食道癌周術期における栄養管理の “State of the art” を共有し、今後の展望と課題について議論することを目的として企画された。本討論が、今後の診療の方向性をより明確にし、日常臨床に還元されることを期待する。
-
日本頭頸部癌学会との合同企画
「頭頸部癌・頸部食道癌に対する治療戦略」本セッションは、日本頭頸部癌学会との合同企画として開催されます。食道癌と頭頸部癌は、解剖学的にも機能的にも密接な関係を有しており、治療戦略においても放射線治療、化学療法、手術療法の選択やタイミング、さらには嚥下・発声機能の温存といった観点で多くの共通課題を抱えています。近年では、境界領域における集学的治療の重要性が高まり、診療科を越えた連携が患者予後の向上をもたらす時代となっています。本企画では、両学会のエキスパートが一堂に会し、治療方針の最適化、機能温存の工夫、再建術式の選択、さらには免疫療法やゲノム医療の応用可能性についても議論を深めます。領域横断的な知見の共有を通じて、より質の高い医療の実現に向けた新たな展望を探る場としたいと考えています。
- 患者さん参加企画
-
患者さん参加企画
- International Session
-
SANO trialを語る
SANO試験(オランダ)は、CROSS regimenによる化学放射線療法終了後に、6~12週間cCRを示す局所進行食道癌に対して、積極的サーベイランスを実施する群と、標準手術療法を実施する群のRCTである。標準手術療法に対する積極的サーベイランスの非劣性がOSで証明された。SANO試験の結果を踏まえ、欧州からProf. Bas P.L. Wijnhoven、Prof. Magnus Nilssonの2名の演者を招聘し、日本の演者を加えて、SANO試験の議論を深める。本セッションは指定演者による英語セッションの予定である。
-
TSTS/JES Joint Session
日本食道学会JESと友好関係にある台湾胸部外科医学会TSTSとのコラボ企画で、両国における標準手術術式を議論する。胸部食道癌に対する標準手術術式をビデオ提示により紹介。本セッションはTSTSからは指定演者(3名)、JESからは指定演者+公募(計3名)による英語セッションの予定である。
- ビデオシンポジウム
-
ロボット手術 上縦隔郭清手技
食道癌治療におけるロボット支援胸腔鏡下手術(RAMIE)の進歩は著しく、上縦隔郭清の安全性向上と精度向上を両立させるアプローチであり、短期成績のアウトカムに大きく寄与していると考えられます。本セッションでは、最前線でご活躍の先生方に動画をご提示いただき、それぞれの施設での最新の知見や技術、ならびにその工夫をご紹介いただきます。反回神経麻痺予防を目標とした手術手技、デバイスの選択基準、腹臥位/左側臥位の体位選択やポート配置、助手の位置づけ、手技のピットフォール、さらにロボット手術で明らかとなった上縦隔の気管傍領域の精緻な層構造の解剖など、多岐に亘る議論を行います。日常臨床の質向上や新たな発見に繋がる充実したセッションとなることを期待します。
-
頸部郭清手技
食道癌手術において頸部郭清は必須の手技であるが、複雑な解剖学的構造の理解や反回神経の確実な同定と温存など熟練を要する部分が多い。頸部郭清は直視下の手技であるがゆえに、胸腔鏡やロボットでの胸部操作のように共通の解剖理解が進んでいるとはいまだ言い難く、各施設でさまざまな工夫のもとに行われている。本セッションでは#104リンパ節郭清や#101リンパ節郭清の実際をビデオで供覧していただき、標準的な頸部郭清手技から難易度の高い症例に対する工夫、ピットフォールに至るまで、各施設での手技の全貌を余すことなく解説いただきたい。術者が直面する技術的課題や解剖の理解に焦点をおいて解説いただくことで、参加者が安全かつ確実な郭清手技を習得する一助となることを期待している。エキスパートのみならず、若手食道外科医からの発表もお待ちしている。
-
縦隔鏡手術
縦隔鏡手術は低侵襲食道悪性腫瘍手術の新たなアプローチとして注目されています。特に経胸腔操作を回避できる点から、高齢者や呼吸機能低下例に対し、術後呼吸器合併症発生率の低減に寄与する可能性が示されており、その実施施設数は増加傾向です。一方で、術野の制限やリンパ節郭清の精度、反回神経麻痺のリスク、術者の習熟度による成績のばらつきなど、技術的課題も存在します。近年では、ロボット支援下縦隔鏡手術も増加傾向にあり、縦隔鏡の役割は単なる代替手段から、病態や患者背景に応じた戦略的選択肢へと進化しつつあります。本セッションでは、縦隔鏡手術の現状と課題、またその適応拡大の可能性、さらには今後の技術革新の方向性について、最新の知見と実臨床の経験をもとに多角的に議論したいと考えています。
-
食道癌におけるESDの最前線
食道癌に対するESDは全国的に広く普及し,その手技はすでに標準的治療として確立されつつあり,近年では全周性病変に対しても適応される時代となっております。しかし,短時間でかつ安全・確実に施行するためには,依然として手技的工夫やデバイスの改良が求められています。ESD後や放射線治療後の瘢痕を伴う病変,あるいは食道静脈瘤を合併する病変といった困難症例に対するESD手技の工夫は重要です。さらに,遅発性穿孔や広範囲筋層露出などの有害事象に対するトラブルシューティング,ならびに術後狭窄の予防策についても議論の対象となります。実際の手技の工夫をビデオにより共有することで,食道ESDのさらなる安全性と治療成績向上に資する活発な討論が展開されることを期待しております。
- シンポジウム
-
JCOG1409を科学する
JCOG1409(MONET試験)は、臨床病期I/II/IIIの胸部食道癌を対象に、OSを主要評価項目とした開胸食道切除術に対する胸腔鏡下食道切除術(MIE)のランダム化第III相試験試験であり、低侵襲手術の oncologic safety を検証する重要な臨床試験であった。2024年に発表された結果では、MIEは開胸手術に対して生存率で劣らず、術後合併症の低減やQOLの向上にも寄与する可能性が示され、今後の標準治療の再定義に大きな影響を与えると考えられます。本セッションでは、JCOG1409の試験デザイン、主要・副次的評価項目、サブグループ解析などを多角的に検討し、食道癌における低侵襲手術の位置づけと今後の展望について議論を深めたいと考えています。
-
cT1N0M0食道扁平上皮癌の診断・治療の最前線
本シンポジウムでは,「cT1N0M0」食道扁平上皮癌の診断・治療の最前線を幅広く取り上げます。画像強調併用下拡大内視鏡観察や超音波内視鏡による深達度診断に関する最新のエビデンスや課題をはじめ,粘膜内癌に対する ER の役割を前提に,MM/SM1 の境界症例における脈管侵襲陽性例への対応や,診断的治療後の追加治療の最適化について取り上げます。とくに MM/SM1 では術前深達度診断に限界があり,切除標本に基づく病理評価が意思決定の要となります。JCOG0508 の結果では,ER 先行後に選択的 CRT を加える臓器温存戦略の有効性が示された一方で,手術との直接比較など未解決の課題も残されています。長期成績,脈管侵襲陽性時の対応,サーベイランスと救済治療を含めて,実臨床データに根ざした診断・治療アルゴリズムを多職種で共有します。内科・外科をはじめ,多職種からの実践的な演題のご応募を広く歓迎します。
-
食道癌取扱い規約 第12版 の問題点
2022年に発行された「食道癌取扱い規約第12版」では術前治療が標準となった時代に対応するために新たなステージング分類が策定された。cT3がcT3rとcT3brに亜分類され、N分類に転移個数による分類が採用され、鎖骨上リンパ節がM1aとなった。またリンパ節郭清度(D)が術式により規定される一方、省略可能なリンパ節も示された。食道の区分として腹部食道(Ae)をなくして食道胃接合部(Jz)が新たに規定され、日本胃癌学会と合同で、食道胃接合部癌の定義および記載項目が整理された。このように大幅な改定が行われており、各施設において臨床の場で術前診断や患者説明の内容、郭清リンパ節の範囲などに、以前と比べ差異が生じているものと思われる。本セッションでは各施設における実際の運用において利点・欠点と感じる部分を整理してご発表いただきたい。
- パネルディスカッション
-
Barrett食道ならびにBarrett食道腺癌に対する内視鏡診断と治療
Barrett食道は食道腺癌の発生母地として極めて重要であり,特にlong segment Barrett食道(LSBE)においては,腺癌発症リスクを踏まえた精緻な内視鏡診断およびサーベイランス体制の確立が喫緊の課題とされています。Barrett食道腺癌に対しては,食道学会分類に基づく拡大内視鏡観察と画像強調内視鏡による表面微細構造評価が実臨床に導入されつつあり,さらに人工知能(AI)による診断支援の応用も期待されていますが,いまだ未解決の問題も少なくありません。治療面においては,ESDによる一括切除の有効性と安全性が報告されている一方,全周性病変では高度狭窄の発生が大きな制約となっています。その克服策としてstepwise ESDやESD後狭窄予防を目的とした各種薬物・焼灼併用療法の有効性が検討されています。本セッションでは,これら最新の知見を踏まえ,Barrett食道関連病変に対する内視鏡診断と治療の現状と将来展望について,多角的かつ実践的な討論が行われることを期待いたします。
-
改めて再建を考える「小腸再建 vs 結腸再建」
食道癌手術において再建は根治性と並び重要な要素であり、再建臓器の選択は術後合併症や術後機能、さらには患者のQOLに大きく影響する課題である。標準的には胃管による再建が広く行われているが、胃の使用が困難な症例においては小腸あるいは結腸を用いた再建が必要となる。その選択にあたっては血流の安定性、吻合部位の安全性、栄養状態や長期機能といった多角的な視点が求められる。しかしながら現時点においても小腸再建と結腸再建の優劣に関して明確な結論は得られていない。本セッションでは各施設の経験や工夫を共有し、両者の特性と課題を改めて整理することで、再建法選択の今後の方向性を考えるとともに、発展に向けての課題を議論する場となることを期待する。
-
IO時代における食道癌一次治療のアップデート
免疫チェックポイント阻害薬(IO)の登場は、食道癌治療に大きな変革をもたらしました。近年ではPD-1阻害薬に加え、CTLA-4阻害薬併用の治療開発も進み、一次治療における免疫療法の役割はますます拡大しています。従来の化学療法や化学放射線療法との併用に加え、さらにはバイオマーカーによる層別化や個別化治療の可能性も議論されており、治療体系の再構築が求められています。一方で、扁平上皮癌と腺癌における治療効果の違い、免疫関連有害事象の管理や長期予後の評価、新規IOの位置づけなど、臨床的課題も多く残されています。本セッションでは、IO時代における一次治療の最新エビデンスと今後の一次治療の目指すべき方向性を議論する有意義なセッションを目指します。
-
食道癌Translational researchの最前線
食道癌の治療成績向上には、基礎と臨床をつなぐTranslational Research(橋渡し研究)が不可欠です。近年、食道癌に関しては、分子病態解析、新規バイオマーカー探索、免疫療法の開発、腫瘍微小環境やゲノム・代謝解析、治療耐性機序の解明など、多岐にわたる革新的な成果が報告されています。本セッションでは、これら食道扁平上皮癌および腺癌に関する幅広い領域の最新研究成果を基盤に、今後の新規治療開発に向けた議論を深めます。特に、シングルセル空間解析をはじめとする先端技術や新規アプローチを活用した創造的かつ挑戦的な研究発表を歓迎します。第一線でご活躍される先生方はもちろん、若手の先生方からの積極的なご応募もお待ちしております。
-
食道癌に対するPDTの最前線
食道癌に対する光線力学療法(PDT)は,放射線治療後の遺残あるいは再発病変を対象に施行されています。そのうえで,外科手術や内視鏡的切除術が困難な症例における局所制御の有効な選択肢として位置づけられてきました。近年は第二世代の光感受性薬剤や改良されたレーザー装置の導入により,治療成績や安全性が向上しています。一方で,治療後狭窄や再発時の対応,適応基準の明確化,さらに医療資源やコストの問題など,日常診療において解決すべき課題も少なくありません。本パネルディスカッションでは,最新の臨床データや実際の治療戦略を共有しつつ,PDTの現状と問題点を整理し,今後どのように臨床に位置づけていくべきかを多角的に議論したいと思います。
-
IO時代におけるConversion surgery
切除不能・再発食道癌に対しては全身化学療法が第一選択となるが、そこで奏効が得られた場合、根治を目指したConversion surgeryが検討可能となる。しかし従来の化学療法のみではConversion surgeryを検討できる段階まで進む症例は限られていたが、近年免疫チェックポイント阻害剤(IO)が1次治療で化学療法と使用できるようになり、奏効率が向上している。こうしたIO併用化学療法により、T4が解除され切除可能な状態になったり、遠隔転移が消失または少数転移(Oligometastasis)のみの状況になる機会が増えてきた。こうした症例に対してConversion surgeryが検討されるが、しかし現状その適応基準や治療成績は明確ではない。本セッションでは、Conversion surgeryの各施設での治療方針や治療成績についてご発表いただき、今後の治療戦略の構築に向けて議論を深めていただきたい。
-
食道扁平上皮癌の発癌におけるアルコールの影響
本パネルディスカッションでは,アルコールと食道扁平上皮癌(ESCC)の発癌との関連を,基礎から臨床まで多角的に議論します。WHO(世界保健機関)は「アルコールに安全な量はない」と明確化し,少量でも累積曝露がリスクに寄与するとしています。また IARC(国際がん研究機関)は「飲酒に伴うアセトアルデヒド」をヒト発癌物質 (Group 1)に位置づけ,因果関係は国際的に確立した知見です。近年は ALDH2 機能低下や TP53 経路異常と飲酒が相まってフィールド癌化を促す知見も示され,禁酒後も発癌リスクが残ることから,ハイリスク患者への継続的スクリーニングと指導が重要です。リスク層別化,禁酒支援,内視鏡スクリーニングから治療・サーベイランスまで,実装可能な戦略を広く募集します。
- ビデオワークショップ
-
ロボット手術における手技の工夫
ロボット支援下食道切除術は、食道周囲の複雑な解剖に対して高精度な操作を可能とする低侵襲手術として、近年急速に普及しています。多関節鉗子による繊細な剥離操作や安定した視野の確保により、根治性と安全性の両立が期待されており、術後合併症の低減にも寄与する可能性があります。一方で、術野展開の工夫、ポート配置や鉗子の選択、助手との連携、エネルギーデバイスの使い分けなど、術者の創意工夫が求められる場面も多く、各施設において最適解を模索しているのが現状です。また、ロボット特有の操作体系に対する教育・習熟の課題も重要であり、技術の標準化と継承に向けた取り組みも不可欠です。本セッションでは、ロボット支援下食道切除術における手技の工夫と技術的課題、さらに教育的視点を含め、実臨床に根ざした知見をもとに多角的な議論を深めたいと考えています。
-
胸腔鏡手術における手技の工夫
胸腔鏡手術は、低侵襲性と拡大視野を活かした食道癌手術の標準的アプローチとして広く普及しており、呼吸器合併症の軽減や術後QOLに寄与する技術として高く評価されています。一方で、ロボット支援手術とは異なり、鉗子の可動域や視野の安定性に制限がある中で、術者の熟練した操作と術野展開の工夫が求められます。ポート配置、体位の工夫、重力を活用した臓器牽引、助手との連携、エネルギーデバイスの選択など、術者の経験に基づく細やかな工夫が手術の安全性と根治性に直結します。また、施設間での技術的格差や教育的課題も依然として存在し、標準化に向けた議論も重要です。本セッションでは、胸腔鏡手術における手技の工夫と技術的課題について検討し、今後の発展に向けた展望を共有したいと考えています。
- ワークショップ
-
食道狭窄に対する内視鏡治療の現状と工夫
食道狭窄は,食道切除術やESD後の瘢痕形成,放射線治療後の変化,さらには良性疾患に伴って発生し,嚥下障害を介して患者のQOLを著しく低下させる重要な臨床課題です。従来より内視鏡的バルーン拡張術(EBD)やブジー拡張術が広く行われてきましたが,近年ではradial incision and cutting(RIC)やステロイド局注の併用といった新たな治療戦略も導入されています。それにもかかわらず難治性の食道狭窄は依然として存在し,一時的な自己拡張型金属ステント留置が行われるほか,生体分解型ステントの実臨床への応用も期待されています。本ワークショップでは,各施設における実践的工夫や最新のエビデンスを共有し,食道狭窄に対する内視鏡治療の現状を整理するとともに,今後の治療戦略の方向性について多角的に議論する場としたいと考えております。
-
食道良性疾患に対する内視鏡診断・治療の最前線
日常診療でも遭遇する食道良性疾患として,胃食道逆流症(GERD)をはじめ,好酸球性食道炎/食道筋炎,食道アカラシア,Zenker 憩室,食道粘膜下病変まで多岐にわたります。近年の内視鏡診療の進歩に伴い,各疾患の病態解明が進んだだけでなく,機能内視鏡として EPSIS などの新たな診断モダリティも登場し,病因や診断に関する知見が着実に蓄積されています。一方,治療では,内視鏡的逆流防止粘膜切除術(ARMS/ESD-G)や POEM,Z-POEM,POETなど,食道良性疾患に対する内視鏡治療の開発・発展が進んでおり,従来の外科的治療から内視鏡治療への移行が進展しているとも言えます。本ワークショップでは,これら食道良性疾患に対する各施設における診断の工夫や治療成績,最新のエビデンスを広く募集し,今後の治療戦略の方向性と可能性について多角的に議論する場としたいと考えています。
-
オリゴ転移の治療方針
食道癌におけるオリゴ転移は、従来の全身病という概念から脱却し、局所制御可能な病態として再定義されつつあります。転移巣の数や部位、治療反応性に応じて、外科的切除や定位放射線治療、全身化学療法を組み合わせた集学的治療が現実的な選択肢となり、長期生存を目指す戦略が模索されています。近年では、臨床的に意義のあるオリゴ転移の定義や診断基準の統一、治療介入のタイミングに関する議論も活発化しており、個別化医療の進展とともに治療方針の再構築が求められています。本セッションでは、最新のエビデンスと実臨床の経験をもとに、オリゴ転移に対する治療の可能性と限界を多角的に検討し、今後の標準治療の構築に向けた展望を共有したいと考えています。
-
T3br・T4症例に対する診断と治療
局所進行食道癌 cT3brおよびcT4症例は、診断・治療のいずれにおいても不確実性が高く、施設間格差も大きい。しかしながら近年、テクノロジーの進歩とともに診断能・治療成績はともに改善しつつある。本セッションでは各施設からの画像診断技術や内視鏡所見との組み合わせによる他臓器浸潤評価方法、適切な術前治療とそのタイミングの選択や、ロボットを含む鏡視下手術での拡大視効果による安全な手術操作、各施設での手術アプローチや他臓器合併切除手技、また、食道-大動脈瘻/気管瘻を予防する安全な化学放射線療法、さらには集学的治療の可能性など幅広い観点から演題を募集します。個別化医療と安全性を両立する最適な治療戦略を提示していただき、診断・治療のストラテジーとその適応・限界について多角的に討議したいと思います。
-
特発性食道破裂に対する治療戦略
特発性食道破裂は比較的まれな疾患であるが、発症早期からの診断と適切な治療介入が予後を大きく左右する重篤な病態である。臨床現場では、診断の遅れによる縦隔炎や膿胸の進展を防ぎつつ、患者の全身状態や病態に応じて手術適応や手術法を適切に判断することが求められる。しかしながら、その臨床像は非特異的で診断に難渋することも少なくなく、また症例数の少なさゆえに治療法選択に関する明確な指針は未だ確立されていないのが現状である。各施設での経験や工夫が重要な役割を果たしており、今後は症例の集積と情報の共有を通じて、より実践的なエビデンスを構築することが求められる。本セッションでは多施設からの知見を集約し、診断から治療選択、周術期管理に至るまでの課題を整理することで、今後の診療に生かされる場としたい。
-
食道疾患におけるAI内視鏡診断・AI navigation surgeryの導入
近年、AI技術の発展は医療分野にも急速に波及しており、食道疾患においてもAI内視鏡診断やAI navigation surgeryの導入が現実味を帯びてきています。内視鏡診療において、内視鏡画像をリアルタイムで解析し、病変の検出や深達度の推定を支援する内視鏡AIは、術前評価の精度向上と診断の均質化をもたらす可能性があります。また、手術支援領域では、AIによる解剖構造の認識や、危険領域の警告表示など、術者の判断を補完する技術として期待が高まっています。一方で、AIの臨床導入にあたっては、精度・安全性・責任の所在など、慎重な議論が求められます。本セッションでは、消化器内視鏡および外科の双方の視点から広く演題を募集し、食道疾患におけるAI技術の現状と課題、臨床応用の可能性、そして今後の展望について議論したいと考えています。
-
食道癌術後補助療法の適応とその実際
CheckMate577試験では、術前化学放射線療法(NACRT)で病理学的完全奏効が得られていない食道癌に対する術後ニボルマブの有効性が示された。本邦ではNACRT症例のみならず、術前化学療法(NAC)症例に対しても術後ニボルマブが保険適応となり、エビデンスが確立していない状態で投与されているのが現状であり、現在、JCOG2206試験においてNAC症例に対する術後無治療/ニボルマブ療法/S-1療法のランダム化第III相試験が行われている。本セッションでは、各施設から術後補助療法のデータをご提示いただき、その適応と、実際の治療成績、そして課題について多角的な視点から議論を行う。本邦の実臨床に即した知見を共有し、最適な治療を導き出すための指針を構築する機会としたい。
-
食道扁平上皮癌に対する術前補助療法の実際
食道扁平上皮癌の術前補助療法は、JCOG1109試験により、DCF療法が新たな標準治療として位置づけられ、大きな転換期を迎えている。近年では、免疫チェックポイント阻害薬を併用した術前化学療法の開発も活発で、病理学的奏効率の向上が報告されるなど、今後の治療体系を大きく変える可能性を秘めており、周術期治療はさらなる改良が求められています。本セッションでは、標準化されつつある術前化学療法に加え、その発展が期待される術前免疫化学療法、そしていまだ議論の余地がある術前化学放射線療法の位置づけを各施設からのデータをもとに報告していただきたい。さらに外科医の視点からも、それぞれの術前治療後の鏡視下手術やロボット支援手術における安全性に関する工夫、周術期管理のポイントまで踏み込み、議論を深める機会としたい。
- ディベート
-
食道再建腹部操作 LAP vs HALS vs Robo
食道癌手術における腹部操作は、再建経路の確保と胃管作成に加え、腹部リンパ節郭清を含む極めて重要なプロセスであり、その方法の選択は術後の回復過程や長期機能に直結し、治療成績を左右する重要な要素である。従来は開腹手術が主流であったが、近年は腹腔鏡下手術(LAP)や用手補助腹腔鏡下手術(HALS)が導入され、さらにロボット支援手術(Robo)へと選択肢が広がっている。それぞれに操作性、低侵襲性、習熟度、コストなど利点と課題が存在し、いまだ最適な方法について明確な結論は得られていない。本ディベートではLAP、HALS、Roboそれぞれの立場から最新の知見と経験を提示し、その優位性や適応について議論する。活発な討論を通じて、今後の腹部操作の標準化と発展に向けた方向性を共有する場としたい。
| カテゴリー | テーマ | |
|---|---|---|
| A:基礎 | 1 | 分子生物学 |
| 2 | 病理学 | |
| 3 | バイオマーカー | |
| 4 | その他 | |
| B:全般 | 1 | 疫学 |
| 2 | データベース研究 | |
| 3 | トランスレーショナルリサーチ | |
| 4 | 人工知能 | |
| 5 | 予防 | |
| 6 | メディカルスタッフ | |
| 7 | その他 | |
| C:良性疾患 | 1 | 先天性疾患 |
| 2 | 食道裂孔ヘルニア | |
| 3 | 食道憩室 | |
| 4 | 食道異物 | |
| 5 | 特発性食道破裂 | |
| 6 | 外傷 | |
| 7 | 好酸球性食道炎 | |
| 8 | 逆流性食道炎 | |
| 9 | その他の食道炎・食道潰瘍 | |
| 10 | Barrett食道 | |
| 11 | 良性食道狭窄(術後狭窄を含む) | |
| 12 | アカラシア | |
| 13 | 食道静脈瘤 | |
| 14 | 食道運動機能障害 | |
| 15 | 食道良性腫瘍 | |
| 16 | 症例報告 | |
| 17 | その他 | |
| D:悪性腫瘍 | 1 | 診断ー内視鏡診断 |
| 2 | 診断ー画像診断 | |
| 3 | 診断ーその他 | |
| 4 | 治療(手術)ー手術手技全般 | |
| 5 | 治療(手術)ー内視鏡下手術(胸腔鏡下、腹腔鏡下、縦隔鏡下手術など) | |
| 6 | 治療(手術)ーロボット手術 | |
| 7 | 治療(手術)ーConversion/salvage surgery | |
| 8 | 治療(手術)ー周術期管理 | |
| 9 | 治療(手術)ー合併症 | |
| 10 | 治療(化学療法)ー周術期化学療法 | |
| 11 | 治療(化学療法)ー緩和的化学療法 | |
| 12 | 治療(化学療法)ー免疫療法 | |
| 13 | 治療(放射線療法・化学放射線療法)―根治的 | |
| 14 | 治療(放射線療法・化学放射線療法)―緩和的 | |
| 15 | 集学的治療 | |
| 16 | 治療(内視鏡治療)ーEMR、ESD、ELPSなど | |
| 17 | 治療(内視鏡治療)ーPDT、ステント、PEGなど | |
| 18 | 症状緩和・緩和ケア | |
| 19 | 支持療法ー栄養管理、NST | |
| 20 | 支持療法ーリハビリテーション | |
| 21 | 支持療法ーチーム医療 | |
| 22 | 症例報告 | |
| 23 | その他 |
登録方法
- 抄録の文字数制限
演題タイトル:全角40文字/半角80文字
抄録本文:全角1,100文字/半角2,200文字 - 登録可能な著者数、所属施設
登録可能な著者数:筆頭演者を含め10名以内
登録可能な所属施設:10施設以内
所属登録は主たる所属機関のみとなります。(複数選択不可) - 原則として筆頭演者1名につき1演題のご応募といたします。
- 所属機関名は「大学名 所属科」で記載ください。
原則登録通りとさせていただきますが、一部抄録集に掲載する際に、主催校の判断で表記を統一する場合がございます。 - 演題登録時に、任意のパスワードを設定していただきます。パスワードを紛失した場合でも、セキュリティーの関係上問い合わせには一切応じられませんのでご注意ください。
- ご登録いただいた抄録はそのまま掲載されます。誤字・脱字・変換ミスを含め、校正・訂正は行いませんので、登録送信ボタンを押す前に、必ず内容に間違いがないかを十分にご確認ください。
- 登録完了後、ご登録いただいたメールアドレスに演題受領通知が送信されます。
2日を過ぎても受領通知がない場合、他の受信フォルダー(迷惑メール受信フォルダーなど)を確認のうえ、下記運営事務局までE-mailにてお問い合わせください。 - 一度登録された演題に修正を加えるときは、登録内容確認画面にアクセス後、登録番号とパスワードを入力し、ログイン後「修正」ボタンを利用します。締切期限前であれば、修正ができます。
- 一度登録された演題を削除するときは、登録内容確認画面にアクセス後、登録番号とパスワードを入力し、ログイン後「削除」ボタンを利用します。締切期限前であれば、削除ができます。
言語について
- 演題タイトル・著者名:日本語・英語いずれも可能です。
- 抄録言語:日本語・英語いずれも可能です。
※English Sessionは英語でのご登録、発表をお願いいたします。 - 発表言語:日本語・英語いずれも可能です。
- 発表スライド言語:日本語・英語いずれも可能です。
利益相反について
産学連携による臨床研究には、学術的成果の社会への還元(公的利益)だけでなく、産学連携に伴い取得する金銭・地位・利権など(私的利益)が発生する場合があり、この二つの利益が研究者個人の中に生じる状態を利益相反と呼びます。
日本食道学会は、2011年9月27日に施行された「食道疾患臨床研究の利益相反に関する指針」(平成25年6月12日「食道疾患研究の利益相反に関する指針」に名称変更)に従い、臨床研究の学会発表での公明性を確保するため、第67回学術集会より発表者の利益相反状態について自己申告を行っていただくこととなりました。
当日は、利益相反状態の有無に関わらず、状況を開示いただきます。
なお発表に際し、画像やデータ等の提供を受けた場合、共同演者に加えるか、謝辞に掲載するようにしてください。
| 例) | ・病理画像を病理医に依頼し、コメントを記載した場合 |
| ・放射線画像について放射線科医のコメントを記載した場合 など |
発表当日の開示フォーム
- 口演セッションで発表の方
スライド2枚目(タイトルスライドの次)に、挿入して開示してください。
- ポスターセッションで発表の方
ポスターの演題名の下に COI 状況を開示してください。
各種アワードに関して
以下3種のアワードを学術集会にて選考いたします。
- 優秀演題賞 および 最優秀演題賞
- 若手奨励賞 および 最優秀若手奨励賞
- メディカルスタッフ賞 および 最優秀メディカルスタッフ賞
選考対象
- 優秀演題賞 および 最優秀演題は、全一般演題を選考対象とする。
- 若手奨励賞 および
最優秀若手奨励賞は、演題募集時に応募を希望した演題を対象とする。
若手奨励賞の応募対象は、2026年3月31日時点で40歳以下の医師・研究者とする。
若手奨励賞に応募した場合は、優秀演題賞の選考対象外とする。 - メディカルスタッフ賞 および
最優秀メディカルスタッフ賞は、準会員(看護師、臨床検査技師、薬剤師、放射線技師、理学療法士、作業療法などの医師以外の医療従事者)の演題を対象とする。
なお、演題応募時に非会員の場合には、職種の確認ができないため、対象外とする。
- いずれの賞も一般演題にて採用となった演題を対象とする。
演題登録に関するお問合せ先
第80回日本食道学会学術集会 運営事務局
株式会社コングレ 東北支社
〒980-0811
仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング
E-mail:80jes-abs@m.congre.co.jp
※ご連絡のお問い合わせはメールにていただきますよう、お願い申し上げます。