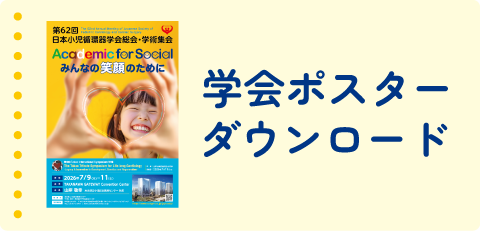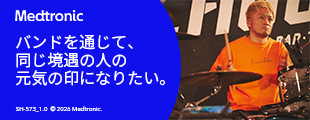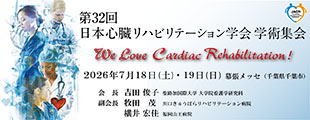会長挨拶

- 第62回日本小児循環器学会総会・学術集会
- 会長 山岸 敬幸
東京都立小児総合医療センター 院長
慶應義塾大学医学部小児科 客員教授
第62回日本小児循環器学会総会・学術集会を、2026年7月9日(木)~11日(土)の3日間、新たに竣工したTAKANAWA GATEWAY Convention Center(東京都港区)において開催する運びとなりました。本学会は、小児期に発症する心血管疾患に対し、胎児期から成人期に至るまでの切れ目ない医療の実現をめざし、専門職の垣根を越えた連携と学術の発展を通じて、こどもたちの健やかな成長を支えることを使命としてまいりました。今回のテーマは、「Academic for Social みんなの笑顔のために」です。小児循環器学は、科学的・専門的な知見を深めるのみならず、その成果を社会に広く還元し、医療・教育・福祉に寄与する責任を担っています。医療が社会に果たす役割は今、大きな転換点を迎えており、医療者と研究者の「学術(Academic)」活動を「社会(Social)」にどうつなげるかが問われています。私は、これまで2期4年間、本学会理事長を務め、この課題に積極的に取り組む中、新たに開発された薬剤・医療機器や考案された医療体制を、いち早く患者さんに届けるために、産官学が連携して顔の見える関係で、同じ方向に力を合わせることの大切さを改めて痛感しました。私たちの学術集会が、医療現場と社会、科学と生活、そして未来のこどもたちを結ぶ架け橋となり、社会のみんなの笑顔につながることを願い、このテーマを掲げました。
本学術集会では専門的な学術セッションに加え、「市民公開講座」を拡大し、このテーマの実践の場と位置づけ、著名人のご登壇も得て、患者さん・ご家族、一般の市民と医療者・研究者が直接交流・対話できる機会を設けます。医療者が科学をやさしく社会に伝え、市民の声に耳を傾けることは、共感に基づく医療の第一歩です。この公開講座では、社会とつながる「開かれた学会」の姿を具現化します。
小児循環器学領域を取り巻く社会環境は、近年大きく変化しています。こども家庭庁の発足、成育基本法・循環器病対策基本法の施行などにより、こどもと家庭を包括的に支援する体制が整いつつある一方、成人先天性心疾患患者は50万人を超え、年間約1万人ずつ増えており、私たちの領域はもはや小児期にとどまりません。成人期医療を含む生涯にわたるシームレスな「小児・成育循環器学」が学術集会の大きなターゲットとなります。
国際的な協力関係の強化も本学術集会の柱です。American Heart Association(AHA)、Association for European Pediatric and Congenital Cardiology(AEPC)などとの国際ジョイントセッションや、アジア諸国の関連学会との連携を通じて、グローバルな視点から最新の課題と解決策を議論します。さらに今回、国際交流の象徴ともいえる第9回Takao International Symposiumを併催します。国内外の超一流の医学者と対面・聴講・議論することで、わが国そして欧米・アジア諸国の、特に将来を担う小児循環器学に携わるすべての参加者のモチベーションを高め、国際的に本領域の研究・診療・教育のレベルの向上に寄与することを目指します。
本学会は、創設以来、小児科医、心臓外科医、循環器内科医、産婦人科医、集中治療医、看護師、臨床工学技士、検査技師、薬剤師、心理士、社会福祉士など多様な職種が垣根を越えて集う、学際的な学会として発展してきました。本学術集会でも、多職種が協働し、チーム医療のあり方をともに考えるプログラムを多数企画しています。
私たちが目指すのは、「学術と社会」が響き合う場です。本学術集会を、未来都市をイメージして創造されたTAKANAWA GATEWAYの会場で、日本の小児循環器学の新たな時代の幕開けを皆様と共有し、すべてのこどもたちと家族の笑顔につながる実り多き機会にしたく、全力で臨みます。