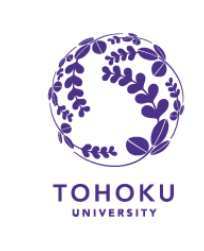

コンパニオンミーティング
開催一覧
4月17日(木)18:40~20:10
コンパニオンミーティング 1
日本膵胆道病理研究会
B会場(会議棟 2F 橘)
「膵胆道病理学と国際連携」
日本膵胆道病理研究会(PCPCJ)は、2006年に結成された日本膵臓病理研究会(PPCJ)を前身とし2017年に現在の形となった研究会で、膵胆道病変の病理に興味を持つ病理医が集まった研究会です。これまでほぼ毎年、コンパニオンミーティングにも応募し開催してきました。
今回は、学会にジョンズホプキンス大学のRalph Hruban教授が招待されることになっていることから、「胆膵病理学と国際連携」と題して、日本の膵胆道病理領域におけるこれまでの国際連携を紹介するとともに今後を考える企画としました。なお、Ralph Hruban教授にも参加いただき、最後に特別発言をいただく予定です。
コンパニオンミーティング 2
日本デジタルパソロジー研究会
C会場(会議棟 2F 萩)
「世界は進んでいる - 知っておくべきデジタルパソロジーと病理人工知能アップデート -」
欧米のみならず、アジア各国を含む世界ではデジタルパソロジーと人工知能の分野における発展は目覚ましいものがあります。今後病理の業務を変えてしまうインパクトのあるデジタルパソロジー。日進月歩のこの分野について情報をアップデートすることはとても重要と思われます。しかし、病理学会の中で充分な教育プログラムは組まれておらず、教育と情報提供の場が必要と感じています。日本デジタルパソロジー研究会では、コンパニオンミーティングにて現在国内外にて起こっているデジタルパソロジーの分野について病理学会員が知っておくべきと思われる情報の提供を考えています。免疫染色を始めとする分子生物学が病理に導入された時と同程度のインパクトがあるとおもわれるデジタルパソロジーと人工知能。デジタルパソロジーの進歩のエッセンスについて4つのレクチャーを企画しています。
1)デジタルパソロジーの基礎 (導入するには何をすればいいのか)
2)病理人工知能の基礎(知っておくべきタームや使い方)
3)アジアにおけるデジタルパソロジーと人工知能の現状(日本の遅れがわかります)
4)最新の重要な研究紹介(知っておくべき重要な最新の技術や論文を紹介します)
コンパニオンミーティング 3
日本腎病理協会プレゼンツ
D会場(会議棟 2F 桜1)
「知っておくと得する病理解剖診断に役立つ腎病理所見」
腎病理はちょっと苦手だけど剖検診断では腎臓を避けては通れない…どうしよう…。そんなふうに思っておられる先生方、日本腎病理協会のコンパニオンミーティングで一緒に勉強しませんか。剖検腎では原発性の腎疾患ばかりではなく、加齢性変化、全身性疾患や生活習慣病の影響、使用薬剤の影響、死戦期の影響など、さまざまな病変が見出されます。そしてこれらはしばしば混在し、各病変の明確な線引きが難しいことも多いです。本コンパニオンミーティングでは、剖検腎にみられる様々な病変を取り上げてその意義や病態を考察してみたいと思います。腎病理が得意か苦手かにかかわらず、普段剖検診断を行っておられる先生、剖検を指導しておられる先生、そして専門医試験を受験予定の先生も是非ご参加下さい。
コンパニオンミーティング 4
唾液腺腫瘍病理研究会
E会場(会議棟 2F 桜2)
「唾液腺腫瘍病理の新知見ー基礎と臨床の両サイドからー」
本研究会は、1999年にサリバリークラブとして発足して以来、毎年12月に行われる定例会に加えて、10年前からはほぼ毎回日本病理学会でのコンパニオンミーティングとしても開催してきている。コロナ禍で診療・研究ともに厳しい環境が取り巻く中ではあるが、ごく最近になって本邦から唾液腺腫瘍病理に関しての新展開となるデータや症例が続けて報告された。今回は「唾液腺腫瘍病理の新知見ー基礎と臨床の両サイドからー」と題して、その一端を本研究会会員のみならず日本病理学会参加者全員で共有したい。
唾液腺腫瘍に認められる遺伝子異常については徐々に明らかになっているものの、その直接的な腫瘍発生機序は明らかになっていない。今回多形腺腫で再構成が報告されているPLAG1の過剰発現による腫瘍形成モデルに関して、また、腫瘍ではないが壊死性唾液腺化生の発症機構解明に関する唾液腺オルガノイドを用いた基礎医学的研究を紹介する。臨床サイドからは、形態学と遺伝子異常が最終的に一致し、良性の扁平上皮系腫瘍として確立した角化嚢胞腫に関して、また、腺様嚢胞癌において以前から知られるMYB/MYBL1のみでなく、その近傍での遺伝子再構成を網羅的に解析したデータを紹介する。
唾液腺腫瘍病理に関して熱い議論を交わし、唾液腺腫瘍の病理学的理解や診断の向上に役立つ機会となることを願っている。
コンパニオンミーティング 5
国際病理アカデミー日本支部
F-1会場(会議棟 3F 白橿1)
「ふぁんだめんたる講座:腎腫瘍の新潮流」
国際病理アカデミー本部(JDIAP)ではふぁんだめんたる講座として毎年テーマを決めて、病理学会会員の先生方への情報発信を行うとともに、JDIAPのご紹介をさせていただいております。今回のテーマは『腎腫瘍の新潮流』で、新理事の孝橋賢一先生(大阪公立大学)と大橋瑠子先生の(新潟大学)講演を予定しています。
コンパニオンミーティング 6
神経疾患の病理診断
F-2会場(会議棟 3F 白橿2)
「神経病理学の愉しみ」
病理診断が鍵となる神経疾患について代表的な疾患群毎に神経病理所見の検索法を解説する
コンパニオンミーティング 7
日本サルコーマ治療研究学会
G会場(展示棟 1F 会議室1)
「ANNUBP-MPNST revisited、病理と臨床の融合」
悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST)は化学療法・放射線療法抵抗性であり、広範切除による手術が唯一治癒を目指せる治療とされているが、5年生存率は40%程度と極めて悪い。MPNSTの約半数が遺伝病である神経線維腫症1型(NF1)患者に発症し、NF1患者の生命予後短縮の最大要因となっている。NF1患者に発症するMPNSTの多くは、基盤となる叢状神経線維腫(PN)が中間型のANNUBPを経てMPNSTへと悪性化して発症するとされている。ANNUBPの段階で侵襲の少ない手術を実施すれば治癒できるとする報告があるため、適時に的確な病理診断をつけ、適切な手術を実施することがMPNSTへの先制医療につながり、NF1患者の生命予後延伸につながると考えられる。本コンパニオンミーティングでは、NF1患者におけるPN-ANNUBP-MPNSTのステップを病理と臨床の視点から発表、討論し、先制医療につながる理解を深めることを目的とする。
コンパニオンミーティング 8
日本肺病理学会
H会場(展示棟 1F 会議室2)
「呼吸器MDD」
間質性肺炎は、その病態により治療選択が大きく異なるため、精度の高い慎重な診断が求められます。診断は、多職種(呼吸器内科医、リウマチ・膠原病内科医、画像診断医、病理医)による集学的合議(multidisciplinary discussion : MDD)で決定することが強く推奨されています。MDDにより診断精度と予後の予測能が向上し、最適な治療を提供することが可能となり、さらにMDD介入は医療費の削減と死亡数減少にも寄与します。日本呼吸器学会 MDD 委員会では、関連学会と協働して MDD評価に必要な専門知識と技術を持つ医師の育成と、認定を目的に令和6年4月4日に「MDD認定医制度」を策定しました。そこで、本会ではこの制度への理解を深めることを目的とし、模擬MDDを実施します。
[プログラム内容]
呼吸器MDD Overview
谷野 美智枝(旭川医科大学病院病理診断科)
模擬MDD
臨床:大河内 眞也 (東北大学大学院医学系研究科産業医学)
画像:冨永 循哉 (東北大学病院放射線診断科)
病理:井上 千裕(東北大学大学院医学系研究科病理診断学)
ファシリテーター:小山 涼子(NHO仙台医療センター病理診断科)
オーガナイザー:
谷野 美智枝(旭川医科大学病院病理診断科)
奥寺 康司 (埼玉医科大学医学部病理学)
コンパニオンミーティング 9
日本婦人科病理学会
I会場(展示棟 1F 会議室3)
「子宮頸部扁平上皮内病変の病理診断チュートリアル」
2024年4月のがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の改定により、我が国はHPV検診の普及に舵を切った。HPV検診により、コルポスコピー・生検の数は細胞診による検診法の3倍程度の増加があるとの報告があり、またハイリスクHPV陽性というバイアスがかかった状態での診断といった新たな背景が加わる中で、扁平上皮内病変 (SIL) の診断基準の標準化、均てん化が求められている。本企画では、日常診断で診断者間の診断に違いを生じやすい症例を手がかりとしてSILの診断に重要な所見、診断のピットフォールを3名のエキスパートがそれぞれの視点から解説する。講演前後のセルフアセスメントを組み入れるなど、双方向性の講義形態を予定している。初心者を含めた日常的に婦人科の病理診断にかかわる全ての医師を対象として、双方向性の講義形態を通してSILの診断の段階的・実践的なレベルアップを目的とする。
コンパニオンミーティング 10
日本皮膚病理組織学会
J会場(展示棟 1F 会議室4)
「生検診断の限界値を上げていこう ~最終診断からの再考~」
日本皮膚病理組織学会では、年1回の総会・学術大会に加えて、皮膚病理に関する講習会を企画しています(https://jdps.jp)。毎年コンパニオンミーティングでは、皮膚科領域検体の病理診断をする上で、実践に役立つ具体的な内容をテーマとしています。
今回は、「生検診断の限界値を上げていこう」というテーマで症例提示を行います。生検で診断確定が困難であった症例を最終診断から再考し、次回診断時に気を付ける所見やポイントについて検討します。提示予定症例の生検標本バーチャルスライドをご希望の方に事前公開いたします(ご希望の方はdermpathseminar@gmail.comにご連絡ください)。皆様のご来場をお待ちしております。
予定演者:
大槻 真也(京都大学医学部附属病院 病理診断科)
岸川 さつき(国立がん研究センター中央病院 病理診断科)
古賀 佳織(福岡大学病院 病理部)
中里 信一(社会福祉法人函館厚生院函館中央病院病理診断科)
平木 翼(静岡県立がんセンター 病理診断科)
座長:
三浦 圭子 (東京科学大学病院 病理部)
藤本 正数 (京都大学医学部附属病院 病理診断科)
4月18日(金)18:20~19:50
コンパニオンミーティング 11
心筋生検研究会
B会場(会議棟 2F 橘)
「突然死の解剖では心臓・血管をどのように解析して報告すれば良いのか?」
病院内外を問わず突然死症例の死因究明のための解剖では、心臓・血管の病理学的解析は死因決定に重要であることに疑いはないが、循環器を専門にしない病理医は次の 3点について困窮することがある。① 急性心筋梗塞や心筋炎、大動脈解離など、明らかな異常が心血管系にあるが、その詳細をどのように剖検報告書に書くべきか。② 死因と断定するには軽微な異常しかみられない場合、その所見をどの程度死因の説明に反映させるか。③ 心血管系に死因に直結する所見が肉眼的に見当たらない場合にどこまで詳細に組織学的検索をしておくべきか。この3点は医療安全が関連する可能性のある症例の検索でもよくわきまえておきたい事項である。心筋生検研究会は臨床の心内膜心筋生検のみならず、その背景にある心臓血管病理学全般の研究も対象にしており、今回は心血管性突然死の症例を担当した場合の病理医としての対応として知っておきたいことを発表者の経験をもとに討議したい。
<予定演題>
1.病理医が知っておくべき、主要な心血管疾患の所見の取り方と報告書に記載すべきこと
1) 虚血性心疾患 (冠動脈疾患) とその他、突然死で考慮すべき心疾患
2) 大血管疾患(大動脈解離、大動脈瘤), 脳血管
2.陰性所見の取り方:死因に直結する肉眼所見がない時にどのように肉眼・組織学的検討をしておくか ―心臓・血管の切り出し方・固定法と組織学的観察の注意点―
コンパニオンミーティング 12
PathPortどこでも病理ラボの集い
C会場(会議棟 2F 萩)
「”若手”病理医集合!病理の現場で役立つTips」
PathPortどこでも病理ラボは、地域医療における病理医の相互支援と次世代病理医育成を目指すプロジェクトです。「症例相談室」での症例相談や意見交換を主事業とし、そこに提示された症例を会員の皆で供覧・検討する「症例相談室レビュー」(月2回)や若手メンバー主導の「病理Daily Practice」(月1回)、各分野の専門家を招いて行う「PathPortライブセミナー&ケーススタディ」(月1回)および専門分野で立ち上がったいくつかの分科会などをオンラインで開催しています。
今回は、「”若手”病理医集合!病理の現場で役立つTips」と題して、日々の業務で得た経験や工夫、そして熱い想いを共有してもらう場にしたいと考えています。対象は主に若手病理医を想定していますが、特に年齢に関係なく、病理診断の精度向上を目指したい人、病理医としてのキャリアアップに興味があるひと、病理の面白さを再発見したい人、同世代の病理医と交流したい人たちに集まってもらえればと考えています。
【プログラム内容(予定)】
(1)臨床病理カンファレンスの準備と伝わるプレゼン
(2)患者の検体を最大限に活かす方法
(3)部内鏡検会の効果的な開催方法
(4)病理診断報告Do & Don’t
(5)PathPortを使い倒してキャリアアップ!
コンパニオンミーティング 13
D会場(会議棟 2F 桜1)
「OTS-アッセイ:遺伝子パネル検査を起点としたctDNAと病理検体モニタリング」
OTS(Off-The-Shelf)-アッセイは遺伝子パネル検査で同定された体細胞変異による、ctDNAモニタリング検査である。NGSではなくデジタルPCRを用いることで高感度測定を実現している。経時的に採取された血液を用いてctDNAを測定することが主たる目的であるが、転移巣の由来臓器を同定することも可能である。その場合、FFPE検体を活用した腫瘍組織の診断が重要な役割を果たす。本発表では、病理部門が臨床医およびctDNA測定機関のハブとして機能する利点について、検体管理、検査結果の解釈、臨床医へのフィードバックを含めて議論する。また、オーガナイザーの立場から、岩手医大で実装化したアッセイの標準化・精度向上やctDNAデータを治療にどう結びつけるかといった実用性と課題についても考察し、がん治療におけるOTS-アッセイの役割と今後の可能性を議論する。
コンパニオンミーティング 14
消化管病理医の会
E会場(会議棟 2F 桜2)
「消化管疾患の病理診断」
消化管の腫瘍性・腫瘍病変や炎症性病変のうちまれなものや誤診の危険のある疾患の提示・解説を行い、消化管病理の診断向上に有益になるような会にしたい
コンパニオンミーティング 15
日本泌尿器病理研究会
F-1会場(会議棟 3F 白橿1)
「尿路上皮腫瘍の病理-最近の話題と鑑別のピットフォール」
尿路上皮腫瘍が発生する臓器は、腎盂、尿管、膀胱、尿道、さらには尿膜管遺残や憩室、尿道附属腺に腫瘍が生ずることもあり多彩です。提出される病理検体の種類も細胞診、TUR・生検検体、手術検体と様々です。また、後腹膜や骨盤腔内には多数の臓器があるため、例えば腎盂癌と腎癌の鑑別を要するケースがあるほか、膀胱TURBT検体に前立腺癌の浸潤を認めることや、逆に前立腺TUR-P検体で尿路上皮癌をみることがあるなど他臓器癌との鑑別や組織型・組織亜型の判定に苦慮することもあります。今回のコンパニオンミーティングでは様々なシチュエーションにおける尿路上皮腫瘍の病理診断に焦点を当て、3人の演者から尿路上皮腫瘍の最近の話題と鑑別のピットフォールについてお話いただきます。新分類であるWHO分類第5版やパリシステム第2版が浸透しつつある中で、参加者の皆さんにはあらためて尿路上皮腫瘍の病理診断について理解を深めていただき、本コンパニオンミーティングで得た情報を明日からの診療にお役立ていただければ幸いです。
コンパニオンミーティング 16
小児病理研究会
F-2会場(会議棟 3F 白橿2)
「小児・AYA世代の造血器・リンパ系腫瘍の病理」
造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類5版の冊子体が発刊されました。近年、造血器腫瘍も他の臓器の腫瘍と同様に組織学的所見に分子遺伝学的異常を加えた診断がなされ、疾患概念の再編も見られます。本企画を通じて新WHO分類における小児・AYA世代の造血器・リンパ系腫瘍の病理について理解を深め、今後の診療に役立つ知識、情報が共有されることを期待します。
募集期間
2024年9月3日(火)~10月31日(木)
11月15日(金)正午まで
延長しました。
コンパニオンミーティング登録を締め切りました。
多数のご応募をいただきありがとうございました。
※開催枠が無くなり次第、
締め切りといたします。
コンパニオンミーティング
公募のご案内
第114回日本病理学会総会におきましても、第1日目 2025年4月17日(木)と第2日目 2024年4月18日(金)にて、コンパニオンミーティングの開催を予定しております。
今回もコンパニオンミーティング企画を一般公募いたしますので、下記の募集要項をご参照のうえ奮ってご応募ください。
なお、企画の採択につきましては、会長に一任いただくことをご承諾お願いいたします。
※採択のご案内は2024年12月上旬頃を予定しております。
コンパニオンミーティング
企画 募集要項
開催日時(予定)2025年
- 第1日目 4月17日(木)18:40~20:10
- 第2日目 4月18日(金)18:40~20:10
今後、時間が多少変動する可能性がございます。
開催会場(予定)
総会で使用する講演会場をミーテイング会場としてご用意いたします。
| 会場 | 部屋名 | 席数 |
|---|---|---|
| 第2会場 | 橘(会議棟) | 450席 |
| 第3会場 | 萩(会議棟) | 330席 |
| 第4会場 | 桜1(会議棟) | 340席 |
| 第5会場 | 桜2(会議棟) | 240席 |
| 第6会場 | 白橿1(会議棟) | 234席 |
| 第7会場 | 白橿2(会議棟) | 101席 |
| 第8会場 | 会議室1(展示棟) | 166席 |
| 第9会場 | 会議室2(展示棟) | 161席 |
| 第10会場 | 会議室3(展示棟) | 164席 |
| 第11会場 | 会議室4(展示棟) | 164席 |
内容・演者の選定について
コンパニオンミーティングの内容、演者数等につきましては、オーガナイザーの先生にご一任いたします。
演者については、非会員を加えることも可能です。非会員演者の参加費は該当のコンパニオンミーティングに限り無料とさせていただきますが、旅費、宿泊費、謝礼等につきましては、総会側ではご用意いたしませんことをご了承ください。
今回、コンパニオンミーティングにつきましては、プログラム・抄録集への抄録掲載はいたしません。採択された場合、抄録集日程表に掲載いたしますプログラム内容、座長情報を、2025年1月10日(金)までに、総会運営事務局までご提出ください。
お申込みについて
下記のお申し込みフォームより2024年10月31日(木)までに、お申し込みください。
開催枠が埋まり次第、期間中でも募集を締め切ることがございますので予めご了承ください。
| 1 | コンパニオンミーティング名 | 日本語・英語併記 |
|---|---|---|
| 2 | テーマタイトル | 日本語・英語併記 |
| 3 | オーガナイザー | 氏名・所属については、日本語・英語併記
連絡先の電話番号、メールアドレスを必ずご記入ください。 (オーガナイザーが複数の場合、それぞれのご連絡先もお願いいたします。) |
| 4 | 開催内容 | 400文字程度にてお知らせください。 |
| 5 | 使用言語 | 日本語セッションか英語セッションかをお知らせください。 |
| 6 | 参加予定者数 | 会場選定の目安にさせていただきます。 |
| 7 | 飲食提供 | 飲食提供の有無をお知らせください。
(会場によっては、飲食の提供が難しい場合もございます。) |
| 8 | 予定演者 | お申し込みの段階で、演者が決まっている場合はお知らせください。 |
お問い合わせ先
株式会社コングレ東北支社
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング
TEL:022-723-3211 FAX:022-723-3210
E-mail:114jsp@congre.co.jp
© 2024 The 114th Annual Meeting
of the Japanese Society of Pathology


