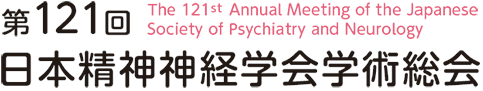会長挨拶

第121回日本精神神経学会学術総会
会長 上野 修一
(愛媛大学大学院医学系研究科 精神神経科学講座 教授)
第121回日本精神神経学会学術総会を開催するに当たり、総会長として一言ご挨拶申し上げます。
所信表明でも申し上げましたように、中国・四国地区の担当した総会は、広島大学山脇成人先生が総会長となられた2010年が最後です。現在、専門医制度の本格化に伴い、参加者すべてが収容可能な会場は、中国・四国地区にはありません。最近、オンデマンドで視聴できるようになり、開催場所の重要性は薄まると思いますが、地域からの発信は重要で、隣接地域神戸市で中国・四国地区の担当として開催できることを嬉しく思います。
学術総会のテーマは、「精神神経科学の充実・発展のために取り組むべきこと- Enhancing and Developing Psychiatry and Neurology: Issues To Be Addressed -」としました。還暦を2回迎えた、大還暦後の最初の総会で、我々の学会の進む道を少しは示せればと思っています。以下に今回の総会で意識した点を示させていただきます。
まず、総会は、研究・診療における新知見の発表や勉強の機会、相互研鑽の場です。これまでも運営に関わる皆様のご尽力で内容は充実していますが、今回、特に、若い先生方の苦手な部分を補い、精神神経科学を取り巻く学会のハブとしての企画を加えます。これらは、どの会員にとっても身になると考えています。
次に、精神科医としてのアイデンティティを高める企画を組み込みます。医学の中で精神神経科学の重要性を示すとともに、精神科医として存在意義が高められ、自分らしさを積極的に示せる場を提示したいと思います。医師の働き方改革やAIによる医療の変革により激変する医療環境に対して、精神科医としての活動も変わらざるを得ないでしょう。ワークライフバランスの中で精神科医のあるべき姿についても、人生百年時代で考えたいと思います。
最後に、社会の中で精神科医としての行動を考える企画を考えます。精神医学は、福祉など精神障害患者の日常生活に深く入り込むことが必要な部門です。加えて、こころの専門家として、精神科医療の啓発だけでなく、社会的弱者であり発言力の弱い精神的ハンディキャップを持つものの代わりとなり、発信することも必要で、会員が互いに検討しあえる総会にしたいと思います。
最初に述べましたように、今回の総会の開催に当たり、中国四国地区の医育機関、精神科病院協会や精神科診療所協会の会員の皆様からご支援頂きました。若手のメンバーにもプログラム委員に加わっていただき、現在の精神科医療に必要な最新情報を提示できるように致しました。これまでの当学会の良い流れを遮ることなく、新世代の精神科医の方向性を考えるヒントとなる学術総会になるよう配慮したつもりです。多くの会員の皆様に神戸に参集いただき、第121回総会が、精神科医療について討論し、相互に交流できる機会になれば幸いです。