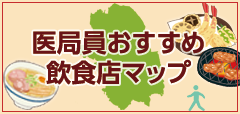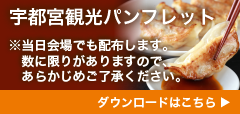演題募集
演題募集期間
公募演題募集を締め切りました。
多数のご応募ありがとうございました。
応募資格
発表者(筆頭演者)は、原則会員に限ります。
発表者(筆頭演者)で本学会未入会の方は、学会当日までに日本ロボット外科学会ホームページ「入会のご案内」にて入会手続きをお済ませください。
ただし、研修医、専攻医の先生、メディカルスタッフの方におかれましては、本学術集会への参加登録をいただければ、非会員でも筆頭演者としてご発表いただけます。
募集要項
主題演題(シンポジウム、ワークショップ、領域横断シンポジウム、パネルディスカッション、領域横断パネルディスカッション、ビデオワークショップ)、ならびに一般演題を公募いたします。
なお、主題演題登録にあたっての顔写真登録は任意となります。登録された場合、プログラム・抄録集に顔写真を掲載いたします。
 すべての座長の言葉を表示
すべての座長の言葉を表示  すべての座長の言葉を閉じる
すべての座長の言葉を閉じる
シンポジウム
-
「直腸癌 TMEのコツとピットフォール」
座長のことば
近年、直腸癌に対するロボット支援手術の症例が急速に増加している。自由度の高い多関節機能は直腸癌手術の遂行にあたり有効である一方、アームの干渉などロボット特有の問題点も有している。本シンポジウムではロボットの種類は問わず、直腸癌に対するTMEのコツとピットフォールについて治療成績も交えて各施設の取り組みを供覧いただきたい。特にCRTやTNTなどの術前治療が広く行われるようになり、術野の浮腫や瘢痕が手術に及ぼす影響およびその対処法の工夫についても言及していただきたい。
-
「ロボット腎部分切除術においてどのようにして仮性動脈瘤を予防するか?」
座長のことば
ロボット腎部分切除術は、癌制御と腎機能温存を両立する標準術式となり、テクノロジーの進歩や術者の経験とともにさらに進化を遂げている。一方で、ロボット腎部分切除術において、仮性動脈瘤は致死的出血を起こしうる稀であるが厄介な合併症である。どのように予防するかは非常に重要な課題である。仮性動脈瘤の病態生理、自然史、手術手技、エネルギーデバイス、ナビゲーションなど様々な視点からこの課題を掘り下げ、解決に向け議論し、コンセンサスを得ることを目標にしたい。
-
「心臓血管外科 ロボット支援弁形成術
現況と展望」座長のことば
ロボット心臓手術の普及が進み2024年には弁置換術も保険収載された。今では僧帽弁手術にとどまらず三尖弁や大動脈弁、メイズ手術、非弁膜症領域の手術にもその使用が広がっている。今回は本来ロボットが一番得意とする僧帽弁形成術を改めて考察したい。手術適応や病態ごとの形成の戦略、弁輪形成の方法など各施設の現状と今後の展望を論じることで、今後のロボット僧帽弁形成術の発展に寄与するシンポジウムとしたい。
-
「結腸癌に対するロボット手術」
座長のことば
結腸癌に対するロボット手術は、2022年4月に保険適応となり、結腸癌ロボット手術は急速に普及してきている。腹腔鏡手術で難易度が高いとされるSurgical trunkの郭清や中結腸動脈周囲の郭清、左側横行結腸癌手術や下行結腸癌手術への適応が進められている。しかし、ポート配置、アプローチ法、吻合方法などは施設によって異なっており、標準化には至っていない。また、多数のロボットが承認され、ロボットの使い分けをいかにするか、ロボット手術のエビデンスの不足、今後の加算取得に向けての方策など、今後の課題も多い。本セッションでは、各施設の結腸癌に対するロボット手術の短期成績など現状を報告していただくとともに、標準化や課題の克服について、ビデオ供覧を通じて論じて頂きたい。
-
「肝・胆道手術の現状」
座長のことば
現在保険診療として実施できる肝胆道ロボット支援手術は、肝腫瘍に対する肝切除術、胆道がんに対する膵頭十二指腸切除術、先天性胆道拡張症手術と多岐に渡る。一方、低い疾患頻度や高い手術難度の問題から多くの施設が依然導入期ないし安定期にさしかかった状況にある。また様々なロボット機種が保険認可され、機種ごとの術者資格・プロクター制度への対応がスムーズな普及の足枷となっている。さらに今後保険認可を目指すロボット支援手術として胆嚢摘出術、胆嚢悪性腫瘍手術、肝門部領域胆管癌手術などにも克服すべき課題がある。本セッションではロボット支援肝胆道手術の現状の課題と今後の展望について様々な視点からの発表をお願いしたい。
-
「膵頭十二指腸切除術」
座長のことば
日本におけるロボット支援膵頭十二指腸切除術(RPD)は、保険収載の遅れから導入が遅れていたが、2020年に保険収載され、近年、ハイボリュームセンターを中心に急速に手術件数が増加している。導入時の安全性の担保は世界的な課題であるが、日本では学会主導の導入プロセスの確立により、安全にRPDが施行されており、出血の少ない解剖構造を基にした精緻な手術技術においては世界で先進的な立場になりつつある。一方で、更なる普及に向けた若手への教育プログラムの確立や、膵癌におけるRPDの適応やアプローチ法については、さらなる議論が必要である。本セッションでは、各施設のRPDの適応や手術方法、手術成績、若手教育の取り組みなどを提示していただき、今後のRPDの方向性について論じていただきたい。
-
「食道癌手術 ロボットがもたらしたものと今後の展望」
座長のことば
食道癌に対するロボット手術は、2018年の保険収載以降、急速に増加している。ロボット手術がもたらしたものの中で、安定した術野や3D拡大視、精緻な鉗子操作により得られたメリットは実臨床で患者さんにどのような形で還元されているかというプラスの側面、一方、コストや手術時間、麻酔に関連する事項、ロボット導入の有無や症例数の制限による施設間格差など、もたらされたマイナスの側面もあり、この両者について論じていただきたい。また、食道癌ロボット手術が急速に広まって行く中で、食道外科医の育成システムを含めた今後の展望、あるべき姿についても議論いただく。
-
「肺癌リンパ節郭清におけるロボット手術のメリット」
座長のことば
2018年に保険診療が認められ、肺癌に対するロボット支援手術が急速に普及してきているが、胸腔鏡手術に対してのメリットは明らかでなく、現状ではコストが高い。手術支援ロボットは、先端に回転する関節・Motion scale機能を有し、深部での繊細な操作が可能であり、胸腔深部での操作を要するリンパ節郭清において有用性を発揮できると考えられる。各施設でのリンパ節郭清における工夫・ピットフォールを含め、現状での到達点を示して頂きたい。
-
「食道・胃接合部手術(食道浸潤長2-4cm)
再建法(経裂孔、胸腔内、頸部)」座長のことば
食道胃接合部癌においてリンパ節郭清の範囲は癌の食道浸潤長が重要であることに一定のコンセンサスが得られるようになってきたが、再建法はいまだ施設間差が著しい。その中で最も多様性が要求される食道浸潤長2-4 cmの食道胃接合部癌切除後の再建術は経裂孔、胸腔内、頸部からのアプローチでいずれの方法が選択されるかは再建臓器の選択や残食道の長さ、食道裂孔ヘルニアの有無、体型、食道裂孔周囲の解剖関係、使用デバイスの制限など多くの因子を考慮しなければならない。このセッションでは各施設の本術式に対するロボット術式において様々な吻合の特徴を説明してその適応と術後成績を議論していただきたい。
-
「胃癌手術 最新のエビデンスと将来展望」
座長のことば
これまで胃癌手術に関する様々な臨床試験が行われ、D2郭清を基本とする現在の標準術式が確立された。アプローチとしては、進行癌に対する腹腔鏡下胃切除術の非劣性も証明されたが、急速に導入が進んでいるロボット支援胃切除術については、有用性に関するエビデンスは少ないのが現状である。本セッションでは、ロボット支援胃切除術に関する各施設の最新のエビデンスを紹介いただくと共に、ロボット支援手術がより活きる手技として食道胃接合部に対する郭清・再建や脾門部の郭清等に対する成績なども発表いただき、今後の胃癌手術におけるロボット支援胃切除術の将来展望について議論していただきたい。
-
「ロボット支援下子宮体がん手術の今後の展開」
座長のことば
2018年4月に子宮体癌に対するロボット支援下手術が保険適用となり、全国で展開されてきている。現在3機種での手術の施行が可能であるが、骨盤深部での手術に適するとされるロボット支援下子宮体癌手術の適応と限界、各機種の特徴、骨盤リンパ節郭清を含めた子宮体癌手術での腹腔鏡手術との違いやtipsなどをエキスパートの先生方と議論する。さらにロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術を含めた適応拡大と今後の展開についての討議を行いたい。
領域横断シンポジウム
-
「今後、保険収載が期待されるロボット支援手術」
座長のことば
ロボット支援手術は、従来の体腔鏡手術の限界点を補完する優れた機能を有し、適切な手術のコンセプトとロボットを使い熟す技術を両立することで、術後合併症を軽減し、がんの長期予後まで改善される可能性が示唆されています。本邦では、2012年に前立腺全摘除術、2016年に腎部分切除術、そして、2018年に胃切除術、食道亜全摘術、胸腔鏡下弁形成術を含む12の術式が保険収載され、その後も各学会からの要望に基づき診療報酬改定の都度、術式が追加されてきました。当セッションでは、今後、どのような術式の保険収載が期待されるか、領域毎の取り組みについて情報共有し、向かうべき方向性について討議します。
-
「ロボット支援手術の教育 いつから修練を開始するか?」
座長のことば
ロボット支援手術が急速に普及していくなかで、若手医師にロボット支援手術の修練・教育をいつから開始すべきであるかが議論になっている。一方、手術支援ロボットが各医療機関に充足されていない現状を考慮すれば、引き続き開腹・開胸、腹腔鏡・胸腔鏡手術の修練も必要と考えられる。限られたリソースの中で、若手医師のニーズに応えながらロボット支援手術、内視鏡手術、Open手術をどのように教育していくべきか、本領域横断シンポジウムで議論したい。各領域、各施設のユニークな修練・教育の取り組みを発表していただきたい。
-
「骨盤内臓器 解剖学的骨盤リンパ節郭清
-骨盤三科のコンセンサス(腹部外科、泌尿器科、婦人科)」座長のことば
解剖に則った手術は、骨盤内手術において、機能温存と根治性の両立を図るうえで極めて重要である。骨盤外科領域ではロボット支援下手術の導入が進んでおり、骨盤リンパ節郭清は、腹部外科、泌尿器科、婦人科の共通項目として挙げられる代表的な手技の一つとなっている。日本内視鏡外科学会主導で行われた骨盤リンパ節郭清ワーキングでは、腫瘍学的な面や手技に関して、各領域独自の文化を保ちつつも、共通の解剖学的コンセンサスが図られるようになった。このセッションでは、解剖に則ったロボット支援手術について、正しい解剖の理解とそれに則った手術手技と継承教育法について、各領域の特徴および診療連携の工夫を含めて詳細に解説頂きたい。
-
「ロボット手術の技術認定の今後」
座長のことば
技術認定制度は内視鏡外科手術の安全な普及を目的として2004年に開始、2020年には申請者数が1000名を超え多くの外科医の関心を集めています。一方、ロボット手術の技術認定制度は、“ロボット手術も鏡視下手術の一つ”というコンセプトで従来の枠組みを大きく変えることなく、2023年から消化器・一般外科領域(食道、胃、大腸)で開始されました。2024年からは泌尿器科、呼吸器外科で、さらに2025年には婦人科でも開始予定です。本セッションでは、技術認定医取得が今後も若手外科医にとって魅力あるものであり続けるために、ロボット手術の技術認定はどうあるべきか、各領域の現況も踏まえて、意義深い討論を期待しています。ご応募をお待ちしております。
パネルディスカッション
-
「ロボット支援手術における最適なエネルギーデバイスとは?(消化管)」
座長のことば
消化管に対する低侵襲手術は、その有用性から腹腔鏡からロボットへシフトしているのが現状である。これまで腹腔鏡で使用されてきたエネルギーデバイスは、超音波凝固切開装置もしくはベッセルシーリングシステムが主体であったが、関節機能を有するロボットでは、モノポーラやダブルバイポーラー法などの手技が確立されてきた。一方で、関節のない従来のデバイスを使いこなす方法や、腹腔鏡とロボットのエネルギーデバイス両者の利点を活かしたコンバインド手術など、施設によって様々な手技が生みだされている。当セッションでは、消化管領域のエキスパートより手技を提示していただき、ロボット手術におけるエネルギーデバイスの最適解についてディスカッションを行いたい。
-
「CE,Ns.コメディカルセッション」
座長のことば
ロボット手術が日本全国の多くの施設で導入される中、手術室での効率的な運用が求められている。近年は様々な種類のロボットシステムも採用されており、その運用において未知数のことも多く、情報を共有することが重要だと考えられる。本セッションではロボット手術を導入されている施設で事務部門、CE、手術部Ns.など日々運用をサポートしている方々の各施設での取組みや工夫、そして今後の課題をディスカッションして頂きたい。
領域横断パネルディスカッション
-
「ロボット支援手術におけるピットフォールとトラブルシューティング」
座長のことば
ロボット支援手術は、医療技術の革新により、手術の精度が飛躍的に向上し、合併症の軽減効果も示唆されてきている。また胃がんについてはロボット支援手術の生存における優越性が評価され、保険点数の引き上げが行われている。一方で、新しい技術には新しい課題やトラブルも伴い、思わぬところに危険が潜んでいる。本セッションでは、さまざまな領域でのロボット支援手術における具体的なピットフォールやトラブルシューティングの事例を共有し、参加者全員で知見を深めることを目的とする。
-
「ロボット支援手術を安全に行うために」
座長のことば
ロボット手術は多くの施設で導入が進み、多臓器にわたる術式や新規ロボット機器の導入など、ロボット関連手術はますます増加傾向にあります。本セッションでは、各施設から、安全性に対する工夫について発表していただき討議します。
麻酔科、看護師、臨床工学士など多職種による安全対策、新規ロボットの導入、若手の執刀機会の増加に伴うトレーニング方法についてご発表いただきたいと思います。また、術前・術中の工夫など、手術に関わる各種の取り組みも提示していただき、臓器横断的な安全性に関わる工夫を共有していただきたいと考えています。
ワークショップ
-
「RARPの手術成績」
座長のことば
本セッションではまず、日本導入10年以上を経たRARPのこれまでの成績をhigh volume centerのリアルなデータで示していただき、本術式の現在地点を明らかにしたい。成績には標準的な手術適応症例に対する癌制御だけではなく、放射線治療後のサルベージ手術、進行前立腺癌に対するチャレンジングな症例への手術も含まれると考える。また、RARP時代となってより注目されるようになった機能温存に関してもエキスパートから最新の術式と成績を示して頂く予定である。更に多くの術者を育成した施設から教育・育成をテーマに発表いただく。これらの発表を通じ、来たる10年への課題を明らかにし、議論を深めるシンポジウムとしたい。
-
「高齢者に対するロボット支援膀胱全摘除術」
座長のことば
筋層浸潤性膀胱癌に対する膀胱全摘除術はそれ自体が侵襲度の高い手術であり、さらに尿路変向を必要とすることから術中だけではなく術後も患者負荷の高いものである。一方で、全摘除術に代替しうる治療法は限られていることから高齢者であっても膀胱全摘除を選択しなければならないことは少なくない。そのなかでロボット支援膀胱全摘除術(RARC)の普及によりその出血量の少なさなどで侵襲の軽減が期待される。しかしながら、高齢者におけるRARCの適応とその成績、安全面での留意点や尿路変向法や体内操作、体外操作の選択、さらにはリンパ節郭清の適応と範囲などまだまだ検討すべき点がある。
本ワークショップでは、高齢者におけるRARCにおけるこれらの点を明らかにし、その適応を含めて安全な手術のありかたを明らかにしたい。 -
「鼠径ヘルニア修復術
ヘルニア手術の未来~
徹底討論:ロボット vs. 腹腔鏡」座長のことば
近年、ロボット支援手術を用いた鼠径部ヘルニア修復術の報告が増加しています。ロボット支援手術には、より精密な操作、安全性、早期回復などが期待されています。一方、鼠径部切開法・腹腔鏡手術は、高い再現性とこれまでの実績があります。しかしながらロボット支援手術と他の術式を比較検討した報告は本邦では限定的です。各施設の臨床データを基に、鼠径部ヘルニアに対するロボット支援手術と腹腔鏡手術を比較し、その適応、手技の違い、手術アウトカム、費用対効果など多角的な視点から、患者にとって最良の治療法を見出すため、双方の術式のさらなる改善点およびロボット支援手術の現状と今後について議論します。
-
「低侵襲子宮体癌手術
―ロボット or 腹腔鏡 どちらを選ぶ?―」座長のことば
子宮体がんに対する腹腔鏡下手術は2014年に、ロボット支援手術は2018年に保険収載され、子宮体がんIA期の約53%に腹腔鏡下手術やロボット支援手術が実施されるまでになってきた。最近では、腹腔鏡下手術と比較してより精緻な操作が可能といわれるロボット支援手術が増加傾向にあるが、一方で、まだ歴史が浅いこともあり、腹腔鏡下手術やロボット支援手術の適切な症例選択、適切な手術方法などまだまだ課題も多い。本ワークショップでは、子宮体がんに対する手術として腹腔鏡下手術、ロボット支援手術のそれぞれの利点、課題などを議論していただきたい。
・メリットとデメリット
・手術手技と短期成績
・骨盤・傍大動脈リンパ節郭清
・合併症
・マニピュレーター使用
・pitfall -
「大腸領域に対するロボット手術の新展開」
座長のことば
2022年4月、直腸癌に加えて結腸癌に対するロボット支援手術も保険適応となり、大腸癌に対するロボット支援手術は急速普及してきた。一方、炎症性腸疾患や骨盤臓器脱など、癌以外でのロボット大腸手術への取り組みも始まり、癌が対象であっても定型的でない術式も増加している。また新機種への拡大や遠隔手術指導への新たな展開も始まっている。本ワークショップでは、大腸領域におけるロボット支援手術の新展開として、手術用ロボットの持つ特色を、どのような対象疾患にどのように活かすか、各施設の新たな取り組みや工夫を紹介いただき、大腸領域の新たな方向性について議論を深めたい。
-
「センチネルナビゲーションロボット手術」
座長のことば
婦人科悪性腫瘍におけるセンチネルリンパ節ナビゲーション手術(SNNS)は海外では標準治療の1つとして広く普及しているが、本邦では保険収載されておらず、臨床研究として限定的に実施されてきた。しかし、2023年にRIトレーサーであるテクネフチン酸が子宮頸癌、子宮体癌、外陰癌に適用拡大し、また2024年改定で外陰癌に対するセンチネルリンパ節生検加算が認められるなど、SNNSの臨床実装の機運が高まってきている。子宮悪性腫瘍へのSNNSは鏡視下手術との相性が良く、特に蛍光色素トレーサーを用いたロボット支援手術は、子宮悪性腫瘍への低侵襲手術の1つの着地点と考えられる。本ワークショップでは婦人科SNNSをとりまく現状と課題について議論を深めるとともに、保険適用拡大後を見据えたSNNSの道筋を明らかにしたい。
-
「ロボット手術から解る詳細な解剖、攻め方の変化、腹腔鏡下手術へのフィードバック(消化管)」
座長のことば
手術ロボットの導入により、外科医は局所の微細な解剖学的構造と向き合いながら手術を行うことができるようになり、手術の高度化がさらに進んでいる。同時に、ロボットの利点を生かした新たな攻略法も提案され、開腹手術や内視鏡手術では困難であった部位へのアクセスが可能となっている。本ワークショップでは、消化器外科の様々な分野において、ロボット手術がもたらす新たな解剖学的知見やそれに基づく手技、アプローチなどについて議論したい。
ビデオワークショップ
-
「ロボット支援膀胱全摘除術
腔内尿路変向術の標準化」座長のことば
2003年Menonらにより膀胱悪性腫瘍手術に対するロボット支援膀胱全摘除術(Robot Assisted Radical Cystectomy: RARC)が報告されて以降、2010年を境に体腔外尿路変更術から、体腔内尿路変更術(Intra corporeal urinary diversion: ICUD)が多く行われるようにシフトしてきた。日本では2018年にRARCが保険収載され、100例前後の比較的まとまった周術期成績の英文原著が散見されるようになってきており、RARC・ICUDが広く普及してきている。また、保険収載当初は施設基準が年間10例以上であったが、実施症例数と合併症発生率に有意差が無いことから、5例に緩和され今後も広く普及していくことが予想される。本シンポジウムでは国内で症例数の多い施設での経験を紹介いただき、RARC・ICUDの標準化について議論していきたい。
-
「縦隔腫瘍に対するロボット支援手術の工夫」
座長のことば
縦隔腫瘍に対するロボット支援手術は、そのアプローチや使用する器具など、その方法は多様である。側方や剣状突起下のアプローチがあるが、それぞれ一長一短あり、腫瘍の局在によっても選択が異なりうる。剥離操作や視野展開に使用する器具も様々なものがある。手術の安全性と根治性が担保されることが前提ではあるが、縦隔腫瘍に対するロボット支援手術における各施設の工夫を発表していただきたい。
一般演題
発表形式
一般演題は「口演発表」と、「ミニオーラル発表」 のいずれかになります。
※応募演題の採否および発表形式等は、会長にご一任ください。
演題登録時に下記の中から該当する発表分野を選択してください。
発表分野
| 01 | 心臓・血管 |
|---|---|
| 02 | 肺・縦隔 |
| 03 | 食道 |
| 04 | 胃 |
| 05 | 肝胆膵 |
| 06 | 結腸 |
| 07 | 直腸 |
| 08 | ヘルニア |
| 09 | 前立腺 |
| 10 | 腎・膀胱 |
| 11 | 副腎 |
| 12 | 子宮・付属器 |
| 13 | 仙骨腟固定術 |
| 14 | 小児外科 |
| 15 | 頭頚部外科 |
| 16 | 整形外科 |
| 17 | 看護 |
| 18 | 臨床工学 |
| 19 | その他 |
優秀演題賞について
一般口演の発表に関して、各セッションの座長による評価・推薦に基づき、「優秀演題賞」を選出いたします。
受賞者は、全員懇親会で発表いたします。対象の先生へ事前にご連絡いたしますので、全員懇親会へのご出席をお願いいたします。
登録内容について
- 演者:20名以内(筆頭演者含む)
- 所属施設:20施設以内
- 演題名:全角換算60文字以内(スペース含む)
- 抄録本文:全角換算600字以内(スペース含む。図表は使用出来ません)
※抄録本文は【目的】【方法】【結果】【考察】【結語】を用いて作成してください。
※プログラム・抄録集へは、登録者本人が登録したデータをそのまま使用します。
誤字・脱字・変換ミスには十分にご注意ください。
登録演題確認・修正
一度登録された演題に修正を加えるときは、確認・修正ボタンを使用します。
締め切り期限前であれば、ログインIDとパスワードを入力することにより、何度でも修正・確認をすることができます。また、削除ボタンから、登録された演題を削除することもできます。
採否について
演題の採否、発表セッション等の決定は会長に一任とします。
採否・発表日時の通知は、12月中旬頃に、演題登録の際に入力されたメールアドレス宛に配信する予定です。メールアドレスは正確にご入力ください。
新規演題登録
確認・修正・削除
※演題登録したはずが、登録完了のメールが届かない方へ
正しいメールアドレスが登録されていれば、演題登録完了メールは数時間のうちに自動送信されています。演題登録完了メールが「迷惑フォルダ」に振り分けられてしまっている場合がございますので、未着と思われる場合は迷惑フォルダをご確認ください。メールが届かず、迷惑フォルダの中にも確認できない場合は、登録自体が完了していない可能性がありますので、下記運営事務局までメールにてお問い合わせください。
演題登録に関するお問合せ先
第17回日本ロボット外科学会学術集会
運営事務局
株式会社コングレ
E-mail:j-robo17-abs@congre.co.jp
TEL:03-3510-3701