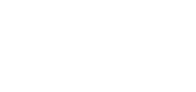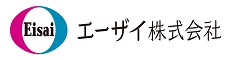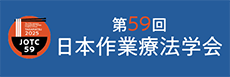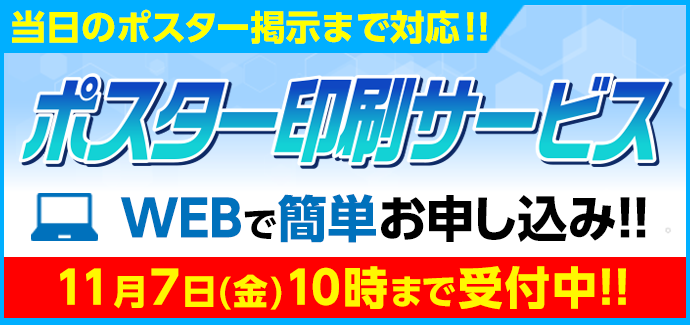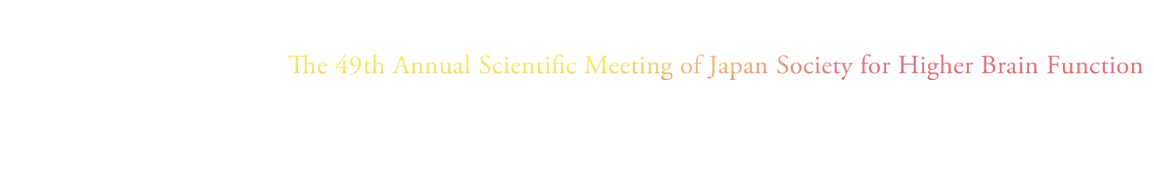運営事務局
株式会社コングレ 中部支社
〒461-0008
愛知県名古屋市東区武平町5-1
名古屋栄ビルディング7F
TEL:052-950-3430
FAX:052-950-3370
E-mail:jshbd2025@congre.co.jp
プログラム
会長講演
脳力共創
~多職種で拓く高次脳機能の未来~
| 座長: | 椿原 彰夫 | (川崎医療福祉大学 学長) |
|---|
| 演者: | 前島 伸一郎 | (国立長寿医療研究センター 長寿医療研修センター長) |
|---|
和歌山県出身
1986年 藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)医学部医学科卒業後、同大学院医学研究科(リハビリテーション医学)で学位取得
2004年 川崎医療福祉大学教授
2007年 埼玉医科大学国際医療センター教授
2013年 藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)医学部リハビリテーション医学教授
2018年 金城大学学長を経て、2022年国立長寿医療研究センター長寿医療研修センター長。
アルペンスキーでは全日本に3回、国体に35回出場。
日本スポーツ協会公認コーチ(スキー)。柔道3段。
<資格>
医師、臨床神経心理士
日本高次脳機能学会・理事、日本神経心理学会・理事
日本意識障害学会・理事
日本リハビリテーション医学会・代議員・指導医・専門医・認定臨床医
日本脳卒中学会・評議員・指導医・専門医
日本認知症学会・代議員・指導医・専門医
日本サルコペニアフレイル学会・代議員・指導士
日本摂食嚥下リハビリテーション学会・評議員・認定士
日本義肢装具学会・評議員・認定医
日本リウマチ学会 専門医
日本内科学会 認定内科医
日本温泉気候物理医学会 温泉療法医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター
日本ニューロリハビリテーション学会 認定医
義肢装具判定適合医、認知症サポート医、コグニサイズ指導者
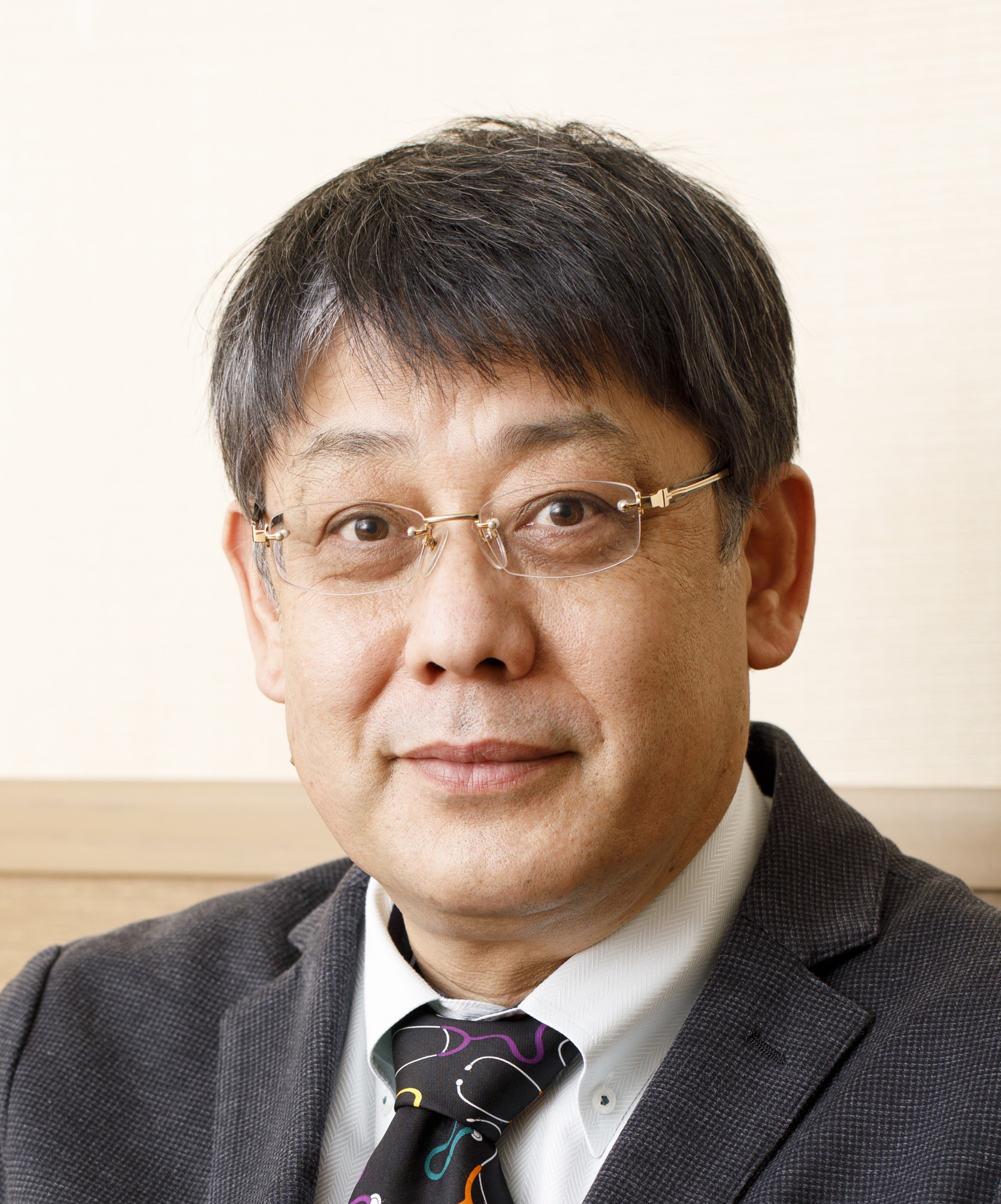
特別講演
Brain HealthとMuscle Healthを維持して築く健康長寿社会
| 座長: | 三村 將 | (慶應義塾大学 予防医療センター 特任教授) |
|---|
| 演者: | 荒井 秀典 | (国立長寿医療研究センター 理事長) |
|---|
1984年、京都大学医学部卒業
1991年、京都大学大学院医学研究科博士課程修了
2003年より京都大学大学院医学研究科加齢医学講師
2009年4月より京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻教授
2015年1月より国立長寿医療研究センター副院長、4月より老年学・社会科学研究センター長兼務(2019年3月まで)
2018年4月より同病院長
2019年4月より同理事長
専門は老年医学、フレイル、サルコペニア、認知症。
<資格・公職等>
医学博士。日本サルコペニア・フレイル学会代表理事、日本老年医学会理事・代議員、日本老年学会理事、日本動脈硬化学会理事・評議員、日本脆弱性骨折ネットワーク理事。日本学術会議会員(第25・26期、第2部)、長寿科学研究振興財団理事、小野医学研究財団評議員、興和生命科学財団評議員、杉浦記念財団評議員。

教育講演
レジェンドによる寺子屋授業〜語り、つながり、受け継ぐ「知と心」〜
セッション要旨
本企画は、我が国における失語症・高次脳機能障害学の黎明期から現在に至るまで、学問と臨床の発展を牽引してこられた「レジェンド」と呼ばれる歴代会長たちが、熱い思いを込めて若い世代に直接語りかける、またとない機会を提供するものです。教科書や論文でしか知らなかった憧れの先生方が一堂に会し、その歩み、診療の哲学、研究の発想、そして人生の選択に至るまで、多彩な語りを通して、高次脳機能障害の魅力や、それに携わる者としての在り方を伝えていただきます。学生や若手医療者にとって、レジェンドの声を「生」で聴き、その場で質問し、対話できることは、知識だけでなく、情熱や志を受け継ぐかけがえのない体験となるでしょう。あのレジェンドに会いたい——。そんな憧れを原動力に、世代を超えた対話が生まれ、学会の未来をより豊かに育む契機となることを目指します。
教育講演1
レジェンドによる寺子屋授業〜語り、つながり、受け継ぐ「知と心」〜
神経文字学の誕生
| 座長: | 永井 知代子 | (帝京平成大学 健康メディカル学部 教授) |
|---|
| 演者: | 岩田 誠 | (メディカルクリニック柿の木坂 院長) |
|---|
1967年東京大学医学部卒。1994年東京女子医科大学神経内科主任教授。2004年東京女子医科大学医学部長。2008年同大学定年退職し名誉教授の称号授与。2009年よりメディカルクリニック柿の木坂院長。日本神経学会、日本高次脳機能学会、日本神経心理学会など名誉会員。仏国立医学アカデミー外国人連絡会員。米国神経学会外国人フェロー

教育講演2
レジェンドによる寺子屋授業〜語り、つながり、受け継ぐ「知と心」〜
「失行」と脳梁病変
| 座長: | 緑川 晶 | (中央大学 文学部 学部長/教授) |
|---|
| 演者: | 河村 満 | (昭和医科大学 医学部 名誉教授) |
|---|
| 1977(昭和52)年 | 横浜市立大学医学部 卒業 |
| 1978(昭和53)年 | 千葉大学神経内科開設時(平山惠造教授) 入局 |
| 1994(平成 6)年 | 昭和大学神経内科(杉田幸二郎教授) 助教授 |
| 1994(平成13)年 | 昭和大学神経内科 教授 (14年間) |
| 2008(平成20)年 | 昭和大学病院附属東病院 院長 (9年間) |
| 2017(平成29)年~ | 2025(令和 7)年3月 奥沢病院 名誉院長 |
| 2020(令和 2)年 | 昭和大学医学部 名誉教授 |
| 2025(令和 7)年~ | 昭和医科大学医学部 名誉教授(校名変更のため) |
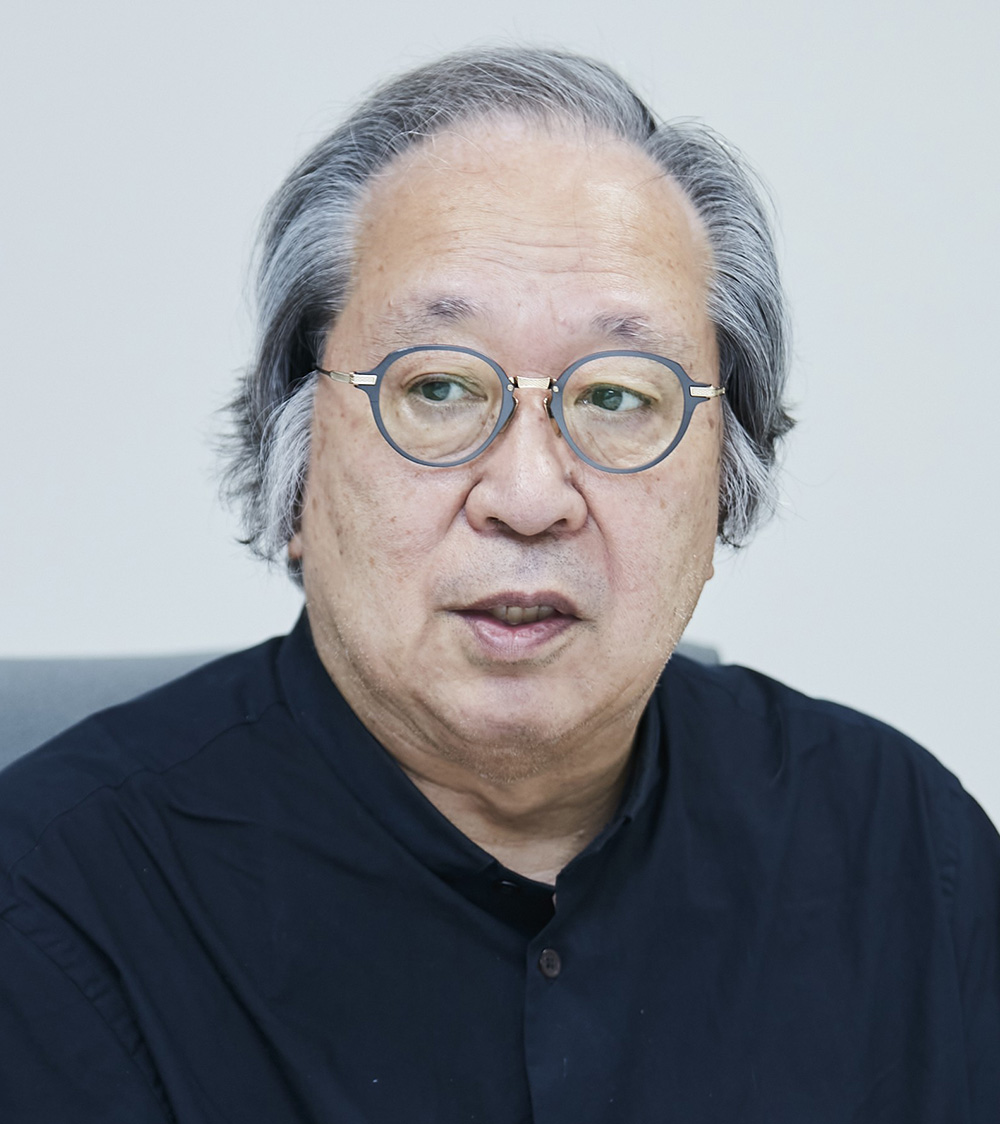
教育講演3
レジェンドによる寺子屋授業〜語り、つながり、受け継ぐ「知と心」〜
失語症状のとらえかた
| 座長: | 田中 春美 | (関西電力病院 リハビリテーション部) |
|---|
| 演者: | 松田 実 | (清山会医療福祉グループ 顧問) |
|---|
<学歴>
・昭和53年:京都大学医学部卒業 老年科(亀山正邦教授)入局
倉敷中央病院などでの初期研修を経た後
・昭和58年:京都大学医学部大学院(神経内科:亀山正邦教授)入学
・昭和62年:同卒業(医学博士:脳卒中患者の脂質代謝異常)
<職歴>
・昭和62年4月より有馬温泉病院リハビリテーション科部長
・平成2年6月:滋賀県立成人病センター神経内科医長
・平成5年4月: 同 神経内科部長
・平成14年4月: 同 老年内科部長
以後の10年間は、同センターで認知症と失語症の医療に専念する
・平成25年4月:東北大学大学院医学研究科 高次機能障害分野 准教授
・平成28年6月より、清山会医療福祉グループ顧問 いずみの杜診療所勤務
<資格等>
・日本神経学会専門医指導医、日本認知症学会専門医指導医
・日本高次脳機能障害学会名誉会員、老年精神医学会特別会員、認知症学会代議員、
神経精神医学会評議員
・「高次脳機能研究」編集委員長(2023年12月まで)、「神経心理学」編集委員
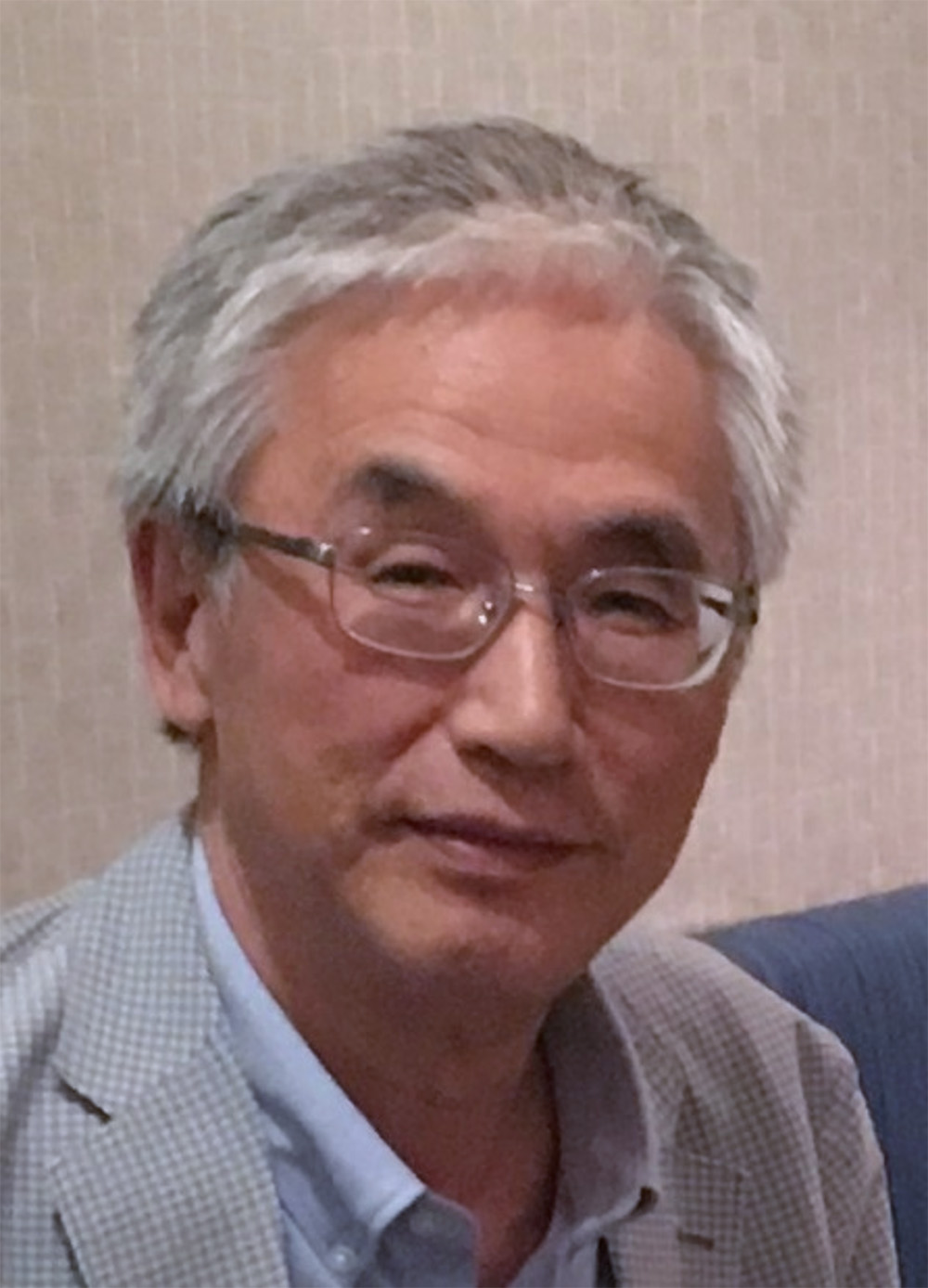
教育講演4
レジェンドによる寺子屋授業〜語り、つながり、受け継ぐ「知と心」〜
行動神経学の軌跡と展望
| 座長: | 西尾 慶之 | (大阪大学 行動神経学・神経精神医学寄付講座 教授) |
|---|
| 演者: | 森 悦朗 | (大阪大学大学院 特任教授) |
|---|
1977年 神戸大学医学部卒業、神戸大学医学部附属病院 研修医。1982年 神戸大学大学院医学研究科博士課程(内科学系)修了、兵庫県立姫路循環器病センター神経内科医長、1990年 Scripps Clinic and Research Foundation(米国加州)研究員、1993年 兵庫県立高齢者脳機能研究センター附属病院診療部長 兼 臨床研究科長、1999年 同附属病院副院長、2003年 東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学分野教授、2017年 同 定年退職。東北大学名誉教授、2017年 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院特任顧問、大阪大学招へい教授、2017年 大阪大学大学院連合小児発達学研究科行動神経学・神経精神医学寄附講座教授、2024年 同 特任教授
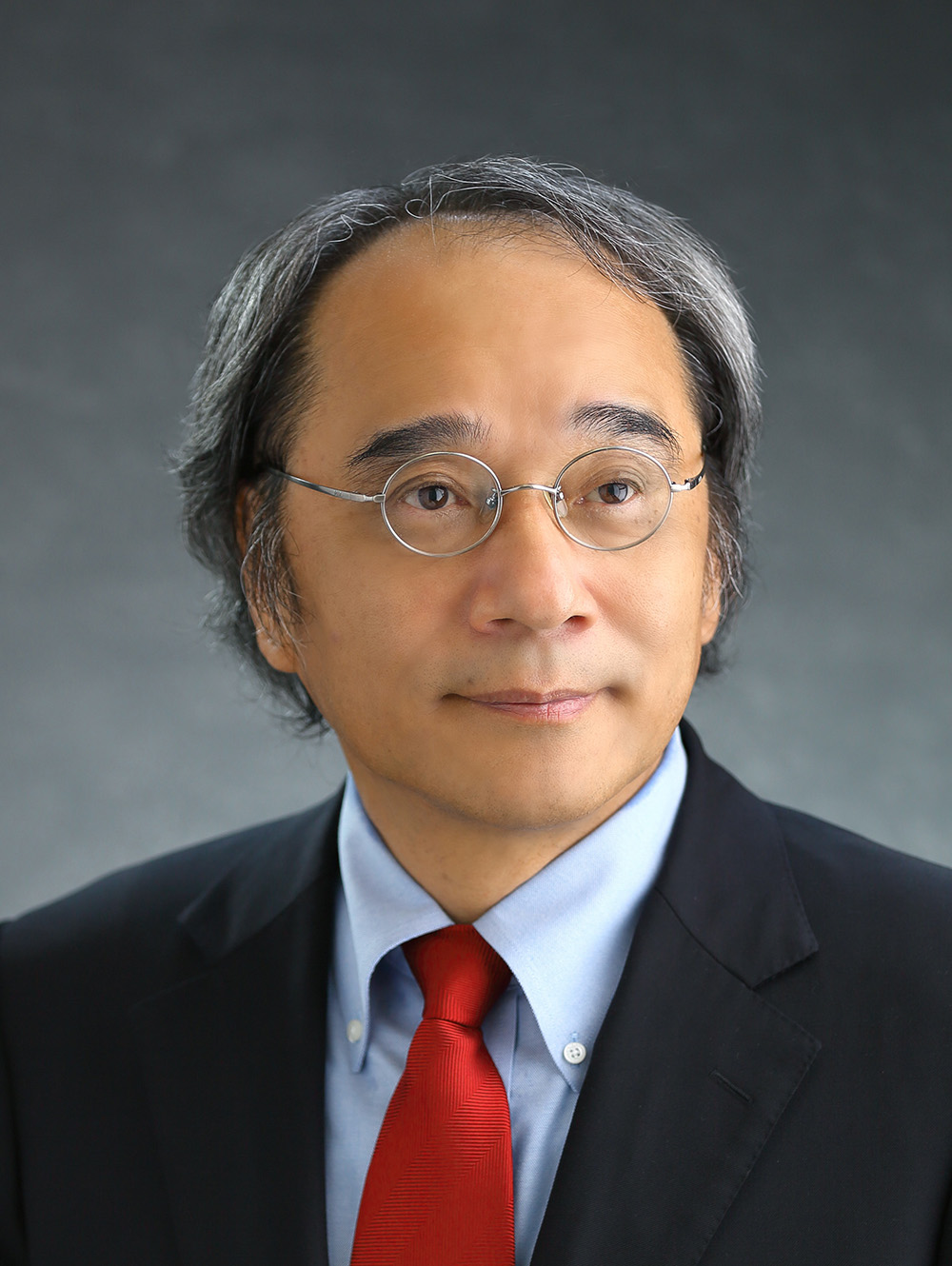
教育講演5
レジェンドによる寺子屋授業〜語り、つながり、受け継ぐ「知と心」〜
失認症
| 座長: | 花田 恵介 | (四條畷学園大学 リハビリテーション学部 教授) |
|---|
| 演者: | 平山 和美 | (仙台青葉学院大学 リハビリテーション学部 教授) |
|---|
現職: 仙台青葉学院大学リハビリテーション学部 教授
1980年 早稲田大学第一文学部卒業
1987年 福島県立医科大学卒業
福島県立医科大学神経精神科
1989年 福島県立医科大学医学部付属病院神経内科 助手
1997年 財団法人脳神経疾患研究所付属総合南東北病院第二神経内科 科長
2004年 東北大学病院高次機能障害リハビリテーション科 助手
2007年 同リハビリテーション部 講師
2009年 山形県立保健医療大学作業療法学科 教授
2022年 山形県立保健医療大学 特任教授
2024年 現職

教育講演6
レジェンドによる寺子屋授業〜語り、つながり、受け継ぐ「知と心」〜
認知症診療には「心のつながり」を ~認知症診断の心構えとpitfall(落とし穴)~
| 座長: | 長濱 康弘 | (かわさき記念病院 院長) |
|---|
| 演者: | 福井 俊哉 | (かわさき記念病院 脳神経内科) |
|---|
| 1980年3月 | 東京医科歯科大学医学部卒業 |
| 1980年5月 | 同医学部神経内科学教室入局 |
| 1982年4月 | 東京医科歯科大学神経内科助手 |
| 1983年7月 | 都立養育院病院神経内科医員 |
| 1985年8月 | 鹿教湯病院神経内科医長 |
| 1988年11月 | 昭和大学医学部神経内科助手 |
| 1990年5月 | 昭和大学医学部神経内科専任講師 |
| 1997年7月 | University of Western Ontario Research fellow |
| 2000年4月 | 昭和大学横浜市北部病院神経内科 専任講師 |
| 2002年11月 | 同 助教授 |
| 2005年4月 | 同 准教授 |
| 2012年10月 | 同 教授 |
| 2014年4月 | 花咲会かわさき記念病院 病院長・昭和大学医学部神経内科 客員教授 |
| 2025年4月 | 三星会かわさき記念病院 脳神経内科 |

教育講演7
レジェンドによる寺子屋授業〜語り、つながり、受け継ぐ「知と心」〜
抑制障害として前頭葉機能障害を捉える
| 座長: | 三村 將 | (慶應義塾大学 予防医療センター 特任教授) |
|---|
| 演者: | 鹿島 晴雄 | (慶應義塾大学 医学部 名誉教授/中山病院) |
|---|
| 1970年3月 |
慶應義塾大学医学部 卒業 木野崎病院、国立千葉病院神経科、慶應義塾大学医学部精神神経科助手、専任講師、助教授を経て |
| 2001年4月 | 慶應義塾大学医学部精神神経科 教授 |
| 2014年4月 |
国際医療福祉大学大学院 教授(臨床心理学専攻) 慶應義塾大学医学部 客員教授 中山病院 日本高次脳機能学会 元理事長 日本精神神経学会 元理事長 |

カレントスピーチ
カレントスピーチ1
高次脳機能障害を見落とさないために~被害者側弁護士の視点から~
| 座長: | 大沢 愛子 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科 医長) |
|---|
| 演者: | 古田 兼裕 | (古田総合法律事務所 代表弁護士) |
|---|
昭和23年生(岐阜県出身)
| 昭和48年3月 | 東京大学法学部政治学科卒業 |
| 昭和52年10月 | 司法試験合格 |
| 昭和55年4月 |
第32期司法修習修了 第二東京弁護士会登録 足立・ヘンダーソン法律事務所入所 |
| 昭和55年10月 | 古田法律事務所設立 |
| 昭和61年1月 | 古田・羽鳥法律事務所に組織変更 |
| 平成3年9月 | 古田・秋山・田中法律事務所に組織変更 |
| 平成9年4月 | 古田総合法律事務所に組織変更 |

カレントスピーチ2
高次脳機能障害者支援法の制定に向けて
| 座長: | 吉益 晴夫 | (埼玉医科大学総合医療センター 神経精神科 教授) |
|---|
| 演者: | 渡邉 修 | ((一社)戸田メディカルケアグループ(TMG) TMG本部 特別顧問) |
|---|
| 昭和60年 | 浜松医科大学医学部卒業 |
| 平成3年 | 脳神経外科学会認定医 |
| 平成7年 | スウェーデン カロリンスカ病院 臨床神経生理学部門 研究生 |
| 平成17年 | 首都大学東京教授 |
| 平成25年 | 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座教授 |
| 令和7年 |
一般社団法人 TMG本部/リハビリテーション医療 特別顧問/日本リハビリテーション医学会専門医、代議員、医学博士/日本交通科学学会理事、日本安全運転医療学会理事長/認知神経学会理事、日本高次脳機能障害学会評議員/国立障害者リハビリテーションセンター高次脳機能障害情報・支援運営委員会委員/東京都高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会委員長 日本高次脳機能障害友の会顧問、東京高次脳機能障害協議会顧問/東京慈恵医科大学客員教授 東京都立大学客員教授 |
海外講演
アフリカケニアの医療事情と生きる事を見つめ直して
| 座長: | 前島 伸一郎 | (国立長寿医療研究センター 長寿医療研修センター長) |
|---|
| 演者: | 武居 光雄 | (医療法人光心会諏訪の杜病院 理事長・院長) |
|---|
日本高次脳機能学会評議員、日本腎臓リハ学会理事・診療報酬対策委員会委員長、日本透析医学会透析専門医、日本リハ医学会専門医・指導責任者・元代議員、医学博士。日本政府内閣官房健康医療戦略室医療アドバイザー
1985年3月大分医大医学部卒業、信州大学医学部附属病院脳神経外科、相澤病院(リハ科、脳神経外科、救命救急科、麻酔科)、九州大学生体防御医学研究所附属病院気候内科(循環器科、呼吸器科、リハ科)等を経て、2000年4月諏訪の杜病院開設(日本リハ医学会研修指定病院)。1996年4月~2003年3月防衛医科大学校附属病院リハ科にて研鑽。2012年4月~2016年3月愛知医科大学医学教育センター客員教授。2007年6月共生の会:地域福祉作業所『工房きらら』を設立、2014年4月多機能型事業所(就労移行支援・就労継続支援B型)へ移行。2013年5月ケニア共和国ナクル州にて巡回診療開始、2016年4月ナイロビ市内にてメディカルセンター開設。2020年12月リハセンター開設。2024年12月第76回保健文化賞受賞。

文化講演(ティーサロン)
文化講演1(ティーサロン)
アナザーストーリーズ
ようやく解放されて青春時代の夢を追う-日本の美しい鉄道風景を求めて-
| 座長: | 中川 佳子 | (一般社団法人日本高次脳機能学会事務局) |
|---|
| 演者: | 石合 純夫 | (新さっぽろ脳神経外科病院 名誉院長) |
|---|
| 昭和58年3月 | 東京医科歯科大学医学部卒業 |
| 昭和58年4月 | 東京医科歯科大学医学部神経内科入局 |
| 昭和59年11月 | 埼玉県障害者リハビリテーションセンター,医員 |
| 昭和62年9月 | 東京医科歯科大学医学部助手,神経内科 |
| 昭和63年11月 | 東京都神経科学総合研究所リハビリテーション研究室/部門,主任研究員,副参事研究員,部門長と昇任 |
| 平成17年1月 | 札幌医科大学医学部リハビリテーション医学講座,教授 |
| 令和5年3月 | 同,定年退職 |
| 令和5年4月 | 新さっぽろ脳神経外科病院 名誉院長 |
日本高次脳機能学会:理事,BFT委員会委員長,長谷川賞選考委員会委員長,編集委員
日本神経心理学会:名誉会員,編集委員
日本神経学会:神経内科専門医,指導医
日本認知症学会:日本認知症学会認定専門医
<著書>
失われた空間 (神経心理学コレクション) 医学書院,2009
高次脳機能障害学第3版 医歯薬出版,2022
文化講演2(ティーサロン)
アナザーストーリーズ
脳外科医の探求心が辿り着いた邪馬台国と出雲の国およびヤマト政権の真相
| 座長: | 伊藤 皇一 | (医療法人敬寿会 吉村病院) |
|---|
| 演者: | 濵田 博文 | (鹿児島大学 名誉教授/日本高次脳機能学会 名誉会員・第35回学術総会 会長/社会医療法人緑泉会 米盛病院リハビリテーション科) |
|---|
昭和46年 鹿児島大学医学部医学科(以下、鹿医)卒
昭和46年 東京女子医大脳神経外科 研修医➡助手
昭和55年 鹿医脳神経外科講師
昭和55年 医学博士学位取得
昭和56年 (旧西)ドイツデュッセルドルフ大学神経病理学研究所 留学
昭和63年 鹿医保健学科 教授
平成15年 鹿大大学院保健学研究科 教授
平成19年 同大学保健学研究科長・保健学科長
平成21年 鹿大退職 現在同大名誉教授
・日本脳神経外科学会 昭和54年:専門医取得
・日本高次脳機能学会 平成2年:評議員 失語症実態調査委員会委員長、Brain Function Test・注意意欲評価法作成委員会委員 平成16年:理事 第35回日本高次脳機能学会学術総会 会長
・日本リハ医学会 平成元:認定臨床医・H4年:専門医取得 平成20年:評議員 指導責任者取得
・日本神経心理学会 昭和60年:評議員・会則検討委員会委員
・認知リハ研究会 平成14年:世話人・会誌編集委員

文化講演3(ティーサロン)
アナザーストーリーズ
温泉は心にも脳にも効果がある―湯けむりに秘められた医学的効果とは―
| 座長: | 菅原 光晴 | (清伸会ふじの温泉病院 リハビリテーション課) |
|---|
| 演者: | 前田 眞治 | (国際医療福祉大学 名誉教授) |
|---|
<略歴>
1983年 北里大学医学部医学科大学院修了
1991年 北里大学医療衛生学部助教授
2005年 国際医療福祉大学大学院 リハビリテーション学分野 教授
2025年 国際医療福祉大学 名誉教授 現在に至る
<学会役員>
2024年 日本高次脳機能学会 特別会員
2025年 日本温泉気候物理医学会 名誉会員
日本温泉科学会会長、日本温泉協会副会長、日本人工炭酸泉研究会会長 現在に至る
<専門医>
リハビリテーション専門医・指導医、脳卒中専門医・指導医、温泉療法専門医
<主な著書>
菅原光晴ら編の「臨床で使える半側空間無視への実践的アプローチ」医学書院の監修,
温泉の最新健康学、新温泉医学 など
温泉の脱衣場に行くと掲げてある温泉の禁忌症、適応症および注意事項の2012年改訂に、中心的役割を担って活動した。

文化講演4(ティーサロン)
アナザーストーリーズ
出雲神話に見える医療の原点―高次脳機能研究の視座から
| 座長: | 村井 俊哉 | (京都大学大学院 医学研究科 精神医学 教授) |
|---|
| 演者: | 小林 祥泰 | (島根大学 医学部 名誉教授) |
|---|
<略歴>
| 昭和47年3月 | 慶應義塾大学医学部卒業 |
| 昭和47年5月 | 北里大学病院病棟医(研修医) |
| 昭和54年4月 | 北里大学医学部内科講師(神経内科学) |
| 昭和55年4月 | 島根医科大学附属病院第3内科講師 |
| 平成5年11月 | 島根医科大学内科学講座第三・教授 |
| 平成17年4月 | 国立大学法人島根大学医学部附属病院長 |
| 平成24年4月 | ―同27年3月 島根大学学長 |
| 平成27年4月 | 島根大学名誉教授、医学部特任教授(6年間) |
| 平成27年4月 | 耕雲堂小林病院理事長 |
<主研究領域>
神経内科学、脳卒中学、高次脳機能(認知症含む)
日本初のMRIによる脳ドックの開設(1988)と追跡調査によるエビデンス作成
日本初の脳卒中データバンクの構築(1999)
脳疾患によるアパシーの臨床(2008)新興医学出版社
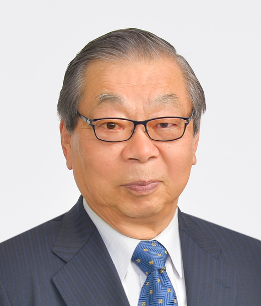
シンポジウム
シンポジウム1
失語症のリハビリテーション再考
セッション要旨
日本高次脳機能障害学会の前身である失語症学会の歴史を振り返りつつ、現在の失語症リハビリテーションの最新動向を探ります。本シンポジウムでは、失語症の評価・治療に関する伝統的アプローチと革新的アプローチを融合し、これからのリハビリテーションの方向性を議論します。このシンポジウムを通じて、従来の治療法を踏まえつつ、テクノロジーや多職種連携を取り入れた新たな失語症リハビリテーションの可能性を探ります。
| 座長: | 大槻 美佳 | (北海道大学大学院 保健科学研究院) |
|---|---|---|
| 種村 純 | (びわこリハビリテーション専門職大学 リハビリテーション学部) |
「失語症の長期的変遷から考える言語訓練の在り方について」
| 演者: | 中川 良尚 | (江戸川病院 リハビリテーション科) |
|---|
言語聴覚士、臨床神経心理士、公認心理師、認定言語聴覚士(失語・高次脳機能障害領域)
1998年東京理科大学理学部卒業
2000年日本福祉教育専門学校卒業
2001年より社会福祉法人仁生社江戸川病院リハビリテーション科勤務
2007年より同言語室主任
2008年筑波大学大学院夜間修士課程カウンセリング専攻リハビリテーションコース修了
2020年より社会福祉法人仁生社江戸川病院リハビリテーション科言語療法専門科長 現在に至る
日本高次脳機能学会(代議員、教育・研修委員会副委員長、機関紙編集委員会委員、失語症レジストリ委員会委員、Brain Function Test委員会委員)、日本神経心理学会(評議員)、日本言語聴覚士協会(代議員、学術研究部部員)、認知リハビリテーション研究会(世話人)

「失語症リハビリテーションにおける複合的介入の臨床実践と課題」
| 演者: | 辰巳 寛 | (愛知学院大学 健康科学部 健康科学科) |
|---|
愛知学院大学健康科学部健康科学科教授
名古屋市立大学大学院医学研究科生体情報・機能制御医学専攻修了
博士(医学) 言語聴覚士 精神保健福祉士
名古屋第二赤十字病院神経病センターの勤務を経て、現職
NPO法人高次脳機能障害者支援「笑い太鼓」、NPO法人つばさ吃音相談室などで臨床に従事
「術前・術中・術後とシームレスな介入で言語機能を守る覚醒下手術の世界」
| 演者: | 二村 美也子 | (福島県立医科大学附属病院 リハビリテーションセンター) |
|---|
<学歴>
2000年 愛知淑徳大学文学部コミュニケーション学科 卒業
2002年 日本聴能言語福祉学院聴能言語学科 卒業
2023年 福島県立医科大学大学院医学研究科 医科学専攻 修士課程 修了
<職歴>
2002年 医療法人白山会白山リハビリテーション病院 療法部 入職
2009年 名古屋大学医学部附属病院 リハビリテーション部 入職
2012年 国立病院機構名古屋医療センター リハビリテーション科 入職
2015年 福島県立医科大学医学部脳神経外科学講座 非常勤職員
2016年 福島県立医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 入職(現職)
<主な所属学会>
日本神経心理学会(評議員)
日本高次脳機能障害学会(代議員)
日本ヒト脳マッピング学会
日本脳腫瘍の外科学会
日本脳腫瘍学会
日本Awake Surgery学会
<資格>
2002年 言語聴覚士
2022年 臨床神経心理士

「ことばの間違いと高次脳機能障害」
| 演者: | 佐藤 厚 | (愛知淑徳大学 健康医療科学部 言語聴覚学専攻) |
|---|
| 昭和63年5月 | 三之町病院言語治療室 |
| 平成13年4月 | 新潟リハビリテーション病院リハビリテーション部 |
| 平成23年3月 | 新潟医療福祉大学大学院修士課程修了 |
| 平成27年4月 | 新潟リハビリテーション大学医療学部言語聴覚学専攻 |
| 令和3年4月 | 五泉中央病院リハビリテーション科 |
| 令和4年10月 | 愛知淑徳大学健康医療科学部言語聴覚学専攻 |

「失語症者の社会復帰を支える支援」
| 演者: | 八木 真美 | (川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター) |
|---|
| 1997年~ | 特定医療法人暲純会 榊原温泉病院 |
| 2002年~ | 川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター |
現在に至る

シンポジウム2
障害の理解を深めるー効果的な高次脳機能リハビリテーションをめざして
セッション要旨
リハビリテーション医療において、複数の職種が協業する現代の医療現場では、高次脳機能や多様な疾患・病態に関する理解が欠かせません。さまざまな高次脳機能障害がリハビリに与える影響を知ることで、治療方針がより的確になり、支援の質も向上します。本シンポジウムを通じて各職種が高次脳機能の知識を深め、現場での効果的なリハビリテーションにつなげることを目指します。
| 座長: | 豊倉 穣 | (東海大学 医学部 リハビリテーション科学) |
|---|---|---|
| 近藤 正樹 | (京都府立医科大学 脳神経内科) |
「高次脳機能障害者支援拠点機関の外来医師の視点から」
| 演者: | 先崎 章 | (埼玉県総合リハビリテーションセンター 高次脳機能障害者支援センター/東京福祉大学 社会福祉学部) |
|---|
1961年生まれ。1986年東京医科歯科大学医学部卒業後、都立広尾病院、静和会浅井病院、都立豊島病院、埼玉県総合リハビリテーションセンターなどに勤務。2009年より東京福祉大学社会福祉学部教授(週4日)および埼玉県総合リハビリテーションセンター医師(週2日)にて現在に至る。精神神経学会専門医、リハビリテーション医学会専門医、てんかん学会専門医。
「進行性疾患における高次脳機能障害外来の現状と課題」
| 演者: | 永井 知代子 | (帝京平成大学 健康メディカル学部 言語聴覚学科) |
|---|
| 1991年 |
山形大学医学部卒業 同 第三内科研修医 |
| 1992年 | 米沢市立病院内科 |
| 1994年 | 東京都立老人(現・健康長寿)医療センター神経内科 |
| 1995年 | 東京女子医科大学神経内科研究生→非常勤講師 |
| 1999年 | 東京大学大学院医学系研究科博士課程終了 |
| 2006年 | 科学技術振興機構ERATO浅田共創知能システムプロジェクト研究員 |
| 2011年〜 | 帝京平成大学健康メディカル学部言語聴覚学科教授 |
「高次脳機能障害と神経発達症」
| 演者: | 橋本 圭司 | (錦海リハビリテーション病院 リハビリテーション科/昭和医科大学藤が丘リハビリテーション病院 リハビリテーション科) |
|---|
1998年 東京慈恵会医科大学卒業
1999年 東京都リハビリテーション病院
2000年 神奈川リハビリテーション病院
2004年 東京医科歯科大学難治疾患研究所
2005年 東京慈恵会医科大学附属病院
2009年 国立成育医療研究センター
2016年 はしもとクリニック経堂
2021年 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
2025年 錦海リハビリテーション病院

「高次脳機能障害に対する非侵襲的脳刺激」
| 演者: | 角田 亘 | (国際医療福祉大学 医学部 リハビリテーション医学教室) |
|---|
1991年 東京慈恵会医科大学卒業
1993年 国立循環器病センター(現国立循環器病研究センター)内科脳血管部門レジデント
2000年 星ヶ丘厚生年金病院(大阪府枚方市)脳血管内科医長
2004年 Stanford大学(米国カリフォルニア州)脳卒中センター客員研究員
2012年 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座准教授
2017年 国際医療福祉大学医学部リハビリテーション医学教室主任教授
現在、日本リハビリテーション医学教育推進機構理事、日本急性期リハビリテーション医学会理事、日本スティミュレーションセラピー学会副理事長、日本脳卒中学会理事、日本リハビリテーション医学会代議員、日本神経学会代議員。
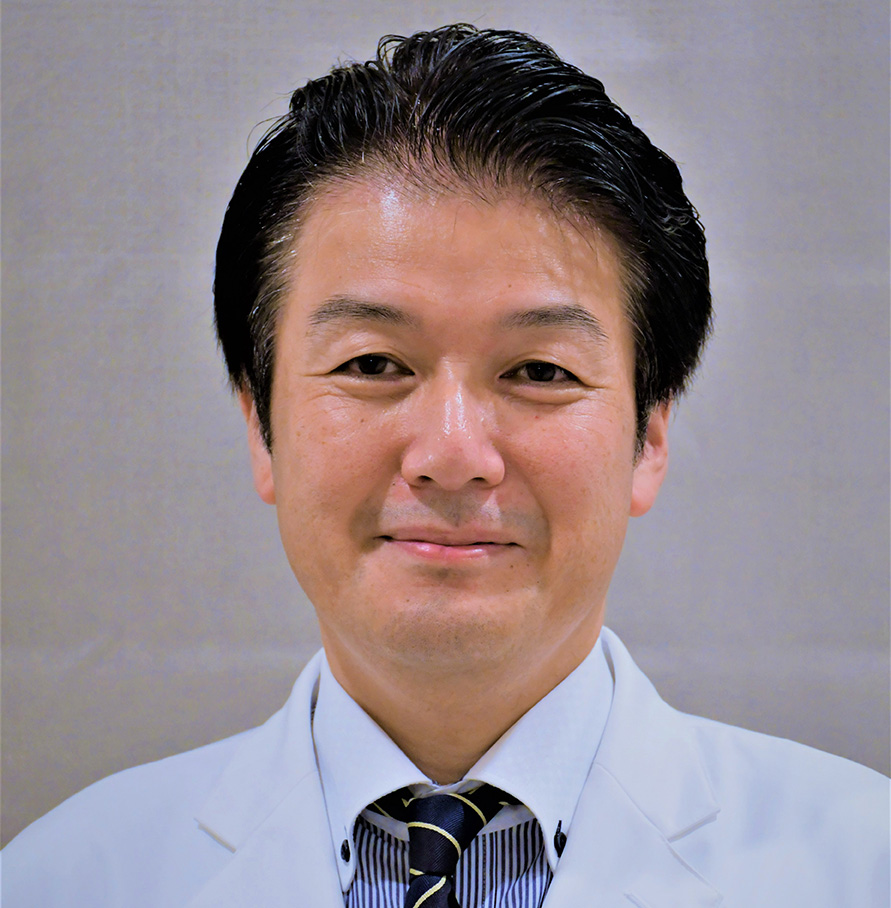
シンポジウム3
記憶障害とそのリハビリテーションの現在と未来
セッション要旨
記憶は私たちのアイデンティティや日常生活を支える重要な機能であり、記憶障害によって失われた記憶力をいかに回復し、また新たな生活スキルとして補完していくかが課題となります。本シンポジウムでは、脳の可塑性を活かしたリハビリ手法や、支援者と患者が共に取り組むエビデンスベースのアプローチについて、臨床の第一線で活躍する専門家が多角的に紹介し、効果的なリハビリの在り方を探ります。
| 座長: | 月浦 崇 | (京都大学 人間・環境学研究科 認知・行動・健康科学講座) |
|---|---|---|
| 緑川 晶 | (中央大学 文学部) |
「脳卒中後の記憶障害:オーバービュー」
| 演者: | 石原 健司 | (旭神経内科リハビリテーション病院 神経内科) |
|---|
1989年 東京大学教養学部卒
1995年 千葉大学医学部卒
昭和大学病院、亀田総合病院、汐田総合病院で臨床研修を行ない
2006年 昭和大学神経内科講師
2016年より現職
専門領域 臨床神経学 神経心理学 神経病理学
「外傷性脳損傷と記憶障害」
| 演者: | 岡﨑 哲也 | (博愛会病院 リハビリテーション科) |
|---|
<経歴>
1991年 産業医科大学医学部卒業
1999年 産業医科大学大学院修了・博士(医学)
1999年 長崎労災病院リハビリテーション科診療科長
2002年 産業医科大学リハビリテーション医学講座講師
2015年 産業医科大学若松病院リハビリテーション科診療教授
2018年 博愛会病院副院長 現在に至る
<所属学会>
日本高次脳機能障害学会(代議員)
日本リハビリテーション医学会(専門医・指導医,代議員,九州地方会幹事)
日本安全運転医療学会(理事)ほか

「覚えてなくても大丈夫?: デジタル技術による認知的サポートの現在地」
| 演者: | 船山 道隆 | (足利赤十字病院 神経精神科) |
|---|
| 1996年 | 慶應義塾大学医学部卒、同年同大学精神神経科入局 |
| 1997年 | 足利赤十字病院内科 |
| 1998年 | 足利赤十字病院 神経精神科 |
| 2009年~ | 足利赤十字病院 神経精神科部長 |
| 2023年~ | 慶應義塾大学医学部 精神神経科 特任准教授 |
<専門医>
1. 専門医:精神科専門医および指導医
2. 指定医:精神科指定医
<学会>
1. 日本高次脳機能学会:編集委員長, 理事
2. 日本神経心理学会:理事、編集委員
3. 日本老年精神医学会:評議員
4. 日本認知症学会:評議員
5. 総合病院精神医学会:理事、医療政策委員長、編集委員
6. 日本神経精神医学会:評議員
<学位>
医学博士(2017年取得)
「作業記憶への介入は記憶リハビリテーションにおける基盤となりうるのか」
| 指定発言: | 吉村 貴子 | (京都先端科学大学 健康医療学部 言語聴覚学科) |
|---|
<学歴>
1994年 慶應義塾大学総合政策学部卒業
1998年 大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程修了
2002年 大阪外国語大学大学院言語社会研究科博士後期課程単位取得退学
2005年 博士(学術)(大阪外国語大学) 取得
<主な職歴>
1997年 和歌山県立医科大学附属病院脳神経外科言語聴覚療法担当
2007年 大阪河﨑リハビリテーション大学言語聴覚学専攻 講師
2009年 大阪滋慶学園 大阪医療技術学園専門学校言語聴覚士学科学科長
2015年 京都学園大学 准教授
2019年 京都先端科学大学(京都学園大学から校名変更)教授(~現在学科長)

「展望記憶の特性を踏まえたリハビリテーション」
| 指定発言: | 梅田 聡 | (慶應義塾大学 文学部 心理学研究室) |
|---|
1998年 慶應義塾大学 大学院社会学研究科心理学専攻博士課程単位取得退学,2002年 博士(心理学)取得
1998年 日本学術振興会 特別研究員 (PD)
1999年 慶應義塾大学 文学部人文社会学科心理学専攻 助手
2006年 同 助教授 (2007年より准教授)
2006~2007年 ロンドン大学 認知神経科学研究所・神経学研究所・国立神経学神経外科病院 訪問研究員
2014年 同 教授
2020年 慶應義塾大学 医学部精神・神経科学教室 兼担教授

シンポジウム4
在宅復帰を目指した高次脳機能障害のリハビリテーション
セッション要旨
本シンポジウムでは、高次脳機能障害患者のケアが始まる急性期から、退院後の在宅生活までを一つの連続した流れとして捉え、評価から治療・再統合までの包括的アプローチを探求します。急性期病棟での早期介入による機能回復のエビデンス、回復期リハビリテーション病棟での多職種連携、さらに在宅復帰後に必要とされるモニタリングと生活環境調整。各ステージで求められる専門職の役割や、ICT・遠隔リハビリなどの最新手法を提示し、患者一人ひとりに寄り添った質の高い継続ケアを実現するための実践知を共有します。
公益財団法人在宅医療助成 勇美記念財団の助成による
| 座長: | 木戸 保秀 | (松山リハビリテーション病院) |
|---|---|---|
| 櫻井 靖久 | (三井記念病院 健康管理科) |
「高次脳機能障害患者診療における急性期病院の役割」
| 演者: | 稲富 雄一郎 | (済生会熊本病院 脳神経内科) |
|---|
1991年 徳島大学医学部卒業
1991年 麻生飯塚病院 研修医を経て 神経内科
1998年 済生会熊本病院 脳神経内科 現在に至る
日本神経学会 指導医
日本神経心理学会 評議員,理事
日本高次脳機能学会 代議員
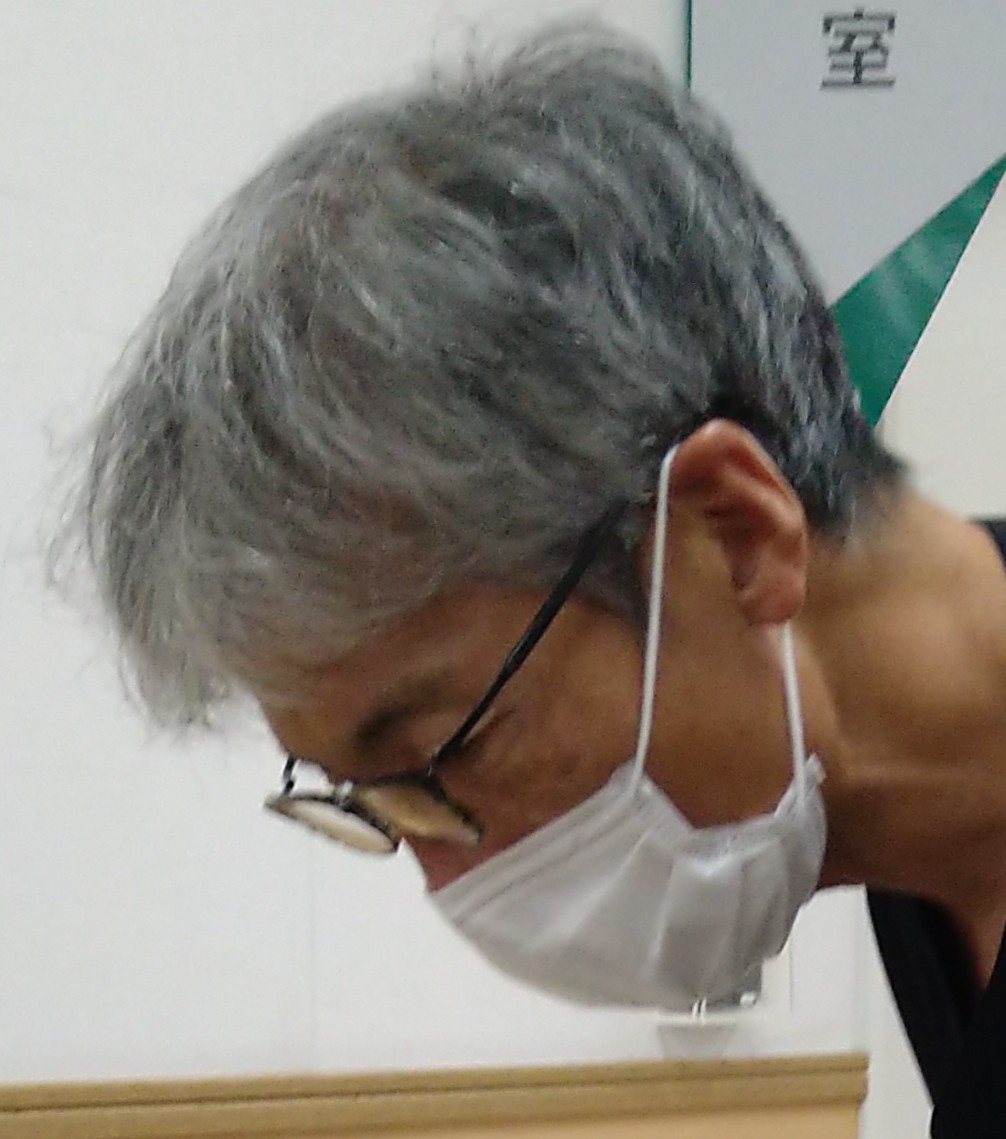
「回復期リハ病棟における評価・介入の実際や、その後の在宅復帰を見据えた診療連携の視点」
| 演者: | 渡邉 誠 | (藤田医科大学七栗記念病院 リハビリテーション部門) |
|---|
1999年3月中京大学文学部国文学科卒業。2005年3月藤田保健衛生大学リハビリテーション専門医療専門課程作業療法科を修了し、作業療法士資格を取得。同年4月より藤田保健生大学七栗サナトリウム(藤田医科大学七栗2018年藤田保健衛生大学大学院医療科学部保健衛生学科修士課程を修了。

「当院における高次脳機能障害への遠隔リハビリテーションの経験」
| 演者: | 青木 重陽 | (神奈川リハビリテーション病院 リハビリテーション科) |
|---|
1991年 千葉大学卒業
同大学脳神経外科入局
2001年 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座入局
2002年 東京都立大塚病院リハビリテーション科
2004年 神奈川リハビリテーション病院リハビリテーション科
2010年 同病院 高次脳機能障害支援室長
2017年 英国The Oliver Zangwill Centreに留学
2018年 神奈川リハビリテーション病院リハビリテーション科、高次脳機能障害支援室長

「高次脳機能障害と自動車運転支援」
| 演者: | 加藤 徳明 | (社会医療法人陽明会 小波瀬病院 リハビリテーション科/産業医科大学 リハビリテーション医学講座) |
|---|
| 平成13年3月 | 産業医科大学医学部卒業 |
| 平成13年6月 |
産業医科大学リハビリテーション医学講座入局、 臨床研修医、専門修練医 |
| 平成19年6月 | 門司労災病院リハビリテーション科勤務 |
| 平成20年4月 | (財)西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所 勤務 |
| 平成22年6月 | 産業医科大学病院リハビリテーション医学講座 助教 |
| 平成31年1月 | 産業医科大学病院リハビリテーション医学講座 講師 |
| 平成31年4月 | 産業医科大学若松病院リハビリテーション科 診療科長 |
| 令和3年4月 | 小波瀬病院リハビリテーション科 医長 |
| 令和4年4月 |
小波瀬病院リハビリテーション科 部長 産業医科大学リハビリテーション医学講座非常勤医師 現在に至る |

「高次脳機能障害のある方の退院後のリハビリテーション」
| 演者: | 深津 玲子 | (国立障害者リハビリテーションセンター 脳神経内科) |
|---|
東北大学医学部を卒業後、同大神経内科入局。宮城病院神経内科部長などを経て2006年より国立障害者リハビリテーションセンター勤務。同センター学院長、高次脳機能障害情報・支援センター長、東北大学医学部高次脳機能障害科担当臨床教授を務めた。2022年4月より国立障害者リハビリテーションセンター顧問。
脳神経内科専門医、リハビリテーション認定臨床医

パネルディスカッション
指導者必見!どうして伝える高次脳機能の魅力
セッション要旨
近年、研究離れや働き方改革の影響で、若手の関心を高めることが課題となっています。高次脳機能の理解は医療、教育、福祉の発展に大きく貢献する重要な分野です。本パネルディスカッションでは、若手が情熱を持って学び、成長できる環境づくりについて、リハビリテーションに関わる療法士、医師、学生を指導する立場の先生から報告していただきます。
| 座長: | 鈴木 匡子 | (東北医科薬科大学病院 高次脳機能障害支援センター、山形県高次脳機能障がい者支援センタ―) |
|---|---|---|
| 椿原 彰夫 | (川崎医療福祉大学) |
「高次脳機能障害学の世界へようこそ-わかる高次脳機能障害学の工夫」
| 演者: | 太田 信子 | (川崎医療福祉大学 リハビリテーション学部 言語聴覚療法学科) |
|---|
1997年 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科言語聴覚専攻卒業
倉敷平成病院リハビリテーション科
2011年 川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科感覚矯正学専攻修了
川崎医科大学附属川崎病院リハビリテーションセンター
2014年 川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター
2015年 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科言語聴覚専攻講師
2019年 川崎医療福祉大学リハビリテーション学部言語聴覚療法学科准教授
2025年 教授、現在に至る

「臨床現場はわからないことだらけ!だったら知っている人に訊く!!」
| 演者: | 高岩 亜輝子 | (九州大学大学院 医学研究院 神経内科 ブレインセンター/広島大学大学院 医系科学研究科) |
|---|
<学歴>
| 平成7年 | 福岡教育大学 障害児教育科 言語障害教育教員養成課程 修了 |
| 平成13年 | 明星大学 人文学部 心理教育科 心理学専攻卒業 |
| 平成22年 | 富山大学大学院 医学薬学教育部 生命・臨床医学専攻 博士課程 修了(医学博士) |
<職歴>
| 平成7年〜 | 白十字会 白十字病院 リハビリテーション科 言語聴覚士 |
| 平成15年〜 | 九州大学大学院 医学研究院 神経内科 研究員 心理士 |
| 平成16年〜 | 富山大学附属病院 リハビリテーション部(脳神経外科)言語聴覚士 |
| 平成29年〜 | 十文字学園女子大学 人間生活学部 児童教育科 准教授 |
| 令和元年〜 | 富山県済生会富山病院 高次脳機能障害ケア管理臨床診療部 科長 |
| 令和3年〜 | 福岡青洲会病院 リハビリテーション部 教育主任 |
| 現在 |
九州大学大学院 医学研究院 神経内科 共同研究員 公認心理師 広島大学大学院 医系科学研究科 客員准教授 |
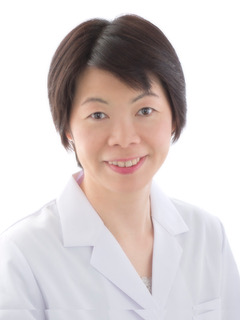
「若いOTの発表意欲を高めるためには?~私の体験談から思うこと~」
| 演者: | 種村 留美 | (関西医科大学 リハビリテーション学部) |
|---|
平成16年 広島大学大学院博士(後期)課程修了 博士(保健学)
平成12年~平成19年 京都大学医学部保健学科作業療法学専攻 助教授
平成19年4月~令和5年3月 神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域
運動器障害学分野教授、神戸大学大学院保健学研究科 副研究科長、アジア健康科学フロンティアセンター長
令和5年4月~ 関西医科大学リハビリテーション学部作業療法学科長現在に至る
「医師に高次脳機能を学んでもらうには?」
| 演者: | 鈴木 匡子 | (東北医科薬科大学病院高次脳機能障害支援センター/山形県高次脳機能障がい者支援センター) |
|---|
ワークショップ
臨床神経心理士とは~私たち役に立ってるよ!~
セッション要旨
資格制度創設から4年を経て、臨床神経心理士の現場での活躍や資格取得による変化を振り返り、本音での議論を行います。臨床神経心理士試験の合格した資格取得が日々の臨床活動にどう貢献しているか、また職場や患者にどのような影響を与えているかを、さまざまな現場から具体的なエピソードとともに共有していただきます。このワークショップを通して、臨床神経心理士の役割や課題を再確認し、今後の展望を考える機会にしたいと思います。
| 座長: | 橋本 衛 | (近畿大学 医学部 精神神経科学教室) |
|---|---|---|
| 小森 憲治郎 | (愛媛県認知症疾患医療センター 十全ユリノキ病院 医療福祉相談室) |
「臨床神経心理士がチーム・ビルディングをする」
| 演者: | 穴水 幸子 | (NHO栃木医療センター 精神科/東京都立大学 人文社会学部) |
|---|
1991年新潟大学医学部卒業。1991年慶應義塾大学医学部精神・神経科入局。2000年同大学同科助教。その後、民間病院の勤務を経て、2011年より国際医療福祉大学言語聴覚学科講師。のちに心理学科准教授
2020年より栃木県精神保健福祉センター副主幹。2022年よりNHO栃木医療センター精神科 医長、現在に至る。
東京都立大学人文社会学部客員研究員。精神科専門医。公認心理師。臨床神経心理士。日本精神神経学会代議員、日本高次脳機能学会代議員

「認知症疾患医療センターで働く作業療法士の力の見せどころ」
| 演者: | 植田 郁恵 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部) |
|---|
2003年 愛知医療専門学校 作業療法学科卒
2003年 独立行政法人 国立病院機構 東名古屋病院勤務
2007年 国立長寿医療研究センター勤務 作業療法士長(現職)
<受賞歴>
2024 国立長寿医療研究センター 理事長奨励賞
<資格免許>
作業療法士
介護支援専門員
心不全療養指導士
臨床神経心理士
「進行性疾患から小児、もやもや病まで!多様なフィールドでのSTの“高次脳”支援」
| 演者: | 宮﨑 彰子 | (川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター) |
|---|
| 1995年3月 | 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科 卒業 |
| 1995年4月 | 川崎医科大学附属病院 入職 |
| 2003年6月 | 川崎医科大学附属病院 言語聴覚士副主任 |
| 2012年10月 | 川崎医科大学附属病院 言語聴覚士主任 |
| 2018年4月 | 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科 特任講師 |
| 2020年4月 | 川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター療法士長 |
| 2022年4月 | 川崎医療福祉大学リハビリテーション学部言語聴覚療法学科 特任准教授 |
2018年 第42回 日本高次脳機能障害学会学術総会 優秀ポスター賞受賞
日本高次脳機能障害学会会員 代議員
日本摂食嚥下リハビリテーション学会会員 評議員

「公認心理師の立場から考える臨床神経心理士」
| 演者: | 菅 寛子 | (医療法人三星会 かわさき記念病院 認知症疾患医療センター) |
|---|
淑徳大学大学院修了後、臨床心理士として高齢者専門病院で勤務。2018年、認知症専門のかわさき記念病院に転職し、翌年、公認心理師を取得。脳神経内科医のもとで臨床活動を行い、「神経心理学」の視点から認知症を解明する面白さに魅了される。仲間と共に学びを深め、2022年第1回試験で臨床神経心理士を取得。現在は、神経心理学的検査・医療相談・家族や関係者支援・啓発活動・地域支援など幅広い認知症臨床に従事。

基礎から学ぶシリーズ
基礎から学ぶシリーズ:レクチャー
今さら聞けない脳疾患〜病態の理解と対応~
セッション要旨
医療系大学や専門学校では学びきれない、脳疾患の病態とリハビリテーションの実際について、若手セラピストが知るべき「現場のリアル」に迫る講座です。経験を積んだ専門医が、脳卒中や頭部外傷、脳腫瘍などの病態と治療について、最前線で活躍されている臨床医が現場での生々しいケースを交えながら解説します。若手セラピストが日々のリハビリを自信を持ってできるよう、質問や討論の機会を通じて実践的なスキルの習得を目指します。
| 座長: | 西林 宏起 | (国立病院機構南和歌山医療センター 脳神経外科) |
|---|---|---|
| 前澤 聡 | (国立病院機構名古屋医療センター 脳神経外科) |
「今さら聞けない脳疾患 ~病態の理解と対応~ 脳出血編」
| 演者: | 中井 康雄 | (和歌山県立医科大学 脳神経外科) |
|---|
「脳血管内治療後急性期リハビリテーションにおける留意事項」
| 演者: | 山根 文孝 | (国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科) |
|---|
| 1986年3月 | 福井医科大学医学部医学科卒業 |
| 1986年4月 | 東京女子医大脳神経外科入局 |
| 1996年7月 | Montreal Neurological Institute, Research fellow |
| 2007年4月 | 埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科 講師 |
| 2010年3月 | 埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科 准教授 |
| 2017年4月 | 帝京大学医学部附属病院脳神経外科 病院教授 |
| 2021年4月 | 国際医療福祉大学成田病院 脳神経外科教授 |
| 2024年4月 | 現職 |

「脳外傷の病態 -高次脳機能障害を惹起しやすい脳挫傷とびまん性軸索損傷を中心に-」
| 演者: | 中 大輔 | (日本赤十字社和歌山医療センター 救急科・集中治療部) |
|---|
| 平成元年3月 | 和歌山県立医科大学 卒業 |
| 平成2年4月 | 和歌山県立医科大学付属病院 研修医 |
| 平成4年7月 | 和歌山労災病院 脳神経外科 |
| 平成7年4月 | 和歌山県立医科大学付属病院 臨床研究医 |
| 平成8年6月 | 岡崎国立共同研究機構 生理学研究所 助手 |
| 平成8年8月 | 日本脳神経外科学会 専門医 |
| 平成10年1月 | 博士号(医学)取得 |
| 平成10年4月 | 英国オックスフォード大学留学 |
| 平成11年4月 | 和歌山県立医科大学付属病院 脳神経外科 助手 |
| 平成15年4月 | 日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科 |
| 平成21年2月 | 日本赤十字社和歌山医療センター 神経救急部 部長 |
| 平成22年8月 | 日本脳卒中学会 専門医 |
| 令和元年7月 | 日本赤十字社和歌山医療センター 高度救命救急センター長 |
| 令和3年5月 | 日本脳神経外傷学会 指導医 |
| 令和6年4月 | 日本赤十字社和歌山医療センター 副院長 |

「リハビリテーションに活かす脳腫瘍の知識-腫瘍を見極めて可塑性を引き出す-」
| 演者: | 藤井 正純 | (福島県立医科大学 医学部 脳神経外科学講座) |
|---|
1992年 名古屋大学医学部卒業
1995年 マサチューセッツ総合病院・研究員(Research fellow, Stroke and Neurovascular Regulation Lab. Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School)
1997年 名古屋大学医学部附属病院脳神経外科・医員
1999年 小牧市民病院脳神経外科・医員
2000年 名古屋大学医学部附属病院脳神経外科・助手
2005年 国家公務員共済組合連合会名城病院脳神経外科・部長
2007年 名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学・助教
2015年 福島県立医科大学医学部脳神経外科学講座・准教授
2021年 福島県立医科大学医学部脳神経外科学講座・主任教授
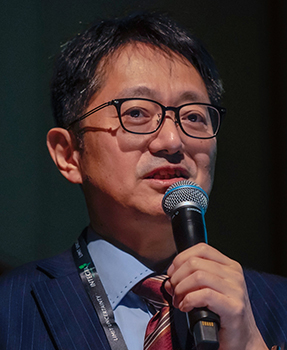
基礎から学ぶシリーズ:ワークショップ
高次脳機能リハビリテーションを支えるチーム連携
セッション要旨
高次脳機能障害の診療・支援においては、多職種の専門的な知識・技術・倫理観が密接に関わります。本セッションでは、脳神経外科、精神科、リハビリテーション科などの若手専門医や、臨床神経心理士の資格を取得した作業療法士・言語聴覚士など、実際に資格取得に至る過程を経験した若い先生方にご登壇いただき、それぞれの立場から、資格取得までに求められた学習・臨床経験と直面した困難や成長の契機、高次脳機能に関わる専門職としての責任や姿勢について語っていただき、多職種で「高次脳機能障害とどう向き合うか」を再考する場とします。
| 座長: | 平岡 崇 | (川崎医科大学 リハビリテーション医学教室) |
|---|---|---|
| 伊藤 直樹 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部) |
「脳神経外科領域における高次脳機能障害」
| 演者: | 前島 一偉 | (日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科) |
|---|
<学歴・職歴>
| 2017年3月 | 藤田保健衛生大学(現 藤田医科大学) 卒業 |
| 2017年4月 | 碧南市民病院 初期研修医 |
| 2019年4月 | 関西医科大学附属病院 心臓血管外科 |
| 2019年7月 | 日本赤十字社和歌山医療センター 救急科部 |
| 2020年4月 | 和歌山県立医科大学附属病院 脳神経外科 |
| 2021年4月 | 岸和田徳洲会病院 脳神経外科 |
| 2023年4月 | 日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科部 |
現在に至る
<資格>
| 2024年9月 | 日本脳神経外科学会 専門医 |
| 2025年9月 | 日本脳神経血管内治療学会 専門医 |

「失語症者の意思決定支援について」
| 演者: | 神里 千瑛 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科) |
|---|
<学歴・職歴>
| 2019年3月 | 琉球大学医学部 卒業 |
| 2019年4月 | 国立長寿医療研究センター初期臨床研修医 |
| 2021年4月 | 同 リハビリテーション科 専攻医 |
| 2024年6月 | 同 リハビリテーション科 医師 |
現在に至る
<資格>
| 2024年6月 | 日本リハビリテーション医学会 専門医 |
「高次脳機能リハビリテーションを支えるチーム連携 -精神科医の立場から-」
| 演者: | 三村 悠 | (慶應義塾大学 医学部 精神・神経科学教室) |
|---|
<職歴>
2016年4月 - 2018年3月 足利赤十字病院 初期臨床研修医
2018年4月 - 2019年3月 足利赤十字病院 神経精神科
2019年4月 - 2019年12月 慶應義塾大学病院 精神・神経科 専修医
2020年1月 - 2020年3月 杏林大学病院 Trauma and Critical Care center 専修医
2020年4月1日- 2022年2月28日 慶應義塾大学医学部助教
2022年3月1日- 現在まで 慶應義塾大学特任助教
2024年4月1日- 2025年3月31日 東京都立松沢病院 精神科医員
2025年4月1日- 医療法人財団厚生協会 大泉病院
<資格>
| 2016年3月 | 日本医師免許 |
| 2022年5月 | 精神保健指定医 |
| 2022年7月 | 臨床神経心理士 |
| 2023年2月 | 日本精神神経学会 専門医 |
| 2024年6月 | 認知症学会 専門医 |

「高次脳機能障害とどう向き合うか〜言語聴覚士の立場から〜」
| 演者: | 山路 千明 | (藤田医科大学七栗記念病院 リハビリテーション科) |
|---|
<学歴・職歴>
2009年 三重大学教育学部 学校教育教員養成課程卒業
2011年 日本聴能言語福祉学院 聴能言語学科卒業
2012年 藤田医科大学病院入職
2014年 藤田医科大学七栗記念病院へ異動
2022年 金城大学大学院 総合リハビリテーション学研究科 修士課程修了
現在、藤田医科大学七栗記念病院リハビリテーション部 副主任 言語聴覚士
<認定資格>
日本言語聴覚士協会 失語・高次脳機能障害領域 認定言語聴覚士
日本言語聴覚士協会 摂食嚥下障害領域 認定言語聴覚士
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 チーム医療実践リーダー育成研修修了
日本神経心理学会・日本高次脳機能学会 臨床神経心理士
<活動>
三重県失語症者向け意思疎通支援者養成研修
三重県高次脳機能障害支援者養成研修
津市失語症サロン支援
「「わからない」が続くから、おもしろい」
| 演者: | 早川 裕子 | (横浜市立脳卒中・神経脊椎センター リハビリテーション部) |
|---|
1990年 東京都立医療技術短期大学作業療法学科卒業
同年 東京女子医科大学病院リハビリテーション部入職
1994年 東京女子医科大学病院リハビリテーション部退職
同年 東北大学医学系研究科障害科学専攻高次機能障害分野修士課程入学
1999年 東北大学医学系研究科障害科学専攻高次機能障害分野博士課程修了
同年 横浜市立脳血管医療センター(現:横浜市立脳卒中・神経脊椎センター)入職
現在に至る
<所属学会等>
日本作業療法士協会(認定作業療法士・高次脳機能障害分野専門作業療法士)
日本高次脳機能学会(代議員)
日本神経心理学会(評議員)
認知リハビリテーション研究会(世話人)
臨床神経心理士

クロストーク
新しい高次脳のリーダーズ:密談クロストーク〜高次脳機能領域の未来を描こう~
セッション要旨
本セッションは、高次脳機能領域の未来を切り拓く若手リーダーたちと会場のオーディエンスが一体となり、臨床・研究・教育、そして学会のこれからについて、率直かつ建設的に語り合うクロストーク企画です。多職種・多分野にわたる演者たちが、それぞれの現場で感じている課題意識や展望を出発点に、未来に向けた具体的なアクションや連携のあり方を議論します。セッション後半では、会場からの意見・質問も積極的に取り入れながら、聴衆との双方向の対話を通じて「高次脳機能領域の未来地図」を共に描く場とします。参加者全員が「当事者」として、高次脳機能のフィールドを自分たちの手で進化させていく覚悟と希望を共有する、熱量の高いセッションを目指します。
| 司会: | 船山 道隆 | (足利赤十字病院 神経精神科) |
|---|---|---|
| 大沢 愛子 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科) |
| 演者: | 上田 敬太 | (京都光華女子大学 看護福祉リハビリテーション学部 福祉リハビリテーション学科言語聴覚専攻) |
|---|
<略歴>
内科を中心にローテートを4年間行い,その後京大精神科に入局。
| 2001年4月 | 京都大学医学部附属病院 精神科 神経科 非常勤医師 |
| 2002年4月 | 大阪赤十字病院精神科医師 |
| 2004年4月 | 京都大学大学院医学研究科入学 |
| 2008年4月 | 京都大学研修員 |
| 2009年11月 |
京都大学大学院医学研究科 精神医学 助教 同時に京都市身体障害者リハビリテーションセンター附属病院(現在は京都市地域リハビリテーション推進センター)【嘱託医】 京都大学医学部附属病院 脳神経外科 神経心理外来を担当 |
| 2015年1月 | 御所南リハビリテーションクリニックでも神経心理外来を担当 |
| 2019年11月~ | 京都大学大学院医学研究科 精神医学 講師 |
| 2021年4月~ | 京都光華女子大学 健康科学部医療福祉学科 言語聴覚専攻 教授 |
| 2024年4月~ | 京都光華女子大学 看護福祉リハビリテーション学部 福祉リハビリテーション学科 言語聴覚専攻 教授 |
専門は器質性精神疾患 神経心理学
<所属学会>
日本精神神経学会
高次脳機能障害学会
日本神経心理学会
日本認知神経科学会
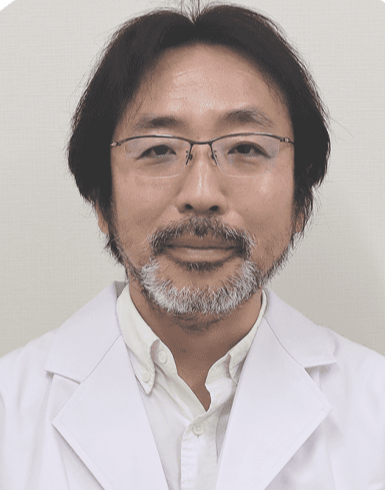
| 高倉 祐樹 | (北海道ことばのリハビリ相談室) |
2006年 北海道医療大学心理科学部言語聴覚療法学科 卒業
2006年 特別医療法人明生会網走脳神経外科・リハビリテーション病院 入職
2012年 社会医療法人明生会道東脳神経外科病院 入職
2013年 医療法人秀友会札幌秀友会病院 入職
2015年 北海道大学大学院保健科学院保健科学専攻修士課程 修了
2017年 北海道医療大学リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科 助教
2019年 北海道大学大学院保健科学院保健科学専攻博士後期課程 修了
2019年 北海道大学大学院保健科学研究院高次脳機能創発分野 特任助教
2023年 北海道大学大学院保健科学研究院 客員研究員
2024年 北海道ことばのリハビリ相談室 主宰 現在に至る

| 西尾 慶之 | (大阪大学大学院 行動神経学・神経精神医学寄附講座) |
医学博士
脳神経内科専門医、精神科専門医、精神保健指定医
日本認知症学会専門医
日本神経心理学会理事、日本高次脳機能障害学会代議員
1998年 慈恵医大卒業
慈恵医大と(旧)兵庫県立高齢者脳機能研究センターで初期研修と脳神経内科レジデント
2004年 東北大学医学系研究科高次機能障害学分野博士課程
2007年 同 助教
2010年 同 講師
(2013−2014年 ニューヨーク大学てんかんセンター 客員研究員)
2016年 同 准教授
2018年 東京都立松沢病院 精神科・脳神経内科 医長
2023年 大阪大学大学院行動神経学・神経精神医学寄附講座 准教授
2024年 同教授

| 船山 道隆 | (足利赤十字病院 神経精神科) |
| 1996年 | 慶應義塾大学医学部卒、同年同大学精神神経科入局 |
| 1997年 | 足利赤十字病院内科 |
| 1998年 | 足利赤十字病院 神経精神科 |
| 2009年~ | 足利赤十字病院 神経精神科部長 |
| 2023年~ | 慶應義塾大学医学部 精神神経科 特任准教授 |
<専門医>
1. 専門医:精神科専門医および指導医
2. 指定医:精神科指定医
<学会>
1. 日本高次脳機能学会:編集委員長, 理事
2. 日本神経心理学会:理事、編集委員
3. 日本老年精神医学会:評議員
4. 日本認知症学会:評議員
5. 総合病院精神医学会:理事、医療政策委員長、編集委員
6. 日本神経精神医学会:評議員
<学位>
医学博士(2017年取得)
| 大沢 愛子 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科) |
| 2002年3月 | 和歌山県立医科大学医学部医学科卒業 |
| 2002年4月 | 和歌山県立医科大学附属病院 診療医臨床研修 |
| 2004年4月 | 川崎医科大学リハビリテーション科 臨床助手 |
| 2010年12月 | 埼玉医科大学医学部 講師(埼玉医科大学国際医療センターリハビリテーション科副診療科長) |
| 2013年5月 | 国立長寿医療研究センターリハビリテーション科医員 |
| 2014年8月 | 同 認知症支援・ロボット応用研究室) 室長 |
| 2017年4月 | 同 リハビリテーション科医長 |
医学博士 臨床神経心理士
日本リハビリテーション医学会 代議員・認定臨床医・専門医・指導医
日本認知症学会 専門医・指導医・代議員
日本脳卒中学会 評議員・専門医・指導医
日本老年医学会 代議員
日本サルコペニアフレイル学会 評議員・指導士
日本意識障害学会 理事・サポート医
日本高次脳機能障害学会 幹事 代議員
日本旅行医学会 認定医
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士

編集委員会共催セミナー
知っておきたい論文の書き方講座
| 座長: | 長濱 康弘 | (かわさき記念病院 院長) |
|---|
| 演者: | 小林 俊輔 | (帝京大学 医学部 脳神経内科 教授) |
|---|
1993年3月 東京大学医学部卒業
1998年6月~2002年3月 東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程
2002年4月~2005年3月 日本学術振興会研究員(玉川大学脳科学研究施設)
2005年4月~2010年3月 ケンブリッジ大学 Wellcome Trust特別研究員
2010年4月~2019年12月 福島県立医科大学神経内科学講座
2020年1月~2021年12月 帝京大学医学部神経内科学講座准教授
2021年12月~2023年3月 同教授
2023年4月~ 帝京大学医学部脳神経内科学講座主任教授
<専門領域>
高次脳機能障害学,運動障害性疾患,神経生理学
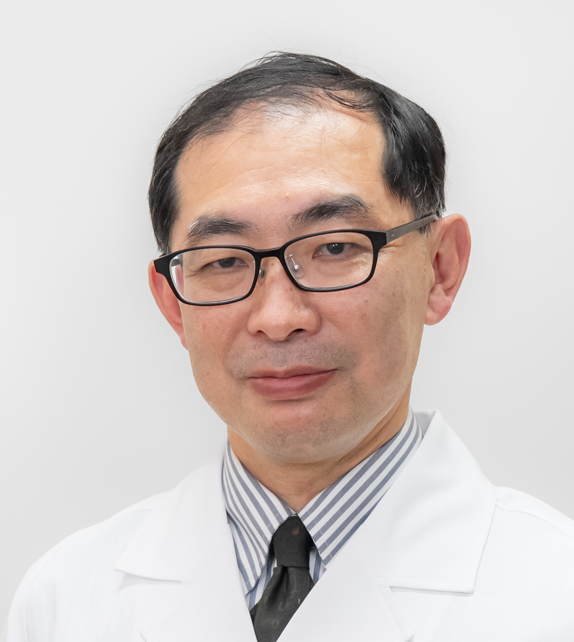
利益相反・倫理委員会共催セミナー
知っておきたい研究倫理ならびに利益相反(COI: Conflict of Interest)の考え方
| 座長: | 中川 賀嗣 | (北海道医療大学 リハビリテーション科学部 教授) |
|---|
| 演者: | 平岡 崇 | (川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 教授) |
|---|
| 平成8年 | 川崎医科大学卒業 |
| 平成14年 | 川崎医科大学大学院 生理系病態運動生理学 修了(博士(医学)) |
| 平成17年 |
川崎医科大学リハビリテーション医学教室 講師 川崎医科大学附属病院リハビリテーション科 医長 |
| 平成22年 | Johns Hopkins University, PM&R, Post Doctoral Research Fellow |
| 平成25年 |
川崎医科大学リハビリテーション医学教室 准教授 川崎医科大学附属病院リハビリテーション科 副部長 川崎医療福祉大学リハビリテーション学部 教授(現職/兼務) |
| 令和7年7月 |
川崎医科大学リハビリテーション医学教室 教授(現職) 川崎医科大学附属病院リハビリテーション科 部長(現職) 川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター センター長(現職) |

広報委員会共催セミナー
高次脳機能障害に対する障害者手帳の書き方
| 座長: | 平岡 崇 | (川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 教授) |
|---|
| 演者: | 大沢 愛子 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科 医長) |
|---|
| 2002年3月 | 和歌山県立医科大学医学部医学科卒業 |
| 2002年4月 | 和歌山県立医科大学附属病院 診療医臨床研修 |
| 2004年4月 | 川崎医科大学リハビリテーション科 臨床助手 |
| 2010年12月 | 埼玉医科大学医学部 講師(埼玉医科大学国際医療センターリハビリテーション科副診療科長) |
| 2013年5月 | 国立長寿医療研究センターリハビリテーション科医員 |
| 2014年8月 | 同 認知症支援・ロボット応用研究室) 室長 |
| 2017年4月 | 同 リハビリテーション科医長 |
医学博士 臨床神経心理士
日本リハビリテーション医学会 代議員・認定臨床医・専門医・指導医
日本認知症学会 専門医・指導医・代議員
日本脳卒中学会 評議員・専門医・指導医
日本老年医学会 代議員
日本サルコペニアフレイル学会 評議員・指導士
日本意識障害学会 理事・サポート医
日本高次脳機能障害学会 幹事 代議員
日本旅行医学会 認定医
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士

AMED特別シンポジウム
遊んで学ぶ!eSportsの社会実装
セッション要旨
本シンポジウムは、日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受けて進められている最新の研究成果を広く共有し、認知症および軽度認知障害(MCI)に対する新たなアプローチの可能性を探ることを目的としています。現在、大沢班では、eスポーツやタブレット端末などの電子機器を活用し、「認知」「身体」「社会性」を複合的に刺激するデジタルヘルスプログラムの実施可能性とその効果検証に取り組んでいます。これまでの医療やリハビリの枠を超えたアプローチは、高齢者のQOL(生活の質)の向上、孤立の予防、疾患の進行抑制といった多面的な価値を持ち得るものです。本シンポジウムでは、当該プロジェクトを中心に、AMEDが支援する他の認知症関連研究についても紹介しながら、テクノロジーと人のつながりが生み出す「支援の未来」について、議論を深めていきます。
| 座長: | 古和 久朋 | (神戸大学大学院 保健学研究科) |
|---|---|---|
| 大沢 愛子 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科) |
「認知症、および軽度認知障害の人に対する非薬物的介入の社会実装への期待」
| 演者: | 數井 裕光 | (高知大学 医学部 神経精神科学講座) |
|---|
1989年 鳥取大学医学部 卒業
1989年 大阪大学医学部神経科精神科 入局
1995年 大阪大学大学院医学系研究科博士課程 修了
1997年 兵庫県立高齢者脳機能研究センター臨床研究科老年精神科研究室 室長
2002年 大阪大学大学院医学系研究科精神医学分野 助手
2006年 同上 講師
2018年 高知大学医学部神経精神科学講座 教授 現在に至る、
大阪大学キャンパスライフ健康支援センター 特任教授併任(2020年3月まで)
2020年 大阪大学大学院医学系研究科精神医学分野 招聘教授併任
2022年 AMED長寿科学研究開発事業 プログラムオフィサー併任
2024年 高知大学医学部 副学部長併任、特定非営利活動法人 高知医学研究・教育支援機構 理事長併任

「認知症共生社会の実現を目指すための他者交流多因子ヘルスケアサービスの社会実装研究の概要」
| 演者: | 伊藤 直樹 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部) |
|---|
| 1996年3月 | 藤田保健衛生大学(現藤田医科大学)リハビリテーション専門学校 理学療法科卒業 |
| 1996年4月 | 同大学病院 リハビリテーション科入職 |
| 2005年4月 | 同大学 衛生学部(現保健衛生学部)リハビリテーション学科 |
| 2012年3月 | 同大学大学院にて博士(医学)を取得 |
| 2013年1月 | 国立長寿医療研究センターへ理学療法主任として入職 |
| 2016年4月 | 同センター 副理学療法士長 |
| 2018年5月 | 同センター 理学療法士長 |
| 2021年4月 | 同センター 統括管理士長(現在に至る) |

「地域高齢者と学生の電子機器(含,eスポーツ)を介した交流がもたらす効果」
| 演者: | 木林 勉 | (金城大学大学院 総合リハビリテーション学研究科) |
|---|
<略歴>
| 1986年6月 | 富山市民病院 リハビリテーション部勤務 |
| 1999年4月 | 富山市保健所 健康課 |
| 2004年4月 | 富山市役所 福祉保健部 介護保険課 |
| 2008年4月 | 金城大学 医療健康学部 准教授 |
| 2012年4月 | 金城大学 医療健康学部 教授 |
| 2014年4月 | 金城大学 医療健康学部 学部長補佐 教授 |
| 2015年4月 |
金城大学 医療健康学部 学部長補佐 教授 金城大学大学院リハビリテーション学研究科 教授 |
| 2019年4月 |
金城大学 医療健康学部 学部長 金城大学大学院総合リハビリテーション学研究科 教授 |
| 2024年4月 | 金城大学大学院総合リハビリテーション学研究科長 |
| 2025年4月 |
金城大学副学長 金城大学大学院総合リハビリテーション学研究科長 |
<取得資格>
保健学博士
理学療法士免許
呼吸療法認定士(日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔学会合同)
介護支援専門員
福祉用具プランナー講師
<主な社会活動>
富山県立大学大学院看護学研究科講師(非常勤)
富山県介護支援専門員専門研修講師(専門Ⅰ・Ⅱ・主任更新研修)
富山県腰痛予防指導者育成研修会講師
富山市地域包括支援センター運営協議会委員
富山市地域包括支援センター評価委員
富山市介護予防推進会議委員
全国リハビリテーション学校協会理事
理学療法・作業療法専任教員養成講習会講師
<好きな食べ物>
チョコレート
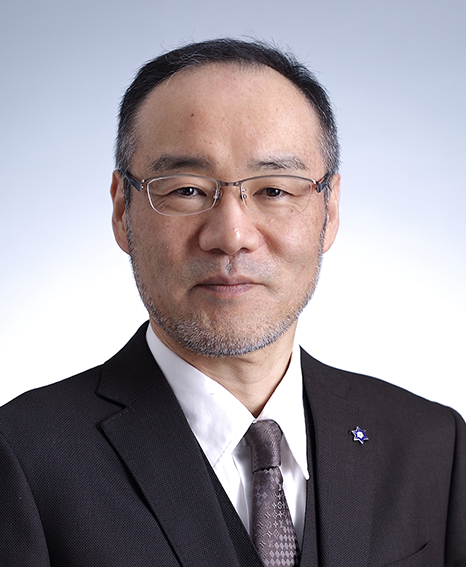
「軽度認知障害または認知症の人に対する電子機器を用いた複合介入の効果検証」
| 演者: | 神谷 正樹 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部) |
|---|
2009年 藤田医科大学 リハビリテーション部
2012年 国立長寿医療研究センター もの忘れセンター
2013年 国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部
2014年 藤田医科大学大学院 保健学研究科 修了
2019年 国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部 主任
2021年 同所属 リサーチマネージャー(兼務)

長寿研特別シンポジウム
超高齢社会における高齢者医療の最前線~認知症・フレイル・嚥下障害をどう支えるか~
セッション要旨
本邦は世界でも類を見ない超高齢社会を迎え、高齢者医療の課題はますます複雑化しています。認知症、フレイル、嚥下障害などの加齢に伴う機能低下は、高齢者のQOLや自立度に大きな影響を与えるとともに、医療・介護の現場においても深刻な問題となっています。本シンポジウムでは、高齢者医療の最前線で活躍する専門家を招き、認知症を中心にフレイルや嚥下障害を含めた包括的なケアと介入の最新知見を共有し、今後の高齢者医療のあり方について議論します。
| 座長: | 長田 乾 | (横浜総合病院 臨床研究センター) |
|---|---|---|
| 佐藤 正之 | (国立長寿医療研究センター もの忘れセンター) |
「認知症の人と家族をどう支えるか」
| 演者: | 武田 章敬 | (国立長寿医療研究センター もの忘れセンター) |
|---|
1989年 名古屋大学医学部 卒業
2004年 国立長寿医療センター 第一アルツハイマー型認知症科医長
2008年 厚生労働省老健局 認知症対策専門官
2010年 国立長寿医療研究センター 脳機能診療部第二脳機能診療科医長
2020年 国立長寿医療研究センター 長寿医療研修センター長
2022年 国立長寿医療研究センター もの忘れセンター長
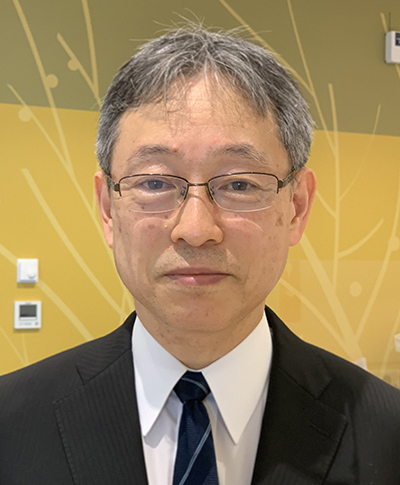
「フレイルを軸とした高齢者への新たな取り組み」
| 演者: | 赤津 裕康 | (国立長寿医療研究センター ロコモフレイルセンター) |
|---|
1991年 名古屋市立大学医学部医学科卒業
同年 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院(八事日赤)初期研修
1992年 名古屋市立大学大学院医学研究科入学/医療法人さわらび会福祉村病院勤務
2018年 名古屋市立大学大学院地域医療教育学教授(診療担当)/同病院地域包括ケア推進研究センター長
2024年 国立長寿医療研究センターロコモフレイルセンター長
2025年 同 在宅医療・地域医療連携推進部長
補体制御因子、神経病理、高齢者栄養管理の研究を行うと共に終末期高齢者医療に従事してきた。現在はフレイルレジストリー研究を中心に早期からの介護予防策の検討を行っている。
「高齢者の摂食嚥下障害」
| 演者: | 加賀谷 斉 | (国立長寿医療研究センター 摂食嚥下・排泄センター) |
|---|
1988年 東北大学医学部卒業
1994年 秋田大学大学院修了
1995年 秋田大学医学部付属病院助手
1997年 市立秋田総合病院リハビリテーション科医長
2001年 同科長
2006年 藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学 I 講座助教授
2007年 同准教授
2016年 藤田保健衛生大学(現:藤田医科大学)医学部リハビリテーション医学 I 講座教授
2022年 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部長
2022年 同摂食嚥下・排泄センター長
2022年 藤田医科大学客員教授
2023年 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 副院長
2025年 同健康長寿支援ロボットセンター長

「運動による認知症への対応:コグニサイズ」
| 演者: | 島田 裕之 | (国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター) |
|---|
| 2003-2005 | 東京都老人総合研究所(研究員) |
| 2005-2006 | Prince of Wales Medical Research Institute(客員研究員) |
| 2006-2010 | 東京都老人総合研究所(研究員) |
| 2010-2014 | 国立長寿医療研究センター(室長) |
| 2014-現在 | 国立長寿医療研究センター(部長) |
| 2019-現在 | 国立長寿医療研究センター研究所老年学・社会科学研究センター(センター長) |
| 2015-現在 | 信州大学大学院(特任教授:兼任) |
| 2019-現在 | 同志社大学(客員教授:兼任) |
| 2023-現在 | 理化学研究所(客員研究員:兼任) |
| 2024-現在 | 東京都立大学(客員教授:兼任) |
| 2025-現在 | 名古屋大学(連携教授:兼任) |
| 2025-現在 | 日本福祉大学(客員教授:兼任) |

ランチョンセミナー
ランチョンセミナー1
抗アミロイドβ抗体療法をタイムリーに届けるために
| 座長: | 大沢 愛子 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科 医長) |
|---|
| 演者: | 古和 久朋 | (神戸大学大学院 保健学研究科 リハビリテーション科学領域 教授) |
|---|
共催:エーザイ株式会社/
バイオジェン・ジャパン株式会社
ランチョンセミナー2
アルツハイマー病治療の最前線〜抗アミロイドβ抗体治療薬〜
| 座長: | 前島 伸一郎 | (国立長寿医療研究センター 長寿医療研修センター長) |
|---|
| 演者: | 武地 一 | (藤田医科大学 医学部 認知症・高齢診療科 教授) |
|---|
共催:日本イーライリリー株式会社
ランチョンセミナー3
治らぬ疾患 へのアプローチ:認知症と失語症
| 座長: | 長田 乾 | (横浜総合病院 臨床研究センター センター長) |
|---|
| 演者: | 佐藤 正之 | (国立長寿医療研究センター もの忘れセンター) |
|---|
共催:興和株式会社
ランチョンセミナー4
認知症の行動・心理症状に対する包括的治療
| 座長: | 小野 賢二郎 | (金沢大学 医薬保健研究域医学系 脳神経内科学 教授) |
|---|
| 演者: | 數井 裕光 | (高知大学 医学部 神経精神科学講座 教授) |
|---|
共催:大塚製薬株式会社
イブニングセミナー
ここまで見える!日常臨床における認知症画像診断の最前線
| 座長: | 大沢 愛子 | (国立長寿医療研究センター リハビリテーション科 医長) |
|---|
| 演者: | 櫻井 圭太 | (独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院 放射線科 統括診療部 放射線部長) |
|---|
共催:PDRファーマ株式会社
© 2024 The 49th Annual Scientific Meeting
of Japan Society for Higher Brain Function