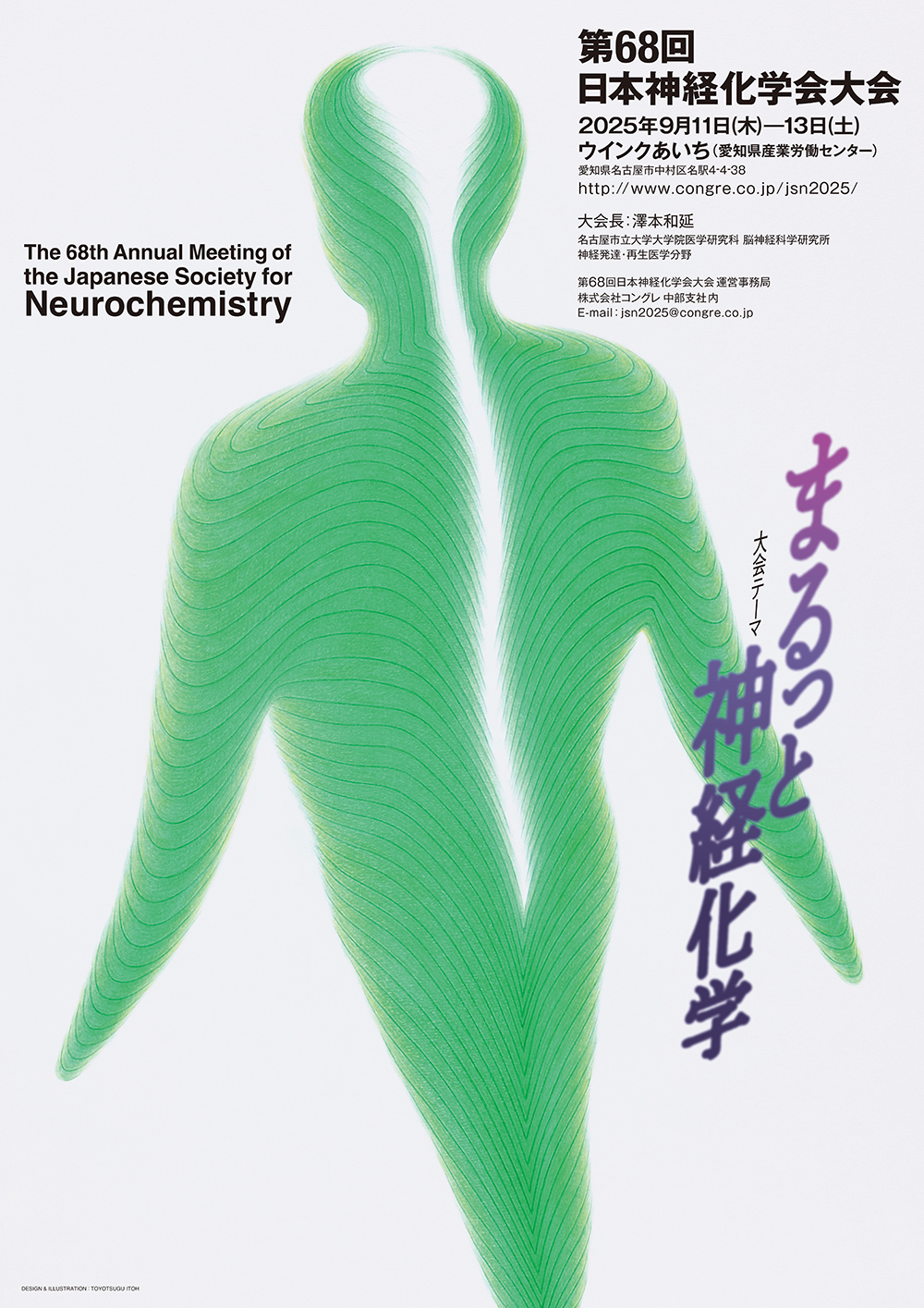企画・公募シンポジウム
企画シンポジウム
SS-1 日本神経化学会理事会企画シンポジウム
9月11日(木)9:20~11:20
第1会場(2F 大ホール)
双方向性TR・RTRで達成するブレークスルー
Breakthroughs Achieved through Interactive TR and RTR

座長・オーガナイザー
林(高木)朗子
(理化学研究所)

座長
岡野 栄之
(慶應義塾大学)

オーガナイザー
七田 崇
(東京科学大学)
セッション詳細
神経精神疾患は社会への影響が大きいにもかかわらず、病態理解は依然として不十分であり、治療効果にも限界があります。その要因の一つとして、動物モデルでは疾患を完全に再現できない一方、生体脳を細胞レベルで直接観察・操作することが倫理的・技術的に困難な点が挙げられます。本シンポジウムでは、この難題を克服すべく、基礎神経科学の最前線と臨床現場で得られる知見を双方向にフィードバックし、病態の本質に挑む研究を推進している演者にご登壇いただきます。玉石混交の膨大な手がかりの中から本質を見極め、組み合わせることで、神経精神疾患理解のブレークスルーを目指す最先端の取り組みをご紹介いただきます。
演者:
増田 隆博
高橋 琢哉
岩坪 威
七田 崇
(九州大学)
(横浜市立大学)
(東京大学)
(東京科学大学)
SS-2 前年度優秀賞受賞者企画シンポジウム
9月11日(木)16:15~18:15
第1会場(2F 大ホール)
行動を司るナノスケール・グリア-神経回路動態
Nanoscopic Glia-Neuron Circuit Dynamics in Behavior

オーガナイザー
長井 淳
(理化学研究所)
セッション詳細
アストロサイトをはじめとしたグリアは従来の光学顕微鏡では捉えきれないナノスケールの構造を持ち、神経細胞やシナプスと相互作用して脳機能を支えています。しかし、その動態が行動レベルの脳活動とどのように相関し、相互に影響を及ぼすのかは長らく不明でした。近年、超解像ライブイメージングや先端的な細胞形態の操作技術、行動解析とCLEM(相関光電子顕微鏡)の発展により、アストロサイトの微細形態の変化が記憶や睡眠などの行動とどのように関わるのかが明らかになりつつあります。本シンポジウムでは、分子・細胞形態レベルから行動レベルまでの最前線の研究を議論します。神経科学や行動研究に興味のある方、学生から専門家まで広く歓迎します。
演者:
有薗 美沙
田中 和正
窪田 芳之
仙波 和恵
長井 淳
(京都大学)
(沖縄科学技術大学院大学)
(生理学研究所)
(Dalhousie University)
(理化学研究所)
SS-3 ISN-JSNジョイントシンポジウム
9月12日(金)9:20~11:20
第1会場(2F 大ホール)
精神展開剤の治療メカニズム
Therapeutic Mechanisms of Classical and Non-classical Psychedelics for Stress-related Disorders

オーガナイザー
田中 謙二
(慶應義塾大学)
セッション詳細
麻酔薬ケタミン、幻覚剤シロシビンは、いずれも麻薬として扱われています。これらの薬は今や精神展開剤と呼ばれ、ストレス関連精神疾患に治癒をもたらす新たな治療薬として注目を集めています。その治療メカニズムには不明なところが多いので、精神薬理学、構造生物学、神経解剖学、分子生物学、トランスレーショナルリサーチなど、さまざまな観点から世界中の研究者がこの問題に取り組んでいます。今回は、Eero Castrén(Nat Neurosci 2023, Cell 2021)、Christine Denny(Biol Psychiatry 2024)、Leigh Walker (Br J Pharmacol 2024)、阿部欣史(Cell Rep Med 2023)の各大陸を代表する4名の研究者を迎えます。本シンポジウムは新規抗うつ薬の作用機序を理解するための重要な枠組みを提供し、JSN会員のサイエンスを深め、ISNへの参加意欲を高めます。若い人は留学先を探すチャンスです!
共催:International Society for Neurochemistry (ISN)
演者:
Eero Castrén
Christine Ann Denny
Leigh C Walker
阿部 欣史
(ヘルシンキ大学)
(コロンビア大学)
(メルボルン大学)
(慶應義塾大学)
SS-4 大会長企画シンポジウム
9月12日(金)13:35~15:35
第1会場(2F 大ホール)
生後ニューロン新生の観察と操作 ― ライブイメージングと光操作が示す脳の可塑性
Postnatal Neurogenesis – Live Imaging and Optical Manipulation of Brain Plasticity

オーガナイザー
澤本 和延
(名古屋市立大学)
セッション詳細
出生後のニューロン新生は、脳の可塑性や機能回復において重要な役割を果たします。本シンポジウムでは、最先端の技術を用いた研究により、ニューロン新生の動態とその制御メカニズムについて、新たな発見をもたらした最新の成果 を紹介します。 in vivoイメージングや光操作技術を駆使し、ニューロンの誕生、移動、回路統合のプロセスを可視化し、その調節機構に迫ります。 ニューロンはどのように生まれ、ネットワークを形成するのか。その鍵は何か。 本シンポジウムでは、リアルタイム解析によって得られた、これまでの常識を覆す発見や、ニューロン新生の未知の性質について議論します。 最前線の研究者とともに、その未来を探りましょう。ぜひご参加ください!
共催:日本学術振興会拠点形成事業「国際ニューロン新生研究拠点 (NeuRIC)」
演者:
Armen Saghatelyan
Francis Szele
山田 真弓
荻野 崇
Zhejing Zhang
(オタワ大学)
(オックスフォード大学)
(京都大学)
(名古屋市立大学)
(京都大学)
SS-5 日本再生医療学会-日本神経化学会ジョイントシンポジウム
9月13日(土)13:30~15:30
第1会場(2F 大ホール)
脳と再生医療が出会う場所—神経化学、次のステージへ
Where Brain Meets Regeneration: Neurochemistry's Next Frontier

オーガナイザー
岡野 栄之
(慶應義塾大学)

オーガナイザー
澤本 和延
(名古屋市立大学)
セッション詳細
本シンポジウムでは、日本再生医療学会をパートナーに迎え、最先端の研究成果を共有し、活発な議論を交わします。再生医療は、細胞・遺伝子を活用し、損傷した組織・臓器の機能回復を目指す次世代医療であり、中枢神経系の再生も現実味を帯びつつあります。日本神経化学会は、精神・神経疾患の分子メカニズム解明と治療法開発を推進し、アプローチは異なるものの、「疾患の克服」という目標において、日本再生医療学会と深く共鳴する部分があります。本シンポジウムでは、両学会の知見を融合し、神経科学と再生医療の未来を切り拓く新たな治療戦略を探ります。分野を超えたコラボレーションが生む革新をともに議論し、次世代の医療を創造しましょう!
演者:
高橋 淳
戸田 正博
松田 泰斗
村松 里衣子
(京都大学)
(慶應義塾大学)
(奈良先端科学技術大学院大学)
(国立精神・神経医療研究センター)
公募シンポジウム
OS-1
9月11日(木)9:20~11:20
第2会場(5F 小ホール1)
New Developments in Research on Neurodevelopmental and Neurodegenerative Diseases
神経発達疾患・神経変性疾患研究の新展開

オーガナイザー
吉川 貴子
(東北大学)

オーガナイザー
星野 幹雄
(国立精神・神経医療研究センター)
セッション詳細
神経発達疾患や神経変性疾患を含む神経疾患の罹患数は年々増加の一途を辿り、深刻な社会問題となっています。本シンポジウムでは、これらの疾患の原因解明の足がかりとして、神経の発達・機能・病理から見た神経疾患を引き起こす新たな病態機構に着目します。脳発生の異常による神経発達疾患や、病理学的観点から見た分子機能の異常による神経変性疾患について最新の知見をご紹介いたします。これらの最先端の研究成果をもとに、神経発達・変性疾患の診断や治療法の開発への展開について議論します。
演者:
中島 欽一
山田 薫
吉川 貴子
永井 義隆
香川 慶輝
星野 幹雄
(九州大学)
(東京大学)
(東北大学)
(近畿大学)
(メルボルン大学)
(国立精神・神経医療研究センター)
OS-2
9月11日(木)9:20~11:20
第3会場(5F 小ホール2)
Functional Control of Neural Regeneration: From Stem Cell Quiescence to Memory Formation
神経再生機能制御:幹細胞休眠から記憶形成へ

オーガナイザー
坂口 昌徳
(筑波大学)
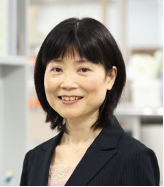
オーガナイザー
金子 奈穂子
(同志社大学)
セッション詳細
本シンポジウムでは、神経再生と脳機能の関係を、幹細胞の休眠から新生ニューロンの定着、記憶形成まで包括的に探ります。神経幹細胞の休眠維持(小林)、損傷脳における新生ニューロンの分化・定着機構(金子)、記憶形成過程への新生ニューロンの関与(今吉)、睡眠中の記憶固定化に果たす役割(坂口)を通して、細胞レベルの知見を行動や認知機能へとつなぎます。学生や分野外の方にも脳再生研究の最前線を分かりやすくお伝えします。
演者:
小林 妙子
金子 奈穂子
今吉 格
坂口 昌徳
(東京大学)
(同志社大学)
(京都大学)
(筑波大学)
OS-3
9月11日(木)16:15~18:15
第2会場(5F 小ホール1)
New Insights into Neuronal Injury, Neurodegenerative Disease, and Their Relevance
神経損傷と神経変性疾患:そこに隠された関連性に迫る

オーガナイザー
小西 博之
(山口大学)

オーガナイザー
桐生 寿美子
(名古屋大学)
セッション詳細
神経損傷と神経変性疾患に共通するメカニズムは多いと考えられます。本シンポジウムでは、神経損傷、神経変性、さらにそれらを結ぶ最新の研究成果を紹介します。脳を包む硬膜など新たな視点、3次元電顕など新たな技術、特殊な遺伝子改変マウスやマウスモデルなど新たなツール、病態原因分子の新たな機能同定などから、先進的な話題を提供します。幅広いアプローチを通じて、神経損傷と神経変性疾患の共通メカニズムから病態の統合的な理解を目指します。
演者:
小西 博之
松本 真実
松田 憲之
木村 妙子
桐生 寿美子
(山口大学)
(名古屋市立大学)
(東京科学大学)
(東京大学)
(名古屋大学)
OS-4
9月11日(木)16:15~18:15
第3会場(5F 小ホール2)
Understanding and Manipulation of Adaptive Neural Circuit Formation and Reorganization
適応脳機能を担う神経回路構築・変遷メカニズムの理解と操作

オーガナイザー
大野 伸彦
(自治医科大学)
セッション詳細
動物が体内や外界の変化に適応して行動を変化させるためには、神経回路の形成とその変遷が重要な役割を果たしています。近年、オミックス技術や、人工分子デザインの急速な進歩により、神経回路の形成や再編のメカニズムを詳細に解析することが可能になり、さらに異なるアプローチを用いてそのような神経回路を操作する技術も発展してきています。本シンポジウムでは、こうした神経回路研究の最先端の研究成果、その中で使われている最新技術や方法論、その有用性を共有し、議論したいと思います。
共催:日本学術振興会学術変革領域A 「適応回路センサス」
演者:
佐々木 拓哉
伊藤 有紀
武内 恒成
下郡 智美
(東北大学)
(九州大学)
(愛知医科大学)
(理化学研究所)
OS-5
9月12日(金)9:20~11:20
第2会場(5F 小ホール1)
Cutting-edge Technologies Unveiling Diverse Characteristics of Brain Macrophages During Development
先端技術が解き明かす発達期の脳内マクロファージの多様な特性と機能
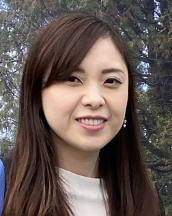
オーガナイザー
服部 祐季
(名古屋大学)

オーガナイザー
増田 隆博
(九州大学)
セッション詳細
近年の一細胞解像度の解析技術の発展により、中枢神経系の免疫細胞であるミクログリアの多様な特性と機能が明らかになりつつあります。一方、脳にはミクログリアに加えて脳境界マクロファージが存在し、それぞれの免疫細胞が脳の発生、成熟、老化、さらには疾患に至るまで重要な役割を担っていることが示唆されています。本シンポジウムでは、最新の一細胞レベルの遺伝子・分子発現解析、培養モデル、生体イメージング等の技術的ノウハウを共有しながら、発達過程における脳内免疫細胞の時空間的特性、多様性な性質を制御する分子機構、および、生理条件・病態下における機能に迫る先端研究を紹介します。
演者:
服部 祐季
山本 将大
鶴田 文憲
小山 隆太
(名古屋大学)
(九州大学)
(筑波大学)
(国立精神・神経医療研究センター)
OS-6
9月12日(金)9:20~11:20
第3会場(5F 小ホール2)
Dynamics of Cell Structural Morphology in Neural Function
神経機能における細胞構造形態ダイナミクスの新展開

オーガナイザー
岸 雄介
(東京大学)

オーガナイザー
澤田 雅人
(名古屋市立大学)
セッション詳細
発生、加齢、病態など、神経機能が大きく変化する過程では、細胞がもつ構造物の形態もダイナミックに変化します。ニューロンの軸索・樹状突起やスパインの構造変化がよく研究されてきていますが、近年では神経機能の生理や病態において様々な細胞構造の形態変化の重要性がわかってきました。本シンポジウムでは、神経系細胞における細胞構造のユニークな形態変化を捉え、その制御や意義に迫る研究者のプロジェクトをご紹介します。さらに、神経機能のダイナミクスの基盤となる多様な分子・構造基盤の将来的な研究展開を議論します。
演者:
高岸 麻紀
澤田 雅人
岸 雄介
前田 ちひろ
牧 功一郎
(名古屋市立大学)
(名古屋市立大学)
(東京大学)
(筑波大学)
(京都大学)
OS-7
9月12日(金)13:35~15:35
第2会場(5F 小ホール1)
Glial Cell Diversity in CNS Disorders: Exploring Subpopulation-specific Mechanisms and Treatments
グリアの多様性が拓く中枢神経疾患治療の未来:亜集団特異的アプローチの追究
オーガナイザー
繁冨 英治
(山梨大学)
セッション詳細
中枢神経疾患において、病態に応じてグリア細胞は多様なフェノタイプへと変化し、その多様性が病態メカニズムを解明する上で重要な鍵を握ることが、最新の研究で示されてきています。本シンポジウムでは、この分野を先導する演者が、神経変性疾患、疼痛、神経炎症といった疾患におけるグリア細胞の多様性を決める分子メカニズムや、その多様性に着眼した新しい治療法開発に向けた最新の成果を紹介します。このシンポジウムを通して、グリア細胞の多様性が中枢神経疾患の病態メカニズムにどのように関わっているのかを、分子レベルで深く理解することを目指します。
演者:
遠藤 史人
小林 亜希子
高露 雄太
繁冨 英治
(名古屋大学)
(京都大学)
(九州大学)
(山梨大学)
OS-8
9月12日(金)13:35~15:35
第3会場(5F 小ホール2)
Frontiers of Research on the Pathogenesis of Mental Disorders Revealed by Molecular Mechanisms
分子メカニズムから解き明かす精神疾患病態研究の最前線

オーガナイザー
永井 拓
(藤田医科大学)
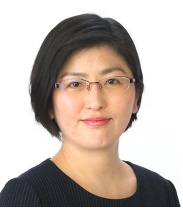
オーガナイザー
竹本 さやか
(名古屋大学)
セッション詳細
精神疾患は、当事者のみならず社会的にも多くの人々に影響を与えることから、その治療法の開発は急務です。気分障害や依存症など環境要因と遺伝要因が影響するものから、レット症候群やティモシー症候群といった単一遺伝性疾患で発症する症候性神経発達症まで原因は多岐にわたり、その病態についてはよく分かっていません。したがって現代社会において精神疾患の克服は特に重要な課題であり、これらの問題を分子メカニズムから理解することは、新しい治療法の開発に重要な知見をもたらします。本シンポジウムでは、分子メカニズムから解き明かす精神疾患病態研究の最前線と題して、精神疾患の病態研究に関する最新の成果を紹介します。このシンポジウムを通じて、研究者間の連携を強化し、新しい知見を共有することで、精神疾患の治療法開発に向けた新たな道を切り開くことを目指します。また、学生さんが理解できるように最新の研究成果を分かりやすく紹介するので、皆さん是非参加してください。
演者:
永井 拓
内田 周作
石田 綾
竹本 さやか
久保 健一郎
(藤田医科大学)
(名古屋市立大学)
(理化学研究所)
(名古屋大学)
(東京慈恵会医科大学)
OS-9
9月13日(土)9:20~11:20
第1会場(2F 大ホール)
Molecular, Cellular, and Circuit Mechanisms of Fear Memory Regulation and the Related-disease
恐怖記憶とその関連疾患の細胞・分子・回路機構

オーガナイザー
喜田 聡
(東京大学)
セッション詳細
恐怖体験の記憶、すなわち、恐怖記憶は記憶研究領域で最も研究されている記憶であり、この恐怖記憶制御の破綻が心的外傷後障害(PTSD)の原因となると考えられています。そこで、現在、恐怖記憶制御プロセスを標的としたPTSDの治療法開発も試みられています。本シンポジウムでは国内外より恐怖記憶制御とPTSDの先駆的な解明を試みている研究者が集い、国際的に最先端の研究成果を紹介します。海馬と扁桃体、脳内炎症、グリア細胞、PTSDのメカニズムと治療方法などの多彩な視点から恐怖記憶を統合的に理解する機会を提供します。
演者:
藤川 理沙子
和氣 弘明
喜田 聡
Jelena Radulovic
Andrew Holmes
Paul Frankland
(福岡大学)
(名古屋大学)
(東京大学)
(Albert Einstein College of Medicine)
(NIAAA)
(Hospital for Sick Children)
OS-10
9月13日(土)9:20~11:20
第2会場(5F 小ホール1)
Molecular Assembly: Implications for Pathophysiology and Drug Development
分子アセンブリーから解き明かす生命現象・疾患病態そして治療薬開発

オーガナイザー
池中 建介
(大阪大学)

オーガナイザー
味岡 逸樹
(東京科学大学)
セッション詳細
分子アセンブリが生み出す生命現象や疾患病態の理解について興味がある方はいますか?異分野の専門家が集まってビッグバンが生まれる瞬間に立ち会いたいと思いませんか?分子アセンブリは、神経変性疾患に関わるアミロイド線維や微小管形成など様々な生命現象や疾患の発症に関わっています。また、人工的な分子アセンブリー技術の発展で、創薬への応用なども試みられています。それぞれの分野で独自の発展を遂げてきましたが、今回各分野の第一人者が一堂に会して、分子アセンブリーをとことん味わうシンポジウムを開催することになりました!演者自身が、ここで起こる新しい化学反応にワクワクして参加します。ぜひご参加くださると幸いです。
演者:
池中 建介
原 央子
Saikat Chowdhury
齋尾 智英
(大阪大学)
(地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所)
(CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology)
(徳島大学)
OS-11
9月13日(土)9:20~11:20
第3会場(5F 小ホール2)
Immune-mediated Control Mechanisms in the Central Nervous System
免疫が司る脳神経系の制御機構
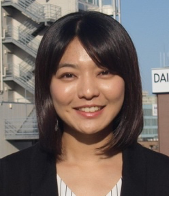
オーガナイザー
伊藤 美菜子
(九州大学)
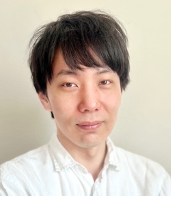
オーガナイザー
田辺 章悟
(国立精神・神経医療研究センター)
セッション詳細
本シンポジウムでは、神経系と免疫系の相互連関システムに焦点を当て、動物モデル、臨床検体、ヒトモデル研究を用いた多角的視点からヒトの脳神経疾患の克服を目指した議論を深めます。新進気鋭の若手研究者による感覚伝達、脳発達障害、精神疾患に関する最先端の研究知見を交えて疾患の治療・予防に向けた未来のアプローチを探ります。神経科学、免疫学、精神医学など幅広い領域の異分野融合の視点から脳神経疾患の病態理解を深める機会となります。本シンポジウムを通じて、神経免疫学の最新知見を共有し、脳神経疾患の新たな治療法開発に向けた学術的基盤の構築を目指します。
演者:
田中 達英
伊藤 美菜子
田辺 章悟
塩飽 裕紀
有岡 祐子
(奈良県立医科大学)
(九州大学)
(国立精神・神経医療研究センター)
(東京科学大学)
(名古屋大学)
OS-12
9月13日(土)13:30~15:30
第2会場(5F 小ホール1)
Revealing the Mechanisms Underlying the Regulation of Neuronal Functions by Myelin Sheaths
髄鞘による神経機能制御メカニズムの解明

オーガナイザー
長内 康幸
(自治医科大学)
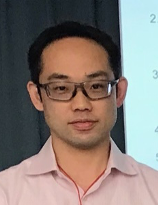
オーガナイザー
石野 雄吾
(近畿大学)
セッション詳細
私たちの脳や脊髄では「髄鞘」という膜で神経軸索を包むことで、情報を素早く伝えています。近年の研究により、髄鞘の異常が認知症の原因になることや、運動学習の成立に髄鞘形成が必須であることが分かってきました。最新の顕微鏡技術や遺伝子解析により、髄鞘を作る細胞(オリゴデンドロサイト)の働きが解明されつつありますが、脳の高度な機能と髄鞘の関係にはまだ多くの謎が残っています。本シンポジウムでは、次世代の髄鞘研究を牽引する若手研究者が最新の知見と今後の展望を議論します。髄鞘研究に興味のある方や、グリア細胞による神経機能制御メカニズムに興味のある方は、ぜひご参加ください。本シンポジウムは国際的な視点に配慮し英語で行われます。
演者:
杉尾 翔太
矢野 佳芳
Lili Quan
宮崎 晴子
長内 康幸
(名古屋大学)
(東京慈恵会医科大学)
(国立精神・神経医療研究センター)
(岡山大学)
(自治医科大学)
OS-13
9月13日(土)13:30~15:30
第3会場(5F 小ホール2)
Diversity in Alzheimer's Research
多様性で挑むアルツハイマー病研究

オーガナイザー
小野 賢二郎
(金沢大学)

オーガナイザー
東田 千尋
(富山大学)
セッション詳細
アルツハイマー病(Alzheimer’s disease: AD)は長らく症状改善薬が中心で、ADの病理変化自体を食い止める根治的治療薬の開発が急務でした。そのような中で昨年末よりレカネマブ、そして昨冬よりドナネマブという抗アミロイド抗体療法が臨床現場に出てきてAD診療のパラダイムシフトが起き、基礎、臨床双方の面で研究の進捗が注目されています。本シンポジウムではAD研究の現状と展望について、実験モデル、漢方薬、実臨床、疫学コホート、脳画像といった多方面から講演をしていただき、聴講してくださる研究者、医師の方々とともに日本のAD研究の底上げをはかっていきたいと思います。
演者:
安藤 香奈絵
東田 千尋
小野 賢二郎
木村 篤史
篠原 もえ子
(東京都立大学)
(富山大学)
(金沢大学)
(新潟大学)
(金沢大学)