プログラム
大会長講演(オープニングセレモニー) /Presidential Lecture (Opening Ceremony)
7月25日(金)14:45~15:00
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:錦織 宏(名古屋大学大学院 医学教育研究室)
PL
秋田の医療と医学教育 ―未来を託せる医師を創る―
羽渕 友則
(秋田大学医学部長・大学院医学系研究科長、秋田大学大学院 腎泌尿器科学講座)

実行委員長講演(オープニングセレモニー)/Executive Committee Chairman Lecture (Opening Ceremony)
7月25日(金)15:00~15:10
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:錦織 宏(名古屋大学大学院 医学教育研究室)
ECCL
次世代の医学・医療を拓くデジタル教育の新たなステージへ -思慮深く、思いやりに満ちた理想的チームビルディングを目指して:秋田宣言 2025-
長谷川 仁志
(秋田大学大学院 医学教育学講座、総合臨床教育研修センター)

理事長講演(オープニングセレモニー) /JSME Presidential Lecture (Opening Ceremony)
7月25日(金)15:10~15:22
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:小西 靖彦(順天堂大学 医学教育研究室)
JPL
日本医学教育学会の現在と近未来構想
錦織 宏
(名古屋大学大学院 医学教育研究室)

Asia-Pacific Medical Education Conference (APMEC) 2027日本開催について
Dujeepa D. Samarasekera理事長からのビデオメッセージ

招請講演1 /Invited Lecture1
7月25日(金)9:00~9:45
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:羽渕 友則(秋田大学医学部長、大学院医学系研究科長)
IL-1
複雑で不確実な医療システムにおいて成功するためのチームワーク教育
中島 和江
(大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部、大阪大学医学部附属病院長補佐、大阪大学総長補佐)

招請講演2 /Invited Lecture2
7月25日(金)9:45~10:30
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:長谷川 仁志(秋田大学大学院 医学教育学講座)
IL-2
正しい医療と医学教育は正しい「ことば」から ―ここが変だよ!医師の業界用語―
河野 博隆
(帝京大学医学部長、帝京大学医学部 整形外科学講座)

招請講演3 AMEE-JSME連携企画(オープニングセレモニー)/Invited Lecture3 AMEE-JSME Collaborative Session (Opening Ceremony)
7月25日(金)オープニングセレモニー内15:25~15:50
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:錦織 宏(名古屋大学大学院 総合医学教育センター)
IL-3
Transforming Medical Education: Five Global Trends that could shape the Next Generation of Health Professionals
Subha Ramani, MBBS, MPH, MMEd, PhD, FAMEE
(Past President, AMEE; Associate Professor of Medicine/Harvard Medical School, Assistant Director/Global Perspectives and Community/ Brigham Education Institute, Director of Residency Assessment and Scholars in Medical Education Pathway, Internal Medicine Residency Program, Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA)

オンデマンド講演/On-demand Lecture
座 長:野村 恭子(秋田大学大学院 衛生学・公衆衛生学講座)
OL-1
Closing the educational loop: the development of a model to ensure transfer of learning to clinical practice and patient benefit.
Jan Illing, PhD, MPhil, BSc (hons), CQSW, HonFAcadMed
(Professor of Health Professions Education and Director of the Health Professions Education Centre at RCSI University of Medicine and Health Sciences, Dublin, Ireland)

大会長特別企画シンポジウム/President Special Symposium
日本の医療状況をどう教えるか ―これだけは教えたい―
How to Tell the Realities of the Today's Japanese Healthcare Status?
― The Message We Should Absolutely Give to All Students ―
7月26日(土)9:00~12:20
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:大坪 徹也(秋田大学大学院医学系研究科医療情報学講座)
PSS-1
医療を支えるシステムやコストの存在を、できるだけリアルに伝えることの意義 -社会学博士課程、厚生労働省医系技官の経験をもとに-
加藤 源太
(京都大学医学部附属 病院病床運営管理部)

座 長:武中 篤(鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野)
PSS-2
攻める医療~デジタル時代の社会医学教育
高橋 昌
(新潟大学大学院医歯学総合研究科、地域医療確保・地域医療課題解決支援講座、災害医学・医療人育成分野)
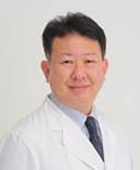
座 長:髙橋 悟(日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野)
PSS-3
人口動態の変化と日本の医療システムへの影響
村上 正泰
(山形大学大学院医学系研究科 医療政策学講座)

座 長:土谷 順彦(山形大学医学部腎泌尿器外科学講座)
PSS-4
保険指導で遭遇する諸問題;医学教育は何ができるか?
佐藤 洋一
(岩手医科大学名誉教授、東北厚生局指導医療官)

日韓台合同シンポジウム /Japan, Korea and Taiwan Joint Symposium
医療者教育のデジタル化 ―東アジアの現状を共有する―
7月25日(金)16:30~17:30
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:矢野(五味)晴美(国際医療福祉大学 国際医療者教育学・感染症学)
及川 沙耶佳 (秋田大学大学院 先進デジタル医学・医療教育学講座)
Special commentator: Ming-Jung Ho, MD, DPhil
(Senior Director, Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER)
Professor, Department of Family Medicine, Georgetown University School of Medicine)
JKT-1
The Flow of Information Science in Korean Medical Education
Seok Hoon Kang, MD, PhD
(Associate Professor, Department of Medical Education, Kangwon National University College of Medicine, Department of Family Medicine, Kangwon National University Hospital)

JKT-2
AI Applications in Healthcare and Medical Education: Challenges and Concerns
Jen-Hung Yang, MD, PhD
(Chair Professor, Director of Medical Education Research Center, Chung Shan Medical University (CSMU), Taiwan, Fellow of the Association for Medical Education in Europe (AMEE) (2024~) )

アジア太平洋医学教育者交流シンポジウム/Exchange Symposium of Health Professions Educators in Asia-Pacific regions
デジタルを用いたシミュレーション教育の展望 ―世界の潮流を知る―
7月25日(金)10:50~12:20
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
座 長:大内 元(琉球大学病院 救命救急センター)
武田 聡(東京慈恵会医科大学救急災害医学講座)
PA-1
Cultural Gap Between Learners In Simulation Based Education, An Experience From Taylor's: Tips in UG medical education
Narendiran Krishnasamy, MBBS, MMedEdu, MBA(Hospital Management), Diploma in Diabetology
(UN Consultant for Simulation Training Centers, Director of Medical Education, Clinical Skills coordinator in the School of Medicine, Taylor’s University)

PA-2
Interprofessional Simulation for healthcare professionals training to enhance patient outcomes
Ashokka Balakrishnan, MBBS, MD, DNB, FANZA, EDRA, MHPE
(Senior Consultant Anaesthesiologist and Simulation Program Director (anaesthesia division) at National University Hospital Singapore)

PA-3
The Application of AI in Simulation-Based Education
Che-Wei Lin, M.D, PhD, FSSH
(Attending physician at Taipei Medical University Shuang
Ho Hospital, Director of the Clinical Skills Center, CEO of the Center for Education in Medical Simulation at Taipei Medical University, President of the Taiwan Society of Simulation in Acute and Critical Care Medicine. )
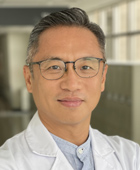
PA-4
Navigating the Operating Theatre: A Digital Approach to Training Novice Learners. The IMU University experience
Thiruselvi Subramaniam, MBBS, MMed(anes), Pg Cert Med Edu
(Associate Prof and Consultant Anaesthesiologist at IMU University, Malaysia)

PA-5
Development a Nationwide Simulation-based Education Program: The Healthcare Simulation Literacy (HSL) Program
Ismail Mohd Saiboon, MBBS, Dr Orth & Trauma, Emerg Med(NSR), CHSE, FSSH
(Senior consultant of Emergency Department, HCTM, Faculty of Medicine University Kebangsaan Malaysia (UKM), Founder of the Malaysian College of Emergency Physicians, and the Malaysian Society for Simulation in Healthcare (MaSSH))

インターナショナルワークショップ1/International Workshop 1 (シミュレーション教育のデブリーフィングスキルを磨く! ―ハワイ大学特別企画―)
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月24日(木)17:00~18:30
会場:にぎわい交流館AU 多目的ホール
WSでは、最初にデブリーフィングの基本やいくつかのフレームワークについて簡潔に復習する。その後小グループに分かれ、短いシナリオ実演のあと、模擬学習者に対して実際にデブリーフィングをする。実践の後にシミュレーション教育のエキスパートからメタデブリーフィングを受け、実施されたデブリーフィングについて省察し、具体的な改善方法などを探っていく。担当ファシリテーターはハワイ大学医学部SimTikiシミュレーションセンターの指導医、およびSimTikiで指導者としてのトレーニングを積んだシミュレーションエキスパートである。デブリーフィング実践とメタデブリーフィング、およびディスカッションの繰り返しを行い、最後に学んだことを全体で共有する。時間の都合上デブリーフィングを実践できる人数には限りがあるが、デブリーフィング実践者以外の参加者も共にデブリーフィング ― メタデブリーフィングの過程を観察し、ディスカッションに加わることで相互学習を促進する。
デブリーフィングスキルはシミュレーション教育以外の教育現場でも役に立つスキルであり、また日々の臨床教育や更新指導にも役立つものである。なお本セッションは、Dr. AAまたはDr. BBがデブリーファーとなるグループでは英語での実施となるが、適宜日本人ファシリテータによる通訳を行う。
IWS-1
デブリーフィングスキル向上ワークショップ ―メタデブリーフィングを受けてみよう!/Enhancing Debriefing Skills: An Advanced Workshop for Simulation Educators with Meta-Debriefing
Benjamin W Berg, MD, CHSE
(Professor of Medicine (Critical Care) and Founding Director of the Society of Simulation in Healthcare accredited SimTiki Simulation Center, John A Burns School of Medicine, University of Hawaii)

Jannet Lee-Jayaram, MD, CHSE, FAAP
(Associate Professor, the Associate Director of the SimTiki Simulation Center, John A Burns School of Medicine, University of Hawaii, and the Director of Medical Student Simulation Education at the University of Hawaii, John A Burns School of Medicine)

日本人ファシリテーター・通訳
- 衛藤 由佳(東京慈恵会医科大学救急災害医学講座/ハワイ大学SimTikiシミュレーションセンター)
- 佐藤 絵梨(ねりま健育会病院/ハワイ大学SimTikiシミュレーションセンター)
- 大内 元(琉球大学病院 救命救急センター)
- 万代 康弘(東京慈恵会医科大学救急災害医学講座)
インターナショナルワークショップ2/International Workshop 2 (シミュレーション教育をアクティブラーニングにする! ―ハワイ大学特別企画―)
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)9:00~10:30
会場:にぎわい交流館AU 多目的ホール
Use active learning techniques during simulation-based healthcare education
Objectives
- Recognize components of orientation that prepare learners to actively participate in simulation-based training
- Describe facilitation techniques to guide learners through an active simulation
- Identify elements of structured and supported debriefing after an active simulation
- Apply simulation education techniques to other active learning in clinical settings
IWS-2
Active Learning Techniques for Simulation and Clinical teaching
Benjamin W Berg, MD, CHSE
(Professor of Medicine (Critical Care) and Founding Director of the Society of Simulation in Healthcare accredited SimTiki Simulation Center, John A Burns School of Medicine, University of Hawaii)

Jannet Lee-Jayaram, MD, CHSE, FAAP
(Associate Professor, the Associate Director of the SimTiki Simulation Center, John A Burns School of Medicine, University of Hawaii, and the Director of Medical Student Simulation Education at the University of Hawaii, John A Burns School of Medicine)

日本人ファシリテーター・通訳
- 衛藤 由佳(東京慈恵会医科大学救急災害医学講座/ハワイ大学SimTikiシミュレーションセンター)
- 佐藤 絵梨(ねりま健育会病院/ハワイ大学SimTikiシミュレーションセンター)
- 大内 元(琉球大学病院 救命救急センター)
- 万代 康弘(東京慈恵会医科大学救急災害医学講座)
- 武田 聡(東京慈恵会医科大学救急災害医学講座)
インターナショナルワークショップ3/International Workshop 3
定員あり
事前登録
当日参加OK
セッション1 7月26日(土)15:50~17:20
セッション2 7月27日(日)8:45~10:15
会場:にぎわい交流館AU 多目的ホール
Clinical teaching occurs in a variety of settings- inpatient, outpatient, conference rooms, simulation or clinical skills centres, patient homes or long-term care facilities- but always focussed on patient care and outcomes. Clinical teachers need to constantly balance clinical care, supervision of trainees and teaching. Teaching in these settings is complex and requires flexibility on the part of the teacher in adapting to evolving patient needs, context and learner needs. In this workshop, we will focus on the learning triad, consisting of the learner/s, teacher and patient. Specifically, we will emphasise the importance of establishing a safe learning environment, effective teaching when time is limited and/or learners are at different levels of training, diagnosing clinical performance of learners through direct observation and engaging in feedback conversations that target learner growth and practice improvement.
Learning objectives
Workshop part 1 (90 minutes):
- Apply an educational framework to guide effective clinical teaching practices
- Adopt a flexible approach in selecting clinical teaching strategies (based on context and setting, learner levels, goals and needs, content to be taught)
- Gain comfort and confidence in teaching when time is limited
- Apply effective bedside (in the presence of patients) teaching strategies
- Reflect on the importance of direct observation of learners in the clinical setting
- Practice direct observation and narrative description of learner performance
- Engage in feedback conversations that impact learner behaviour and practice
IWS-3
Effective teaching in the clinical environment: Tips for clinical teachers
Subha Ramani, MBBS, MPH, MMEd, PhD, FAMEE
(Past President, AMEE; Associate Professor of Medicine/Harvard Medical School, Assistant Director/Global Perspectives and Community/ Brigham Education Institute, Director of Residency Assessment and Scholars in Medical Education Pathway, Internal Medicine Residency Program, Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA)

James Kwan, MBBS BSc (Hons) MMed (ClinEpi) MHPE MRCSEd FACEM FRCEM FAMS
(Senior Consultant, Department of Emergency Medicine Tan Tock Seng Hospital, Singapore. Adjunct Associate Professor, Emergency Medicine, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore)

日本人ファシリテーター・通訳
- 橋本 忠幸(Brigham and Women's Hospital / 大阪医科薬科大学)
- 林 幹雄(関西医科大学教育センター)
JSME57 特別企画1/JSME57 Special Event1
7月25日(金)10:50~12:20
会場:あきた芸術劇場ミルハス 中ホール
ポストコロナ時代の地域医療教育:持続可能な医療人材の養成から共創へ
Community based medical education in the post-COVID era: From training sustainable medical personnel to co-creation
座 長:鬼島 宏(弘前大学・大学院医学研究科)
永田 康浩(長崎大学大学院 地域医療学分野)
JSE-1-1
ポストコロナ時代の地域医療教育:持続可能な人材育成と大学間連携のあり方を考える
永田 康浩(長崎大学大学院 地域医療学分野)
JSE-1-2
千葉県における地域志向型医療人材養成プログラムの現状と今後の展開
伊藤 彰一(千葉大学大学院 医学教育学、地域医療教育学)
JSE-1-3
ポストコロナ時代の地域医療教育の実践と大学間連携の推進
前野 哲博(筑波大学 地域医療教育学)
JSE-1-4
医療人類学を取り入れた地域医療教育の可能性:濃尾+Aにおける実践を通して
宮地 純一郎(名古屋大学大学院 総合医学教育センター)
JSE-1-5
多職種連携とDXによる北東北の地域医療教育の実践と展開
鬼島 宏(弘前大学・大学院医学研究科)
JSME57 特別企画2/JSME57 Special Event2
7月25日(金)16:30~18:00
会場:あきた芸術劇場ミルハス 中ホール
メイヨークリニックと国内例から考える:日々遭遇する多様な患者・困難な患者への思慮深い対応実践教育
Learning from Mayo Clinic and Domestic Cases: Educational Practices for Thoughtful Care of Diverse and Difficult Patients
座 長:芦田 ルリ(聖路加国際大学)
長谷川 仁志(秋田大学)
JSE-2-1
メイヨークリニックにおける医学教育:思慮深く思いやりのある医療提供者の育成
David Rosenman, MD, MBA, MS, MA
(Assistant Professor of Medicine
Mayo Clinic College of Medicine and Science
Rochester, Minnesota, USA)

JSE-2-2
指導者が各種の対応困難な模擬患者になる:教室内を日々の臨床現場にして思慮深い診療の経験値を上げる
長谷川 仁志(秋田大学)
JSE-2-3
社会文化的背景の異なる患者を総合的に診る力を育成する実践教育:ネイティブ英語医療面接と海外での実践例
芦田 ルリ(聖路加国際大学)
JSE-2-4
英語OSCE導入の試み
岡崎 史子(新潟大学)
JSE-2-5
日本の看護学生の英語コミュニケーション能力と文化的対応能力を育成する外国人模擬患者演習
Jeffrey Huffman(聖路加国際大学)
JSME57 特別企画3/JSME57 Special Event3
7月26日(土)14:00~15:30
会場:あきた芸術劇場ミルハス 中ホール
次世代の医学・医療を支える外科医の教育戦略
Strategies for the development of the next generations as surgeons.
ファシリテーター:
磯部 真倫(岐阜大学産婦人科)
高見 秀樹(名古屋大学消化器・腫瘍外科)
JSE-3-1
デジタル時代の外科教育
肥田 侯矢(京都大学消化管外科)
JSE-3-2
「教育」を専門とする産婦人科教授が医学生に魅力的な臨床実習を構築する
磯部 真倫(岐阜大学産婦人科)
JSE-3-3
泌尿器科の外科教育の展望
木村 友和(名古屋大学大学院 泌尿器科学)
JSE-3-4
激減する消化器外科医が行う外科教育
高見 秀樹(名古屋大学消化器・腫瘍外科)
JSE-3-5
一般病院で行う外科教育
大下 彰彦(JA尾道総合病院外科)
JSME57 特別企画4/JSME57 Special Event4
7月26日(土)15:50~17:20
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
次世代に向けたデジタル教育の新たなステージを見据えて
Envisioning a New Stage of Digital Medical Education for the Next Generation
座 長:長谷川 仁志(秋田大学大学院 医学教育学講座)
山本 憲(順天堂大学 健康データサイエンス学部)
JSE-4-1
一人称視点の映像解析を用いた新たなリーダーシップの質評価
野沢 永貴(東京大学医学部附属病院小児科)
JSE-4-2
生成AIを活用した試験問題作成支援アプリケーションの開発と課題
橋本 恵太郎(筑波大学 医学類医学教育センター)
JSE-4-3
質の高い試験問題作成に向けた国家試験問題の出題基準準拠度の定量的評価
津田賀 俊(兵庫医科大学)
JSE-4-4
ラーニングアナリティクスへの活用を目指した講義復習テストと学年成績の分析III
辻野 賢治(東京女子医科大学)
JSE-4-5
デジタルデバイスを活用した手術所見作成および手術動画編集の効率化と教育資材としての応用
八木 史生(社会医療法人青嵐会本荘第一病院 外科)
JSE-4-6
次世代医学教育の可視化と標準化:ステップラダーシステムアプリの展開と活用
小松 宏彰(鳥取大学 産科婦人科学分野)
JSE-4-7
スマートフォンで撮影した動画を利用したAIによるBLS手技評価
川村 勇樹(埼玉医科大学 医学教育センター)
JSE-4-8
分娩と胎児超音波検査の教育におけるVirtual Realityの活用
長田 広樹(鳥取大学医学部産科婦人科学分野)
JSE-4-9
デジタルタキソノミーから学ぶ臨床研修プログラム開発
平出 敦(明治国際医療大学)
JSME57 特別企画5/JSME57 Special Event5
7月27日(日)8:45~12:05
(第1部 8:45~10:15)
(第2部 10:35~12:05)
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
第2回デジタル医学・医療教育ネットワーク推進 全国シンポジウム
医学生とともに考える
医療現場の理想的チームビルディングのための卒前・卒後・生涯教育シンポジウム 2025 AKITA
ー次世代にむけてのデジタル教育ネットワーク構築と組織形成のためにー
The 2nd National Symposium for the Promotion of Digital Medical and Healthcare Education Networks
A Symposium for Building Ideal Healthcare Teams Together with Medical Students
Undergraduate, Postgraduate, and Lifelong Medical Education Symposium
2025 AKITA
— For the Development of Digital Education Networks and Organizational Structures for the Next Generation —
第一部(8:45~10:15)
座 長:長谷川 仁志(秋田大学大学院医学教育学講座)
岡崎史子(新潟大学医学部医学科医学教育センター)
JSE-5-1
オープニングリマークス
デジタル教育の工夫した活用を ―省察と改善を継続する理想的・教育的な各種医療チーム・組織作りのために ―
長谷川 仁志(秋田大学大学院 医学教育学講座)
JSE-5-2
特別講演
メイヨークリニックの臨床・研究・教育におけるAI(人工知能)の活用 -次世代の理想的医療を実現するために-
David J. Rosenman, MD, MBA, MS, MA
(Assistant Professor of Medicine Mayo Clinic College of Medicine and Science Rochester, Minnesota, USA)

JSE-5-3
学生セッション
全医学生と指導者が知っておくべき日本の医学教育における課題と国情に合った理想的方向性
―カリキュラム改革に医学生の参画が必須となっている時代に―
・日本の医学生が知っておくべき医学教育の課題と国情に合った理想像
・すべての医療者が教育者でもあることが求められる時代に向けて、どうあるべきか?
・日本特有の熱心な部活動・課外活動は、これからの医学教育にとって有益か?バランスをどうすべきか?
・長谷川 可季音(国際医療福祉大学医学部医学科5年)
・白築 美結(東京医科大学医学部医学科5年)
・村岡 暁(東京医科大学医学部医学科6年)
・津村 佳生(順天堂大学医学部医学科6年)
・佐藤 孝紀(秋田大学医学部医学科4年)
・渡邉 杏香(秋田大学医学部医学科5年)
・小西 美奈(秋田大学医学部医学科5年)
・吉田 和未(秋田大学医学部医学科5年)
・松浦 佐紀(佐賀大学医学部医学科6年)
・西牟田 はずき(佐賀大学医学部医学科3年)
・日南 凜子(佐賀大学医学部医学科3年)
・沖田 愛珠(国際医療福祉大学医学部医学科5年)
Faculty Advisors:
押味 貴之(国際医療福祉大学)
原田 芳巳(東京医科大学)
西﨑 祐史(順天堂大学)
小田 康友(佐賀大学)
長谷川 仁志(秋田大学)
第二部(10:35~12:05)
座 長:長谷川 仁志(秋田大学大学院 医学教育学講座)
岡崎史子(新潟大学医学部医学科医学教育センター)
JSE-5-4
生成AIで医療ゲームを進化させ、動画生成AIで臨床現場を振り返る—インタラクティブな医療教育の新たな可能性
三原 弘(札幌医科大学 医療人育成センター教育開発研究部門)
JSE-5-5
Deep learning(深い学び)は紙が良い – 生成AIを超える知能は紙で育てる
山田 正明(富山大学 学術研究部 疫学・健康政策学講座)
JSE-5-6
患者支援のためのデジタル教育戦略
山口 育子(認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML(コムル))
JSE-5-7
デジタルトランスフォーメーション(DX)で実現する質の高い医療と豊かなPeople Journey~ DXを活用した協働型医療の実践 ~
小坂 鎮太郎(東京都立広尾病院 病院総合診療科)
JSE-5-8
米国におけるデジタル活用医学・多職種教育の取り組み ~市民を巻き込んだ災害医療連携まで
小林 天美(ハーバード大学医学部、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院)
JSME57 特別企画6/JSME57 Special Event6
7月27日(日)14:00~16:30
会場:あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
市民公開講座(対象:市民の皆様、医療従事者の皆様)
医療の未来はあなた次第!
デジタル情報を活用したこれからの医療のかかり方:2025
ご家族の皆さんでいっしょにデジタル情報を活用して医療チームの一員になりましょう!
Public Lecture for Citizens:
The Future of Healthcare Is in Your Hands!
How to Navigate Healthcare Using Digital Information: 2025 and Beyond
-Let’s work together with your family to use digital information and become part of the healthcare team!–
JSE-6-1
オープニングリマークス
市民の皆様と医師・医療者がチームとなってデジタル情報を活用し次世代の理想的な医療を実現しましょう!
長谷川 仁志(秋田大学大学院 医学教育学講座)
座 長:大田 秀隆(秋田大学高齢者医療先端研究センター)
JSE-6-2
特別講演1
音楽の力- DMV (深層振動)による認知機能低下やフレイル予防の可能性-
野口 五郎

座 長:藤原 慶正(日本医師会常任理事)
JSE-6-3
特別講演2
市民・医療者協働のチーム医療で危機に備えるーC0VID-19対応の経験からー
横倉義武(日本危機管理医学会理事長、日本医師会名誉会長、元世界医師会長)

シンポジウム
座 長:長谷川 仁志(秋田大学大学院 医学教育学講座)
三原 弘(札幌医科大学 医療人育成センター教育開発研究部門)
コメンテーター:
野口五郎 (特別講演1担当)
横倉義武 (特別講演2担当)
JSE-6-4
デジタル情報を活用したこれからの医療のかかり方 患者支援の立場から
山口育子(認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML(コムル))
JSE-6-5
デジタルトランスフォーメーション(DX)でみんなが安心できる医療をつくろう!~ DXを活用した協働型医療の実践 ~
小坂 鎮太郎(東京都立広尾病院 病院総合診療科)
JSE-6-6
デジタル時代の新しい医療のかかり方—AIで受診前医療面接を
三原 弘(札幌医科大学医療人育成センター教育開発研究部門)
JSE-6-7
世界一優しいドクターがあなたの手の中に──生成AIが切り拓く医療の未来
高橋 宏瑞(順天堂大学医学部附属浦安病院 )
JSE-6-8
患者と医療者がデジタルを介して協働して医療の質を向上させる:米国の近況
小林 天美(ハーバード大学医学部、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院)
JSE-6-9
医学生による実践セミナー:
ChatGPT (生成AI) への上手な質問や医療情報の入力ポイント
-健診・予防・想定される疾患・検査・治療からセカンドオピニオンまでー
池原 誠人(秋田大学医学部医学科 3年)
小野 佑一郎(秋田大学医学部医学科 3年)
小林 美月(秋田大学医学部医学科 3年)
関口 実優(秋田大学医学部医学科 3年)
千葉 映雅(秋田大学医学部医学科 3年)
渡邉 雅輝(秋田大学医学部医学科 3年)
シンポジウム1/Symposium 1
7月25日(金)9:00~10:30
会場:第2会場(あきた芸術劇場ミルハス 2F 中ホール)
生成AIの病院や学部での利活用状況について
Report on the utilization status of generative AI in hospitals and faculties
(1)薬学部としての生成AI利用についての公式通知内容の取りまとめでは、薬学部における対応状況を紹介する。(2)医学部としての生成AI利用についての公式通知内容の取りまとめとして、手動および生成AIを利用した整理の結果を紹介する。(3)大学での生成AI導入事例の紹介として、大学教育における生成AIの活用方法を報告する。(4)病院での生成AI導入事例の紹介では、医療現場での生成AIの実践例と課題を共有する。これらの講演後、全体ディスカッションを行い、生成AIの現状と課題、今後の活用方法について参加者全員で意見交換を行う。
対象者は、医療教育関係者、医療従事者、教育機関の管理者、生成AIに関心のある者を想定している。本シンポジウムの目的は、生成AIの教育・医療分野での最新活用事例を共有し、公式通知の比較から各学部の対応状況を理解することである。これにより、生成AI活用における課題と解決策を明確にし、今後の教育・医療現場での生成AI導入の方向性を検討することを目指す。本シンポジウムを通じて、生成AIの持つ可能性と現場での実践的な活用方法について深い理解を促進し、医療教育と医療サービスの質の向上に寄与したいと考えている。
座 長:椎橋 実智男(埼玉医科大学)
小林 直人(愛媛大学)
S-1-1
薬学部における「生成AIの利用に関する通知」の公開状況とMDASH認定に関する調査
村岡 千種(藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科)
S-1-2
我が国の医学部を対象とした生成AIの使用に関する通知・ガイドライン調査報告
山本 憲(順天堂大学健康データサイエンス学部)
S-1-3
医学部での教育における生成AIの活用方法例
淺田 義和(自治医科大学 医学教育センター)
S-1-4
医療現場における生成AIの活用と課題
山岸 秀嗣(獨協医科大学)
シンポジウム2/Symposium 2
7月25日(金)9:00~10:30
会場:第3会場(あきた芸術劇場ミルハス 4F 小ホールA)
EPOC Update:卒前から卒後教育評価の実際
EPOC Update
本シンポジウムでは以下の視点からこれまでのEPOCを用いた卒前卒後のシームレスな教育評価システムのデータ分析及びデータ利活用について最新の情報を共有する。
1)侵襲的医行為を含む基本的臨床手技の習得度の適切な評価法の確立と有効性の検証
臨床手技修得度評価について、医学教育モデル・コア・カリキュラムおよび医師臨床研修指導ガイドライン記載の手技について評価方法を紹介する。
2)ICTを活用したシームレスな臨床教育評価システムの構築
独自評価票の機能改修・機能追加、、評価データダウンロード機能の改修、および、新規帳票ダウンロード機能の開発、指導医・上級医の指導履歴機能のアップデートを紹介する。
3)シームレスな医師養成を促進する評価方法の確立
EPOCを用いた学修トラジェクトリー曲線による分析方法を確立した。PG-EPOCの分析では研修医の成長は6つのグループに分類され、それぞれ評価項目によって異なる特徴が見られた。
4)学修プログラムの特徴による評価の差異
到達目標・評価の到達状況の分析を実施するにあたって、評価票自体の信頼性、妥当性、再現性について検討し、分析結果に関して分析をすすめている。
5)Workplace-based assessment (WBA)としてのEPOCデータの利活用法の確立
trajectory分析をはじめとする各種評価分析方法を開発した。WBAとしてのEPOCデータの利活用については、医師国家試験に関する研究班、診療参加型臨床実習に関する研究班との連携を行っている。
座 長:山脇 正永(東京科学大学)
高橋 誠(北海道大学 大学院医学研究院 医学教育・国際交流推進センター)
S-2-1
EPOCにおける基本的臨床手技の習得度評価
高橋 誠(北海道大学 大学院医学研究院 医学教育・国際交流推進センター)
S-2-2
ICTを活用したシームレスな臨床教育評価システムの構築
木内 貴弘(東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学)
S-2-3
EPOC評価データを用いた学習者のトラジェクトリーの分析
那波 伸敏(東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 公衆衛生学分野)
S-2-4
学修プログラムの特徴による評価の差異
大出 幸子(聖路加国際大学公衆衛生大学院)
S-2-5
Workplace-based assessment (WBA)としてのEPOCデータの利活用
岡田 英理子(東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 臨床医学教育開発学分野)
シンポジウム3/Symposium 3
7月25日(金)9:00~10:30
会場:第4会場(あきた芸術劇場ミルハス B1F 小ホールB)
医療者教育に精神科が最大限の貢献をするために
To maximize the contribution of psychiatry to medical education
新専門医制度において精神科を専攻する者は毎年6%ほどである。残りの94%を含めたすべての医学生が3週間以上の精神科臨床実習を受け、またすべての研修医が4週間以上の精神科研修を受けている。医師養成プロセスにおいて精神科が重要な位置づけであることが容易に認識できるものの、他科とは毛色の異なる面の多い領域において、あらゆる専門分野に進む学習者たちがどのようなことを学ぶべきなのか、あまり明確ではないというのが現場で教育に当たるものの実感である。前回大会で我々はオンデマンドシンポジウム「全ての医師に向けた精神医学教育を考える」を実施した。今回はさらに多くの医学教育者たちとより深いディスカッションができることを願っている。
発表ではまず、日本精神神経学会の中で徐々に高まりを見せている教育への関心について、卒前医学教育・卒後臨床研修委員会をはじめ各種教育関連の取り組みを紹介する。次いで、医学生の臨床実習期間を外部施設の協力を得て2週間から6週間に延長させた取り組み、人気研修病院において比較的小規模でマンパワーの少ない精神科でリエゾン精神医学を中心に研修医を活躍させる工夫、専門性の高い精神科単科病院で研修医教育を行う際に意識するピットフォールなど、多彩な精神医学教育の現場における各演者の具体的な教育実践を報告する。その後、会場の参加者を交えて総合討論を行う。
本シンポジウムが医学教育に携わる人と、精神医療の現場で教育に携わる人との対話を生み、両学会間の連携が促進される機会となることを強く望む。
座 長:藤田 博一(高知大学医学部附属医学教育創造センター)
岡崎 史子(新潟大学医学部)
S-3-1
日本精神神経学会における教育への関心
村井 俊哉(京都大学)
S-3-2
医学部における精神科の多施設臨床実習のための工夫と課題
中瀧 理仁(徳島大学病院 精神科神経科)
S-3-3
精神科リエゾンチームを活用した初期研修医指導-市中総合病院精神科での持続可能な教育システムの構築-
猪狩 圭介(麻生飯塚病院)
S-3-4
精神科単科病院で行う研修の強みとピットフォール
松坂 雄亮(長崎県精神医療センター)
シンポジウム4/Symposium 4
7月25日(金)10:50~12:20
会場:第3会場(あきた芸術劇場ミルハス 4F 小ホールA)
公衆衛生の新たな視点と医学教育モデルコアカリキュラム: 現在と未来への展望
New Perspectives from Public Health and the Model Core Curriculum for Medical Education- Present and Future Perspectives
座 長:中山 健夫(京都大学)
錦織 宏(名古屋大学大学院医学系研究科総合医学教育センター)
S-4-1
医学教育モデル・コア・カリキュラムにおける公衆衛生の位置づけ
松島 加代子(長崎大学病院医療教育開発センター)
S-4-2
社会と医療の架け橋としての公衆衛生:医学教育の新たな展望
春田 淳志(慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター)
S-4-3
公衆衛生医師人材確保を見据えた医学部の卒前教育(講義と実習)に関する調査
野村 恭子(秋田大学医学部衛生学公衆衛生学)
S-4-4
「医学部における健康危機管理教育体制の構築に向けたワークショップ」実施報告
冨尾 淳(国立保健医療科学院)
シンポジウム5/Symposium 5
7月25日(金)10:50~11:50
会場:第4会場(あきた芸術劇場ミルハス B1F 小ホールB)
なぜ医療人文学が必要なのか
Why Medical Humanities are essential
座 長:横山 彰三(宮崎大学)
S-5-1
医療人としての読書・赤ひげの中のSDH、NVC(非暴力コミュニケーション)による共感と自己表現、など
横山 彰三(宮崎大学)
S-5-2
医療人文学における映像教材を用いた対話型授業の実践と考察
南部 みゆき(宮崎大学)
S-5-3
A Medical Humanities Pilot Study: Foreign Patient Narratives & Peer Poetry
ALAN M. SIMPSON(宮崎大学)
S-5-4
Medical Anthropology: Possibilities for the Humanities in Medical Education in Japan
Donald Wood(秋田大学)
シンポジウム6/Symposium 6
7月25日(金)16:30~18:00
会場:第3会場(あきた芸術劇場ミルハス 4F 小ホールA)
素養としての在宅医療・学術としての在宅医療教育
Home Healthcare as a Competency, Home Healthcare Education as an Academic Discipline
座 長:井口 清太郎(新潟大学大学院医歯学総合研究科)
大脇 哲洋(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科)
S-6-1
素養としての在宅医療
大島 伸一(公益財団法人長寿科学振興財団)
S-6-2
人工呼吸器管理中の筋萎縮性側索硬化症の事例に協力により実施した在宅多職種連携教育の経験
伊藤 智範(岩手医科大学 医学部)
S-6-3
臨床実習とVirtual Realityを組み合わせた在宅医療教育
崎山 隼人(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 医療人材連携教育センター)
S-6-4
医学生の地域医療実習感想からみた島根大学医学部在宅医療教育の現地点
佐野 千晶(島根大学医学部 地域医療支援学講座)
S-6-5
在宅医療は医学教育のテキストブックだ~長崎大学における経験より~
永田 康浩(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学分野)
シンポジウム7/Symposium 7
7月26日(土)9:00~10:30
会場:第3会場(あきた芸術劇場ミルハス 4F 小ホールA)
診療参加型臨床実習のグッド・プラクティス
Good Practices for Clinical Clerkship
令和4年度改訂版コアカリには、方略・評価の事例が記載されているが、CCの事例の記載はないため、CCの具体的事例を指導者間で共有することでCCの導入が促進されることが期待される。本セッションでは、CCのグッド・プラクティスを紹介するとともに、その理論的背景やカリキュラム管理運営の観点からも議論することで、CCを推進するためのヒントを参加者間で共有することを目標とする。
座 長:高橋 誠(北海道大学)
谷口 純一(天草地域医療センター)
S-7-1
参加型臨床実習を可能にするためにー先行研究の知見からー
及川 沙耶佳(秋田大学)
S-7-2
診療参加型臨床実習の標準化
西屋 克己(関西医科大学教育センター)
S-7-3
授業をやめ、医療現場を経験すれば学生は自ら勉強する -昭和大学の新カリキュラムへの挑戦-
泉 美貴(昭和医科大学 医学部 医学教育学講座)
S-7-4
学生のニーズと臨床実習~北海道大学医学部小児科における臨床実習の変遷~
佐藤 泰征(北海道大学大学院医学研究院 小児科学教室)
S-7-5
くまもと県北病院総合診療科における診療参加型臨床実習の報告
中村 孝典(くまもと県北病院)
シンポジウム8/Symposium 8
7月26日(土)9:00~10:30
会場:第4会場(あきた芸術劇場ミルハス B1F 小ホールB)
臨床研修指導医講習会の創意と工夫
Innovation and Creativity in Clinical Training Instructor Workshops
厚生労働省として、指導医が参加する指導医講習会の質を確保するため、「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」が定められている。
医師の臨床研修に係る指導医講習会(以下「臨床研修指導医講習会」)は指針に沿って主催者が工夫を凝らして全国で開催されているが、そのgood practiceや工夫は共有される機会は少ない。
そこで、本シンポジウムでは開催指針について厚生労働省により解説頂いた後、good practiceや工夫を凝らした臨床研修指導医講習会を実施している4名の演者に発表頂く。
座 長:石原 慎(藤田医科大学)
横江 正道(日本赤十字社医療事業推進本部)
S-8-1
臨床研修指導医講習会の開催指針について
野口 宏志(厚生労働省)
S-8-2
積極的な意見交換のために、全体発表をなくした指導医養成講習会
瀬尾 恵美子(筑波大学附属病院 総合臨床教育センター)
S-8-3
ハイブリッド型臨床研修指導医講習会の導入と今後の展望
望月 篤(聖マリアンナ医科大学 医学教育文化部門 医学教育研究分野)
S-8-4
研修プログラム立案の理解促進を目的とした「Myミニカリキュラム作成」の試み
小松 弘幸(宮崎大学医学部 医療人育成推進センター)
S-8-5
成人学習理論と指導医の客観的指導能力評価(OSTE)によるフィードバックを組み込んだ指導医講習会の実践
松島 加代子(長崎大学病院医療教育開発センター)
シンポジウム9/Symposium 9
7月26日(土)9:00~10:30
会場:第5会場(秋田市文化創造館 2F スタジオA1)
若手医療者教育者のための教育ポートフォリオ発表会
Educational Portfolio Presentation for Young Healthcare Educators
若手部会は、学会への若手教育者の参加を促進することが目的の1つとして設立された。2020年からの調査によれば、学術大会への若手教育者の参加は年々増加傾向にある。しかし、発表の機会が限られることが参加の障壁となっている現状も過去の学会内でのシンポジウムで明らかになった。そこで、第56回大会(2023年度)では、若手医療者が発表しやすい「若手教育者による教育ケースレポート」を企画し、15演題が発表された。若手教育者が自己の教育手法を考察し、より良い医学教育の実践へ繋げる一助となることを期待し、この企画では若手教育者が実際に行った・受けた教育をその振り返り、その課題や今後の展望を共有する場を設けた。しかし前回はオンラインのみであったこともあり、十分な意見交換や多くの参加者に成果物を見てもらうことが出来なかった。また、フォーマットがなかったため、発表形式がバラバラであった。
第57回大会では、前回同様、公募で募った若手教育者に自身の教育ケースを教育事例を報告する形式で発表してもらうが、当学会が使用している医学教育専門家認定申請用ポートフォリオの形式で発表してもらう。さらに、デジタル技術を利用しながら対面でインタラクティブになる仕組みを取り入れる。すなわち、新しい形のe-ポスター形式を取り入れ、既存の紙で行うポスターではなく、デジタル形式でのポスターセッションを行う。既存のe-ポスターセッションでは機材やプラットフォームの使用にコストがかかるという問題点に対し、今回我々はシンポジウムの形式を取りながらe-ポスターセッションを行う新しい形式を提案する。今回のセッションは、本大会のテーマである、デジタル教育の新たなステージへとつながる学会発表の1つの形になると確信している。
- 座 長:
- 木戸 敏喜(富山大学学術研究部(医学)教育学講座/富山大学附属病院第一内科)
徳増 一樹(岡山大学病院 総合内科・総合診療科)
鈴木 真紀(津和野共存病院 総合診療科)
稲葉 哲士(市立福知山市民病院 総合内科)
平田 香穂里(岡山市立市民病院 総合内科)
小杉 俊介(九州大学大学院医学系学府医学教育学講座/飯塚記念病院)
橋本 忠幸(Brigham and Women’s Hospital)
幕内 安弥子(大阪公立大学 総合医学教育学/総合診療科)
松島 加代子(長崎大学病院医療教育開発センター)
磯部 真倫(岐阜大学医学部附属病院産婦人科)
S-9-1
研修医向け手技教育プログラムにおけるResident as Teachersの実践
大塚 勇輝(岡山市立市民病院救急科)
S-9-2
症例報告執筆教育をいかに普及させるか
池之内 初(東北大学大学院医学系研究科 神経内科学分野)
S-9-3
「ベッドサイド教育は重要」を振り返る
片山 皓太(聖マリアンナ医科大学)
S-9-4
地域医療における研修医教育:外来診療と訪問診療の組み合わせによる効果
黒木 史仁(まどかファミリークリニック)
S-9-5
低学年次の医学生に対する文化人類学教育の実践と振り返り
青野 大輔(金沢大学医薬保健研究域医学系 医学教育学)
S-9-6
リフレクションの意義と実践報告
武島 健人(富山大学 学術研究部医学系(医学) 医学教育学講座)
S-9-7
医学部・薬学部合同薬理学ロールプレイ実習の学習効果と教育的意義の検討
船本 雅文(徳島大学大学院医歯薬学研究部薬理学分野)
S-9-8
上級医が少ない環境下での2年目初期研修医への指導を振り返る
田川 哲也(市立大町総合病院 内科)
S-9-9
地域研修指定病院における、高次医療機関の初期研修医に対して行う主体的な入院診療を促す仕組みづくり
鈴木 智大(兵庫医科大学ささやま医療センター)
S-9-10
柔道整復師養成教育におけるAIを活用した臨床推論トレーニングの実施と課題
祁答院 隼人(日本体育大学スポーツキュアセンター横浜・健志台接骨院)
S-9-11
情報を調べる力、論理的思考力、プレゼンテーション能力の向上を目指した薬学卒業研究での学びと取り組み
高橋 美裕(帝京大学 薬学部 製剤学研究室)
S-9-12
医学生に対して、大学病院の外来での医療面接をmini-CEXを用いて評価した事例
合田 建(神戸大学医学部附属医学教育推進センター)
S-9-13
教育を行う理由は「自己中」で良い
松本 丈雄(安芸太田病院)
S-9-14
肉眼解剖学実習と連携連動した画像解剖学講義
篠田 凜子(東海大学医学部医学科)
S-9-15
診療看護師(NP)が行う教育活動~地域密着型病院における教育実践~
三宅 徹(藤原記念病院 看護部)
S-9-16
若手医師が新たに臨床研修教育に参画する際に、過去に行った自主的取組みを振り返るケーススタディ的考察
池尻 達紀(彦根市立病院)
S-9-17
多職種連携実習を通して広がった協働の視点
宮澤 正咲(富山大学)
S-9-18
高校生の地域医療体験が現場にもたらした影響
村山 愛(君津中央病院大佐和分院)
S-9-19
若手医師主導による初期研修教育改革の実践と成果
佐々木 周(彦根市立病院)
S-9-20
将来の研究者育成、指導者育成、AST活動などを目指した感染症診療教育
石川 和宏(江戸川病院)
S-9-21
シュミレーション教育による教育経験格差の解消
山田 潤一(湘南鎌倉総合病院)
S-9-22
医学生のネットワーク形成を通じた学び。医学生発掘ピッチコンテストなどを中心に。
松下 武史(大阪医科薬科大学病院)
シンポジウム10/Symposium 10
7月26日(土)10:50~12:20
会場:第3会場(あきた芸術劇場ミルハス 4F 小ホールA)
未来の医療者に求められる社会との連携とその教育の在り方を考える
Exploring the Role of Social Engagement and Its Education for Future Healthcare Professionals
本シンポジウムでは、地域診断教育を題材に、地域住民と医療者を志す学生が協働して地域診断を行う実践について検討する。この教育プログラムは、地域の実情を深く理解し、多職種の視点からアプローチすることで、複雑化する社会の課題を解像度高く把握する力を養うことを目的としている。また、学生たちは異なる視点や立場を学び取り、それらを統合するプロセスを通じて、より包括的かつ柔軟な思考を身につけることが期待される。この過程では、多様な価値観を尊重し、共有することで、医療と社会の結びつきをより深める新たな可能性を見出すことができる。
さらに、地域診断教育では、地域住民と学生の対話を通じて「共通性」の発見が重視される。この共通性は、医療者と住民が互いに理解し合い、共に課題解決に向けて協働する基盤となる。本シンポジウムでは、こうした教育の過程で得られる学びや成果について、実際の事例を基に共有するとともに、教員・住民・学習者からの発表を通じて、学習者および住民の多様な視点がもたらす効果や、医療と社会の連携における新たな教育モデルの可能性について議論を深める予定である。参加者には、これらの議論を通じて、医療と社会を結ぶ新たな視点やアイデアを得る機会を提供し、今後の教育や実践に生かしてもらうことを目指している。
座 長:岡田 英理子(東京科学大学医学部 臨床医学教育開発学)
臼井 いづみ(千葉大学医学部附属病院 総合医療教育研修センター)
S-10-1
医療系学生の社会参画を促す教育:地域診断の可能性
春田 淳志(慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター)
S-10-2
医療系学生と住民が共創する地域医療の未来―慶應義塾大学の地域実習が稚内にもたらした変化
飯田 光(道北勤労者医療協会 宗谷友の会)
S-10-3
地域診断実習が都市部の医学部2年生に与えた学び
永田 みのり(慶應義塾大学医学部)
S-10-4
最北の地である稚内で学んだ、地域医療と看護の未来
中島 明音(慶應義塾大学)
S-10-5
地域を視て、考える:地域診断実習を通じた価値判断の変容
永井 淳誠(慶應義塾大学医学部)
S-10-6
地域診断実習を通じて学ぶ医療の多様性ー大学病院との対比から考えるその意義 ー
高橋 伶奈(慶應義塾大学医学部)
シンポジウム11/Symposium 11
7月26日(土)10:50~12:20
会場:第4会場(あきた芸術劇場ミルハス B1F 小ホールB)
医学教育研究におけるアクションリサーチと実装科学
Action Research and Implementation Science in Medical Education Research
アクションリサーチで書かれた論文や教育実践報告論文は、当該分野の教育実践を行う読者にとっては、非常に参考になる論文であろう。一方で、一般化可能性を問わない研究手法であるがゆえに、その科学性の担保においては、科学論に立ち戻って議論をする必要がある。具体的には、研究論文に、新規性に加えて、転用可能性が求められることになるが、これらの条件について、我々の領域で十分なコンセンサスが得られているとは言い難い。加えて、実際の研究の遂行や論文執筆にはいろいろな障壁も伴うが、こうした点についての研究者の実体験を知る機会は必ずしも多くはない。
本シンポジウムでは、アクションリサーチの研究手法で英文原著論文を出版した経験のある三人の演者(うち二人は医学博士学位論文としての審査も経験している)が登壇し、それぞれの研究についての概説を行う。加えて、実装科学やアクションリサーチ、そしてアクションリサーチと類似のデザイン基盤型研究についての概説も行う。他領域における実装科学やアクションリサーチへの取り組み方も参考にしながら、医学教育学におけるこれらのあり方や可能性について検討することが本シンポジウムの目的である。
実装科学やアクションリサーチには、教育の実践と理論を架橋できるという魅力がある。当日は医学教育研究という文脈で、本テーマについて、参加者の皆様と活発な議論ができることを楽しみにしている。
座 長:錦織 宏(名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学教育センター)
村松 友佳子(名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学教育センター)
S-11-1
医学教育研究におけるアクションリサーチの概要と一事例
錦織 宏(名古屋大学大学院医学系研究科総合医学教育センター)
S-11-2
症例検討会開発におけるアクションリサーチ -教育と学術活動が重なる時-
宮地 純一郎(名古屋大学 総合医学教育センター)
S-11-3
指導者養成プログラムにおける文化人類学授業の開発にアクションリサーチを取り入れた実践の共有
及川 沙耶佳(秋田大学)
S-11-4
医療者教育における研究と実践の架橋ー実装科学の視点からー
木村 武司(名古屋大学医学部附属病院)
シンポジウム12/Symposium 12
7月26日(土)14:00~15:30
会場:第3会場(あきた芸術劇場ミルハス 4F 小ホールA)
日本の医学教育は世界に対してどのように貢献しうるか?
What can Japanese medical education contribute to the world
このような背景を踏まえ、令和5年度に実施された「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究委託事業」で、医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度版)の改訂に際する調査研究の成果を国際的に発信するプロジェクトが立ち上がり、2024年11月、『Medical Teacher』誌の日本特集号の発刊を以て結実した。このシンポジウムでは、筆頭著者と編集者が論文化のプロセスを振り返りながら、この特集号を通じて日本の医学教育の現状を国際的に発信することが、どのような形でグローバルな医療コミュニティの発展に寄与しうるか、そして日本自身の医学教育システムのさらなる発展と改善に繋がりうるかを探る。また、グローバルな医療および医学教育の課題に対して、日本の医学教育の発信がどのような形で国際的な医学教育・研究ネットワークの強化に貢献しうるか、そして我々はここから何をしていかなければならないかを議論したい。
座 長:春田 淳志(慶應義塾大学医学部 医学教育統轄センター/総合診療教育センター)
宮地 由佳(名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学教育センター)
S-12-1
日本の医学教育は世界に対してどのように貢献しうるか?
錦織 宏(名古屋大学大学院医学系研究科総合医学教育センター)
S-12-2
日本特集号のもたらすイノベーションと貢献
近藤 猛(名古屋大学医学部附属病院 総合診療科/卒後臨床研修・キャリア形成支援センター)
S-12-3
Competency-based medical education guidelines are context-basedの執筆から
松山 泰(自治医科大学 医学教育センター)
S-12-4
「情報・科学技術を活かす能力」に関する学修目標選定プロセスの論文執筆経験から
尾上 剛史(名古屋大学医学部附属病院)
S-12-5
「総合的に患者・生活者をみる姿勢」策定過程に関する論文執筆経験から
藤川 裕恭(順天堂大学医学部総合診療科学講座)
S-12-6
次のコアカリを海外に発信するために、今できること
野村 理(岐阜大学医学教育開発研究センター)
シンポジウム13/Symposium 13
7月26日(土)14:00~15:30
会場:第4会場(あきた芸術劇場ミルハス B1F 小ホールB)
身体障害のある医師および医学生を支援するための共同創造視点の探索
Exploring a Co-Productive Perspective to Support Physicians and Medical Students with Physical Disabilities
座 長:林 幹雄(関西医科大学教育センター)
瀬戸山 陽子(東京医科大学教育IRセンター)
藤田 博一(高知大学医学部附属 医学教育創造センター)
S-13-1
聴覚障害のある医学生としての経験と実現してきた合理的配慮
荒巻 修治(秋田大学医学部)
S-13-2
聴覚障害を持つ臨床医師の医学生時代の経験と現在の働き方
武地 蒼太(日本大学医学部脳神経外科)
S-13-3
視覚障害のある医師の事例 -全盲・ロービジョンそれぞれの視点から-
守田 稔(かわたペインクリニック心療内科)
S-13-4
すべての医療現場で障害を持つ患者・医療者への環境整備を:聴覚障害を持つ医学生との6年間の取り組みから
長谷川 仁志(秋田大学)
シンポジウム14/Symposium 14
7月26日(土)15:50~17:20
会場:第2会場(あきた芸術劇場ミルハス 2F 中ホール)
臨床実習における医学生の適正な評価と医師国家試験CBT化に向けた展望
Appropriate evaluation of medical students in clinical training and prospects of CBT for National Examination for Medical Practitioners
河北を研究代表者とした厚労科研では、動画や音声、画像等を取り入れた問題を作成し、インターネットを介したCBT試験システム(TAO)を利用して、トライアル試験を2023年度には46大学で円滑に実施し、CBT試験が実施可能であることを示した。また、実際の心音や呼吸音の音声、診察や医療面接、検査時等の動画等を取り入れた、実臨床に近い問題により、現行のPBTによる試験形式に比べ、知識だけでなく一部の技能の評価も可能となった。さらに、医学教育の充実を図るためには、知識・技能を評価するCBT医師国家試験を実施するとともに、臨床実習とそれにおける医学生の適正な評価を行うことが重要であることから、今回、臨床実習の評価と医師国家試験のCBT化を一体的に取り組むこととした。各大学における臨床実習を充実させて、医学生の適正な評価を行うこと、さらにCBT医師国家試験で実臨床に近い問題により深いレベルの知識・技能の評価が可能となることにより、医学生の知識・技能・態度のスキルを高め、国民から信頼される臨床能力に優れた医師を養成することができると考える。AIによる医療の進歩等の中で、2040年、2050年のあるべき医師像を見据えて研究することが重要である。
本シンポジウムでは、医師国家試験のCBT化が早期に実現し、知識・技能・態度の評価が適正に行われるように、マルチメディアを活用したCBT問題作成の体制と人材育成、およびCBTシステムの有用性や実現可能性、CBT医師国家試験を見据えた出題基準の在り方、診療参加型臨床実習と医学生の適正な評価の在り方について議論して、我が国の医学教育と医師国家試験の充実を目指す。単に研究だけに終わらせるのではなく、医師国家試験のCBT化や臨床実習における医学生の適正な評価等を実現するため、現状の課題や展望について、医学教育に携わる皆様と議論する。
座 長:岡崎 仁昭(自治医科大学 医学教育センター)
伴 信太郎(愛知医科大学 医学教育センター)
S-14-1
2040年、2050年の将来の医師を見据えた臨床実習の評価と医師国家試験
河北 博文(公益財団法人日本医療機能評価機構)
S-14-2
マルチメディアを活用したCBT問題の作成
松山 泰(自治医科大学 医学教育センター)
S-14-3
CBT形式での医師国家試験を実現するにあたっての試験システム検討
淺田 義和(自治医科大学)
S-14-4
本邦におけるWBA(Workplace-Based Assessment)の現状と将来展望について
錦織 宏(名古屋大学大学院医学系研究科総合医学教育センター)
S-14-5
卒前卒後の医学教育を俯瞰した医師国家試験の今後
小西 靖彦(順天堂大学)
シンポジウム15/Symposium 15
7月26日(土)15:50~16:50
会場:第3会場(あきた芸術劇場ミルハス 4F 小ホールA)
多様な入学者選抜とアウトカム
Diverse Admissions and Outcomes
現在、多くの大学が入学試験に工夫を凝らし、よりよい医療者になる学生の採用を目指している。それらの成果を様々な指標を用いてアウトカムを評価し、入学試験のあり方を模索している。しかし、入学試験という秘匿性の高い事象がゆえ、それらが共有される機会は少ない。今回は、いくつかの大学で実施されている様々な入学試験制度について、そのアウトカムを含めて紹介することで、各大学の入学試験のあり方について議論を行いたいと考えている。
座 長:門川 俊明(慶應義塾大学)
大久保 由美子(帝京大学)
S-15-1
地域枠入試制度とアウトカム
小松 弘幸(宮崎大学医学部 医療人育成推進センター)
S-15-2
入学者選抜とアウトカム
藤田 博一(高知大学医学部附属医学教育創造センター)
S-15-3
多様な入学試験のあり方とアウトカム
中村 真理子(東京慈恵会医科大学)
シンポジウム16/Symposium 16
7月26日(土)15:50~17:20
会場:第4会場(あきた芸術劇場ミルハス B1F 小ホールB)
共に創る医療者教育:近年の実践例と理論的考察
Co-creating health professions education: Current practices and theoretical consideration
まず「大学と地域の2拠点で教育を共創する教員の働き方」をテーマに、馴質異化および異質順化の視点から、学習者・市民・行政・医療者・大学との関係性を尊重した医療者教育の在り方を議論します。医療者教育者と地域の多様なバックグラウンドや価値観を持つ人々による新たな医療者教育共創への挑戦を共有します。
続いて教育者と学習者の従来の上下関係を脱却し対等な対話による共創的な教育を行った、診療所研修でのCo-creationの実践例を紹介します。そして互いの学びが研修の質を向上させるプロセスについて考察します。
さらに「忙しい現場での教育同盟の構築」では、教育同盟理論をもとに、忙しい臨床現場における教育支援と信頼関係の構築方法を探ります。医療現場での多忙な状況の中でも、教育者と学習者が互いに尊重し合いながらパートナーシップを形成するための工夫や、その重要性について具体例を交えて解説します。
最後に、パネリストと参加者全体での討議を行い、参加者同士の意見交換を通じて、医療教育における「共創」の意義を深めていきます。本シンポジウムは、医療教育に関わる全ての参加者が互いに学び合い、成長し続けるためのヒントを提供し、新たな共創の未来を切り開くことを目的としています。
座 長:西城 卓也(岐阜大学)
山口 佳子(東京医科大学)
S-16-1
学習者、教員、ステークホルダーはどのように教育の共創で相互作用しうるのか
高橋 美裕希(岐阜大学 地域共創型飛騨高山医療者教育学講座)
S-16-2
初期研修医の地域医療研修におけるCo-creationの実践
高橋 慶(医療生協さいたま生活協同組合 川口診療所)
S-16-3
Co-creationとEducational Allianceは卒後研修にどのように影響を与えるのか?
吉田 暁(新潟市民病院)
シンポジウム17/Symposium 17
7月27日(日)10:35~11:35
会場:第2会場(あきた芸術劇場ミルハス 2F 中ホール)
働き方改革における研修医への教え方カイカク
Reforming residency training methods under the implementation of work style reform for physicians.
この働き方改革が始まったいま、どうやって指導医は研修医に教えたらいいのでしょうか?また、研修医はどうやって学ぶとよいのでしょうか?教育病院・診療所で悩んでいるみなさんとともに、多角的にディスカッションできるシンポジウムにしたいと思います。主なテーマとして、①働き方改革前後での臨床研修の変化、②大都市と地方での大病院・中小病院・診療所での研修医教育の変化、③量を経験しづらい環境の中で質の担保はどうするのか?を、プログラム責任者、指導医、専攻医、研修医、事務と言った立場から多角的に意見を出していただきみなさんで考えていきたいと思います。敢えてワークショップとはせず、定員も設けずに会場にふらっと立ち寄って意見して、聞いてもらえる場として、会場のみなさまと flatな関係でよい知恵を出していけることを願います。
座 長:横江 正道(日本赤十字社医療事業推進本部)
尾原 晴雄(沖縄県立中部病院)
S-17-1
中小病院の指導医は今、何に悩み、どう教えているか
南郷 栄秀(社会福祉法人聖母会 聖母病院 総合診療科)
S-17-2
地方研修病院における働き方改革の影響
小杉 俊介(飯塚病院)
S-17-3
臨床研修センターの積極的介入により勤務時間内の効果的教育を実現
白籏 久美子(飯田市立病院)
S-17-4
働き方改革時代における初期研修の現状と指導のあり方
木下 慶一郎(公益財団法人 天理よろづ相談所病院)
S-17-5
働き方改革の中で達成する主治医としての自覚の育成
深田 絵美(社会医療法法人宏潤会 大同病院)
オンデマンドシンポジウム1/On-demand Symposium 1
医学教育DX -学びと成長の新しい形-
Medical Education DX -A New Approach to Learning and Growth-
座 長:西﨑 祐史(順天堂大学 医学教育研究室)
小林 裕幸(筑波大学)
OS-1-1
非同期型動画レビューアプリケーション「tsucom」の医療教育への応用
荘子 万能(BonBon株式会社)
OS-1-2
AI患者を用いた問診トレーニング
高橋 宏瑞(順天堂大学附属浦安病院)
OS-1-3
患者再現VTRを用いた基本的臨床能力評価
鋪野 紀好(千葉大学大学院医学研究院 地域医療教育学)
OS-1-4
LINEアプリを活用した医学部生向けオンライン学習支援システムの導入
西崎 祐史(順天堂大学)
オンデマンドシンポジウム2/On-demand Symposium 2
デジタル教育と生成AIを活用した医学教育の未来 - カルテ記載からシミュレーション教育まで
The Future of Medical Education with Digital Tools and Generative AI From Medical Charting to Simulation-Based Learning
座 長:三原 弘(札幌医科大学医療人育成センター)
OS-2-1
生成AIで変わる医学教育
大塚 篤司(近畿大学医学部皮膚科)
OS-2-2
生成AIを活用したレポートフィードバック
沖野 久美子(北海道医療大学医療技術学部)
OS-2-3
看護教育における生成AI活用:カルテ記載からフィードバックまでの新たなアプローチ
永井 翔(人間環境大学 看護学部)
OS-2-4
医療面接の学習者評価におけるAI分析の限界と可能性(KAKEN:24K16755)
三浦 聖子(金沢医科大学、Maastricht大学MHPE)
OS-2-5
地域医療と学際連携を支える生成AI活用の可能性
三原 弘(札幌医科大学医療人育成センター)
オンデマンドシンポジウム3/On-demand Symposium 3
医学部における人文社会科学教育の意義と役割
Significance and Role of Humanities and Social Sciences in Medical School Education in Japan
廣瀬会員は岩手医大教養教育センター に所属し、20年間に亘り必修科目の医事法学や教養の法学や医療と法律を担当してきており、PBL、ディベート、ビブリオバトルなどのアクティブ・ラーニングを実践し学生たちに自ら考えさせる〈反転授業〉を導入し、ベスト・ティーチャー賞を何度も受賞されており、授業実践と科目の教育意義と役割について話題提供を行う。
杉岡会員は、京都府立医大の人文社会科学教室に所属し、医師でもあり医学哲学倫理学会で教育委員長を務めており、学内では1年次生の選択必修科目の医学哲学を担当してきており、授業での工夫や卒前教育における意義と役割について話題提供を行う。
村上会員は京都府立医大教育センターに所属し、1年次の行動科学基礎と4年次の行動科学応用の授業科目を担当している。昨年度より行動科学を必修科目とし、授業で扱う内容や授業方法での工夫、教育の意義と役割について話題提供を行う。
瀬戸山会員は、1年次の必修科目生命倫理学並びに5年次の必修科目医療倫理学の授業を約10年間に亘り担当してきており、臨床倫理の方法論、隠れたカリキュラムやプロフェッショナリズムなどの授業で扱う内容、グループディスカッションやフィードバックなどの教育効果を高める工夫や実践、成績評価方法について話題提供し、それぞれの授業科目が担う意義と役割について検討を行う。
これらの教育実践を踏まえてフロア参加者とともに卒前教育における人文社会科学科目の意義と役割についてディスカッションを行いたい。
座 長:瀬戸山 晃一(京都府立医科大学)
OS-3-1
医学教育における医学哲学の意義
杉岡 良彦(京都府立医科大学)
OS-3-2
医学部における医事法学及びアカデミックリテラシー教育の実践と意義
廣瀬 清英(岩手医科大学)
OS-3-3
行動科学教育の目指すもの ―「理解する」から「説明できる」へ―
村上 嵩至(京都府立医科大学)
OS-3-4
医学部における生命倫理学及び医療倫理学を教育実践とその意義
瀬戸山 晃一(京都府立医科大学 大学院医学研究科 医学生命倫理学)
オンデマンドシンポジウム4/On-demand Symposium 4
地域医療学をいかに教えるか
How to teach community health
座 長:前野 哲博(筑波大学地域医療教育学)
OS-4-1
6年間で地域医療学を教える
小谷 和彦(自治医科大学 地域医療学部門)
OS-4-2
地域医療を教えるー座学と実習のカリキュラム構築
川本 龍一(愛媛大学医学部)
OS-4-3
対話を通して医師の地理的偏在問題を考える:法学、哲学、倫理、政策を絡めて
松本 正俊(広島大学)
OS-4-4
地域医療の視点を養う社会医学実習
井口 清太郎(新潟大学大学院医歯学総合研究科 地域医療学分野)
オンデマンドシンポジウム5/On-demand Symposium 5
海外医療援助活動における非認知能力育成効果とチームビルディングについて
The effects of non-cognetive ability development and team bulding in overseas medical activities
国境なき医師団などの国際医療援助活動においては、極限の状況の中で医療活動を続けるうちに、特殊な環境への適応や人びととの共感、ストレスへの対処などといった、非認知能力を高める要素が極めて多く含まれており、実際に活動から帰国したスタッフが元の病院スタッフから”変わった”と言われることが多いのも事実である。
国際医療援助活動を経験した結果、誠実性、情動知能、共感性、自尊感情、セルフコンパッション、エゴレジリエンスなどといった非認知能力が向上し、医療者としてのチームビルディング能力が高まることは海外での医療貢献のみならず、帰国後の日本における医療においても活かすことができると考えられる。
今回は、海外での医療援助活動を通じて非認知能力の改善についてどのような効果を得ることができたのか、そしてそれによってチームビルディングにおいてどのような効果が得られたかについて検討する。
座 長:久留宮 隆(国境なき医師団)
OS-5-1
MSFにおける海外医療活動が帰国後の非認知能力に与える影響について
久留宮 隆(国境なき医師団)
OS-5-2
海外医療援助活動における非認知能力育成効果とチームビルディングについて
浦部 優子(国境なき医師団)
オンデマンドシンポジウム6/On-demand Symposium 6
医師・医療者人生100年時代、個人とチーム・組織の質を向上し続ける卒後80年間に渡る生涯教育を考える
Considering CME to continuously enhance the quality of individuals, teams, and organizations in the era of 100-year lifespans for physicians and healthcare professionals.
委員会は、内科系、外科系、医育機関・医療機関・診療所と臨床的にも教育的にも幅広く専門性を持つ国内・外のメンバーで構成されている。シンポジウムでは、『コアカリをシームレスに生かして常に個人と周囲のすべてのチーム・組織の質を向上し続ける卒後80年間のこれからの生涯教育について』、『非同期型オンライン多職種連携シミュレーションプログラム構築&評価」の可能性』、『生成系AI活用型リカレント教育システムの展開』、『厚労科研費事業ICTを利用した医学教育コンテンツ』、『一括導入した電子教科書を軸とした臨床前教育の試みからの展開』、『コロナ禍の学生臨床実習から学んだ教訓と生涯教育への応用』、『医療MaaSを用いた医療過疎地域の医学教育モデルの構築』、『オンラインシミュレーションの経験から考える医師・医療者の生涯教育における「対面」教育の意義』、『臨床研修指導医講習会における事前学習としてのe-learningの導入』、『AIを使用した患者満足度を向上させるための非言語的な医療面接教育方法』、『AIを用いて英語に関する負担を軽減する方法』といった幅広い視点で、それぞれの先生から次世代へのコアなメッセージを発信していただいて、次のステップに進んでいきたい。
座 長:長谷川 仁志(秋田大学)
近藤 昭信(済生会松阪総合病院)
OS-6-1
卒前~生涯教育まで一貫したテクニカル・ノンテクニカル統合教育のための県内デジタルネットワーク構築
長谷川 仁志(秋田大学)
OS-6-2
非同期型オンライン多職種連携プログラムの卒前多職種連携教育から医師・医療者生涯教育への応用
小林 天美(ハーバード大学医学部)
OS-6-3
持続可能性を追求した生成AI活用型生涯・リカレント教育の展開
三原 弘(札幌医科大学医療人育成センター教育開発研究部門)
OS-6-4
厚労科研費事業「ICTを利用した医学教育コンテンツ」の生涯教育への応用
松山 泰(自治医科大学 医学教育センター)
OS-6-5
入学時に一括導入した電子教科書を軸とした臨床前教育の試みと生涯教育への展望
小田 康友(佐賀大学)
OS-6-6
臨床教育のデジタル化~コロナ禍の学生臨床実習から学んだ教訓と生涯教育への応用
小松 弘幸(宮崎大学医学部 医療人育成推進センター)
OS-6-7
教育病院による医療MaaSを用いた医療過疎地域の医学教育モデルの構築を目指して
山本 浩史(秋田大学附属病院医療DXセンター遠隔医療推進部門)
OS-6-8
オンラインシミュレーションの経験から考える医師・医療者の生涯教育における「学修者主体性」の意義
駒澤 伸泰(香川大学医学部地域医療共育推進オフィス)
OS-6-9
臨床研修指導医講習会における事前学習としてのe-learningの導入と今後の課題
近藤 昭信(済生会松阪総合病院)
OS-6-10
英語によるポスター発表の効果的な指導法
押味 貴之(国際医療福祉大学医学部)
オンデマンドシンポジウム7/On-demand Symposium 7
医学史学修の重要性:医学教育モデルコアカリキュラムの多くの資質を向上させるために
The importance of learning medical history. Enhancing various competencies in the model core curriculum for medical education
座 長:松田 隆秀(聖マリアンナ医科大学)
長谷川 仁志(秋田大学)
OS-7-1
医学部卒前教育における医学史教育の重要性について
松田 隆秀(聖マリアンナ医科大学)
OS-7-2
川崎医科大学における医学史教育の実践
樋田 一徳(川崎医科大学)
OS-7-3
京都大学の医学史教育および医学教育関連歴史資料の活用可能性
森下 真理子(京都大学医学部附属病院 医療安全管理部)
OS-7-4
患者の立場からみた意思決定 患者・医師関係の変遷 医学史教育に期待すること
山口 育子(認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML)
OS-7-5
医学教育モデルコアカリキュラム(R4年度版)の多くの資質を向上させる各分野診療における現代史の重要性
長谷川 仁志(秋田大学)
オンデマンドシンポジウム8/On-demand Symposium 8
若手から考える総合診療・家庭医療の卒前教育の標準化
Standardizing Undergraduate Education in General and Family Medicine from the Perspective of Young Physicians
しかし一口に「総合診療」といっても、それが包括する概念は、家庭医療、病院総合診療(ホスピタリスト)、地域医療、高齢者医療などと幅広い事に加え、各大学の総合診療部門が有する機能や教員の専門分野は大学によって異なっている。また、座学・知識面での教育に関しても各大学が独自に取り組んでおり、大学ごとに具体的内容や方略に差が大きいのが現状である。臨床実習に関しては、市中病院・地域医療機関での実習が推進されているが、地域の臨床現場における学生教育の方法やリソースの共有はあまり進んでおらず、それぞれの実習内容も様々である。そのため、日本全体として各医学部・地域において総合診療に関する教育の内容や方略を共有し標準化していくことは重要な課題であると思われる。
また総合診療医を増やすという視点では、この分野を志望する学生・研修医の増加は緩やかであり、昨今の需要を考えるとその魅力をさらに発信・アピールしていく必要があると思われる。しかし総合診療専門医が、専門医機構直轄で特定の学会の管理下にないという特殊性から、関係の各学会や団体、各大学・病院などがそれぞれ独自に学術集会、勉強会、説明会などを実施しているのが現状で、指導医が所属組織の垣根を超えて連携をとり足並みを揃えて活動することが求められている。
こうした背景を踏まえると、全国での総合診療の教育体制の標準化にむけて学術的な議論が必要であり、その第一段階として本セッションでは、各医学部において様々な立場から医学生への総合診療教育に関わる若手教員・スタッフに登壇を頂き、シンポジウム形式で議論をしたいと考えている。
座 長:大塚 勇輝(岡山大学病院総合内科・総合診療科)
横田 雄也(岡山大学病院総合内科・総合診療科)
OS-8-1
岡山大学における総合診療教育の実践
横田 雄也(岡山大学病院 総合内科・総合診療科)
OS-8-2
「秋田らしさ」を生かした総合診療教育の構築:秋田大学における実践
渡部 健(市立角館総合病院 総合診療科)
OS-8-3
大学と地域医療機関、行政との連携により構築される、強固な地域医療教育の体制
村山 愛(君津中央病院大佐和分院)
OS-8-4
大学における総合診療学の「見える化」への取り組み
今西 明(新潟大学大学院医歯学総合研究科 地域医療確保・地域医療課題解決支援講座 地域医療分野)
OS-8-5
東京での総合診療の卒前教育の取り組み
安藤 崇之(慶應義塾大学医学部総合診療教育センター)
オンデマンドシンポジウム9/On-demand Symposium 9
Learning signalを可視化する:非言語情報の工学的分析と教育現場への応用と課題
Visualizing learning signals/ Engineering analysis of non-verbal information and its application to education and issues
近年、テクノロジーの発展に伴い、従来から研究対象であった表情を含む非言語情報も高度に分析が可能になった。もともと、表情分析は、EkmanらによるFacial Action Coding System(FACS)という解剖学に基づいた識別可能な顔の動きを定量化することから発展してきたが、最近ではAIを利用し、短時間で多くの解析が可能になった。また、認知科学領域でも、言語やジェスチャー、表情などから発話者の意図に関わらず、コミュニケーションの受け手に目に見える変化を与えるsocial signalが学修機会にどのような効果を与えているのか注目を集めている。
一般的に、学修者の学修状態の測定には、確認テストを始め、感情の評価(感情価)、生体反応、非言語情報、脳機能計測などがある。知識の習得状況に、テストは有効であるが、学修状態の測定として万能ではない。一方、表情分析やsocial signalの工学的分析は、学修者の非言語情報を客観的に解析することができる。これらの分析にて、learning signalとも呼べる学修者の非言語信号を捉え、learning signalとテストを組み合わせることで、学修状態をより鋭敏に把握できる可能性がある。
本シンポジウムでは、非言語情報を工学的、認知心理学的観点による最新知見に加えて、医学教育現場への表情分析を始めとする非言語情報の応用と課題について考察する。
座 長:山脇 正永(東京科学大学)
鈴木 健嗣(筑波大学)
OS-9-1
医学教育における学修者Learning Signalの分析と活用
山脇 正永(東京科学大学)
OS-9-2
非言語情報に基づくソーシャル・シグナルの計測と分析法の現在
鈴木 健嗣(筑波大学)
OS-9-3
顔表情解析×IRTと視覚言語統合が拓く医学教育の可能性
熊野 史朗(NTT コミュニケーション科学基礎研究所)
OS-9-4
表情解析と学習満足度への応用の可能性
赤石 雄(東京科学大学)
OS-9-5
医学教育における非言語情報に関するテキスト分析
加藤 寿寿華(東京科学大学)
オンデマンドシンポジウム10/On-demand Symposium 10
全ての学会のダイバーシティ委員会をヨコにつなぐ:卒前卒後の医学部教育ジェンダーギャップを解消するアクションを起こすために
Connecting activists in DEI within the field of medicine
座 長:赤嶺 陽子(大阪市立総合医療センター 小児集中治療部)
岡崎 三枝子(秋田大学医学部付属病院 総合臨床教育研修センター)
OS-10-1
医学系組織における意思決定層のジェンダー格差と課題~可視化から始めるDE&I推進~
村田 亜紀子(京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター)
OS-10-2
理事経験から考えるDE&I推進とリーダーシップ ~キャリア形成を支える行動する組織文化とは~
山内 かづ代(千葉大学大学院医学研究院 地域医療教育学)
OS-10-3
手術とリーダーシップ教育を融合したイクドクセミナーの実践と行動変容
志鎌 あゆみ(筑波大学)
OS-10-4
全ての学会のダイバーシティ委員会をヨコにつなぐ:論理的なDE&Iアクションを起こすために
赤嶺 陽子(大阪市立総合医療センター)
オンデマンドシンポジウム11/On-demand Symposium 11
レジリエントな災害対応を教える ~職種間理解と仮想再現VR教材の可能性について~
Disaster medical education for resilient responses
またKolb学修モデルに示される「具体的経験」→「省察」→「抽象的概念化」→「積極的実践」のサイクルの反復学習をもとに、避難訓練が実施されているが、「大災害」や施設の「垂直避難」を前提にしたものが殆どであるが、実際にはエレベータ閉じ込めや落雷等で生じうる「停電」等の比較的遭遇する可能性の高い災害への対応教育も重要である。また災害対応教育は実際の再現訓練が困難な場合が多く、既視感と没入感を得ることができるVirtual Reality(VR)を用いた教材の開発にも目を向ける必要があると考える。
今回企画したシンポジウムでは災害時に目の前で生じている困難を打破するために、多職種の能力を理解したうえでの協働できる役割分担や、BCPをはじめ過去の経験や訓練に落とし込めるレジリエントな対応ができる医療者育成のために、必要な教育の工夫や災害状況の仮想VR教材の可能性を通じて、被災時に質の高い医療を提供するための医療者教育の在り方を考察する場としたい。
座 長:長南 行浩(札幌医科大学 医療人育成センター)
中村 京太(横浜市立大学附属市民総合医療センター 医療の質・安全管理部)
OS-11-1
災害に対応する医療者を育てるには?医学教育の現状とこれからの在り方を考える
松島 加代子(長崎大学病院医療教育開発センター)
OS-11-2
災害対応の原則と医療のレジリエンス
中村 京太(横浜市立大学附属市民総合医療センター)
OS-11-3
VR技術を活用した災害対応教育の新たな可能性
下川 敦士(株式会社積木製作)
OS-11-4
平時の訓練から学ぶレジリエントな人材の育成のための健康危機管理教材の開発
高橋 敬子(兵庫医科大学 医学部 医療クオリティマネジメント学)
オンデマンドシンポジウム12/On-demand Symposium 12
医学電子教材の未来を切り拓く選択
Decision to Open the Future of Digital Materials for Medical Education
そこで、本企画では如何に電子教材の継続性を担保するかについて、パネラーにディベートしてもらい、継続性と発展性のある医学教材開発について考えることにする。今回、電子教材の継続性を担保する方策として3つの選択(開発モデル)を取り上げ、3名の方にそれぞれの提案者になってもらい、聴衆を交えて議論する。選択1は無料の教材開発プラットフォームを用いて、全大学の教員に協力してもらい、教材開発と維持を行うモデルである。選択2は有料の汎用性の高いプラットフォームを用いることで、技術更新もされ高度な教材開発が共同で行え、持続性も担保できるモデルである。選択3は企業が独自開発したプラットフォームを生かし、民間企業の力を活用することで、大学教員の負担を軽減しながら継続的に教材の品質を高めて行くモデルである。これら3つの選択の優位点と欠点を議論する中で、よりよい医学電子教材開発のあり方を探ることが本企画のねらいである。
座 長:椎橋 実智男(埼玉医科大学情報技術支援推進センター)
藤田 博一(高知大学医学部附属医学教育創造センター)
OS-12-1
医学教育での電子教材開発・利用における課題提起とその解決戦略
栗原 幸男(高知大学医学部看護学科)
OS-12-2
共通基盤を用いた医学電子教材の共有:厚生労働科学研究の事例から
淺田 義和(自治医科大学 医学教育センター)
OS-12-3
有料プラットフォームと生成AIを活用した医療者教育の共同教材開発モデル:その可能性と課題
三原 弘(札幌医科大学医療人育成センター教育開発研究部門)
オンデマンドシンポジウム13/On-demand Symposium 13
「統合教育」って、何をしたら良いの?!
What should be done for Integrated Education
重要なのは、「統合」を進めるべき対象はカリキュラムではなく「学生」であるという点です。統合教育の本質とは、学生が患者の診察時に各専門領域(~ology)を個別に扱うのではなく、統合的に考えられるようになることにあります。この定義を常に念頭に置くことが重要です。
本シンポジウムでは、日本医学教育学会「統合教育委員会」による企画のもと、日本国内で比較的早期に統合教育を導入している関西医科大学医学部、秋田大学医学部、および昭和大学医学部の実践例を紹介し、最後にアメリカにおける現状についても触れ、医学教育学会の会員の皆様に有益な情報を提供できることを目指します。
座 長:泉 美貴(昭和大学医学部医学教育学講座)
小林 直人(愛媛大学医学部大学院医学系研究科医学専攻医学教育学講座)
OS-13-1
入学Day1からの初年次胸痛臨床推論・医療面接OSCEではじまる6年一貫した統合教育の意識づけ
長谷川 仁志(秋田大学)
OS-13-2
昭和大学医学部の新カリキュラムにおける水平・垂直統合について~HからZへそして「ん」へ~
鈴木 慎太郎(昭和大学医学部医学教育学講座)
OS-13-3
なぜ統合教育なのかーアメリカにおける統合医学教育から学ぶ
赤津 晴子(国際医療福祉大学)
OS-13-4
関西医科大学における統合型教育の導入と課題
西屋 克己(関西医科大学教育センター)
オンデマンドシンポジウム14/On-demand Symposium 14
Youは何しに大学院へ?
What brings you to enter Grad school
国内のみならず海外の医学教育・医療者教育学の大学院に入学する者も増えている。
医学教育・医療者教育に興味を持ち、大学院に入学し研究・学修する者は増えているが、これまではそういった大学院生同士のつながりの場はなかった。
「修士課程と博士課程の違いとは?」「医学教育・医療者教育関連の研究をしていて困ること」「他の教室ではどうしてるの?」「医療者教育の研究をしてみたいけど、どこに相談したら」「どこの大学はどういうことをしているの?」といった悩みや現状を共有し、今後大学院進学を検討している方の参加を促すことにより、コミュニティ形成とピアラーニングを促進したい。
本シンポジウムでは現在医学教育・医療者教育系の大学院に通学している、または今後大学院入学を検討している者を対象に、学会内でのコミュニティを形成することを目的とする。
本シンポジウムでは、まず本シンポジウムの目標を共有し、その後国内の博士課程の者や国内外の医療者教育学修士の者など様々な立場のシンポジストから「どうして大学院に入学しようと思ったのか」などに関してプレゼンテーションを行う。その後、このコミュニティから医学教育学会にもたらせる効果について議論を深めたうえで、質疑応答を行う。
現役の国内の博士課程所属の大学院生はもとより、国内外の医療者教育学講座に通学している者の話を踏まえて日本の医学教育関連の大学院生自身の成長と後輩の育成につながることを期待する。
座 長:小杉 俊介(九州大学大学院医学系学府医学教育学講座/飯塚記念病院)
鈴木 真紀(津和野共存病院/自治医科大学大学院 医学研究科 医学教育学専攻)
OS-14-1
Youは何をしに大学院へ?
大城 剛志(昭和大学医学部医学教育学講座)
木戸 敏喜(富山大学附属病院 第一内科/富山大学 学術研究部医学系 医学教育学講座)
OS-14-2
Youは何しに大学院へ?
安原 大生(岐阜大学大学院医学系研究科医療者教育学専攻修士課程)
OS-14-3
医療者教育学の探求:国外修士課程から国内博士課程への進学とその意義
大坪 里織(海老名総合病院)
OS-14-4
博士課程進学の契機と今後の展望-医療者教育と看護学の融合を目指して-
上原 明子(山梨大学大学院医工農学総合教育部博士課程)
太田 雄馬(東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科/自治医科大学大学院 医学研究科 医学教育学専攻)
オンデマンドシンポジウム15/On-demand Symposium 15
医学生・医療系学生のインクルージョンとインクルージョンの医学教育
Inclusion of medical students and medical education of inclusion
座 長:武田 裕子(順天堂大学医学部・医学教育研究室)
笠井 清登(東京大学大学院医学系研究科医学のダイバーシティ教育研究センター)
OS-15-1
日本の医学部における障害学生支援の現状と課題~2024年文科省WS事前アンケートの結果から~
瀬戸山 陽子(東京医科大学)
OS-15-2
医学部におけるDEI教育の実践と課題
里村 嘉弘(東京大学医学系研究科 医学のダイバーシティ教育研究センター)
OS-15-3
障害のある医療学生のインクルージョンに向けた医学・医療の組織変革
熊谷 晋一郎(東京大学先端科学技術研究センター)
OS-15-4
アンプロフェッショナルな行動の評価とインクルージョン
錦織 宏(名古屋大学大学院医学系研究科総合医学教育センター)
オンデマンドシンポジウム16/On-demand Symposium 16
XRシミュレーション教育実践に関する分野横断研究の現在と将来展望
Cross-disciplinary collaboration and future prospects in XR simulation education practice
2019年より約4年間続いたCOVID-19パンデミックは、高等教育機関におけるシミュレーション教育と遠隔教育の急速な普及をもたらした。XRシミュレータの最大の利点として、地理的、空間的、時間的制約からの解放が挙げられる。学生が臨床実習で見学することの少ない場面であっても、全員が公平に同じ内容の教育を受けられるようになった。
文科省は2021年4月、各大学に「対面授業の一部として半分以下の時間をオンラインで実施する場合は対面授業と見なし、オンライン授業の上限60単位に含めなくてもよい」という趣旨の通知を出した。これにより、学生がボランティアやアルバイトなどの社会活動と学業を両立する機会を提供し、短期留学を目指すなど柔軟なスケジュールを学習者が自己決定できるようになった。
本セッションは、データサイエンスを積極的に活用した教育を実施している大学より最新の分野横断共同研究の実際をご紹介いただくとともに、工学研究者の立場からシミュレーション教育に対する期待や、新人を受け入れる病院管理者の立場から、クリニカルシミュレーションセンター運営に関する知見についてご講演いただき、今後の課題と将来展望について検討する。
- 座 長:
- 村上 壮一(北海道大学大学院医学研究院 消化器外科学教室Ⅱ、先端医療技術教育研究開発センター)
コリー 紀代(北海道大学大学院保健科学研究院)
OS-16-1
情報工学の視点から考えるVR教育 - データ駆動型シミュレーションの可能性
湯田 恵美(三重大学)
OS-16-2
仮想的に生体反応を再現する呼吸器ケアXRシミュレータの開発と医療安全教育への展開
二宮 伸治(広島国際大学)
OS-16-3
情報工学技術を用いた手術教育:技術の見える化を目指した腹腔鏡手術トレーニングと遠隔手術指導の紹介
安部 崇重(北海道大学大学院医学研究院腎泌尿器外科)
OS-16-4
最近のデジタルトランスフォーメーション (DX)がもたらす医療環境について
宮永 喜一(公立千歳科学技術大学)
OS-16-5
シミュレーションセンターの中核拠点化への道程
栗栖 薫((独)労働者健康安全機構 中国労災病院)
オンデマンドシンポジウム17/On-demand Symposium 17
医学教育・総合診療・社会医学のトリアッド:人材育成と研究の推進
Triad of medical education, general medicine, and social medicine- human resource development and research
また、上記の議論に対して、社会医学・公衆衛生学、医学教育について、政府の立場から俯瞰し、今後の在り方を考察している堀岡伸彦先生(文部科学省 高等教育局 医学教育課 企画官)からも特別発言を頂き、議論する。
座 長:今中 雄一(社会医学系専門医協会)
錦織 宏(日本医学教育学会)
特別発言:堀岡 伸彦(文部科学省高等教育局 医学教育課 企画官)
OS-17-1
医学生はいつ社会の一員となるのか:地域理解と公共性を育む教育実践
松井 善典(浅井東診療所)
OS-17-2
総合内科・総合診療における人材育成と教育の推進 米国内科学会日本支部の活動
北野 夕佳(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院)
OS-17-3
社会医学・公衆衛生学領域の専門医のキャリア形成
和田 裕雄(社会医学系専門医協会)
オンデマンドシンポジウム18/On-demand Symposium 18
デジタルツイン時代の医学教育
Medical education in the digital twin age.
本シンポジウムでは、「デジタルツイン時代の医学教育」をテーマに、最新の教育手法や技術を活用した取り組みを紹介し、その可能性と課題について議論します。鹿島田らは、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を用いた360度VR教材を活用した診療技能教育の実践について発表します。VR技術を用いることで、学生は臨床現場を仮想的に体験しながら、診療技能を反復的に学ぶことが可能となります。次に、岡本らは、3D裸眼立体視ディスプレイを用いた解剖学実習の取り組みを紹介します。この技術により、学生は解剖学的構造を立体的に視覚化し、より深い理解を得ることが期待されます。さらに、伊藤らは、メタバース環境を活用し、教師と学生がアバターとして仮想空間に入り込み、共同で解剖学実習を行う方法について発表します。これにより、インタラクティブな教育が可能となり、学生の主体的な学びを促進します。最後に、角らは、大規模言語モデル(LLM)を用いた医療面接AIの開発について報告します。このAIは、学生が医療面接の練習を行う際に、患者役としてリアルな応答を提供し、実践的なスキルの向上を支援します。本シンポジウムを通じて、デジタルツイン技術を活用した医学教育の新たな可能性を探り、未来の医療教育の在り方について議論を深めます。
座 長:山脇 正永(東京科学大学臨床医学教育開発学分野)
角 勇樹(東京科学大学生命情報応用学分野)
OS-18-1
360度VR教材を活用した診療技能の教育
鹿島田 彩子(東京科学大学臨床医学教育開発学)
OS-18-2
3D裸眼立体視ディスプレイを用いた解剖学実習の取り組み
岡本 健太郎(東京科学大学 小児外科)
OS-18-3
臓器3Dモデルが配置されたVR空間に教師と学生がアバターとなって入り込んで行うメタバース解剖教育
伊藤 卓(東京科学大学)
OS-18-4
大規模言語モデル(LLM)を用いた医療面接AIの開発
角 勇樹(東京科学大学)
オンデマンドシンポジウム19/On-demand Symposium 19
脱出ゲームを用いた医療者教育の現状:事例から考える課題と展望
The Current State of Healthcare Professional Education Using Escape Room Games-Challenges and Future Prospects Based on Case Studies
本シンポジウムでは、「脱出ゲームを用いた医療者教育の現状:事例共有、課題と展望」をテーマに、ERを用いた医療者教育に関する情報共有を行う。第1演者は、ERを用いた医療者教育の全体像を紹介する。特にコロナ禍を経て発展したICTを活用したERの運用方法、ERを教育手法として活用する際の学修目標や評価方法について文献をもとに解説する。第2・第3・第4演者は、それぞれの領域で実施した具体的な教育実践事例を共有する。事例は医学だけでなく、看護学や薬学など多領域にわたる取り組みを含むものとする。事例共有後の総合討論では、各事例における課題や今後の展望について議論を行う。また、ゲーム活用教育を設計・運用する際の利点や注意点についても取り上げる。
2023年に開催された第56回日本医学教育学会大会では、関連するシンポジウムにおいて、ERだけでなく、他のゲーム手法を活用した教育の設計・運用における利点や注意点が話題となった。これらの内容も踏まえつつ、多領域の視点からERを活用した教育の課題をどのように解決できるかについて具体的な意見交換を行う。ゲーム活用教育、特にERを活用した教育に対して興味・関心のある医療者教育者にとって、知見を深めるための場になれば幸いである。
座 長:淺田 義和(自治医科大学)
村岡 千種(藤田医科大学)
OS-19-1
脱出ゲームを用いた医療者教育
村岡 千種(藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科)
OS-19-2
医学部における脱出ゲーム活用教育事例:コロナ前後の変遷とICT活用
淺田 義和(自治医科大学)
OS-19-3
解剖生理学の苦手意識を持つ看護学生の学習意欲向上を目指した脱出ゲーム型解剖模型学習
古堅 裕章(九州看護福祉大学)
OS-19-4
薬学生を対象としたコミュニケーション科目における脱出ゲームの活用
長谷川 仁美(昭和薬科大学)
オンデマンドシンポジウム20/On-demand Symposium 20
生成AI時代における論文指導 - 教員に求められるAIリテラシー
Thesis Guidance in the Age of Generative Artificial Intelligence - Required AI Literacy for Faculty
座 長:香田 将英(岡山大学学術研究院医歯薬学域地域医療共育推進オフィス)
OS-20-1
論文執筆における生成AIの実践的活用法
松井 健太郎(国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部)
OS-20-2
研究活動における生成AIの実践的活用法: 文献検索や学会発表等を中心に
吉田 和生(慶應義塾大学病院臨床研究推進センター )
オンデマンドシンポジウム21/On-demand Symposium 21
医療安全教育におけるNon-Technical Skills強化の新たな実践教育手法
A new approach for medical safety educational method of Non-Technical Skills
今回、海外における医学・実践教育の現状、航空会社におけるパイロット養成訓練の現状などを踏まえ、演者考案NTS 強化の新たな教育手法「KIT-Works:北野」導入の可能性や医療面接技法、臨床推論、確定診断のほか、今後、医学部・医系大学等における次世代医療人育成のための新たな実践教育手法導入の可能性について議論を重ねたい。
- 座 長:
- 北野 達也(星城大学 経営学部 健康マネジメント系 医療マネジメント分野/医療マネジメント研究室 星城大学大学院 健康マネジメント系 医療安全管理学 教授)
OS-21-1
医療安全教育におけるNon-Technical Skills強化の新たな実践教育手法
北野 達也(星城大学 経営学部 医療マネジメント分野/医療マネジメント研究室)
OS-21-2
日本の医学教育が必要とするVR教育法とLME(Learning Medicine in English)
佐野 潔(米国財団野口医学研究所 理事長、藤田医科大学医学部 家庭医学教育 特任教授)
OS-21-3
エアラインにおけるNon-technical skillの醸成及びリジリエンス強化
関谷 洋平(Aviator Science)
オンデマンドシンポジウム22/On-demand Symposium 22
共感的理解の先にある反抑圧実践:権力勾配を超える共同創造
Anti-oppressive practices beyond empathy
医療者においても、共感力が欠如していると抑うつや燃えつきを生じやすく、患者診療に負の影響をもたらす。しかし、医療現場では、共感することが難しい患者の態度や行動に遭遇し、それが陰性感情を惹起することがある。一方、その背景にある患者の境遇や置かれている状況から構造的不公正や格差を認識すると、むしろそうした「困った患者」ほど困っていると気づくことができる。生きにくさを経験している人たちの状況を、「当事者の立場から理解する」ことが求められるのであるが、それは可能であろうか。
当事者は、集団の属性に付されたスティグマを負い、さらに文化的、構造的、複合的な抑圧下に置かれやすい。そのため、社会福祉学では当事者と専門家との間の権威勾配を意識する「反抑圧的実践(anti-oppressive practice)」が進められている。医学教育においても、医療サービスの利用者とフラットな立場で協働して策定することを「共同創造(Co-Production)」という。「共同創造」の遂行には、教育者も多数派の特権に自覚的になり、歴史的な経緯も理解する必要がある。
本シンポジウムでは、マイノリティ性を有する個人、家族、コミュニティやグループが医療機関で遭遇しがちな困難・抑圧について紹介する。顕在化している問題だけでなく、構造的な要因を視野に入れて、その背景について考察する。そこから、多様性・包摂性が進む医学教育において、学修者、教育者それぞれの心理的安全性を確保しながら、どのように学びを促進するか討議する。
座 長:武田 裕子(順天堂大学大学院医学研究科)
OS-22-1
LGBTQと医療から考える構造的差別
吉田 絵理子(川崎医療生活協同組合 川崎協同病院)
OS-22-2
トランスジェンダーが医療機関で遭遇する困難:患者の視点
宮田 瑠珂(順天堂大学)
OS-22-3
障がい者に向けられるまなざし、交差する困難さと協働の可能性
岩隈 美穂(京都大学 医学コミュニケーション学)
OS-22-4
手話言語話者であるろう者が医療機関で遭遇する困難
今川 竜二(東大阪生協病院)
OS-22-5
医療人育成における反抑圧実践とSDH教育
武田 裕子(順天堂大学大学院医学研究科)
ワークショップ1/Workshop 1
7月24日(木)17:00~18:30
会場:第5会場(秋田市文化創造館 2F スタジオA1)
発達障害の特性のある学習者と非認知能力の教育-共感について事例を通して考える-
Educating Non-Cognitive Skills to Learners with Developmental Disorders -Reflecting on Empathy Through Case Studies-
- 座 長:
- 川上 ちひろ(岐阜大学医学教育開発研究センター/ 岐阜大学大学院医学系研究科医療者教育学専攻)
木村 武司(名古屋大学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター) - 演 者:
- 森下 真理子(京都大学医学部附属病院 医療安全管理部)
- ファシリテーター:
佐野 樹(三重県立こころの医療センター/名古屋大学大学院医学研究科総合医学教育センター)
堀田 亮(岐阜大学保健管理センター/岐阜大学医学教育開発研究センター)
藤江 里衣子(藤田医科大学医学部医療コミュニケーション)
ワークショップ2/Workshop 2
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月24日(木)17:00~18:30
会場:第6会場(秋田市文化創造館 2F スタジオB)
医療現場の「わかりあえない」をNVC(非暴力コミュニケーション)で越える
Connect before Correct - Introducing NVC to Healthcare Professionals
- 座 長:
- 横山 彰三(宮崎大学医学部)
- 演 者:
- 横山 彰三(宮崎大学医学部)
益田 真樹(済生会横浜市東部病院) - ファシリテーター:
横山 彰三(宮崎大学医学部)
益田 真樹(済生会横浜市東部病院)
ワークショップ3/Workshop 3
事前登録
当日参加OK
7月24日(木)17:00~18:30
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
人口減少社会で医学生/研修医がキャリアの成功を目指すための科学的な授業
Evidence-based education for career success
本WSでは、医学生および研修医が自身のキャリアを科学的かつ戦略的に設計する基盤を築く方法を学びます。キャリアコンピテンシーの向上を基に、適職を見つけるための具体的なステップを180分で実施できるようなコンテンツを提供します。
まずキャリアの成功の定義と、成功に必要な能力やリソースについて解説します。ここでキャリアを主体的にマネージできる力の概要を把握します。
次にキャリアプランニングの手法と自己分析の重要性を解説します。心理学的アプローチや自己評価ツールを用いて、自身の価値観や興味を明確にし、短期および長期の目標設定を理解します。これにより、計画的なキャリア構築が可能になります。
最後に、キャリア選択に役立つ情報収集の方法とネットワーキングの重要性を学びます。効果的なネットワーキングの方法や、実習やインターンシップでの情報収集法を紹介し、意思決定プロセスの基本概念とその重要性についても示します。
本WSは、医学教育モデル・コア・カリキュラムの「キャリア開発」および医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針に準拠しました。受講者は、自身の職業観を涵養しながら主体的にキャリアを構築し、自らの心身を大切にする方法を学びます。これにより、将来のの活躍に向けた第一歩を踏み出すことを目指します。
特徴:
本来180分程度で提供するコンテンツを90分間のワークショップで行うため、反転授業形式で実施し、レクチャーは事前動画で提供します。当日はキャリアワーク15分×5つを実施します。
キャリアコンサルタントの国家資格をもつ医学教育者3名と若手グループらとのコラボ企画です。
- 座 長:
- 賀來 敦(洛陽病院)
- 演 者:
- 柿崎 真沙子(名古屋市立大学)
川口 満理奈(岡山大学病院)
種村 文孝(東洋学園大学)
渡部 健(秋田大学医学部附属病院)
ワークショップ4/Workshop 4
事前登録
当日参加OK
7月24日(木)17:00~18:30
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
大学全入時代に備える!動機付けが乏しい医療系学生の背景にあるものとは? ― 施設も職種も越えて学生をその気にさせる仕掛けづくりを共有しよう ―
What's behind the lack of motivation among healthcare students in the upcoming full university enrollment era.
気がかりなのは、今後このような学生が増えるかもしれない状況が迫っていることにある。2024年、大学の入学定員と受験者数の差は、僅か1.1万人となった。2035年には、真の大学全入時代が訪れると予測されている。その職業に対して、それほど強い志を持たない医療系学生が今より多く入学してくる可能性があるのだ。そのような学生らに対して、教員としてどのように関わることができるのか、学生を動機付ける授業や演習、実習の仕掛けづくり、カリキュラム全体の設計を考えていく必要性が求められている。
近年、医療系学生の燃え尽き症候群や留年が問題となっている。医学生においては、入学後早期における動機付けの低下が報告されており、また動機付けの低下が燃え尽き症候群や学業不振のリスクであることも示唆されている。看護学生においては、学業不振者に欠席や遅刻、居眠りなどの授業態度が良くないことが明らかとなっており、動機付けが乏しい学生らに対する取り組みが喫緊の課題となっている。
これらの問題に取り組むべく、医療系学生に対する動機付けや学習意欲に関する研究は盛んになされているが、個々の学生が入学時の時点で動機付けがすでに曖昧であったか、入学後に動機付けが弱くなっていったかなどは解明されていない部分が多い。
本ワークショップでは、各職種の教育者が集い、動機付けが乏しいと認識する学生を取り巻く問題として、どのような要因が背景にあるのか、また実際にどのような取り組みを行なっているのかについて、互いの実践や経験を共有することを目的としている。また、動機付けの乏しい医療系学生のケースカンファレンスを行い、その分析ならびに対策を検討することで、医療系学生を支援するカリキュラム構築の足掛かりを探る。
- 企画代表者:
熊木 天児(愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター)- 演 者:
- 菊池 明日香(愛媛大学医学部附属病院 総合診療科)
- ファシリテーター:
内藤 知佐子(愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター)
田坂 祐一(就実大学薬学部)
ワークショップ5/Workshop 5
当日参加OK
7月24日(木)17:00~18:30
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
日本医学教育学会大会プログラムの挑戦―次世代の医学・医療を拓く医療者教育へ
Challenges of the Japanese Society for Medical Education Program/Shaping Health Professional Education for the Next Generation
1)大会プログラムの視点:大会間でのネットワーク構築/学会抄録査読プロセスのマニュアル化と医学教育専門家/大会準備・運営スケジュールのマニュアル作成
2)財務の視点:学術大会収支を安定化と課題・改善計画/財務内容の可視化と継続的/大会収支の動向分析/収支項目の統一化
3)ICT の視点:学術大会の参加者データの収集と今後のプログラム改善を目的とした活用/オンラインやオンデマンドなどのICTの有効活用のための方略/今後のさらなるICT活用
4)国際化の視点:医学教育の国際化/今後の望ましい大会国際化のあり方と展望
- 座 長:
- 錦織 宏(名古屋大学)
鋪野 紀好(千葉大学) - 演 者:
- 長谷川 仁志(秋田大学)
田中 淳一(東北大学)
淺田 義和(自治医科大学)
矢野 晴美(国際医療福祉大学) - ファシリテーター:
堀田 晶子(帝京大学)
岸 美紀子(群馬大学)
及川 沙耶佳(秋田大学)
高村 昭輝(富山大学)
大久保 由美子(帝京大学)
橋本 忠幸(ブリグハムアンドウィメンズホスピタル)
ワークショップ6/Workshop 6
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)9:00~10:30
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
模擬患者(SP)のフィードバック力を磨く!フィードバックへの理解を深め、実践的トレーニングを体験しよう!
Improve your simulated patient feedback skills. Deepen your understanding of feedback and experience practical training.
- 座 長:
- 阿部 恵子(金城学院大学看護学部看護学科)
後藤 道子(名古屋市立大学大学院医学研究科 地域医療学寄附講座) - 演 者:
- 井上 千鹿子(日本医科大学医学教育センター)
早川 佳穂(岐阜大学医学教育開発研究センター)
吉田 登志子(日本SP協会)
ワークショップ7/Workshop 7
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)9:00~10:30
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
障害のある医師の働く現場/働き方から考える ~車椅子を使用する医師の体験を通じて~
Workplaces and work styles of doctors with disabilities -Observations from a physician who uses a wheelchair
2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、私立を含め医学部のあるすべての大学で障害のある医学生が求めた場合の合理的配慮が義務化された。障害のある医学生に関する網羅的なデータはないが、例えば2023年6月~2024年1月までの医学の共用試験における合理的配慮の申請数は、98件に上る(藤田ら, 2024)。米国では、自らに障害があると回答した医学生の割合は全体の11%であり、これらのデータから、様々な調整を行いながら学び、医師を目指す障害のある医学生は、日本にも一定数いると推測される。
しかし学生時代に障害学生支援室等と調整を行って医師を目指して学んだ学生も、医師として就職する際には、自らのことを知っている人ばかりではない新しい環境に身を置くことになる。医療分野以外の障害学生支援においても、在学中から就職活動、その後の就労までのシームレスな支援・調整は今も多くの課題が残る。医療現場においても同様に様々な障壁があることが想像されるが、障害のある医学生が医師として就職することにおいて、どのような課題が存在するかは明らかにされていない。また、様々な課題をどのように整理し、どこがどのように取り組む必要があるかは、ほとんど議論されてきていない。このテーマは、現在医学部で学ぶ障害のある学生が就職する際に多かれ少なかれ表面化する問題であり、早急に取り組むべきものと言える。
企画者は、昨年の本学会におけるWSで、車椅子を使用する医師に学生時代を振り返ってもらうWSを行った。今回は続編として、学生から医師への移行期や、医師として働くことにおけるニーズや環境調整、社会に対する要望等に焦点を当て、当事者の体験をもとに課題の整理と今後に向けたあり方を考える機会としたい。想定する参加者は、現在、障害のある医学生支援にかかわっている教職員や、障害のある医師と共に働くことが想定されるすべての人とする。
- 座 長:
- 瀬戸山 陽子(東京医科大学)
- 演 者:
- 瀧澤 晃司(横浜市立大学医学部リハビリテーション科学教室)
- ファシリテーター:
田中 邦彦(元長崎大学)
Peter Bernick(長崎大学)
青木 昭子(新生病院)
川上 ちひろ(岐阜大学)
堀田 亮(岐阜大学)
ワークショップ8/Workshop 8
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)9:00~10:30
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
【学会誌編集委員会企画】 査読者に学ぶ!よい“医学教育論文”の書き方ワークショップ!
Develop your skills in writing and evaluating an informative articles in hearth professions education as a researcher and a reviewer
医学教育研究の分野では、内容や手法の多様性から査読プロセスを具体的に学ぶ機会が限られているのが現状です。本ワークショップでは、研究者としての経験が豊富なベテランから初心者まで、幅広い層を対象に、体験学修を通じて具体的な査読プロセスを学びます。参加者は事前に、実際に『医学教育』誌に投稿され掲載されたサンプル論文の査読コメントを作成し、当日はグループ討論を通じて査読コメントのポイントを学びます。その後、実際の査読コメントと修正過程を確認し、投稿論文が掲載に向けて完成していく過程を概観します。また、新しい投稿規定と編集方針の説明を通じて、最新の論文執筆の基準を共有します。
本ワークショップは、査読プロセスの理解を深めるとともに、より良い論文を執筆するための実践的な知識を得る貴重な機会です。研究者としての成長を目指す皆様のための企画を、何卒よろしくお願い申し上げます。
- 座 長:
- 土屋 静馬(昭和大学)
武田 裕子(順天堂大学) - 演 者:
- 前野 貴美(筑波大学)
西城 卓也(岐阜大学)
八木 街子(自治医科大学) - ファシリテーター:
錦織 宏(名古屋大学)
松山 泰(自治医科大学)
今福 輪太郎(岐阜大学)
高村 昭輝(富山大学)
椎橋 実智男(埼玉医科大学)
鶴田 潤(東京科学大学)
中村 真理子(東京慈恵会医科大学)
菊川 誠(九州大学)
片岡 裕貴(京都民医連あすかい病院)
尾原 晴雄(沖縄県立中部病院)
長崎 一哉(名古屋市立大学)
宮地 由佳(名古屋大学)
野村 理(岐阜大学)
ワークショップ9/Workshop 9
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)9:00~10:30
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
医学教育を最近始めた人を応援するワークショップ ~All for Novice Medical Educators, All Together~
Workshop for beginners of medical education -All for Novice Medical educator All Together-
医療者は教えられるよりも教える期間の方が圧倒的に長いにもかかわらず、それまで系統立てられた「教育についての教育」を受ける機会は、ほとんどない。そのため、自身が受けた教育をもとに後進を教えていると、「本当にこの方法でいいのか?」、「ちゃんと教育できているのか?」、「どう教えたらよいかわからない」、「自分自身がまだ教育を受けてる側なのに教えてもいいのか・・・」など悩みもある。近年は、オンラインツール等が急速に普及し、デジタル技術の導入や管理等も対応せざるを得なくなってきた。また、「教育の業務を周りに手伝ってくれる人がいなくて大変だ」、「時間外労働が制限され教育に時間なんてとれない」、「教育だけやっていたら今後のキャリアがどうなるのか不安」、など教育に関わる悩みは尽きない。
本ワークショップでは、各演者に「私は医学教育になぜ関わるようになったのか」、「いま何にもがいているのか」、「今後どうなってしまうのか」、など、医学教育初学者の時代を中心に、これまでの道のりを自己開示していただく。そして参加者にもグループディスカッションを通じ、医学教育に携わることになった自身の過去・現実・未来について言語化していただきたい。演者、ファシリテーターとともに、今後の医学教育に携わるモチベーションとなる時間を過ごし、今後の医学教育に携わっていくための目標を立てていただける機会としてご参加いただきたい。「今回初めて医学教育学会に参加する」、「大会の演題抄録を読んでも難しい単語が多くて意味が分からない」、「来ては見たものの周りに知っている人がいなくて心細い」、そんな方には、ぜひ今回で3回目になる本ワークショップにご参加いただきたい。
- 座 長:
- 木村 友和(名古屋大学)
森本 勝彦(奈良県西和医療センター) - 演 者:
- 貫戸 明子(近畿大学)
佐藤 泰征(北海道大学)
細川 幸希(昭和大学) - ファシリテーター:
尾上 剛史(名古屋大学)
鈴木 創(立川相互病院 )
村松 友佳子(名古屋大学)
與那覇 忠博(社会医療法人敬愛会 中頭病院)
小西 泰介(獨協医科大学)
三浦 聖子(金沢医科大学 / マーストリヒト大学)
宮本 真豪(昭和大学藤が丘病院)
谷口 大介(浦添総合病院)
鳥居 暁子(慶応義塾大学)
ワークショップ10/Workshop 10
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)10:50~12:20
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
医療者教育者のウェルビーイング:自分と学習者を支える対話の場
Cultivating Well-being Through Dialogue -Supporting Ourselves and Our Learners as Healthcare Educators-
本ワークショップでは、**「ウェルビーイング・ダイアログ・カード®」** を活用し、参加者同士の対話を通じて以下の2つの目的を達成することを目指します。
① 医療者教育者として、自分自身のウェルビーイングを大切にし、高めるための具体的な方法を見出す。
② 学習者がウェルビーイングを大切にする意識や行動を育むための教育方法を探る。
参加者は「ウェルビーイング・ダイアログ・カード®」を用いた対話を行い、自身の経験や視点を共有します。共通の課題や可能性を探りながら、具体的なアイデアを得ることで、日常の実践に活かせる知見を持ち帰ることを目指します。本ワークショップでは「幸せの4因子」(前野ら)や心理的安全性の概念も取り入れながら、より深い対話を促進します。
- 座 長:
- 北原 佑介(たのはたラボ)
- 演 者:
- 北原 佑介(たのはたラボ)
- ファシリテーター:
戸田 合香(Bridge of voice)
照屋 周造(沖縄県立中部病院)
川越 美咲(医療法人社団やまと)
森永 聡美(宝塚大学 看護学部)
馬場 華奈己(大阪公立大学医学部附属病院)
井上 和興(大山町国民健康保険大山診療所)
ワークショップ11/Workshop 11
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)10:50~12:20
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
実践!漢方の診察方法の基本をロールプレイで体験しよう!
Simulation Training in Kampol Medical Examination Methods
漢方医学の診察法は卒後に学ぶ機会が少ないため、ぜひ体験してみたいという方も多いのではないでしょうか。そこで、本企画では漢方医学の診察法を模擬患者とのロールプレイを通して医学教育に携わる多くの医療者に漢方診療を体験してもらいたいと考えています。
今回私たちは、漢方の学び方について、漢方の問診、舌所見、模擬患者に対して腹部診察を行うなどのシミュレーショントレーニングで漢方を学ぶワークショップを企画しました。漢方初心者や医師以外でも参加可能で多職種の人に参加いただけるプログラムであり、シミュレーショントレーニングを通して、難しいイメージのある漢方を初学者でもわかりやすく、学びやすいワークショップです。
本ワークショップに参加することで漢方と医学教育の融合した新たな学習の世界を体験してもらいたいです。
本ワークショップは《日本東洋医学会学術委員会による共同企画》です。
- ファシリテーター:
網谷 真理恵(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野 離島へき地医療人育成センター)
高山 真(東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学共同研究講座)
吉野 鉄大(慶應義塾大学医学部漢方医学センター)
堀場 裕子(慶應義塾大学医学部漢方医学センター)
佐藤 浩子(群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学講座)
野上 達也(東海大学医学部医学科専門診療学系漢方医学領域)
ワークショップ12/Workshop 12
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)10:50~12:20
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
職種共通の日本版医療安全コンピテンシーフレームワークを作ろう(医学教育部門編)
Developing a patient safety competency framework in Japan - educators' perspective
- 座 長:
- 清水 郁夫(千葉大学大学院医学教育学、千葉大学医学部附属病院医療安全管理部)
田中 和美(群馬大学医学部附属病院医療の質・安全管理部)
西村 礼子(東京医療保健大学 医療保健学部看護学科)
ワークショップ13/Workshop 13
当日参加OK
7月25日(金)10:50~12:20
会場:第8会場(にぎわい交流館AU 3F 多目的ホール)
AMEEでの発表を目指して: 日本拠点の医療教育者向けワークショップ
Aiming to Present at AMEE Workshop for Japan-based Medical Educators
This workshop intends to provide a forum within the JSME 2025 Conference for Japan-based medical educators whose answer to the above questions is “Yes” (or “Maybe”).
Format of presentations by Japan-based medical educators
・8-minute presentation in English using slides (PowerPoint, Keynote, etc.)
・2-minute general feedback from audience
・5-minute Q&A session
Intended outcomes: By the end of this workshop, participants will be able to
・Feel more confident about giving an academic presentation in English
・Interact more smoothly with international (English-speaking) conference participants
・Apply specific techniques to deliver a more powerful presentation
- 座 長:
- FLORESCU Mihail Cosmin (筑波大学)
松山 泰(自治医科大学) - 演 者:
- FLORESCU Mihail Cosmin (筑波大学)
鷺島 史歩(秋田大学医学部4年次)
山本 幸近(飯塚病院、総合診療科/福岡県飯塚市)
大塚 勇輝(岡山大学病院 総合内科・総合診療科)
林 幹雄(関西医科大学教育センター) - ファシリテーター:
Raoul BREUGELMANS(関西医科大学)
今福 輪太郎(岐阜大学)
野呂瀬 崇彦(ならは薬局)
三浦 聖子(金沢医科大学、マーストリヒト大学)
徳増 一樹(岡山大学)
ワークショップ14/Workshop 14
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)10:50~12:20
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
Co-creation(学習者と共に創る教育)で実現する学びのチームビルディング
Team building for learning enabled by co-creation
Co-creationは、学びの改善における「学習者と教育者の密接な協働」であり「学習者の価値観を歓迎し教育(デザイン)のプロセスに学習者が積極的に関与すること」と定義されています。Co-creationでは教育理論としてポジショニング理論、心理的安全性、自己決定理論の3つを利用します。ポジショニング理論は、人は会話の中で自己と他者の位置づけを行い、それが他者との関係の中での自己のアイデンティティ形成につながると考える、チームビルディングと関わる理論です。Co-creationでは、教育者が教え学習者が学ぶという上下関係のあるアイデンティティや役割から、教育者が“学び”学習者が“教える”という関係のアイデンティティや役割へと相互の位置づけの再構築を行い、それをCo-creationの根幹となる共創的な対話の前提とします。この前提に支えられた教育者と学習者という学びのチームとしての心理的安全性をもとに、学習者の意欲を引き出す自己決定理論を援用しながら、共創的な対話を通じて教育を改善していくというクリエイティブな学びをこのチームで共に創ります。この過程をロールプレイで体験することで、メンバー内に上下関係がある中でのチームビルディングを教育者と学習者という学びのチームでの実践として学ぶことができます。
本セッションではCo-creationの概念を説明したのちに実践事例を紹介し、そのあと実際に参加者にCo-creationについてロールプレイを通じて体験していただく予定です。そして学会終了後に参加者が所属施設で実際にCo-creationを導入し、学習者を含む学びのチームがよりクリエイティブなチームに成長し、よりよい教育組織となることを目指します。
- 座 長:
- 高橋 慶(医療生協さいたま 川口診療所)
- 演 者:
- 山口 佳子(東京医科大学病院 総合診療科)
髙橋 美裕希(岐阜大学 地域共創型飛騨高山医療者教育学講座)
安田 恵(福島県立医科大学医療人育成・支援センター)
ワークショップ15/Workshop 15
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)16:30~18:00
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
まずはココカラ!「主体的な学び」を深める!
Starting point. Deepen your Self-Directed Learning
ワークショップでは, はじめに「成人学習理論」や関連する代表的な教育理論にも触れながら、講義形式で「自己主導型学習とは何か?」, 「自己主導型学習を促す段階的なアプローチとは?」について学びます。
次に, ケースシナリオについて 「自己主導型学習を促す段階的なアプローチ」を用いながら、学習や教育をどのように改善点したらよいか、またその解決方法について参加者の皆さんとディスカッションしながら学びを深めていきます。
最後に、参加者の皆さんとともに、学ぶものとして、あるいは教えるものとしての気づきや、明日から実践できる取り組みは何かなどについて共有していただきながら、このワークショップの学びをまとめます。
このワークショップが終わった時には、「学ぶ」「教える」という日常に、希望の光が差し込むはずです。学会でどんな発表を聞いて、どんなワークショップに参加するべきか迷われている方も、自分にとっての具体的なテーマが見つかるかもしれません!これから自分の学習をレベルアップしたい方や、教育に興味を持ち始めた方、もう1段階学習や教育のスキルアップしたい方など、教育の基本を学びたい方であればどなたでも大歓迎です。
まずはココカラ!「主体的な学び」について、皆さんと深めていきましょう!
- 座 長:
- 利根川 尚也(国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 教育研修センター)
田原 卓矢(昭和医科大学藤が丘病院 臨床工学室) - 演 者:
- 山口 佳子(東京医科大学病院 総合診療科)
吉澤 悠喜(赤穂中央病院 リハビリテーション部) - ファシリテーター:
横尾 英孝(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 医歯学教育開発センター)
高橋 美裕希(岐阜大学大学院医学系研究科寄附講座地域共創型飛騨高山医療者教育学講座)
ワークショップ16/Workshop 16
定員あり
事前登録
7月25日(金)16:30~18:00
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
学習者の「恥」に配慮した医学教育の試み~感情を身体感覚からとらえる~
An attempt at medical education that takes into consideration the shame of the learner -capturing emotions from somatic sensation-
近年欧米では、医学教育における学習者の感情の中で、「恥(shame)」についての研究が進んでいる。教育課程における恥の体験は、学習者の意欲や共感性の低下と関連しており、教育トラウマとなる危険性が指摘されている。
「恥」に代表される感情に配慮することは、心理的安全性の高い教育環境を整える上でも重要であり、学習者の成長にとっても、医師自身のセルフケアとしても有益であると考える。
そこで今回我々は、学習者の「恥」という感情に注目し、教育者、指導者側が「恥」についての感受性を持ち、その扱い方を学ぶことを目的としたワークショップを企画することとした。企画者は、2024年度シンポジウム:グラフィック・メディスン~医学教育と「恥」を考える~座長の小比賀と、医師の感情労働について社会学の視点からも研究している精神科医の川又を中心としたメンバーである。
本ワークショップでは、学習者-指導者間で生じやすい「恥」を広義のトラウマ体験と捉え、トラウマインフォームドケアの考え方を援用した関わり方を提案する。参加者には、恥という感情を自律神経の活動とそれに伴う身体感覚として体験してもらう。本ワークショップを通じて、参加者に安全にその経験をしてもらうことで、今後の教育活動を行っていくうえでの一助になればと考えている。
- 座 長:
- 小比賀 美香子(岡山大学学術研究院医歯薬学域総合内科学)
- 演 者:
- 角⽥ みすゞ(ベル相談室・臨床心理士/公認心理師)
川⼜ 実紀(大⾕地病院・精神科)
中村 ⾹代子(自治医科大学附属病院総合診療内科)
ワークショップ17/Workshop 17
7月25日(金)16:30~18:00
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
生涯キャリアヒストリー法ファシリテーション体験をしてみよう!
Lifelong Career History Act Facilitation Event
- 座 長:
- 貫戸 明子(近畿大学)
種村 文孝(東洋学園大学)
鳥居 暁子(慶応義塾大学) - 演 者:
- 渡邊 洋子(新潟大学)
- ファシリテーター:
三浦 聖子(金沢医科大学)
小西 泰介(獨協医科大学)
細川 幸希(昭和大学)
宮本 真豪(昭和大学)
西村 謙一(横浜市立大学)
谷口 大介(浦添総合病院)
犬塚 典子(田園調布学園大学)
池田 雅則(兵庫県立大学)
池田 法子(足利短期大学)
柏木 睦月(十文字学園女子大学)
ワークショップ18/Workshop 18
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)16:30~18:00
会場:第8会場(にぎわい交流館AU 3F 多目的ホール)
学習者のアイデンティティを形成する医学教育の新たなステージへ
A New Stage in Medical Education Fostering the Professional Identity of Learners
PIは、専門職としての価値観や信念、態度を備えた自己認識のことをいいます。つまりは、「医療者らしさ」と言い換えることもでき、「医療者として考え、行動し、感じる」ことができるようになることが医学教育の最終的な目標の一つともされています。PIの形成を促進することで、学習者は多様な価値観を理解し、倫理観や責任感の強化、自己主導型学習へと繋がることや、医療専門職としての適応力の向上など多くの利点があります。
そのため、近年ではPIの形成を意識したカリキュラムづくりが求められています。しかし、PIは、入学や入職前に培われた個人的なアイデンティティを基に、教育を含めた数多くの要因に影響を受けながら、専門職としてのアイデンティティへと発展していきます。この過程には非常に多くの要因が関与するため、どのようにカリキュラムを設計すればよいのか分からなくなってしまうことがあります。
そこで本ワークショップでは、まずPIの形成や、その影響因子について学んでいきます。そのうえで、学生や研修生のPIの形成を促進させるカリキュラム上の工夫や方略について、事例を通じて小グループで議論を行っていただきます。そして、全体で議論の内容を共有することで、PIを意識したカリキュラムづくりについてさらに考察を深めます。本ワークショップを通じて、ご自身の医学教育者としてのPIの促進にもつなげていきましょう!
- 企画代表者:
大戸 敬之(鹿児島大学病院歯科総合診療部)- 座 長:
- 岡崎 史子(新潟大学医学部医学科医学教育センター)
- 演 者:
- 三好 智子(京都大学医学研究科 医学教育・国際化推進センター)
- ファシリテーター:
舩越 拓(東京ベイ・浦安市川医療センター救急集中治療科 救急外来部門)
吉田 暁(新潟市民病院救急科)
芳野 純(帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科)
ワークショップ19/Workshop 19
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月25日(金)16:30~18:00
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
第7回医療系IR友の会ミーティング~質的データをIRに活かす
Seventh meeting of the community for institutional research in healthcare professional education - Applying qualitative data to IR
しかしながら、行動心理学的に質的データを上手く使うことは、執行部の行動変容、つまりInstitutional Effectivenessの成功に重要な意味を持つ。さらに、質的研究はリサーチクエスチョンの生成に必要な手法である(問題に関する知性)上、IR担当者がインタビューを実施することで、それ自体が自大学の教育における文脈の理解や学内での関係性の構築に寄与する(文脈に関する知性)可能性が示唆されている。つまり、IRで質的データを取り扱うことは「執行部やIR担当者のためのFaculty Development」となりえる。
そこで、今回のワークショップでは、質的データ、特に「インタビューデータ」と「アンケートの自由記載データ」について取り扱うこととする。まず、質的研究を専門とする今福輪太郎氏に、「IR分野でのインタビューデータ解析の可能性」、質的データを基にIRを実践している香田将英氏に、「質的データを使った、生成AIによる解析を用いたIR」に関するMini Lectureをそれぞれいただく。そして、質的データの取り扱いや、質的データをIR/IEに利用していく方法について議論する。本WSで、「専門的・分析的知性」をMini Lectureで習得しつつ、「問題に関する知性」と「文脈に関する知性」をディスカッションして、IRに必要な能力を高めることができれば幸いである。
*IR部門に所属されていなくても、IRに関心のある方の参加を歓迎いたします。
*本ワークショップ実施に向けて、参加者には事前アンケートを行います。
- 演 者:
- 今福 輪太郎(名古屋市立大学)
香田 将英(岡山大学) - ファシリテーター:
淺田 義和(自治医科大学)
岡田 聡志(千葉大学)
佐藤 麻紀(愛知医科大学)
椎橋 実智男(埼玉医科大学)
恒川 幸司(名古屋市立大学)
中村 真理子(東京慈恵会医科大学)
濵﨑 景子(長崎大学)
ワークショップ20/Workshop 20
7月26日(土)9:00~10:30
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
ヴァーチャルシミュレーションを用いた医療安全研修運営
Workshop for Medical Safety Session by Virtual Simulation System
急変には誰がいつ遭遇するかわかりません。しかし遭遇した時には迅速かつ適切な対応が求められます!
急変対応については各医療機関でレクチャーが行われたり、蘇生講習会が行われたりしていますが、急変に対する不安は尽きません。また実技講習会を開こうと思うとその準備に追われるのも大変です。
このワークショップでは簡単に短時間でシミュレーションを行う方法として、ヴァーチャルシミュレーションシステムの使用を提案します。
レクチャーを聴講するだけでは記憶には残りにくい、でも実技講習会は時間と人手と準備が大変・・・ヴァーチャルシミュレーションを使用すれば「実技」はトレーニングできませんが「判断」と「行動」については十分なトレーニングができます。
使用するヴァーチャルシミュレーションシステムは、自由にシナリオを設定でき、自由に画像を設定することができ、かつ画面内で生体監視モニターを表示して容体を反映させることで臨場感を感じることができます。
ワークショップではシナリオを体験するとともに、シナリオの運営についても体験することができます。後半ではその使用方法について参加者を交えてディスカッションを行う予定です。
- 座 長:
- 山畑 佳篤(京都府立医科大学)
- 演 者:
- 山畑 佳篤(京都府立医科大学)
- ファシリテーター:
山畑 佳篤(京都府立医科大学)
宮道 亮輔(自治医科大学)
望月 礼子(鹿児島大学)
ワークショップ21/Workshop 21
定員あり
事前登録
7月26日(土)9:00~10:30
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
医学教育研究の基本を学ぶワークショップ
Workshop to learn the basics of educational research
【対象】 大会参加者で、医学教育の領域で活動を始めたばかりの方や、医学教育に関する研究を今まで行ったことがない方を対象とした、初心者向けの企画です。研究初心者が抱く疑問や不安など、ファシリテーターとともにグループ・ディスカッションを行い、ワークショップ参加者全体で討議し、問題解決へと繋げましょう。何の準備も要りません。気軽にご参加ください。事前参加登録制ですが、余裕があれば飛び入り参加も可能です。
【関連情報】 研究推進委員会では、今後このワークショップと学術大会期間中のメンタリングプログラム、リサーチクエスチョンのブラッシュアップを図るアドバンストワークショップとも関連付けた、一つの教育研究支援パッケージとして提供すべく準備を進めています。これも念頭に置きご参加、ご活用頂けますと幸いです。
【ワークショップの流れ】
1) オリエンテーション(全体)(5分)
2)グループワーク(グループ10班、各班タスク1人)(30分)
3)全体討議 (全体)グループ毎に議論の内容を発表する (3分×10班)。全体で疑問に答える。(30分)
4)講義+質疑応答 (学会誌「医学教育」の紹介、医学教 育関係の学術雑誌や学術団体、研究費申請、倫理審査、メンタリングプログラムについて)(20分)
5)まとめとアンケート記入 (5分)
【グループ・ディスカッションのテーマ例】
研究テーマの立案、質的研究、教育効果の評価、データサイエンス・AI関連教育研究など。事前参加登録時に医学教育研究に関する疑問や不安をお伺いし、皆様のニーズに沿ったワークショップとしたいと思います。
- 座 長:
- 大久保 由美子(帝京大学)
- 演 者:
- 藤倉 輝道(日本医科大学)
石川 ひろの(帝京大学)
菊川 誠(九州大学)
武冨 貴久子(札幌市立大学) - ファシリテーター:
今福 輪太郎(名古屋市立大学)
片岡 仁美(京都大学)
鋪野 紀好(千葉大学)
野村 理(岐阜大学)
宮地 由佳(名古屋大学)
林 幹雄(関西医科大学)
ワークショップ22/Workshop 22
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)9:00~10:30
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
ICT技術、AI(生成AI)を医療者教育にどのように活用するか(認定医学教育専門家更新用講習会を兼ねる)
How ICT technology and Generative AI can be used to educate medical professional//Certified Medical Education Specialist Renewal Courses
医療者教育分野においても、これらのICT技術やAI特に生成AIなどを活かしたものが実施されつつあり、今後の発展が期待されている。教育者側の視点では、教育コンテンツの効率的な生成や、個別化学修への対応などが可能になることなどが予想される。学修者の視点では、情報収集のツールやレポート作成の補助としての可能性が考えられる。しかし、生成AI、ICTを用いて適切かつ有効な教育を実施するためには様々な問題も指摘されている。
本ワークショップでは、はじめにこの分野に詳しい演者が講演を行い、「AI(特に生成AI)」の概念と活用方法の例を提示する。その後、これらの技術が医療系教育のどのような場面に、どのように活用できるかを(予想される問題点を含めて)グループワークにて検討する。さらに、グループワークの成果を共有しながら、新たなツールを有効に活用するポイントを考える。
*医学教育学会認定医学教育専門家更新用講習会を兼ねています。あらかじめ申し込みが必要です。更新用講習会への出席が必要な方を優先しますが、空きがあれば参加可能です。
- 座 長:
- 高村 昭輝(富山大学 学術研究部医学系 医学教育学)
守屋 利佳(北里大学医学部医学教育研究部門) - 演 者:
- 淺田 義和(自治医科大学 医学教育センター)
三原 弘(札幌医科大学医療人育成センター教育開発研究部門)
椎橋 実智男(埼玉医科大学 医学部IRセンター) - ファシリテーター:
伊藤 彰一(千葉大学 大学院医学研究院 医学教育学)
岡崎 史子(新潟大学医学部医学科医学教育学分野)
三好 智子(京都大学 医学教育・国際化推進センター)
高村 昭輝(富山大学 学術研究部医学系 医学教育学)
守屋 利佳(北里大学医学部 医学教育研究部門)
ワークショップ23/Workshop 23
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)9:00~10:30
会場:第8会場(にぎわい交流館AU 3F 多目的ホール)
生涯キャリアの観点から大学生活の意味を考えよう
Reflecting on the Meaning of University Life from the Perspective of a Lifelong Career
これまで教育学者を中心とする生涯キャリアヒストリー研究会では、生涯キャリアヒストリー法フォーマットを開発し、医療専門職の生涯キャリアと生涯学習について探究してきた。そして、生涯キャリアというLifewideかつLIfelongという視点を活かすことで、大学生活やそこでの学びの意味をより多面的に理解し、大学生活の捉え直し、キャリア支援、学生の生涯学習的態度の涵養につなげられる可能性を感じるに至った。
そこで本ワークショップでは、医療者及び学生が、生涯キャリアという観点から大学生活の過ごし方や経験を振り返り、対話を通して、大学の可能性を捉え直すことを試みる。大学における学びを、授業、実習、部活動、バイト、趣味、友人や先輩や教員などの周りの人のサポート、予備校での学びなどを含めて広く捉え、自身がどんな学生生活だったか、何を大切にしていたかについて対話を通して振り返ることにする。そして、大学生活における出来事や経験、考えたことが、その後のキャリアや医療職としての仕事にどう影響してきたかまで省察する。なお、医療専門職、研修医、学生などと、幅広い層の参加を歓迎し、大学生活や学びが自身の生涯キャリアにどう影響を与えているのか、さらに医療専門職養成における大学の意味やキャリア支援のあり方まで捉え直す場にしたい。
このように本ワークショップは、学生にとっては大学での学びを捉え直したり生涯キャリアを考える場となり、医療専門職にとっては自身の生涯キャリアを振り返るとともに学生や研修医のキャリア支援及び学習支援のあり方を検討する場となるであろう。
- 座 長:
- 種村 文孝(東洋学園大学)
岡崎 三枝子(秋田大学) - ファシリテーター:
渡邊 洋子(新潟大学)
犬塚 典子(田園調布学園大学)
池田 雅則(兵庫県立大学)
池田 法子(足利短期大学)
柏木 睦月(十文字学園女子大学)
三浦 聖子(金沢医科大学)
貫戸 明子(近畿大学)
小西 泰介(獨協医科大学)
細川 幸希(昭和大学)
鳥居 暁子(慶応義塾大学)
鵜沼 篤(秋田大学)
ワークショップ24/Workshop 24
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)9:00~10:30
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
現場を言葉にする――エスノグラフィーことはじめ
Describing social phenomena in the field - An introduction to ethnography
エスノグラフィーにおいて特徴的なのは参与観察である。参与観察とは、対象の人びとの生活や活動の現場に調査者が比較的長期間にわたって身を置き、そこに参与しながら観察するという方法である。参与観察は、対象の人びとの生活やその背景にある社会的側面を知ることはもちろん、調査者自身に生じる反応や自分の生活や活動のあり方との比較を通して、それまで気づいていなかった調査者の活動や捉え方の特徴に気づき、それを相対化する機会にもなる。
参与観察は医学生の実習時の経験と類似点がある。また、医師にとって、医療現場で観察・記述を行う場面は少なくない。しかし、何をどのような視点でどのように観察すると何が見えてくるのか、それをどのように記述し、どう伝えるのかを学ぶ機会はあまりないのではないだろうか。そのため、企画者は「実習のエスノグラフィックな歩き方」という教育手法を開発し、いくつかの大学医学部で実践してきた。「実習のエスノグラフィックな歩き方」では、エスノグラフィーの視点を身につけ、それを通じ、医療現場の社会的側面を見る視点を養うことを目指している。このような授業は潜在的に、医学生が実習において出会う様々な人のありようを通じて、自分が持っていた前提や捉え方に気づく機会も提供しうる。
本ワークショップでは、この「実習のエスノグラフィックな歩き方」を参加者に体験していただく。文化人類学とエスノグラフィーに関するミニ講義の後、写真・動画を用いて観察・記述の演習を行う。その上で、エスノグラフィーの視点やアプローチを医学教育にどのように組み込むことができるかを検討する。
- 企画代表者:
飯田 淳子(川崎医療福祉大学)- ファシリテーター:
斎藤 有吾(新潟大学)
井口 真紀子(祐ホームクリニック大崎)
錦織 宏(名古屋大学)
田代 志門(東北大学)
宮地 純一郎(名古屋大学/北海道家庭医療学センター)
倉田 誠(東京医科大学)
網谷 真理恵(鹿児島大学)
吉内 一浩(東京大学)
鷹田 佳典(日本赤十字看護大学)
川島 大輔(中京大学)
ワークショップ25/Workshop 25
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)10:50~12:20
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
コミュニケーションから医療安全まで:医学教育におけるインプロ(即興演劇)の可能性を体験しよう
Experience the Potential of Medical Improv
- 座 長:
- 岡崎 研太郎(九州大学)
小比賀 美香子(岡山大学) - ファシリテーター:
直井 玲子(東京学芸大学)
岡崎 研太郎(九州大学)
ワークショップ26/Workshop 26
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)10:50~12:20
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
今すぐできる!3×Rから始めるメンタルヘルス系コーチング
Mental health coacning starting with 3xR.
- ファシリテーター:
柏木 孝仁(久留米大学医学部)
安川 秀雄(久留米大学医学部)
満尾 美穂(久留米大学医学部)
小松 誠和(久留米大学医学部)
ワークショップ27/Workshop 27
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)10:50~12:20
会場:第8会場(にぎわい交流館AU 3F 多目的ホール)
Z世代研修医に響く指導を考える~指導医・指導者・事務の立場から~
Exploring Effective Guidance for Generation Z Resident Doctors
このような背景を理解し、指導する立場の感覚・感性と研修医の感覚・感性の違いを認識して研修指導を行うことがより良い医師養成には大切である。
本ワークでは、Z世代の特徴に関する基調講演の後、どうしてそんなことをするのだろうと理解できない行動や困ったと感じた研修医の実例を持ち寄り、世代特性の問題か、それ以外の問題かを同定し、世代特性の問題に関する解決法を参加者全員で共有する。
- 座 長:
- 松島 加代子(長崎大学病院 医療教育開発センター)
近藤 昭信(済生会松阪総合病院 外科) - 演 者:
- 石原 慎(藤田医科大学)
- ファシリテーター:
石丸 裕康(関西医科大学)
稲森 正彦(横浜市立大学医学部医学教育学)
落合 甲太(淀川勤労者厚生協会附属西淀病院)
木村 真希(神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター 保健管理部門)
白籏 久美子(飯田市立病院)
高橋 誠(北海道大学)
栩野 吉弘(大阪公立大学 総合医学教育学)
廣井 直樹(島根大学医学部)
望月 篤(聖マリアンナ医科大学 医学教育文化部門 医学教育研究分野)
早稲田 勝久(愛知医科大学)
ワークショップ28/Workshop 28
当日参加OK
7月26日(土)10:50~12:20
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
日本医学教育学会の未来を共に考える:新しい視点からのニーズ発見ワークショップ
Envisioning the Future of the Japan Society for Medical Education - A Workshop to Explore Emerging Needs and Perspectives
本ワークショップ(WS)では、これまで学術大会の参加経験が少ない若手会員や学生を含む新たな視点を持つ人々から、学会が将来あるべき姿や提供すべき価値について意見を収集し、潜在的なニーズを把握することを目的とする。
WSでは、最初にオープニング・アイスブレイクとして、本WSの目的と流れを説明する。将来構想特別委員会の活動目的について簡単に紹介し、参加者に委員会の目指す方向性を理解してもらう。続けてグループディスカッションとして、小グループに分かれてKJ法を行う。グループは「自分や自分の所属するコミュニティにとって、日本医学教育学会が10年後にどのような存在であってほしいか」という視点で、以下のようなトピックから作成する:「医学教育研究の推進」「日本の医学教育の強みを活かした国際貢献」「情報・科学技術を育て活用することによる革新的な医学教育開発」「次世代の教育者・研究者の育成」「日本の医学教育・医療者教育に関わるコミュニティ間の連携(学会間連携を含む)」「若手のもやもや聞いてくれ!(仮:若手参加者による問題意識の収集)」。グループディスカッションの後、各グループの代表による結果発表、委員会メンバーによる議論の総括を行う。
このWSを通じ、将来構想特別委員会は多様な会員の意見を積極的に学会運営に反映させ、会員が所属感と成長機会を得られる学会の実現を目指す。
- 座 長:
- 宮地 由佳(名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学教育センター)
- 演 者:
- 宮地 由佳(名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学教育センター)
- ファシリテーター:
金田 侑大(北海道大学医学部 )
小杉 俊介(九州大学/飯塚記念病院)
藤川 裕恭(順天堂大学医学部総合診療科学講座)
八木 街子(自治医科大学看護師特定行為研修センター)
高見 秀樹(名古屋大学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター)
野村 理(岐阜大学 医学教育開発研究センター)
淺田 義和(自治医科大学医学教育センター)
ワークショップ29/Workshop 29
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)14:00~15:30
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
市中病院・診療所における診療参加型臨床実習プログラムを作ろう
Developing clinical clerkship programs in non-university teaching hospitals and clinics
本WSの対象は、市中病院・診療所に所属する指導医、専攻医、研修医、医学生、事務担当者です。WSでは、診療参加型実習プログラムの立案・改善に活用できる医学教育理論や他施設での実践のコツを共有し、事務担当者目線からも実習受け入れに関する情報提供を行います。その後、WS参加者同士のディスカッションを通じて、プログラム立案・改善のためのヒント、具体案を持ち帰ることを目標とします。
ざっくばらんなWSを目指しますので、すでに実習の受け入れを行っている方だけでなく、これから受け入れたい!と考えている方、こんな実習にしてほしいという学生さん、研修医の皆さんもぜひお集まりください!
- 座 長:
- 尾原 晴雄(沖縄県立中部病院)
WS-29-1
市中病院実習中に医学生が積極的に参加するために受け入れ側ができる工夫
舩越 拓(東京ベイ・浦安市川医療センター 救命救急センター)
WS-29-2
初期研修医の地域医療研修におけるCo-creationの実践
高橋 慶(医療生協さいたま生活協同組合 川口診療所)
WS-29-3
研修センター事務員としての臨床参加型実習生が参加しやすい環境づくりの工夫
深田 絵美(大同病院)
- ファシリテーター:
南郷 栄秀(社会福祉法人聖母会 聖母病院 総合診療科)
横江 正道(日本赤十字社医療事業推進本部)
石丸 裕康(関西医科大学)
小杉 俊介(飯塚記念病院/飯塚病院)
白籏 久美子(飯田市立病院)
山田 彩乃(認定 NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML)
ワークショップ30/Workshop 30
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)14:00~15:30
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
今日、この場所で。あなたと私で紡ぐ「ことば」の力 ~ 対話型鑑賞から考える地に足のついたコミュニケーションとは~
Here and Now, Weaving the Power of Words Together Grounded Communication Through Dialogical Viewing
今回さらに注目した観点は、医療従事者のコミュニケーションを支える「ことば」である。臨床現場では、各人の常識、知識、経験の違いを背景に、意図しない誤解やすれ違いに起因するトラブルが多々発生している現状は、誰もが感じるところであろう。こうした課題に対して、対話型鑑賞の手法に基づくコミュニケーションは、自らの考えを的確に言語化し伝達する能力を高め、患者やチームとの信頼関係を築き、相互理解を深めるための有効な気づきとなり得る。
本ワークショップでは、様々な教育現場で長年実践と発信を継続されてきた日本語教育学者である細川英雄氏をお招きし、医療現場につながる言語教育のエッセンスや現状、課題に触れていただく。さらに「ことばの力」に焦点を当てた対話型鑑賞における具体的な発言やファシリテーションの進め方について、参加者とともにディスカッションを深めていく。
鑑賞の題材には、「人」「自然」「生活」「思想・美意識」などに深い関連を持つ秋田由来の作品を使用する予定だ。先人たちの思いや暮らしに触れながら、参加者自身が何を感じ、何を思考しているかを、自分の言葉で紡いでいく。互いに理解できるように提示しあいながら、言葉の使い方に焦点を当てた対話型鑑賞を体験していただく。
本ワークショップは、現在の日本における言語教育や医療現場でのコミュニケーションを「ことば」の視点から考察する場となることを目指している。参加者がそれぞれの現場で応用可能な新たな知見やヒントを得られることを期待している。
- 座 長:
- 森永 康平(獨協医科大学)
- 演 者:
- 森永 康平(獨協医科大学)
細川 英雄(早稲田大学)
岡﨑 三枝子(岡﨑三枝子秋田大学医学部附属病院 総合臨床教育研修センター) - ファシリテーター:
黒江 崇史(高知大学)
太田 雄馬(自治医科大学大学院 医学研究科 医学教育学専攻 / 東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科)
髙柿 有里(大阪医療福祉専門学校 言語聴覚士学科)
石黒 一美(日本歯科大学東京短期大学歯科衛生学科)
安倍 弘生(宮崎大学医学部医療人育成推進センター)
ワークショップ31/Workshop 31
定員あり
事前登録
7月26日(土)14:00~15:30
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
教えて!明日から使える授業・研修の作り方のコツ! Instructional Designを楽しく学んで、実践に活かそう!!
Practical Tips for Designing Classes and Training Programs. Learn Instructional Design with Fun and Apply It Tomorrow
Instructional Design(ID)に基づいて授業や研修の設計・開発を効果的に行うためのポイントをわかりやすく解説し、さらに実践例も紹介します!!
はじめに。参加者同士で「こんな時、どうすれば…?なんか、上手くいかない。」となど授業や研修での実際の悩みを共有します。その後、授業や研修の設計に役立つ基本的なフレームワークとしてIDについてベテラン講師からわかりやすくかつ“楽しく”レクチャー!レクチャー後にはきっと参加者の皆さんの現場に応じた具体的な改善アイディアが浮かんでくるはずです。
続いて、「他の施設ではどんな授業や研修を実施しているんだろう?」と気になる方のために、教育熱心な演者から多様な職種、シチュエーションでの事例を授業参観に来た気分で一緒に学ぶ時間を設けています。卒前・卒後教育の中で、IDがどのように現場で活用されているかを紹介します。他施設の実践例を知ることで、自分の現場に応用できる新たな視点やヒントに繋がります。
そして、最後は、これまで学んだことを参加者の皆さんの事例でディスカッションタイム。みんなでワイワイ意見を交わして、現場ですぐに活かせる実践的なコツや授業や研修を次のステージへ進化させるためのアクションプランを立てるワークを予定しています!
明日からすぐにやってみよう!と思えるIDの具体的なヒントやスキルをたっぷりと学べる実践的な内容になっています。IDを知ることで、あなたの授業や研修がぐんとパワーアップすること間違いなし!
どなたでも気軽に参加できる内容ですので、ぜひこの貴重な機会をお見逃しなく!みんなで楽しく学びましょう!!
- 座 長:
- 濱田 千枝美(産業医科大学病院救急集中治療科)
笠井 大(千葉大学大学院医学研究院医学教育研究学) - 演 者:
- 向後 千春(早稲田大学人間科学学術院)
田原 卓矢(昭和医科大学藤が丘病院 臨床工学室)
森木 紀博(関西学研医療福祉学院 作業療法学科) - ファシリテーター:
清水 郁夫(千葉大学大学院医学研究院医学教育研究学)
杉浦 真由美(北海道大学大学院教育推進機構)
西城 卓也(岐阜大学 医学教育開発研究センター)
ワークショップ32/Workshop 32
定員あり
事前登録
7月26日(土)14:00~15:30
会場:第8会場(にぎわい交流館AU 3F 多目的ホール)
メンターシップ
Mentorship
本ワークショップでは、日本における従来のメンターシップおよびメンティシップの認識と、本来あるべき姿とのギャップに焦点を当てる。日本では、メンターとメンティーの関係が忠誠心や感情的絆に基づき、非公式かつ感覚的な方法で構築される傾向があるが、これが必ずしも効果的なキャリア発展に結びつかない場合がある。このギャップを埋めるために、メンターおよびメンティーが果たすべき責任、求められるスキル、そして相互的な関係性の構築について再考することが重要である。
本ワークショップの内容は、ミシガン大学で2017年に初開催され国際的に評価を得ているMentorship Academyでの学びに基づいて設計されている。我々はこれまで同アカデミーのセミナーに参加し、その主催者である専門家たちからの監修を受けながら本プログラムを設計した。我々が得た知見を共有し、参加者が自身の経験を振り返りながらギャップに気づき、今後の実践に活かせる具体的な方法を議論する場を提供する。
ワークショップでは、講義形式での基礎知識と理論的背景の提供とともに、小グループでのディスカッションを行う。以下の内容を含む:
1. メンターシップおよびメンティシップの本来の目的と求められる要素の確認。
2. 参加者自身のこれまでの経験を振り返り、課題やギャップを明確化するプロセス。
3. 自国の文脈に適した実践的なアプローチを設計する方法の探求。
参加者がメンターシップおよびメンティシップの理想的な姿を理解し、それを実現するための具体的な行動計画を持ち帰ることである。このプロセスを通じて、キャリア発展を促進する教育環境の構築に貢献することを目指す。
- 座 長:
- 染谷 真紀(京都大学医学部附属病院)
笠原 桂子(京都大学医学部附属病院)
和足 孝之(京都大学医学部附属病院) - 演 者:
- 笠原 桂子(京都大学医学部附属病院)
染谷 真紀(京都大学医学部附属病院)
和足 孝之(京都大学医学部附属病院)
安本 有佑(板橋中央総合病院 救急総合診療科)
松本 朋弘(上野原市立病院 内科総合診療科) - ファシリテーター:
染谷 真紀(京都大学医学部附属病院)
笠原 桂子(京都大学医学部附属病院)
和足 孝之(京都大学医学部附属病院)
滝澤 あゆみ(東京都立駒込病院)
安本 有佑(板橋中央総合病院 救急総合診療科)
松本 朋弘(上野原私立病院 内科総合診療科)
ワークショップ33/Workshop 33
7月26日(土)14:00~15:30
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
患者安全トレーニングをデザインする
Training design for Patient Safety
限られた時間でのシナリオ作成になるが、シナリオデザインを通して患者安全教育の新たな領域をまたシミュレーション教育の活用方法を体験いただきたい。
- 企画代表者:
大内 元(琉球大学病院)
ワークショップ34/Workshop 34
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)15:50~17:20
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
市中病院研修の未来語る会/なぜ我々は教育に関わるのだろう
Understanding the intrinsic motivation of clinical practitioners and how we identify ourselves as clinical educators
- 座 長:
- 神田 健志(彦根市立病院)
- 演 者:
- 與那覇 忠博(社会医療法人敬愛会 中頭病院)
金森 真紀(洛和会音羽病院) - ファシリテーター:
白籏 久美子(飯田市民病院)
山内 洋介(伊勢赤十字病院)
久保田 尚子(都立駒込病院)
鈴木 創(立川相互病院)
金原 秀雄(福井県済生会病院)
大下 彰彦(尾道総合病院)
木村 武司(名古屋大学医学部附属病院)
宮地 純一郎(名古屋大学、北海道家庭医療学センター)
ワークショップ35/Workshop 35
当日参加OK
7月26日(土)15:50~17:20
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
みんなで作ろう!理想の公衆衛生医師インターンシッププログラム
Internship program for public health physician
本ワークショップでは、医学生と公衆衛生医師が対談を行い、卒前教育における課題やニーズを明らかにするとともに、理想的な公衆衛生医師のインターンシップについて議論します。これにより、大学と自治体の連携を強化し、公衆衛生に関心を持つ若手医師を増やし、持続可能な公衆衛生医師の育成を目指します。その一環として、医学教育学会にワークショップを提案しました。
本企画は、厚生労働省研究班「公衆衛生医師の確保に係る自治体と地域の大学との連携及び自治体におけるインターンシップ事業推進のための研究(24LA1001)」の活動の一部です。島根大学や秋田大学の公衆衛生関連講座の教員、広島市南区役所 厚生部/南保健センター、香川県中讃保健福祉事務所に所属する公衆衛生医師がファシリテーターとして参加します。また、それぞれの機関が、公衆衛生に関心を持つ医学生や若手医師を誘いワークショップを開催しますが、当日でも公衆衛生医師に関心のある学生さんや、教員、医師、自治体職員等の参加を歓迎します。
ワークショップを通じて、公衆衛生医師と医学生が互いのニーズを共有し、公衆衛生医師の確保・育成に向けた効果的なインターンシッププログラムの作成を目指します。
- 座 長:
- 野村 恭子(秋田大学医学部衛生学公衆衛生学)
名越 究(島根大学 医学部 環境保健医学講座 ) - ファシリテーター:
平本 恵子(広島市南区役所 厚生部/南保健センター)
横山 勝教(香川県中讃保健福祉事務所)
名越 究(島根大学 医学部 環境保健医学講座)
野村 恭子(秋田大学 医学系研究科 衛生学公衆衛生学講座)
杉山 雄大(筑波大学医学医療系ヘルスリサーチ分野)
ワークショップ36/Workshop 36
当日参加OK
7月26日(土)15:50~17:20
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
多疾患併存(マルチモビディティ)への視座を育む:学びの場としてのマルモカンファレンス
Fostering Perspectives on Multimorbidity - The Marumo Conference as a Learning Platform
本ワークショップでは、私たちの病院で実施している「マルモカンファレンス」を実演します。このカンファレンスは、次の点に重点を置いています。
・優先順位の付け方:複数のプロブレムから、どのように診療の優先順位を決定するか。
・多職種連携:医療・介護福祉職を含む他職種と、どのように効果的な協働を行うか。
・教育の工夫:領域を超えた視点をどのように養うか。
本セッションでは、実際の症例を用いたカンファレンス形式で、参加者に以下を体験していただきます。
・不確実性の中での意思決定プロセス
・自分の専門領域以外の疾患に対する「気づき」を促す方法
・マルモを体系的に学ぶための具体的な教育アプローチ
特に、領域別専門医や専攻医に向けて、他領域の患者背景を捉える視点をどう教えるか、またそれを臨床現場でどのように実践に結びつけるかについて議論を深めます。マルモ診療を初めて学ぶ医学生から、教育手法を取り入れたい指導医、さらには多職種の方々まで、どなたでも楽しみながら学べる内容となっています。ぜひご参加ください。
- 座 長:
- 大浦 誠(南砺市民病院)
- 演 者:
- 小川 太志(富山大学附属病院 南砺・地域医療支援学講座)
武島 健人(富山大学医学部医学教育学講座)
齊藤 麻由子(富山大学附属病院総合診療科)
木島 朋子(新潟県立中央病院)
池本 正平(東京都立松沢病院内科)
藤田 雅子(亀田総合病院リハビリテーション室)
田中 洋平(医療法人徳洲会 湘南大磯病院)
大村 裕佳子(金城大学看護学部看護学科)
竹林 正樹(青森大学 社会学部)
石田 瞳(追手門学院大学 経営学部) - ファシリテーター:
大浦 誠(南砺市民病院総合診療科)
スポンサードワークショップ(AMED)/Sponsored Workshop(AMED)
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月26日(土)16:00~18:00
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
AMED医学系研究をわかりやすく伝えるワークショップ in 日本医学教育学会
AMED Workshops on how to disseminate medical research process and results in an easy to understant manner
このたび当プロジェクトの取組として、第57回日本医学教育学会大会に「AMED医学系研究をわかりやすく伝えるワークショップ」を出展いたします。ワークショップでは、医療分野の研究開発に関する模擬プレスリリースについて、グループワークで添削を行うことで、医学系研究をわかりやすく伝えるためのテクニックを習得します。医学教育にも役立つスキルでもありますので、ぜひご参加ください。
※ワークショップの詳細は以下ウェブサイトをご参照ください。参加を希望される方は、事前登録をお願いいたします。
https://www.amed.go.jp/news/event/20250726_wakariyasuku.html
- 司 会:
- 勝井 恵子(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)
- 講 師:
- 井出 博生(順天堂大学/東京大学)
小川 留奈(帝京大学)
早川 雅代(東京大学)
山田 恵子(埼玉県立大学) - 共 催 :
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
Japan Agency for Medical Research and Development(AMED)
ワークショップ37/Workshop 37
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月27日(日)8:45~10:15
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
スライド改革 ~生成AIで実現する医学教育の新たなステージ~
Slide Reform: A New Stage of Medical Education Realized by Generative AI
実臨床における医学教育では、スライド作成ツールを用いたスライド作成が欠かせない一方、スライド作成には多くの時間と労力が必要であり、かつ働き方改革が進んでいる昨今において大きな負担となっている。また、デザインのアイデアが浮かばない、見栄えの良いスライドを作る時間がないといった課題も多く、こうした状況に対する解決策が求められている。その解決策として昨今、効率化という面で大きな可能性を示す生成AIに着目する。
本ワークショップ(以下、WS)では、生成AIを活用したスライド作成の革新的なアプローチを紹介する。まず、テキスト生成AIを用いて、参加者が企画する講義や勉強会のテーマ・内容を具体化する。その後、生成したテキストをスライド作成AIに取り込み、効率的で効果的なスライド資料を作成するプロセスを学ぶ。さらに、画像生成AIを活用することで、視覚的なインパクトを高めるデザインを追加し、全体のスライド完成度を向上させる。これらのステップを通して、参加者が実際にリアルタイムでスライド作成を体験し、従来の手間を削減しながら高品質なスライドを短時間で作成できることを実感する機会を提供する。
また、生成AIの導入に不安を感じる参加者を想定し、基礎知識や具体的な活用方法をわかりやすく解説し、AI初心者でも安心して参加できるWSとなっている。本WSは、参加者が生成AIを用いた新しい教育手法を実体験し、実臨床で活用したいと感じられる内容となっている。
本WSを通じて、忙しい中でも効率よくハイクオリティな教育資料を作成するスキルを身につけるとともに、医学教育の新たな可能性を探るきっかけを提供する。参加者が未来の医学教育を支え、将来的な医療の質向上に繋げていく。
- 座 長:
- 橋本 忠幸(Brigham and Women’s Hospital)
小杉 俊介(九州大学大学院医学系学府医学教育学講座/飯塚記念病院) - 演 者:
- 波多間 浩輔(地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 救急科)
山本 幸近(飯塚病院 総合診療科) - ファシリテーター:
波多間 浩輔(地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院)
山本 幸近(飯塚病院 総合診療科)
木戸 敏喜(富山大学附属病院第一内科)
大塚 勇輝(岡山大学病院総合内科・総合診療科)
ワークショップ38/Workshop 38
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月27日(日)8:45~10:15
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
ビギナーズpecha-kucha on moyamoya ~医学教育ビギナーの語り合い/学び合い~
Pecha-Kucha and Moya-moya for beginners in Medical Education
「ワールドカフェ」はリラックスした自由な雰囲気で行う小グループでの対話であり、WSでは以下の4つのテーマを扱う。
テーマ1:「医学教育に携わる動機、普段の活動」
医学教育に携わるきっかけや現在取り組んでいる活動について共有し、初心者が直面する特有の疑問や課題を明確化する。
テーマ2:「失敗談やモヤモヤの共有」
教育実践での試行錯誤や失敗体験、解決の難しい課題について意見を交換し、参加者間での共感や新たな気づきを得ることを目指す。
テーマ3:「医学教育を学ぶための方法」
医学教育を体系的に学ぶ機会として、「富士研ワークショップ(医学教育者のためのワークショップ)」や「医学教育専門家コース」、「FCME(現場で働く指導医のための医学教育学プログラム)」、「メドギフト(MEDC, GIFU Total learning course)」、MHPE(医療者教育学修士)などが知られている。これらの簡単な紹介に続き、初心者が教育リソースを効果的に利用できる道筋を探る。
テーマ4:「あなたが目指す医学教育」
以上を踏まえ、医学教育との関わり方を多角的に考察する。授業方略の見直しや教員間の協力、働き方改革における教育努力の割り当て、さらに、教育専業と兼業の選択やフィードバック活用の適切な方法について検討する。
対話を通じて、医学教育初心者が「モヤモヤ」を言語化し共有することで、仲間関係を築き新たな視点を得ることを期待している。他者との共感や学びが、さらなる一歩を踏み出す契機となるであろう。
- 座 長:
- 町田 幹(日本医科大学)
伊藤 智範(岩手医科大学)
小松 誠和(久留米大学) - ファシリテーター:
三浦 聖子(金沢医科大学・マーストリヒト大学)
貫戸 明子(近畿大学)
松本 卓子(東京女子医科大学)
力丸 由起子(久留米大学)
橋本 克彦(福島県立医科大学)
海津 聖彦(日本医科大学)
谷内 七三子(日本医科大学)
藤田 貢(近畿大学)
有川 智博(東北医科薬科大学)
野村 智久(順天堂大学)
梅村 将就(横浜市立大学)
園井 教裕(岡山大学)
小曽根 早知子(筑波大学)
紺野 久美子(帝京大学)
ワークショップ39/Workshop 39
当日参加OK
7月27日(日)8:45~10:15
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
医療者に役立つノンテクニカルスキル:仕事の教え方
ノンテクニカルスキルも、スキルである以上理論的な背景があり、体系的なトレーニング法も存在する。そこで筑波大学では、対象を医療者に特化し、短時間で効果的にノンテクニカルスキルを学べる研修プログラムを開発した。今回は、そのテーマの中から「仕事の教え方(TEAMS-BI)」を取り上げる。
「仕事の教え方(TEAMS-BI)」は、主に技能領域のスキルを、正確に安全に良心的に速く覚えさせる方法であり、産業界で広く用いられているTWI-JI:Training within Industry-Job Instructionをベースに、医療者向けにアレンジしたものである。研修では「相手が覚えていないのは、自分が教えなかったのだ」を合言葉に、第1段階-習う準備をさせる、第2段階-作業を説明してやって見せる、第3段階-やらせてみる、第4段階-教えたあとをみる の4つのステップから構成される、体系化されたスキルを学ぶ。この「教える技能」を身につけ活用することで、医療の現場で、手早く確実に、質の高い医療サービスを提供できるとともに、ムダ、手直し、ミスを減らすことにも役立つ。
本来は6時間の研修プログラムであるが、本ワークショップでは時間が限られているため、最も重要なパートである作業分解シートの作成を中心に、研修の一部を参加者に実際に体験していただく。
- ファシリテーター:
前野 哲博(筑波大学医学医療系地域医療教育学)
瀬尾 恵美子(筑波大学附属病院総合臨床教育センター)
ワークショップ40/Workshop 40
7月27日(日)8:45~10:15
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
低学年から学ぶエコー手技 Step by Step
ultrasound training for first-year students, Step by Step
- ファシリテーター:
大内 元(琉球大学病院)
武村 克哉(琉球大学病院)
守時 由起(秋田大学)
ワークショップ41/Workshop 41
定員あり
事前登録
当日参加OK
7月27日(日)10:35~12:05
会場:ワークショップ会場1(秋田市文化創造館 1F コミュニティスペース)
医師のためのコーチング ―自己成長とウェルビーイングを促進する新しいアプローチ
Coaching for Doctors -A New Approach to Promoting Personal Growth and Well-Being
コーチングとは「個人やグループの可能性を最大限に引き出すために、対話と創造的プロセスを通じてパートナーシップを築くこと」である。医師に対するコーチングは、バーンアウト予防、キャリア発展、リーダーシップスキル向上、職業満足度の向上に効果があることが明らかになっている。さらに、コーチングを受けた医師が周囲に与える影響を通じて、チームや組織全体のウェルネス文化の醸成も期待される。日本においても、医師をコーチする医師「コーチング・ドクター」育成プログラムがスタートした。
本ワークショップでは、まず医師のウェルビーイングに関する現状と課題を概説し、コーチングがこれらの解決にどのように寄与するかを紹介する。また、スタンフォード大学医学部のウェルネスコーチの協力を得て、医師のためのコーチングが普及しているアメリカの取り組みも紹介する。次に、医師のコーチング経験が豊富なコーチによるデモンストレーションを行い、医師が直面する課題にどのようにコーチングが適用されるかを参加者に体感してもらう。さらに参加者同士で簡単なコーチングスキルを実践する時間を設け、自身の課題に向き合い、新たな気づきを得る場を提供する。
本ワークショップの目標は、以下の3点である。
1.医師のウェルビーイングに関する課題とその解決策を理解する。
2.医師に対するコーチングの意義を理解する。
3.コーチングの基本的なスキルを体験し、応用可能性に気づく。
本ワークショップでは、実際に医師向けコーチングプログラムを受講し、自らのキャリアやウェルビーイングに変化をもたらした医師がファシリテーターとして参加する。そのため、具体的な実例を通じて参加者に学びを提供することができる。多くの方に参加していただき、医師が必要な時にコーチングにアクセスできる体制づくりに向けての一歩となることを願う。
- 座 長:
- 浅川 麻里(岐阜大学医学教育研究開発センター)
- 演 者:
- 村田 亜紀子(京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター)
- ファシリテーター:
阿部 恭子(鶴岡市立荘内病院)
岩田 智子(森町家庭医療クリニック)
達川 知美(光陽生協クリニック )
半田 梓(東京都立広尾病院)
岡田 加恵(たけしファミリークリニック)
ワークショップ42/Workshop 42
事前登録
当日参加OK
7月27日(日)10:35~12:05
会場:ワークショップ会場2(秋田市文化創造館 2F スタジオA2)
国試CBT化を見据えた動画・音声付ICT教材を作成しよう
ICT teaching materials with videos and sounds in anticipation of the CBT of the national licensing exam
我々は、国試CBT化に向けて動画・音声付臨床問題に適合した学習支援教材も同時に作成している。本ワークショップでは、サンプル教材に触れてその特徴を理解するとともに、簡単な教材作成を体験できる。また、ファシリテータや参加者のアイデアを共有し、多様なCBT向けICT教材の作成のヒントを得ることができる。
参加は原則、事前登録制とする。
- 座 長:
- 松山 泰(自治医科大学 医学教育センター)
三原 弘(札幌医科大学 医療人育成センター) - ファシリテーター:
黄 世捷(聖マリアンナ医科大学医学教育文化部門)
鋪野 紀好(千葉大学大学院医学研究院 地域医療教育学)
田鎖 愛理(岩手医科大学 衛生学公衆衛生学講座)
林 幹雄(関西医科大学 教育センター)
早稲田 勝久(愛知医科大学 医学教育センター)
菅野 武(自治医科大学医学教育センター)
松本 卓子(東京女子医科大学統合教育学修センター)
才津 旭弘(自治医科大学医学教育センター)
ワークショップ43/Workshop 43
7月27日(日)10:35~12:05
会場:第7会場(にぎわい交流館AU 2F 展示ホール)
医学教育者への道:経験の取捨選択で描く新たなキャリア
Pathway to Medical Education - Crafting a New Career Through Mindful Selection of Experience-
本ワークショップでは、これから医学教育者を志す参加者には、将来起こりうる変化や課題を見通す視点を、既に医学教育者である参加者には、これまでの過程を再確認し今後の戦略を再考する場を提供する。具体的には、事例提示とグループディスカッションを通じて、医学教育者への転身に際し生じうる問題点や必要なサポートを洗い出し、相互理解を深める。さらに、これまでのキャリアで培った知識・スキル・人脈を「残す・引き継ぐ・手放す」の3要素に整理し、どのリソースを今後の教育活動にどう活かすかを検討する。また、キャリアチェンジを「転機」として捉える理論的枠組みを紹介し、参加者自身が変化を客観的に理解するヒントを提供する。
これらのアクティビティを通じて、参加者はキャリアチェンジに伴う不安や迷いを軽減し、個々の課題や優先事項を明確にするとともに、行動戦略を立案するきっかけを得る。最終的に、本ワークショップは、これから医学教育者を目指す者には未来への指針を、既に医学教育に携わる者にはさらなる飛躍への足掛かりをもたらし、各々が自らの専門性を活かして豊かなキャリアを築くための有益な場となることを目指す。
- 座 長:
- 田中 淳一(東北大学)
- ファシリテーター:
近藤 猛(名古屋大学医学部附属病院総合診療科/卒後臨床研修・キャリア形成支援センター)
柴田 綾子(淀川キリスト教病院)
照屋 周造(沖縄県立中部病院)
米岡 裕美(埼玉医科大学)
ワークショップ44/Workshop 44
7月27日(日)10:35~12:05
会場:第8会場(にぎわい交流館AU 3F 多目的ホール)
JSME FRINGE: 参加者が伝統的な形式を超えて革新的で多様なプレゼンテーションを体験する双方向型ワークショップ
JSME FRINGE is an interactive workshop where participants can experience innovative and diverse presentations that go beyond traditional formats
Background
Over the last two decades FRINGE sessions have become an important and valued addition to academic conferences. Initially introduced in the field of health professions education (HPE) at AMEE 2004 as an “antidote to PowerPoint poisoning”, the concept of Fringe has blossomed into a session renowned for creativity, free-thinking and audience engagement.
What is FRINGE
FRINGE involves presentations which minimalise the use of PowerPoint and traditional presentation formats, instead embracing the visual arts, poetry, drama, music and song or cutting-edge technology in delivering key messages related to topical issues within the field. The highly engaging format is particularly attractive to students and early career researchers and eagerly anticipated by attendees, making it popular session that is notable in its absence at JSME to date.
Workshop concept
The JSME Internationalization Committee proposes a workshop to introduce the JSME audience to FRINGE, where presenters will give talks on topical HPE issues focused on creative presentation, audience engagement, communication and innovation in a relaxed and supportive atmosphere. Presentations should align with at least one of the workshop keywords of communication, creativity or diversity. The workshop offers a unique opportunity for uniting participants through a free format and multi-modal approach to language and presentation, thus supporting inclusion, equality and diversity.
The aims of the workshop are:
・To explore ideas in health professions education with an emphasis on creativity and engagement, minimising the use of traditional presentation formats
・To encourage topics and presentations of international interest
・To support diversity, equality and inclusion
・To provide opportunities for exposure to innovative teaching and learning in a relaxed and enjoyable bilingual setting
Key points:
・Group presentations, presentations from international participants, early-career researchers and students are supported
・Speaker can choose to present in either Japanese/English/sign language, with measures taken to ensure all the audience can follow the content
- 座 長:
- Maham STANYON(福島県立医科大学)
コリー 紀代(北海道大学) - 演 者:
- 島津 和弘(秋田大学大学院 医学系研究科 臨床腫瘍学講座)
池尻 達紀(彦根市立病院臨床教育センター)
金子 堅太郎(獨協医科大学 教育開発・国際交流センター 地域医療教育部門)
佐野 樹(名古屋大学大学院医学研究科総合医学教育センター)
岡崎 研太郎(九州大学大学院医学研究院 地域医療教育ユニット)
直井 玲子(清和大学短期大学部 こども学科) - ファシリテーター:
矢野 晴美(国際医療福祉大学)
山本 さゆり(愛知医科大学)
宮地 由佳(名古屋大学)
Sabina MAHMOOD(岡山大学)
道信 良子(福井県立大学)
阿部 恵子(金城学院大学)
及川 沙耶佳(秋田大学)
ワークショップ45/Workshop 45
事前登録
当日参加OK
7月27日(日)10:35~12:05
会場:第9会場(にぎわい交流館AU 4F 研修室1・2)
日本におけるシミュレーション・オペレーション・スペシャリストのコンピテンシーを考える ~組織的なシミュレーション学習環境の構築を目指して~
The competencies of simulation operation specialists in Japan
Society for Simulation in Healthcare(以下SSH)の認定資格であるCertified Healthcare Simulation Operations Specialist(以下CHSOS)が世界的にその役割の認知を促しているが、日本においてはこの役割の認知度はまだ高くない。その原因としてSSHの資格認定のコンピテンシーは日本の現状に必ずしも合致したものではなく、日本に適応したコンピテンシーを定めることが、今後のシミュレーション・オペレーション・スペシャリスト養成のために今後大きく役立つと考えている。
今回のワークショップでは、この要素を既にその立場で活躍されている方々や運営に携わっている方々とSOSのコンピテンシーを議論したい。今後この結果を検討したうえで、次回日本医学教育学会大会や日本シミュレーション医療教育学会でも議論を繋げていくことで、今後の世界における日本のシミュレーション学習環境のあり方の議論を展開したい。
タイムスケジュール
司会進行 担当:万代康弘
5分 オープニング
シミュレーションスペシャリストのコンピテンシーを考える
15分 レクチャー 5分×2
担当:濱田千枝美、八木街子
15分 グループワーク:現状を言語化する
15分 レクチャー 5分+10分
担当:淺田義和、仲俊行
20分 グループワーク:日本におけるシミュレーション教育に求められる役割・能力
(=コンピテンシー)
10分 グループワーク:それをどうやって組織に取り入れてもらうか?
5分 まとめ 【万代】
- ファシリテーター:
淺田 義和(自治医科大学)
濵田 千枝美(産業医科大学)
八木 街子(自治医科大学)
万代 康弘(東京慈恵会医科大学)
仲 俊行(テルモ株式会社テルモメディカルプラネックス)
