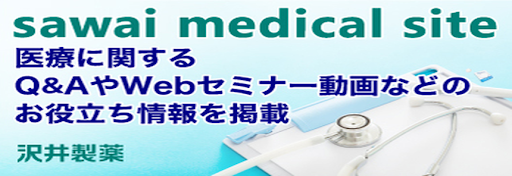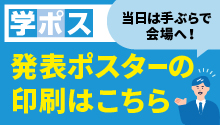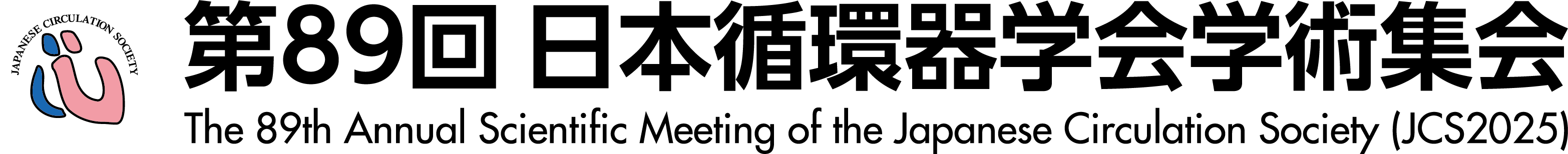プログラム
(2025年3月7日(金)現在)
日程表
プログラム
- 美甘レクチャー(日本心臓財団美甘基金)
- 真下記念講演
- 特別講演
- 代表理事講演
- 会長講演
- Special Lecture
- プレナリーセッション
- シンポジウム
- 会長特別企画
- 会長特別企画(コメディカル)
- ミート・ザ・エキスパート
- ホットトピック
- ラウンドテーブルディスカッション
- コントロバーシー
- JCS2025×JHRS(心電図検定)公認 心電図クイズ大会
- 日本心臓財団シンポジウム
- JCS2025×HEPT企画セッション
- ANP発見40周年記念シンポジウム
- 教育セッション
- チーム医療セッション 教育講演
- チーム医療セッション シンポジウム
- AHA-JCS Joint Symposium
- KSC-JCS Joint Symposium
- CSC-JCS Joint Symposium
- ESC-JCS Joint Symposium
- APSC-JCS Joint Symposium
- WHF-JCS Joint Symposium
- YIA審査講演会(Basic reseach)
- YIA審査講演会(Clinical reseach)
- 国際留学生YIA最終審査講演会
- International Young Investigator’s Award (Basic Research) Finalists Lectures
- International Young Investigator’s Award (Clinical Section) Finalists Lectures
- Asian Pacific Grants for Innovative Research Plan Award(Basic/Clinical)
- APSC President Session
- 日本心臓財団佐藤賞記念講演
- 日本循環器学会 委員会セッション
(医療安全部会) - 日本循環器学会 委員会セッション
(倫理委員会) - 日本循環器学会 委員会セッション
(基本法・5ヵ年計画検討委員会) - 日本循環器連合up-to-dateセミナー
- 日本循環器学会・日本機械学会
ジョイントシンポジウム - 日本循環器学会・日本脳卒中学会
ジョイントシンポジウム - 国際名誉会員セッション
- JIYC オリジナルセッション
- 日本循環器学会 委員会セッション
(ガイドライン部会) - 日本循環器学会 委員会セッション
(学術集会プログラム部会) - 海外留学ネットワーキングセミナー
- 日本循環器学会 委員会セッション
(教育研修/集中・救急委員会) - 日本循環器学会・日本循環器協会
ジョイントシンポジウム - 心不全療養指導士セッション
- 心不全療養指導士Café
- 日本循環器学会委員会セッション
(専門医制度委員会) - JCS EARLY CAREER CHAMPIONSHIP
- 徹底討論:働き方改革から一年、私たちはどう生きるか
- 市民公開講座
- 第23回禁煙推進セミナー
<オンデマンド配信>(現地開催なし)
美甘レクチャー(日本心臓財団美甘基金) 英 語
2025年3月29日(土)10:30~11:30 第1会場(国立大ホール)
Clonal Hematopoiesis: the Emergent Cardiovascular Disease Risk Factor
| 座長: | 佐田 政隆 | 徳島大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | Kenneth Walsh | University of Virginia School of Medicine, USA |
真下記念講演 日本語
2025年3月29日(土)8:40~9:30 第1会場(国立大ホール)
Impaired Integration of Multiple Feedbacks in Atherosclerosis and Cancer
| 座長: | 瀧原 圭子 | 大阪大学キャンパスライフ健康支援センター |
|---|---|---|
| 演者: | 児玉 龍彦 | 東京大学 先端科学技術研究センター |
特別講演日本語
2025年3月28日(金)14:25~15:15 第1会場(国立大ホール)
大規模地震後にも医療を持続するために
| 座長: | 室原 豊明 | 名古屋大学大学院医学系研究科 病態内科学講座 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | 福和 伸夫 | 名古屋大学名誉教授 |
代表理事講演日本語
2025年3月29日(土)13:30~14:00 第1会場(国立大ホール)
日本循環器学会における取り組み
| 座長: | 平田 健一 | 加古川中央市民病院 |
|---|---|---|
| 演者: | 小林 欣夫 | 千葉大学 循環器内科学 |
会長講演日本語
2025年3月28日(金)13:35~14:25 第1会場(国立大ホール)
循環器研究とともに歩んだ軌跡
| 座長: | 外山 淳治 | 名古屋ハートセンター |
|---|---|---|
| 演者: | 室原 豊明 | 名古屋大学大学院医学系研究科 病態内科学講座 循環器内科学 |
Special Lecture
Special Lecture 1英 語
2025年3月28日(金)8:00~8:40 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
SL01
How will novel treatments change the management of patients with PAH
| 座長: | 阿部 弘太郎 | 九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | Marius M Hoeper | Department of Respiratory Medicine and Infectious Diseases, Hannover Medical School, Germany |
Special Lecture 2日本語
2025年3月28日(金)8:50~9:30 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
SL02
Advances in the Treatment of Elderly and Very Elderly Patients with Atrial Fibrillation: Stroke Prevention and Catheter Ablation
| 座長: | 青沼 和隆 | 水戸済生会病院 |
|---|---|---|
| 演者: | 奥村 謙 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 心臓血管センター循環器内科 |
Special Lecture 3英 語
2025年3月28日(金)9:40~10:20 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
SL03
Advance in Catheter Ablation for J Wave Syndrome(仮)
| 座長: | 夛田 浩 | 福井大学 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | Koonlawee Nademanee | Center of Excelence in Arrhythmia Research, Chulalongkorn University; Heart Institute , Bumrungrad International Hospital, Thailand |
Special Lecture 4日本語
2025年3月28日(金)10:30~11:10 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
SL04
Idiopathic Ventricular Arrhythmias: Findings in the past 2 Decades
| 座長: | 池田 隆徳 | 東邦大学大学院医学研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | Takumi Yamada | Cardiovascular Division, University of Minnesota, USA |
Special Lecture 5英 語
2025年3月28日(金)13:35~14:15 第6会場(会議センター3F 304)
SL05
TBA
| 座長: | 天野 哲也 | 愛知医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | Jagat Narula | The University of Texas Health Science Center, USA |
Special Lecture 6日本語
2025年3月28日(金)14:25~15:05 第6会場(会議センター3F 304)
SL06
Senescence Cardiomyopathy
| 座長: | 笠原 英子 | 国際医療福祉大学 予防医学 |
|---|---|---|
| 演者: | Junichi Sadoshima | Rutgers New Jersey Medical School, USA |
Special Lecture 7英 語
2025年3月29日(土)8:00~8:40 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SL07
Heart failure with preserved ejection fraction: progress at last!(仮)
| 座長: | 小川 久雄 | 熊本大学 |
|---|---|---|
| 演者: | John J V McMurray | BHF Glasgow Cardiovascular Research Center, School of Cardiovascular and Metabolic Health, University of Glasgow, UK |
Special Lecture 8日本語
2025年3月29日(土)8:50~9:30 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SL08
Early Results of Myocardial Regenerative Medicine Clinical Trial for Severe Heart Failure due to Ischemic Heart Disease
| 座長: | 柴 祐司 | 信州大学再生医科学教室 |
|---|---|---|
| 演者: | 福田 恵一 | Heartseed株式会社 |
Special Lecture 9英 語
2025年3月29日(土)10:30~11:10 第16会場(会議センター5F 501)
SL09
Novel Proangiogenic Strategies to Prevent Postinfarction Heart Failure
| 座長: | 桑原 宏一郎 | 信州大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | Stefan Offermanns | Pharmacology, Max Planck Institute for Heart and Lung Research Pharmacology, Germany |
Special Lecture 10日本語
2025年3月29日(土)11:20~12:00 第16会場(会議センター5F 501)
SL10
My Clinical Researches on Coronary Artery Disease
| 座長: | 上妻 謙 | 帝京大学医学部内科学講座・循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | 木村 剛 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 循環器内科 |
Special Lecture 11英 語
2025年3月30日(日)8:00~8:40 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SL11
Cardiovascular Risk Prediction: Past, Present, and Future
| 座長: | 石井 秀樹 | 群馬大学大学院医学系研究科内科学講座循環器内科学分野 |
|---|---|---|
| 演者: | Kunihiro Matsushita | Division of Cardiology, Johns Hopkins School of Medicine, USA |
Special Lecture 12日本語
2025年3月30日(日)8:50~9:30 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SL12
Establishment of the Japan Cardiovascular Research Consortium to revitalize cardiovascular research in Japan
| 座長: | 南野 徹 | 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | 小室 一成 | 東京大学大学院医学系研究科 先端循環器医科学講座 |
Special Lecture 13英 語
2025年3月30日(日)10:30~11:10 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SL13
Coronary Revascularization in 2040
| 座長: | 尾崎 行男 | 藤田医科大学岡崎医療センター 循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | Patrick W. Serruys | Established Professor of Interventional Medicine and Innovation, National University of Ireland, Ireland |
Special Lecture 14日本語
2025年3月30日(日)11:20~12:00 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SL14
Time-space Network Hypertension in the Digital Era
| 座長: | 石田 万里 | 広島修道大学 健康科学部 健康栄養学科 |
|---|---|---|
| 演者: | 苅尾 七臣 | 自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門 |
Special Lecture 15英 語
2025年3月30日(日)13:20~14:00 第4会場(会議センター3F 302)
SL15
Two Pathogenesis Mechanisms of for Inflammatory Diseases:
Resistin-Cap1 & PCSK9-Cap1
| 座長: | 佐田 政隆 | 徳島大学循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | Hyo-Soo Kim | Seoul National University Hospital, Korea |
Special Lecture 16日本語
2025年3月30日(日)14:10~14:50 第4会場(会議センター3F 302)
SL16
Adult cardiomyocytes-derived EVs for the treatment of heart failure
| 座長: | 高村 雅之 | 金沢大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | 落谷 孝広 | 東京医科大学・医学総合研究所・未来医療研究センター 分子細胞治療研究部門 |
Special Lecture 17英 語
2025年3月30日(日)15:30~16:10 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SL17
RNA interference: the new revolution in cardiology
| 座長: | 尾野 亘 | 京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | John Vest | Senior Vice President of Clinical Research, Alnylam Pharmaceutical, USA |
Special Lecture 18英 語
2025年3月30日(日)16:20~17:00 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SL18
Impact of Chronic Psychological Stress On Metabolic Disorders:
Focusing on DPP4/GLP-1 and APN/CTSK axis
| 座長: | 竹下 享典 | 埼玉医科大学総合医療センター臨床検査医学講座 |
|---|---|---|
| 演者: | Xiang wu Cheng | Department of Cardiology and Hypertension, Yanbian University Hospital, China |
プレナリーセッション
Plenary Session 1日本語
2025年3月28日(金)8:00~9:30 第3会場(会議センター3F 301)
PL01
次世代テクノロジーを駆使した心臓突然死予防
Prevention of sudden cardiac death using next generation technology
| 座長: | 清水 渉 | 日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 |
|---|---|---|
| 笹野 哲郎 | 東京科学大学 循環器内科 | |
| 演者: | 野村 章洋 | 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科医学専攻 循環器内科学研究分野 |
| 車古 大樹 | 京都府立医科大学附属病院 循環器・腎臓内科 | |
| 佐藤 宏行 | 東北大学大学院医学系研究科 循環器内科 | |
| 藤生 克仁 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 林 明聡 | 馬堀内科医院 |
本邦での心臓突然死は年間8万人を超え、未だに大きな社会的問題である。AEDの普及は心臓突然死の救命率を向上させたが、イベント時に目撃者がおり、適切にAEDを使用できるいう条件があるため、その効果に限界があるのも事実である。
近年のテクノロジーの進歩は、心臓突然死に対しても有用と考えられる。その利用の第一は、種々の情報に機械学習や深層学習を適用して、心臓突然死のリスクを評価することである。従来の単一遺伝子変異の検索にとどまらず、遺伝子多型の解析による遺伝的リスク評価が進展しているほか、12誘導心電図などの情報から不整脈発作のリスクを評価する研究が進んでいる。さらに、複数のモダリティによる評価を統合することで、リスク評価の精度を上げる試みが進んでいる。第二の活用は、ウェアラブルデバイスなどを用いたモニタリングである。現在、種々の生体信号トラッキングの技術が発展しており、心拍や脈拍データから、心臓突然死の発作を検出して通知・対応するシステムの構築が研究されている。さらにウェアラブルデバイスで得られた長時間記録心拍データやホルター心電図データから、近い未来のイベントを予測する技術も開発されており、前述の遺伝子解析や12誘導心電図によるリスク評価との統合も期待される。
本シンポジウムでは、心臓突然死の予防に向けた、最新の解析手法や医療機器の進歩とその応用について、幅広い議論を期待している。
Plenary Session 2英 語
2025年3月28日(金)9:35~11:05 第3会場(会議センター3F 301)
PL02
心不全における心腎貧血鉄欠乏症候群を考える
Cardiorenal Anemia Iron Deficiency Syndrome in Heart Failure
| 座長: | 猪又 孝元 | 新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 斎藤 能彦 | 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター |
State-of-the-art:
| 斎藤 能彦 | 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター |
| 演者: | 土井 研人 | 東京大学 救急・集中治療医学 |
|---|---|---|
| 草場 哲郎 | 京都府立医科大学 腎臓内科 | |
| 中尾 元基 | 北海道大学 大学院医学研究院循環病態内科学 | |
| 小西 正紹 | 横浜市立大学医学部 循環器内科学 | |
| 杜 徳尚 | 岡山大学医学部 循環器内科 |
心腎貧血鉄欠乏症候群とは、心腎から始まるこれまでの臓器連関の研究や診療の歴史を反映する命名である。
心腎連関の概念は、末期腎不全患者の多くが腎機能悪化に起因せず、心血管病で死亡するという疫学データから始まり、慢性腎臓病の診断基準が広まった。その後、因果関係と病相に基づき、心腎症候群として5病型の分類が提唱された。なかでも、急性心不全における急性腎障害は、腎還流圧の低下のみならず腎うっ血の影響も大きいことが指摘され、集中治療の現場では体液バランスの最適化に試行錯誤が今も続いている。一方で、貧血は腎疾患と心不全の両者に合併し、病態に深く関わり強力な予後不良因子であることは知られていた。しかし、心不全患者に赤血球造血刺激因子製剤を投与してヘモグロビンを補正しても生命予後は改善せず、その際の血欠乏および鉄補充に影響されることが報告された。
現時点では、この症候群を構成する各要素の連関が十分には解明されていない。なかでも実臨床へのフィードバックは多くが今後の課題として残されたままであり、本セッションでその議論を整理したい。
Plenary Session 3英 語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第3会場(会議センター3F 301)
PL03
HFpEFの病態・併存症を踏まえた新しい治療戦略
New treatment strategies based on the pathophysiology and comorbidities of HFpEF
| 座長: | 桑原 宏一郎 | 信州大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| John J V McMurray | BHF Glasgow Cardiovascular Research Center, School of Cardiovascular and Metabolic Health, University of Glasgow, UK |
State-of-the-art:
| John J V McMurray | BHF Glasgow Cardiovascular Research Center, School of Cardiovascular and Metabolic Health, University of Glasgow, UK |
| 演者: | 坂田 泰彦 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 臨床研究開発部 |
|---|---|---|
| 近藤 徹 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 齋藤 佑記 | 群馬大学 循環器内科 | |
| 佐藤 大樹 | 東北大学病院 循環器内科 | |
| 西部 倫之 | 岡山大学病院 循環器内科 |
左室駆出率の保たれた心不全(HFpEF)患者数が、超高齢化社会の到来に伴い増加しており、本邦においても全心不全患者に占めるHFpEF患者数の割合は、左室駆出率の低下した心不全(HFrEF)患者の割合を超えるに至っている。HFpEFの予後はHFrEFと同様に不良であるが、HFpEFに対して生命予後改善の明確なエビデンスを示す薬物療法が存在しなかったことが長らくの問題であった。そのような状況の中で、近年SGLT2阻害薬がHFpEFを含むHFrEFではない心不全患者の集団において、心不全イベントと心血管死の複合エンドポイントを有意に低下することが大規模臨床試験にて明らかとなった。また、いくつかのクラスの薬剤が一部のHFpEF患者に効果が期待できることも示されている。こうしたことからHFpEFへの治療アプローチも大きく変わりつつある。一方で、HFpEFが様々な併存症や病態と関連した異質性の高い症候群であることが、HFpEFに対する生命予後改善効果が薬物療法で示されにくいことの一因と考えられ、HFpEFをmultimorbidityの一つの表現型としてとらえ、個々の病態や併存症を考慮した包括的管理を行うことの重要性も認識されている。本セッションではmultimorbidityとしてのHFpEFという視点も含め、その病態や併存疾患を踏まえた治療戦略を議論したい。
Plenary Session 4英 語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第3会場(会議センター3F 301)
PL04
心原性脳塞栓予防における左心耳切除の効果
Left atrial appendage management for prevention of cardiogenic brain infarction
| 座長: | 齋木 佳克 | 東北大学 心臓血管外科 |
|---|---|---|
| Takumi Yamada | Cardiovascular Division, University of Minnesota, USA |
State-of-the-art:
| Takumi Yamada | Cardiovascular Division, University of Minnesota, USA |
| 演者: | 甲斐沼 尚 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓外科 |
|---|---|---|
| 中山 泰介 | 千葉西総合病院 心臓血管外科 | |
| 細山 勝寛 | 東北大学病院 心臓血管外科 | |
| 福永 真人 | 一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 循環器内科 |
心原生脳塞栓をきたす血栓のほとんどは左心耳内で形成される。その左心耳管理が注目されている。2021年にNew England Journal of Medicineに発表されたランドマーク・スタディであるLAAOS III trialにおいて、何らかの主要適応で心臓手術を受けた心房細動患者の脳梗塞予防に、併施手術として外科的左心耳閉鎖処置を行った場合に、左心耳処置無施行群を比較し、一次アウトカムとしての脳梗塞または全身性塞栓症の発生率が有意に低下することが示された。その後の5年間におよぶフォローアップ・スタディのサブ解析では、経口抗凝固薬の継続、非継続を問わずに、外科的左心耳閉鎖処置が血栓塞栓症のリスクを低減したことが実証された。このような大規模な前向き無作為化対照試験による検証の意義は注目に値する。その上で、さらなるクリニカル・クエスチョンが自ずと沸き上がる。弁膜症や冠動脈疾患などの併存心疾患がない場合における単独手術としての左心耳閉鎖術の効果はどうか。開胸手術と鏡視下手術による左心耳閉鎖手術の効果比較、内科的カテーテルによる左心耳閉鎖術と外科的左心耳閉鎖術の効果比較、肺静脈隔離術またはMaze手術を併施した場合の血栓塞栓症の評価等、今後の課題も多い。これらの課題について、解明の糸口をつかめるよう、発表では日本人のリアルワールドデータとして各施設からの研究内容を供覧いただきたい。
Plenary Session 5英 語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第19会場(アネックスホール2F F201+F202)
PL05
心不全に挑むエネルギー代謝研究
Exploring Cardiac Energy Metabolism for Innovative Heart Failure Therapies
| 座長: | 武田 憲彦 | 東京大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| Junichi Sadoshima | Rutgers New Jersey Medical School, USA |
State-of-the-art:
| Junichi Sadoshima | Rutgers New Jersey Medical School, USA |
| 演者: | 有馬 勇一郎 | 熊本大学 国際先端医学研究機構 |
|---|---|---|
| 名越 智古 | 東京慈恵会医科大学 内科学講座 循環器内科 | |
| 上田 和孝 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 桑原 政成 | 自治医科大学 公衆衛生学 兼 循環器内科学 |
生涯にわたり拍動を続ける心臓は、細胞内のエネルギー産生・消費のサイクルが他臓器に比べて際立って活発で、特有のエネルギー代謝経路を持っています。心筋細胞がもつ豊富なミトコンドリアによりATPが盛んに産生され、そのATPはすぐに心筋収縮に消費されます。ミトコンドリア異常が起こると、このエネルギー産生経路が障害され、エネルギーの枯渇や酸化ストレスの増大により、心筋収縮力の低下、慢性炎症、細胞死などを引き起こし、結果として心機能の低下や心不全の発症につながります。また、ダメージを受けた心筋では、エネルギー源が脂肪酸から糖に移行するエネルギー基質のシフトが起こりますが、使用されない脂肪酸の過剰な蓄積は脂肪毒性を引き起こす一方で、脂肪酸の取り込み阻害は心不全の悪化に関与する可能性も示唆されており、心不全における基質シフトの意義についてはまだ明確な見解が得られていません。さらに最近では、SGLT2阻害剤の心不全への有効性が示されたこともあり、ケトン体やアミノ酸などが新たな心筋エネルギー基質として注目されています。そして心筋細胞のみならず、心臓周囲や全身に存在する脂肪組織との代謝的機序を介した組織連関の解明や、複雑な病態メカニズムを紐解くために欠かせないモデル動物の開発も進んできています。本セッションでは、国内外の著名な研究者をお招きし、最新の研究知見に基づいてエネルギー代謝が心不全の発症や進行にどのように影響を与えるか、そして新しい心不全治療法の可能性について発表していただきます。心不全治療の未来を切り開くために、エネルギー代謝研究がどのような可能性を秘めているのか、皆様と共に探求するこの貴重な機会を心より楽しみにしています。
Plenary Session 6英 語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第4会場(会議センター3F 302)
PL06
重症急性心筋梗塞に対する機械的補助循環
Mechanical circulatory support in acute myocardial infarction with cardiogenic shock
| 座長: | 阿古 潤哉 | 北里大学医学部 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 絹川 弘一郎 | 富山大学附属病院 第二内科 |
State-of-the-art:
| 絹川 弘一郎 | 富山大学附属病院 第二内科 |
| 演者: | 中村 牧子 | 富山大学附属病院 第二内科 |
|---|---|---|
| 神戸 茂雄 | 東北大学 循環器内科学 | |
| 西本 裕二 | 市立豊中病院 循環器内科 | |
| 新井 陸 | 日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科 | |
| 中田 淳 | 日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 |
本シンポジウムでは、ショックを伴う急性心筋梗塞の問題点を明らかにするとともに、特に機械的補助循環の使用に関して討論したいと考えている。最新の研究成果や臨床経験に基づく貴重な知見を共有していただくことで、我々医療従事者がより効果的な治療を提供するための新たな洞察を得るものにしたい。
Plenary Session 7英 語
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第3会場(会議センター3F 301)
PL07
重症心不全に対する心房細動治療
AF management in patients with severe heart failure
| 座長: | 里見 和浩 | 東京医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| Koonlawee Nademanee | Center of Excelence in Arrhythmia Research, Chulalongkorn University; Heart Institute , Bumrungrad International Hospital, Thailand |
State-of-the-art:
| Koonlawee Nademanee | Center of Excelence in Arrhythmia Research, Chulalongkorn University; Heart Institute , Bumrungrad International Hospital, Thailand |
| 演者: | 鈴木 敦 | 東京女子医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 向井 靖 | 福岡赤十字病院 循環器内科 | |
| 長谷川 瞬 | 東京女子医科大学病院 循環器内科 | |
| 志賀 剛 | 東京慈恵会医科大学 臨床薬理学 |
心房細動(AF)と心不全は、相互に関連し合い、それぞれが増悪因子となる。重症心不全に対するAF治療は、集中治療における急性期治療と、慢性期における治療選択が主な課題となる。
重症心不全患者では、AFの発症により、頻拍、僧帽弁逆流増悪などに伴い血行動態が破綻しうる。β遮断薬や抗不整脈薬といった薬物治療は、血圧低下や心機能抑制のリスクがあり、その使用はしばしば困難である。心不全に伴う左房圧上昇や交感神経活動亢進のため、電気ショック治療を行っても高率に再発する。
AFに対する非薬物治療として、カテーテルアブレーション、房室ブロックの作成と両心室ペーシングないし刺激伝導系ペーシングといった選択枝が存在するが、急性期を脱した後に適応することがほとんどあり、AFにより急性増悪した重症心不全患者への可及的な適応に関するデータはほとんどない。
慢性期治療として、心移植適応になるような重症心不全に対するアブレーションの有効性が明らかになってきている。しかし、左房が拡大した心不全においてアブレーションの成功率は必ずしも高いといえない。洞調律維持により左房径の減少が得られれば、Atrial functional MRのコントロールも可能になるが、MitraCripによる経皮的僧帽弁接合不全修復術とどちらを先行させるかも議論を要する課題である。
本プレナリーセッションでは、重症心不全例におけるAFの急性期治療、慢性期治療につき、ディスカッションしていきたい。
Plenary Session 8日本語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第6会場(会議センター3F 304)
PL08
Digital Hypertensionは循環器病予防に有用かどうか
Is Digital Hypertension Useful in Preventing Cardiovascular Disease?
| 座長: | 苅尾 七臣 | 自治医科大学内科学講座循環器内科学部門 |
|---|---|---|
| 岸 拓弥 | 国際医療福祉大学大学院医学研究科循環器内科 | |
| 演者: | 内田 亮子 | 東京大学医学部附属病院 先進循環器病学講座 |
| 久松 隆史 | 岡山大学学術研究院医歯薬学域 公衆衛生学分野 | |
| 鈴木 秀明 | 東北大学病院 循環器内科 | |
| 岸 拓弥 | 国際医療福祉大学 大学院医学研究科循環器内科 | |
| 苅尾 七臣 | 自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門 |
高血圧は循環器病の主要な危険因子であり、その対策、特に予防は公衆衛生上の重要課題です。最近のデジタル技術の進展により、人工知能(AI)、ウェアラブルデバイス、および治療補助アプリケーションが高血圧管理に導入され、「Digital Hypertension」として新たな領域を切り開いています。「Digital Hypertension」は、個々の患者に対してリアルタイムでの血圧モニタリング、データ解析、そして個別化された治療指導を可能にし、患者の自己管理能力を向上させると期待されています。特に、AI技術を用いた予測モデルは、患者の血圧変動を予測し、異常値の早期発見を支援します。ウェアラブルデバイスは、継続的な血圧測定を容易にし、データの即時フィードバックを提供します。さらに、治療補助アプリケーションは、患者のライフスタイル改善を促進するための行動変容ツールとして機能し、薬物治療のコンプライアンス向上にも寄与します。本プレナリーセッションでは、最新の研究成果と実臨床における事例を基に、「Digital Hypertension」の有用性と課題について具体的に論じます。また、今後の技術革新がどのように高血圧管理を変革し、最終的には循環器病予防にどのように貢献するかを展望します。
Plenary Session 9英 語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第3会場(会議センター3F 301)
PL09
心エコー図による左室拡張能評価の最前線
Echocardiographic assessment of left ventricular diastolic function by echocardiography
| 座長: | 井上 勝次 | 愛媛大学大学院 地域救急医療学講座 |
|---|---|---|
| Faraz H. Khan | Institute for Surgical Research, Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases, Oslo University Hospital, University of Oslo, Norway |
State-of-the-art:
| Faraz H. Khan | Institute for Surgical Research, Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases, Oslo University Hospital, University of Oslo, Norway |
| 演者: | 岩野 弘幸 | 手稲渓仁会病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 河田 侑 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 循環器内科学 | |
| 小保方 優 | 群馬大学医学部附属病院 循環器内科 |
心エコー図による心不全診断に、左室収縮能評価と共に左室拡張能・充満圧評価は重要である。日本循環器学会(JCS)、米国心エコー図学会(ASE)、欧州心血管イメージング学会(EACVI)は、左室拡張能評価にE/e'、左房容量係数(LAVi)、三尖弁逆流速度(TRV)の三指標に用いることを推奨している。しかしながら、これらのkey parametersを用いて左室拡張能・充満圧を評価できない症例(indeterminate cases)が存在する。このindeterminate casesにおいて、左房ストレインがその補助的診断に有用であることが報告されている。
左室駆出率が保たれた心不全(HFpEF)症例は、労作時息切れを主訴とすることが多く、安静時の心エコー指標で左室充満圧の推定が困難な症例が少なくない。さらに、HFpEF症例において左房ストレインによる左室充満圧評価の精度は低下することが報告されている。運動負荷心エコー図法はHFpEF症例における運動時の左室充満圧上昇を推定する有用な方法である。近年、AIを用いた左室充満圧評価の先進的な研究成果も報告されており、近い将来に心エコー図による左室拡張能評価ガイドラインの改訂が近いと思われる。本セッションは心エコー図による左室拡張能評価の最前線と題し、最新の知見、将来展望について議論したい。
Plenary Session 10英 語
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第2会場(会議センター1F メインホール)
PL10
日本における循環器核酸医薬の開発
Development of Nucleic Acid Drugs for Cardiovascular Diseases in Japan
| 座長: | 尾野 亘 | 京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 山本 剛史 | リードファーマ株式会社 | |
| 演者: | 山本 剛史 | リードファーマ株式会社 |
| 堀江 貴裕 | 京都大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 中岡 良和 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター研究所 血管生理学部 | |
| 西野 共達 | グラッドストーン研究所 心臓血管部門 |
一般的な「低分子薬」や、がんの免疫療法で使われる「抗体医薬」に続く「第3の医薬品」として、『核酸医薬』に注目が集まっている。
核酸医薬とは、化学修飾型ヌクレオチドを主骨格とする薬で、化学合成により製造される。従来から開発が進んでいる代表的な核酸医薬には、アンチセンスオリゴヌクレオチド(ASO)・small interference RNA (siRNA)・アプタマー・デコイなどがある。核酸医薬は、従来の医薬品では治療困難な疾患に対する新しい創薬モダリティとして期待されているが、それは標的に対する高い特異性があること、メッセンジャーRNA(mRNA)やnon-coding RNAなど、従来の医薬品では狙いにくい細胞内の分子を創薬ターゲットにすることが可能であるからである。また、化学合成品のため比較的短時間で候補を得やすく、次世代の医薬品として実用化が進んでいる。
また、これらの核酸医薬を標的臓器、細胞に送達するためのシステムも日々改良されており、安全性と薬効の向上に寄与している。
このプレナリーセッションでは、次々と新しい医薬品が作られているこの領域を、多くのエキスパートの方々に詳細に解説頂く予定である。これにより、技術の進展のスピードを実感していただけると思う。今後も、我が国を含めた世界的な研究開発の活発化が本領域において期待される。
Plenary Session 11英 語
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第18会場(会議センター5F 503)
PL11
医療版Society 5.0と「医療デジタルツイン」
Medical Digital Twin in the Society 5.0
| 座長: | 的場 哲哉 | 九州大学循環器内科 |
|---|---|---|
| Kunihiro Matsushita | Division of Cardiology, Johns Hopkins School of Medicine, USA |
State-of-the-art:
| Kunihiro Matsushita | Division of Cardiology, Johns Hopkins School of Medicine, USA |
| 演者: | 石井 正将 | 熊本大学病院 医療情報経営企画部 |
|---|---|---|
| 甲谷 友幸 | 自治医科大学 循環器内科学 | |
| 小寺 聡 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 佐藤 寿彦 | 株式会社プレシジョン |
内閣府の医療・ヘルスケア版 Society 5.0構想においては、電子カルテの普及による医療情報のデータ化に加え、情報技術の進化により人間の身体と生理機能、行動をデータ化し、クラウドに集められた「医療デジタルツイン」の人工知能(AI)による解析により、個別化された医療を提供することが目指されている。しかしながら、現状、疾患特異的な診療情報の電子カルテへの統合は不十分であり、患者自身が保有するパーソナルヘルスレコード(PHR)やウェラブルデバイスのデータの電子カルテへの取り込みやそれらの情報の統合も容易ではない。日本国内では、内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム第3期「統合型ヘルスケアシステムの構築」において、日本循環器学会と連携し、多種多様なデータの統合による「医療デジタルツイン」の確立と、その基盤をもとに生成AIの開発や新たな医学知識の発見、社会実装ソリューション開発が目指されている。
本セッションでは、医療ビッグデータ、ウェラブルデバイスデータの利活用、機械学習、生成AIの応用、などを含めた先進的な研究開発の取り組みを紹介し、医療版Society 5.0を展望する演題を求めます。
Plenary Session 12英 語
2025年3月30日(日)13:20~14:50 第16会場(会議センター5F 501)
PL12
心疾患を有する女性へのプレコンセプションケア
Preconception care for women with heart diseases
| 座長: | 吉松 淳 | 国立循環器病研究センター循環器病周産期センター産婦人科 |
|---|---|---|
| 石津 智子 | 筑波大学 循環器内科 |
State-of-the-art:
| 吉松 淳 | 国立循環器病研究センター循環器病周産期センター産婦人科 |
| 演者: | 衛藤 英理子 | 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科 |
|---|---|---|
| 荒田 尚子 | 国立成育医療研究センター女性総合医療センター女性内科 | |
| 犬塚 亮 | 東京大学 小児科 | |
| 神谷 千津子 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 産婦人科 | |
| 塚本 泰正 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 移植医療部 |
プレコンセプションケアは近年、特に注目されており、女性やカップルを対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取組をいいます。心疾患を有する女性にとって、AYA世代以降になると自身の妊娠に向き合うことになります。幼少期から心臓に病気があり妊娠はできないものだとずっと思いこんでいる場合や、妊娠には大きな危険が伴う心疾患を有しているが支障がないと思っている場合などさまざまなケースに対して、適切な医学的意見を伝えることが求められます。大切なのは自分が妊娠したらどんなことが起きるのか知っておくことで、さらに大切なのはそれを妊娠する前に知っておくことです。その具体的な利点として、まず、不要な妊娠中絶を避けるという点があります。妊娠をした後にその継続により生命に危険を及ぼす場合、妊娠中絶が選択される場合があり、その精神的、肉体的負担を避けることができます。一方で妊娠の可能性を提示できる場合もあります。また、妊娠中には避けるべき検査ができる点や、避けるべき薬剤を前もって変更できる点もプレコンセプションケアの大きなメリットです。さらに精神的な面から、妊娠中の不安を前もってある程度取り除くことも重要です。このような情報提供をするために妊娠前に心機能の評価を行っておくことが重要です。また、その結果は妊娠した場合の管理を進めるにあたって、多職種専門家による情報共有や管理計画の立案に大きく寄与するものともなります。
このセッションでは心疾患を有する女性へのプレコンセプションケアの現状や問題点を討論し、そのあるべき姿を共有できるようにと考えています。
Plenary Session 13英 語
2025年3月30日(日)15:30~17:00 第1会場(国立大ホール)
PL13
安定冠動脈疾患に対する血行再建の適用と選択:ガイドラインと最新の知見
Revascularization in Chronic Coronary Syndrome: Indication and Choice of treatment
| 座長: | 上村 史朗 | 川崎医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| Patrick W. Serruys | Established Professor of Interventional Medicine and Innovation, National University of Ireland, Iveland |
State-of-the-art:
| Patrick W. Serruys | Established Professor of Interventional Medicine and Innovation, National University of Ireland, Iveland |
| 演者: | 割澤 高行 | NTT東日本関東病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 菊田 雄悦 | 医療法人財団竹政会福山循環器病院 循環器内科 | |
| 金地 嘉久 | 土浦協同病院 循環器内科 | |
| 髙木 健督 | 国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門冠疾患科 |
シンポジウム
Symposium 1日本語
2025年3月28日(金)8:00~9:30 第4会場(会議センター3F 302)
SY01
B型大動脈解離を科学する
The Science of Type B Aortic Dissection
| 座長: | 松田 均 | 国立循環器病研究センター 心臓血管外科 |
|---|---|---|
| 加地 修一郎 | 関西電力病院 循環器内科 | |
| 演者: | 沼田 智 | 京都府立医科大学附属病院 心臓血管外科 |
| 舛本 慧子 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科 | |
| 亀田 柚妃花 | 栃木県済生会宇都宮病院 心臓血管外科 | |
| 圷 宏一 | 東京都CCUネットワーク学術委員会 日本医科大学 | |
| 井上 陽介 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 血管外科 |
緊急手術が行われるA型大動脈解離とは対照的に、B型大動脈解離では内科治療が行われるが、短期および長期予後ともに良好とは言い難い。短期予後が不良となる原因は、破裂や腸管虚血などの急性期合併症にあるが、長期予後を悪化させる主な要因は、慢性期に大動脈径の拡大を来たした結果生じる大動脈関連事象にある。急性期合併症を有するB型解離例に対しては、胸部ステントグラフト内挿術(TEVAR)が第一選択として救命に貢献している一方で、慢性期の大動脈関連事象を回避するために、先制治療としてのTEVARが広く行われるようになってきた。先制TEVARの予防効果は高く、B型解離全体の予後を改善することが期待されているが、科学的根拠となるエビデンスは少なく、逆行性A型解離などの重篤な合併症を危惧して施行に躊躇する施設も多い。すなわち、合併症を有さないB型解離に対する先制TEVARの妥当性については、依然として議論があり、現時点では大動脈関連事象を起こす可能性が高いハイリスク例に対してのみ施行される方向にある。一方、B型解離自体も、解離の範囲や血栓化の有無など、形態は実にさまざまで、病態を多面的に捉えて治療方針を決定する必要がある。本セッションではB型解離を、発症機序、診断、各種の治療、短期および長期予後といった多面的な視点から科学的に議論し、“個々のB型解離をどう診断し、どう治療するべきか”について新しいコンセンサスの形成を目指したい。
Symposium 2日本語
2025年3月28日(金)8:00~9:30 第5会場(会議センター3F 303)
SY02
動脈硬化と口腔疾患
Atherosclerosis and Oral Diseases
| 座長: | 佐田 政隆 | 徳島大学循環器内科 |
|---|---|---|
| 杉浦 剛 | 東北大学大学院歯学研究科顎顔面口腔腫瘍外科学分野 | |
| 演者: | 田中 文隆 | 岩手医科大学医学部 内科学講座腎・高血圧内科分野 |
| 松本 知沙 | 東京医科大学 循環器内科 | |
| 北野 大輔 | 日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野 | |
| 小西 崇夫 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 | |
| 宮内 俊介 | 広島大学大学院医系科学研究科 循環器内科学 |
急性冠症候群や脳卒中の多くは動脈硬化を原因として突然発症し、致命率は高い。その病態を把握して、未然にイベントを防ぐための診断技術や治療法、予防法の開発は喫緊の課題である。ヒトの動脈硬化は、従来考えられていたよりかなり早期から始まり、生活習慣病の進行とともに急速に増悪し、突然イベントを誘発する。その過程においては、従来研究されてきた脂質の沈着や細胞増殖だけでなく、血管周囲のVasa Vasorum からの新生血管を介した細胞流入や微小出血が関与することがわかってきた。また、動脈周囲に分布する血管周囲脂肪組織における慢性炎症が動脈硬化の病態において重要な役割を演じることも示唆されている。しかし、なぜ脂質異常症、糖尿病、高血圧、喫煙といった生活習慣病によって、動脈壁で慢性炎症が引き起こされ動脈硬化が進展して破綻するのか不明な点が多い。近年の報告では、歯周病やピロリ菌感染などによる慢性感染症と動脈硬化との関連性も注目されている。
本シンポジウムでは動脈硬化と口腔疾患の関連性や心血管イベント抑制に向けての口腔ケアの意義を討論したい。画期的な最新の研究成果を期待する。
Symposium 3日本語
2025年3月28日(金)8:00~9:30 第18会場(会議センター5F 503)
SY03
非侵襲的マルチモダリティによるINOCAの評価
Non-invasive assessment of INOCA with mult-modality imaging
| 座長: | 佐久間 肇 | 三重大学 放射線科 |
|---|---|---|
| 松本 直也 | 日本大学病院 循環器内科 | |
| 演者: | 臼井 英祐 | 土浦協同病院 循環器内科 |
| 左山 耕大 | 土浦協同病院 循環器内科 | |
| 田中 匡成 | 日本医科大学付属病院 循環器内科 | |
| 坂井 晶子 | 東京女子医科大学病院 循環器内科 | |
| 石田 正樹 | 三重大学大学院医学系研究科 放射線医学 |
2023年にJCS/CVIT/JCC ガイドラインフォーカスアップデート版冠攣縮性狭心症と冠微小循環障害の診断と治療が発刊された。Ischemia with nonobstructive coronary artery disease (INOCA)は2017年に米国から提唱された概念で、臨床的に狭心症を疑う典型的または非典型的症状があり、心筋虚血の客観的検査所見を有するにもかかわらず、冠動脈に器質的有意狭窄を認めない患者と定義される。INOCAのEndotypeは心外膜冠動脈の狭窄を伴わず冠攣縮や冠微小循環障害(CMD)を起こす病態であるため冠攣縮性狭心症、冠微小血管攣縮、微小血管狭心症が含まれ、これらのオーバラップもあるためより複雑である。
冠攣縮やCMDはカテーテル検査を用いた侵襲的診断法が諸外国からも提示されているが安全性や費用対効果の観点からその方法は統一されていない。一方、非侵襲的診断法としては空間解像度に優れた心臓 MRIまたは PETを用いた心筋血流定量評価に加え、有意狭窄冠動脈病変を除外するためのCT、本邦では特に脂肪酸代謝SPECTによる代謝評価、さらに血管内皮機能検査も実施可能である。本シンポジウムでは各種モダリティの第一人者による講演によって臨床に即したINOCAの包括的診断法に迫りたい。多くの聴講者の参加をお待ちしています。
Symposium 4日本語
2025年3月28日(金)9:35~11:05 第4会場(会議センター3F 302)
SY04
心房細動の包括的治療戦略 ~予防・早期発見から薬物・非薬物治療まで
Comprehensive Treatment Strategies for Atrial Fibrillation - From Prevention and Early Detection to Medical and Interventional Treatment
| 座長: | 中野 由紀子 | 広島大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 井上 耕一 | 国立病院機構大阪医療センター 循環器内科 | |
| 演者: | 佐藤 弘樹 | 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 |
| 仲野 美代 | 千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学 | |
| 大久保 陽策 | 広島大学病院 循環器内科 | |
| 増田 正晴 | 労働者健康安全機構 関西労災病院 循環器内科 | |
| 星山 禎 | 熊本大学病院 循環器科 | |
| 田中 宣暁 | 桜橋渡辺未来医療病院 循環器内科 |
心房細動の早期発見は、脳梗塞や心不全などの心房細動による弊害を予防のために非常に重要である。近年、携帯心電計、長時間心電計、アップルウオッチ、植込み型心電計など様々な心房細動検出デバイス、バイオマーカーや遺伝子解析、AI解析などの進歩により心房細動早期発見のために様々な試みがなされている。しかし、見つかってきたどの程度の心房細動症例にどのくらいの介入をすれば予後が改善するかについてはまだ結論が出ていない。また、究極の目標は発症予防であるが、更なる検討が必要である。
心房細動は、併存疾患を抱えた高齢者に多い不整脈であり、抗凝固療法や薬物療法についても工夫が必要で患者さんの状態に応じた対応が必要である。心房細動の中でも、頻脈誘発性心筋症や、心筋症に合併した心房細動など治療が難しい症例も存在する。心房細動アブレーションについては技術やテクノロジーが格段に進歩してきており、肺静脈隔離の成績も向上し、合併症も減少したことで、心房細動のタイミングや対象も変化してきた。その中で持続性心房細動や肺静脈起源以外など難しい症例をどうするかも大事である。またパルスフィールドを含めた新しいテクノロジーをどう生かすかも今後重要であろう。
本シンポジウムでは心房細動の予防・早期発見から治療まで、最新の知見についてご発表頂き、心房細動の包括的治療戦略についてディスカッションを行いたい。
Symposium 5英 語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第18会場(会議センター5F 503)
SY05
ここまできたStructural Heart Diseaseのデバイス治療
Structural Heart disease intervention.
Current status and future perspectives
| 座長: | 林田 健太郎 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 |
|---|---|---|
| 藤田 知之 | 東京科学大学 心臓血管外科 | |
| 演者: | 赤木 禎治 | 岡山大学病院 循環器内科 成人先天性心疾患センター |
| 阿佐美 匡彦 | 社会福祉法人 三井記念病院 循環器内科 | |
| 佐地 真育 | 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 | |
| 竜崎 俊亘 | 慶應義塾大学病院 循環器内科 | |
| 山本 真功 | 豊橋ハートセンター循環器内科 | |
| 林田 健太郎 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 |
大動脈弁狭窄症に対するTAVIが誕生して22年、本邦における導入後11年が経過し、安全な標準治療の一つとして確立されている。また僧帽弁閉鎖不全症や三尖弁閉鎖不全症に対する弁形成や留置術も急速な進歩を遂げている。さらに左心耳閉鎖や先天性心疾患に対するデバイスの進化も著しい。本セッションでは世界における治療の進化と本邦において確立されたデータについて知見を深めていただき今後の展望について論じていく。
Symposium 6日本語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第5会場(会議センター3F 303)
SY06
超急性期から維持期までの地域包括心臓リハビリテーションの取り組み:現状と今後の展開
Community-based comprehensive cardiac rehabilitation from hyperacute phase to phase 3: current status and future perspectives
| 座長: | 三浦 伸一郎 | 福岡大学 心臓・血管内科学 |
|---|---|---|
| 古川 裕 | 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 | |
| 演者: | 礒 良崇 | 昭和大学藤が丘病院 循環器内科 |
| 村井 亮介 | 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 | |
| 北川 知郎 | 広島大学大学院医系科学研究科 循環器内科学 | |
| 末松 保憲 | 福岡大学医学部心臓・血管内科学 循環器内科 | |
| 渡部 裕 | 医療法人 恒仁会 新潟南病院 |
少子高齢化による労働力人口減少と要介護者の増加は、わが国の国民や社会へ大きな負荷となっている。その対策として、「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」が策定され、それに基づいて脳卒中と循環器病克服 第一次・第二次5カ年計画が進められてきた。その中で、急性期から維持期までのシームレスなリハビリテーションの重要性が強調されたことが、それ以前から取り組まれてきた各地域での心リハ連携を加速させている感がある。また、とくに高齢患者の場合、QOLやADLの維持・改善のためには、回復期から維持期へ長期にわたるシームレスなリハビリを続けることが重要である。それに加えて、ICU/CCU滞在時の超急性期から可及的速やかにリハビリを開始することも重要であり、超急性期の過度の安静などにより、不利な状況からのリハビリとならないよう留意することも重要である。
本シンポジウムでは、地域包括心臓リハビリテーションの先進的な取り組みや実績を発表いただき、より明らかになってきた課題や今後の展望について議論したい。
Symposium 7英 語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第19会場(アネックスホール2F F201+F202)
SY07
肺高血圧症の新たな病態、早期診断法と治療戦略
New Pathophysiology, Early Diagnosis and Treatment Strategies of Pulmonary Hypertension
| 座長: | 阿部 弘太郎 | 九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 |
|---|---|---|
| Marius M Hoeper | Department of Respiratory Medicine and Infectious Diseases, Hannover Medical School, Germany |
Keynote Lecture:
| Marius M Hoeper | Department of Respiratory Medicine and Infectious Diseases, Hannover Medical School, Germany |
| 演者: | 稲垣 薫克 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 血管生理学部 |
|---|---|---|
| 福満 雅史 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター研究所 先進医工学センター 循環動態制御部 | |
| 赤木 達 | 岡山大学学術研究院医歯薬学域 循環器内科学 | |
| 伊波 巧 | 杏林大学医学部 循環器内科学 |
欧州の肺高血圧症ガイドラインが2022年に改訂されたのに続き、2024年にはバルセロナにて第7回肺高血圧症ワールドシンポジウムが開催された。肺動脈性肺高血圧症(PAH)の治療に関しては、ソタテルセプト皮下注射や新たな治療薬の治験も行われ、3系統と別経路の治療薬の承認が期待される。一方、右心不全をきたす重症肺高血圧症に対しては、現在でもエポプロステノール持続静注投与に加え、最終的には肺移植が必要である。慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対しては、バルーン肺動脈形成術、抗凝固療法、肺血管拡張薬、それぞれの有効性と安全性について本邦から数多くのエビデンスが創出された。また、有症候性慢性血栓塞栓性肺疾患(CTEPD) without PHに対するバルーン肺動脈形成術の安全性と有効性に関する臨床研究も本邦を中心に進んでいる。本シンポジウムでは、PHと関連する右心不全の病態解明、診断と治療に関する新たな試みを幅広く公募し、今後のPHの新たな治療方針への課題と展望について議論する場としたい。
Symposium 8日本語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第4会場(会議センター3F 302)
SY08
循環器内科医とダイバーシティ―循環器学における多様性を科学する
Cardiology and Diversity - The Science of Diversity in Cardiology
| 座長: | 塚田(哲翁) 弥生 | 日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科 |
|---|---|---|
| 瀬戸口 聡子 | Department of Medicine, Rutgers University | |
| 演者: | 中尾 葉子 | 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 薬剤疫学分野 |
| 倉林 学 | 横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科 | |
| 山下 侑吾 | 京都大学大学院医学研究科 循環器内科 | |
| 髙橋 佐枝子 | 医療法人徳洲会 湘南大磯病院 循環器科 | |
| 野間 さつき | 日本医科大学付属病院 循環器内科 |
ディスカッサント:
| 石井 秀樹 | 群馬大学医学部附属病院 内科学講座循環器内科学 | |
| 野中 顕子 | 兵庫県立がんセンター 腫瘍循環器科 |
世界における心血管疾患による年間死亡者数は1,790万人に上り、非感染性疾患(NCD)による死亡原因の中で最も多い。しかし、日本は心血管疾患による死亡率が世界でも類を見ないほど低いことで特筆される。これは、遺伝的素因の違いだけでなく、社会経済的要因や質の高い医療が寄与している可能性がある。循環器領域の研究に「多様性」を取り入れ、海外と日本における死亡者数の違いを分析することで、日本の優れた循環器診療を国際的に発信し、世界の循環器診療に貢献することが期待される。
しかし、日本では欧米と異なり、「患者の多様性」の概念が確立されていない現状がある。性別、年齢、病態などの生物学的疫学や、所得、学歴、家庭状況などの社会経済的影響に関する研究も十分に行われておらず、エビデンスが乏しい状況である。また、多職種カンファレンスやハートチームに代表される多職種協働、急性期から慢性期までの質の高い医療、細やかな支援を行う福祉の実態やその費用対効果についても十分に理解されていない。
まずは国内状況を把握し、国際比較を行うことが必要である。日本循環器学会では2023年に循環器ダイバーシティ研究奨励賞を創設し、本領域の研究者を支援している。本セッションでは、生物疫学、社会疫学、医療の質、福祉、さらに医療者の資質の観点から「循環器学の多様性」について議論し、この分野のスターティングポイントとなる機会としたいと考えている。
Symposium 9英 語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第6会場(会議センター3F 304)
SY09
循環器疾患に伴う後天性フォン・ヴィレブランド症候群
Acquired von Willebrand syndrome associated with cardiovascular diseases
| 座長: | 堀内 久徳 | 奈良市立看護専門学校 |
|---|---|---|
| Karen Vanhoorelbeke | Lavoratry for Thrombosis Research, KU Leuven, Belgium |
Keynote Lecture:
| Karen Vanhoorelbeke | Lavoratry for Thrombosis Research, KU Leuven, Belgium |
| 演者: | 全 完 | 京都府立医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 渡邉 真 | 京都大学 循環器内科 | |
| 齋木 佳克 | 東北大学 心臓血管外科 | |
| 堀内 久徳 | 奈良市立看護専門学校 |
大動脈弁狭窄症(AS)や植込型左室補助治療中等には、血流中に非生理的に高度なずり応力が生じ、出血(特に消化管)リスクが亢進する。AS患者が消化管出血を合併すれば、最初の報告者の名をとって、ハイド症候群とよばれているが、今日では、その出血は典型的には後天性フォン・ヴィレブランド症候群(AVWS)という止血異常下の消化管粘膜の直下にできる易出血性異常血管である消化管血管異形成からの出血であると考えられている。一方、V-A ECMOやImpella留置中では、ASと比べてより高度のAVWSを来たし、時に出血が治療継続の問題となる。
von Willebrand因子(VWF)は巨大な多量体として産生され、ずり応力依存的に切断され、血液中では2−80サブユニットからなる多量体として存在する。そして多量体の中では高分子量の多量体ほど止血機能に重要であり、非生理的に高度なずり応力を来す循環器疾患では、VWF多量体の切断が亢進してAVWSとなる。最近、VWF高分子多量体を定量的に評価されるようになり、この臨床実態が明らかになってきた。一方、多くのことが不明なままであった消化管血管異形成も、体系的な評価が行われるようになってきた。本シンポジウムでは、これらの研究成果を集積し、高ずり応力を伴う循環器疾患や機械的補助循環治療に伴う出血(特に消化管出血)の診断・治療について、理解を深めたい。
Symposium 10日本語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第9会場(会議センター3F 315)
SY10
包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)に対する治療戦略
Treatment strategies for patients with chronic limb-threatening ischemia
| 座長: | 児玉 章朗 | 愛知医科大学 血管外科 |
|---|---|---|
| 飯田 修 | 大阪警察病院 循環器内科 | |
| 演者: | 高原 充佳 | 大阪大学大学院医学系研究科 病院臨床検査学講座 |
| 山崎 貴紀 | 大阪公立大学大学院医学研究科 循環器内科学 | |
| 安永 元樹 | 大阪警察病院 循環器内科 | |
| 高木 友誠 | 総合高津中央病院 心臓血管センター | |
| 菊地 信介 | 旭川医科大学 外科学講座血管外科 | |
| 宇都宮 誠 | 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 |
包括的高度慢性下肢虚血 (CLTI)に対する治療戦略は、全身状態や創部重症度や解剖学的な難易度により決定される。BASIL1試験の結果をもとに作成されたガイドラインでは、1) 生命予後が2年以上と予測されかつ2) 良質な自家静脈を有する症例は、外科的治療が第一選択と推奨されてきた。一方で近年CLTIに対するRCT試験が複数報告された。BEST CLI試験では、1) 良質自家静脈を有するCLTIでは外科的バイパス術 (BSX)は血管内治療 (EVT)より良好な結果、2) 良質な自家静脈を有さない場合はBSXとEVTは同等の結果であった。一方で下腿動脈を有するCLTIを対象にしたBASIL 2試験では、BSXと比較してEVTが良好な結果であった。以上のエビデンスを元に、本邦特有のCLTI症例に対する治療戦略のフレームワークにおける岐路に立たされている。今回のシンポジウムのよる議論が、現状の問題点および今後の新しい治療戦略へのフレームワークの一助になればと考える。
Symposium 11英 語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第3会場(会議センター3F 301)
SY11
非動脈硬化性虚血性心疾患の診断と治療
Diagnosis and Treatment of Non-Atherosclerotic Ischemic Heart Disease
| 座長: | 天野 哲也 | 愛知医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| Jennifer Tremmel | Stanford University, USA |
Keynote Lecture:
| Jennifer Tremmel | Stanford University, USA |
| 演者: | 齋藤 佑一 | 千葉大学医学部附属病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 大塚 憲一郎 | 大阪公立大学大学院医学研究科 循環器内科学 | |
| 片岡 有 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 冠疾患科 | |
| 高橋 潤 | 東北大学病院 循環器内科 | |
| 平野 賢一 | 大阪大学大学院医学系研究科 中性脂肪学共同研究講座 |
虚血性心疾患(IHD)は現在なお世界で最も多くの死亡原因となっています。Global Burden of Disease Studyによると、2021年における全死亡数の約16%がIHDによるものでした。IHDは主に、内皮損傷、脂質蓄積、プラーク形成と進行、プラークの不安定化と破裂という複雑なプロセスを経て動脈硬化が発生することが原因であることが広く知られています。
IHDの病因を考慮すると、スタチンやPCSK9阻害剤などの脂質低下療法は、IHD管理の基礎であり、主に低密度リポタンパクコレステロール(LDL-C)のレベルを下げることを目的としています。脂質低下療法は、主要な心血管イベントのリスクを低減するのに非常に効果的ですが、脂質低下療法により最適なLDL-Cレベルを達成した患者でも、心血管疾患の「残余リスク」が依然として存在します。このリスクに対処するには、複合薬物療法、炎症やトリグリセリドなどの追加のリスク要因をターゲットにした包括的なアプローチが必要です。
このシンポジウムでは、非動脈硬化性虚血性心疾患の診断と治療に関する最新の知見と進歩を探求したいと考えています。
Symposium 12英 語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第18会場(会議センター5F 503)
SY12
日本発:AIを用いた医療技術とビックデータ研究
State-of-the-art AI-based medical technology and big data research from Japan
| 座長: | 西村 邦宏 | 国立循環器病研究センター 予防医学・疫学情報部 |
|---|---|---|
| Kunihiro Matsushita | Division of Cardiology, Johns Hopkins School of Medicine, USA |
Keynote Lecture:
| Kunihiro Matsushita | Division of Cardiology, Johns Hopkins School of Medicine, USA |
| 演者: | 釣本 翔太 | 金沢大学附属病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 糀谷 泰彦 | 京都大学大学院医学研究科 健康医療AI講座 | |
| 中山 敦子 | 公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科 | |
| 山地 杏平 | 京都大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 篠原 宏樹 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 |
Deep LearningによるAI革命の開始から20年、AI技術の活用は、研究段階から国内外の様々な医療分野において、画像診断から治療用のプログラム医療機器など普及、一般化の時代にさしかかっている。循環器領域においても、心エコー、冠動脈CTなどの画像、心電図を中心とした波形データ関連する報告が激増している。さらにゲノム・オミックス情報や生体モニングによる情報など個別化医療の現実化の取り組みも多く開始されている。臨床研究においても従来のClinical Randomized Trial(CRT)から大量のReal World DataをChatGPTをはじめとした大規模言語モデルにより活用し、希少疾患のコントロール群として用いる制度が国内でも開始されるなどパラダイムの変換が進んでいる。本シンポジウムでは医療の新時代におけるこれら循環器領域のAIの活用について国内外の最新の動向を紹介し、将来の展望について議論を深めたい。
Symposium 13日本語
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第4会場(会議センター3F 302)
SY13
大動脈弁疾患のライフタイムマネージメント
Lifetime Management of Aortic Valve Disease
| 座長: | 前川 裕一郎 | 浜松医科大学 内科学第三講座(循環器内科) |
|---|---|---|
| 湊谷 謙司 | 京都大学 心臓血管外科 | |
| 演者: | 髙見澤 格 | 公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科 |
| 中村 喜次 | 千葉西総合病院 心臓血管外科 | |
| 岩田 樹里 | 慶應義塾大学病院 循環器内科 | |
| 坂本 知浩 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 循環器内科 | |
| 竹治 泰明 | 金沢大学附属病院 循環器内科 | |
| 入江 勇旗 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心不全部門 |
大動脈弁狭窄症に対する侵襲的治療としてTAVIはいまや外科的弁置換(SAVR)を越える存在感を示している。本年になって、低手術リスクの症例に対するTAVIの成績がSAVRに対して一年間の追跡期間で非劣性であることが報告された。この報告は極めて短期間の結果であり、SAVR群でより合併手術が多い、すでに市場から淘汰された生体弁が多く含まれている等の問題点は指摘されている。しかし、今後はさらにTAVIの適応範囲が拡大していく可能性が高いと考えられている。とは言え、TAVIの耐久性が明らかでは無い現在、10-15年の耐久性が期待できる生体弁使用の意義は確実にある。一方で、TAVIの症例数が増加するにつれ、TAVI後のSAVRが容易ではないこと、SAVR後のいわゆるValve in Valveにも様々な問題点があることが示されてきた。また、透析症例においては、予後改善という点でTAVIの限界が指摘されている。大動脈弁閉鎖不全症に対してもTAVIによる治療の可能性が報告されてきているが、ようやく大動脈弁形成術も標準的な術式が確立しつつあり、生体弁を凌駕する成績も報告されている。大動脈弁形成術、SAVRとTAVIを適切に組み合わせて治療していくことが、大動脈弁疾患を有する患者にとって最大の利益をもたらすものであろうことには疑いが無い。
本セッションでは、最新の大動脈弁の侵襲的治療の現状を報告して頂き、患者の生涯を見据えた適切な治療とは何かについて議論したい。
Symposium 14英 語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第4会場(会議センター3F 302)
SY14
本邦での最適な心不全治療を見直す -EBMと個別化医療の融合-
Reconsidering the optimal treatment for heart failure in Japan
- Fusion of EBM and personalized medicine -
| 座長: | 絹川 弘一郎 | 富山大学附属病院 第二内科 |
|---|---|---|
| John J V McMurray | BHF Glasgow Cardiovascular Research Center, School of Cardiovascular and Metabolic Health, University of Glasgow, UK |
Keynote Lecture:
| John J V McMurray | BHF Glasgow Cardiovascular Research Center, School of Cardiovascular and Metabolic Health, University of Glasgow, UK |
| 演者: | 永井 利幸 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 |
|---|---|---|
| 後岡 広太郎 | 東北大学病院 循環器内科 | |
| 肥後 修一朗 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 内田 圭祐 | 富山大学附属病院 第二内科 | |
| 木岡 秀隆 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 舟越 俊介 | 京都大学iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門 |
慢性心不全治療は日進月歩であり、近年大規模臨床試験の結果に裏打ちされたいくつかの薬剤が新規にラインアップとして加わった。しかしながら、このようなEBMに基づく治療は多くの場合、Caucasianを中心とした患者データであり、我が国の心不全患者の代表的なphenotypeと一致していない場合もある。特にHFpEFのphenotypeが東アジアと欧米で著しく異なることは周知の事実であり、今後我が国独自のHFpEF phenotypeに最適な治療を見出していくことは喫緊の課題である。このようなことはある種の個別化医療と言えるが、本来個別化医療とは人種よりさらに小さな単位でのindividualizationが模索されるべきである。薬物治療やデバイス治療におけるresponseをバイオマーカーや遺伝子検査であらかじめ高い確度で予測することも個別化医療であろう。心筋症発症遺伝子変異の同定からgene therapyに向かうことも、またmy iPS細胞を用いた再生医療も、さらに疾患特異的iPS細胞との向き合いでより効果的な薬剤選択や創薬に至ることも、個別化から発した治療と言える。このシンポジウムでは日本人に特有の心不全治療を模索する試みからさらに個人単位での心不全治療を考える機会としたい。
Symposium 15英 語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第7会場(会議センター3F 311+312)
SY15
小児・成育循環器領域の遺伝子研究最前線
Cutting-edge genetic research in pediatric to grown-up cardiology
| 座長: | 山岸 敬幸 | 東京都立小児総合医療センター |
|---|---|---|
| Seema Mital | Pediatrics, Hospital for Sick Children, Canada |
Keynote Lecture:
| Seema Mital | Pediatrics, Hospital for Sick Children, Canada |
| 演者: | 古庄 知己 | 信州大学医学部 遺伝医学教室 |
|---|---|---|
| 新谷 泰範 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 分子薬理部 | |
| 野村 征太郎 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 井上 忠 | 慶應義塾大学医学部 小児科学 |
先天性心疾患は出生1000人につき、5~10人の頻度で発生し、新生児、乳児死亡の主要な原因の一つである。さらに小児循環器科、小児心臓血管外科の進歩と共に、小児期を乗り越えた成人先天性心疾患の患者は増え続け、今や成人循環器内科でも大きな領域を占めている。複雑な構造異常を有する先天性心疾患は小児期に完治するわけではなく、成人期に次世代の小児への遺伝を含め、様々な問題を抱える。先天性心疾患のうち、60%は多因子遺伝によるが、15%は遺伝子コピー数異常、13%は染色体異常、12%は単一遺伝子病が原因と報告されており、しばしば染色体異常・先天異常症候群の合併症として認識される。近年、染色体異常、先天異常症候群の責任領域・疾患遺伝子が次々と明らかにされ、先天性心疾患の発症メカニズムの解明に寄与している。一方、症候群を合併しない先天性心疾患においても、遺伝子解析技術の進歩により原因候補遺伝子の同定が進み、主に心臓発生に必須な転写因子、シグナル伝達因子、構造蛋白をコードする遺伝子の変化が報告されている。これらの成人を含む先天性心疾患について、遺伝学的検査により遺伝的要因が明らかになることは疾患の遺伝医療および管理に有用であり、今後、疾患の予防、治療にも広がっていくことが期待される。本シンポジウムでは、小児および成人先天性心疾患の遺伝子医学に関連する国内外の第一線の研究者により、最先端の研究を紹介する。
Symposium 16英 語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第2会場(会議センター1F メインホール)
SY16
心血管再生医療の最先端
Progress in Cardiovascular Regenerative Medicine
| 座長: | 家田 真樹 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 |
|---|---|---|
| Kenneth Walsh | University of Virginia School of Medicine, USA |
Keynote Lecture:
| Kenneth Walsh | University of Virginia School of Medicine, USA |
| 演者: | Youngkeun Ahn | Chonnam National University Hospital, Korea |
|---|---|---|
| 吉田 善紀 | 京都大学iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門 | |
| 貞廣 威太郎 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 | |
| 高島 伸一郎 | 金沢大学医薬保健研究域医学系 循環器内科 |
難治性心不全や重症下肢虚血に対する心血管再生医療の期待は高い。ヒトiPS細胞、間葉系細胞、遺伝子治療、核酸医薬など様々な選択肢がでてきた。本シンポジウムでは心血管再生医療の最先端というテーマで、現在臨床研究や治験を行っている研究から、これから臨床応用を目指す基礎的な研究まで、様々な研究者から最先端の研究成果を聞くセッションとしたい。多くの先生方の応募を期待している。
Symposium 17日本語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第6会場(会議センター3F 304)
SY17
脳卒中・心臓病等総合支援センターの現状と今後の展望
Current Situation and Future Prospects of Nōsotchū Shinzō-byō Tō Sōgō Shien Centers
| 座長: | 藤本 茂 | 自治医科大学 内科学講座神経内科学部門 |
|---|---|---|
| 安田 聡 | 東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野 | |
| 演者: | 石津 智子 | 筑波大学 医学医療系 循環器内科 |
| 小田 登 | 広島大学病院 循環器内科 | |
| 白戸 崇 | 東北大学病院 循環器内科 | |
| 栗田 浩樹 | 埼玉医科大学 国際医療センター 脳卒中外科 | |
| 宮本 享 | 京都大学医学部附属病院 脳卒中療養支援センター |
厚生労働省は、循環器病患者支援の中核として「脳卒中・心臓病等総合支援センター」を令和4年度にモデル事業として開始した。初年度は10自治体、令和5年度は15自治体、令和6年度は12自治体に拡大している。これらのセンターは、専門的な知識を持つ医療機関が都道府県と連携し、地域の医療機関と協力体制を強化し、包括的な支援体制を構築することを目的としている。本セッションでは、各事例報告とともにその課題について議論する。
Symposium 18日本語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第19会場(アネックスホール2F F201+F202)
SY18
循環器医が知っておくべきがん治療における心血管毒性のマネジメント
〜Onco-cardiologyガイドラインより
SMO-JCS Joint Symposium: Management of Cancer Therapy-related Cardiovascular Toxicity - What Cardiologists Need to Know from Onco-cardiology Guidelines
| 座長: | 矢野 真吾 | 東京慈恵会医科大学 腫瘍・血液内科 |
|---|---|---|
| 赤澤 宏 | 東京大学大学院医学系研究科循環器内科学 | |
| 演者: | 郡司 匡弘 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 腫瘍・血液内科 |
| 田尻 和子 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 循環器科 | |
| 澤木 正孝 | 国立病院機構 名古屋医療センター ブレストセンター・乳腺外科 | |
| 丸山 大 | 公益財団法人がん研究会有明病院 血液腫瘍科 | |
| 庄司 正昭 | 国立がん研究センター中央病院 総合内科・循環器内科 |
がん治療の目覚ましい進歩にともなって、がん患者・サバイバーにおける心血管リスク因子の管理やがん治療に関連する心血管毒性への対応が生命予後やQOLに大きな影響を与えるようになっている。また、がんの既往が循環器疾患の将来的な発症の重大なリスク因子となるので、がんサバイバーにおいては長期的な心血管モニタリングが必要となる。このような状況の中、がん診療科と循環器科が診療科横断的に、また多職種が連携・協働して対応する腫瘍循環器の診療体制が整備されつつある。2023年3月には本邦で初めてのOnco-cardiologyガイドラインが発表され、専門家らのコンセンサスをベースに具体的な診療指針が示された。一方で、がん薬物療法は治療プロトコールが多様であり、がん種やステージ、患者背景も複雑なためエビデンスは十分とは言い難い。この分野における臨床研究やビッグデータの活用によりエビデンスの集積が求められるが、本ガイドラインはその橋頭堡になると期待される。本シンポジウムでは、腫瘍循循環器マネジメントにおいて循環器医が知っておくべきエッセンスを紹介するとともに、エビデンス診療ギャップの解消のための課題や問題点、今後の方向性について討議したい。
Symposium 19日本語
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第3会場(会議センター3F 301)
SY19
三尖弁閉鎖不全症の診断・治療の最前線
The cutting edge of diagnosis and treatment in tricuspid regurgitation
| 座長: | 國原 孝 | 東京慈恵会医科大学 心臓外科 |
|---|---|---|
| 泉 知里 | 国立循環器病研究センター | |
| 演者: | 宇都宮 裕人 | 広島大学大学院医系科学研究科 循環器内科学 |
| 佐々木 晴香 | 千葉大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 櫻井 啓暢 | 国立循環器病研究センター 心臓外科 | |
| 杉浦 淳史 | University Hospital Bonn ボン大学病院 | |
| 山田 聡 | 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 |
三尖弁に対する手術は、左心系弁膜症の際に同時に行う三尖弁手術と、重症三尖弁逆流(TR)に対する三尖弁単独(または主目的)の手術に分けて考える必要がある。
前者の左心系弁膜症の際に三尖弁形成術を追加するか否か?は外科医にとって永遠のテーマと言える。2000年代に経胸壁エコーで35 or 40 mm (21 mm/m2)あるいは術中所見で70mm 以上であればTR gradeに関わらず三尖弁形成術の追加が推奨された。しかし術前3D経食道エコーがルーチンになり、内視鏡による小切開手術が増加しつつある中、この基準が時代にそぐわないようになってきているのは否めない。
一方、重症TR症例に対する三尖弁単独手術は、通常の左心系弁膜症に比して予後が悪いことが知られている。近い将来カテーテル治療が導入されることが予想され、また右室機能を考慮した術式が提唱されるなど、その介入時期、介入方法が盛んに議論されるようになってきた。三尖弁に対しても3D心エコーやその他の画像診断により新たな知見が重ねられ、また術後の予後に大きく関連しているであろう右室機能に関しても議論が深まっている。
高齢社会においておそらくますます大きな問題になると予想される三尖弁について、ハートチームで活発な議論を行いたい。
Symposium 20日本語
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第6会場(会議センター3F 304)
SY20
クリニックでのガイドラインの使い方
-エビデンス・プラクティス・ギャップはなぜ起こるのか
Utilization of Guidelines in Clinical Settings
- Why Evidence Practice Gaps Occur
| 座長: | 南野 徹 | 順天堂大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 弓野 大 | 医療法人社団ゆみの | |
| 演者: | 北岡 裕章 | 高知大学医学部 老年病・循環器内科学 |
| 勝谷 友宏 | 勝谷医院 内科 | |
| 土肥 智貴 | 医療法人社団ゆみの 循環器予防医療部 | |
| 小田倉 弘典 | 土橋内科医院 | |
| 大西 勝也 | 大西内科ハートクリニック |
超高齢社会にともなう循環器疾患患者の増加とともに、医療体制として機能分化および病診連携が重要となる。このため、地域での循環器医療の充実が必要である。一方で、患者の高齢化とともに、腎機能障害や認知症などの併存疾患の増加、身体機能低下によるサルコペニアによる通院困難患者の増加、独居や老々介護、貧困の問題など、social determinants of healthのimpactなど、エビデンスに基づくガイドラインとのギャップがある。たとえば、心不全治療薬において腎機能障害をもつ患者へどこまでARB、MRAを投与していくおか、また貧困、独居の高齢者に対して新薬を導入していくのか、デバイス植え込みについて患者と家族の希望が一致しない、などがあげられる。本セッションでは、地域での循環器クリニックにおいて、日常診療から起きているエビデンス・プラクティス・ギャップがどのような場面でおきてくるのか、全国の先生方と議論できれば幸甚である。
Symposium 21日本語
2025年3月30日(日)13:20~14:50 第2会場(会議センター1F メインホール)
SY21
不整脈治療のNew Technology
New Technologies for Arrhythmia Treatment
| 座長: | 庄田 守男 | 東京女子医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 因田 恭也 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
演者:【PFA】
| 横山 正明 | 東京慈恵会医科大学 循環器内科 |
【VTアブレーション】
| 鎌倉 令 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 |
【放射線治療】
| 甲谷 太郎 | メイヨークリニック 循環器内科 | |
| 網野 真理 | 東海大学医学部 内科学系循環器内科学 | |
| 下條 将史 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器先端医療研究学寄附講座 |
【CIED】
| 佐藤 俊明 | 杏林大学 医学部不整脈先進治療学研究講座 | |
| 和田 暢 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門 |
近年心臓電気生理学の知見が深まるとともに、種々の頻脈性不整脈メカニズムが3Dマッピングシステムの進歩により詳細に解明され、容易にアブレーション標的部位が同定されるようになった。また治療方法においてもpulsed field ablationや放射線照射などの新機軸が開発されようとしている。致死的心室性不整脈に対するICDなどのデバイス治療においても、小型で長寿命、診断能力が高く心不全にも対応できる機器が開発されている。また、徐脈ペーシングにおいては、伝統的な右室心尖部ペーシングから生理的心室収縮が得られる刺激伝導系ペーシングのような新しい方法にパラダイムシフトしつつある。このように、最近の不整脈診断および治療の進歩は目覚ましいが、われわれ実臨床医にはその光の部分だけではなく闇に関しても明らかにしなければならない責務がある。本セッションでは、現在、不整脈治療に用いられている、あるいは今後使われようとしている最先端・最新の治療法や医療機器について知見を深め、不整脈治療の現状や将来を見極めたい。
Symposium 22日本語
2025年3月30日(日)13:20~14:50 第6会場(会議センター3F 304)
SY22
高度急性期医療体制の構築とMC協議会における循環器内科医の役割
The establishment of an advanced acute medical care system and the role of cardiologists in the MC council
| 座長: | 鈴木 洋 | 昭和大学藤が丘病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 田原 良雄 | 国立循環器病研究センター 心臓血管内科/救急部 | |
| 演者: | 菊地 研 | 獨協医科大学 心臓・血管内科/循環器内科 救命救急センター |
| 石倉 健 | 三重大学医学部附属病院 高度救命救急・総合集中治療センター | |
| 山本 剛 | 日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 | |
| 松澤 泰志 | 熊本大学病院 循環器内科 | |
| 花田 裕之 | 弘前大学大学院医学研究科 救急災害・総合診療医学講座 | |
| 竹内 一郎 | 横浜市立大学 救急医学/高度救命救急センター |
厚生労働省の地域医療構想のもと、各地域の高度急性期医療体制の整備が徐々に進んでいるが、急速な高齢化にともない高度急性期医療を必要とする症例も増加しており、また2024年4月からの医師の働き方改革にともない、高度急性期医療体制のすみやかな構築や再編成が急務である。人口密集地域では、緊急PCIが可能な病院が多数存在する一方、人口非密集地域ではSTEMI症例の長時間搬送を余儀なくされている地域も多いのが現状である。高度急性期医療体制の構築には何が必要であるか、また都道府県や各地域における現在の状況や問題点を討論したい。
一方、MC協議会について循環器領域で議論をされることはこれまで少なく、それは各都道府県や地域のMC協議会の医師側の構成メンバーが救急医療の専門家が主体で循環器医師が少ない場合が多いことが一因にあげられる。病院前12誘導心電図の有用性が幅広く認識されてきた現在、救急現場から医療機関への搬送に係る事項に循環器内科医が密接にかかわることが重要と考える。スムーズな循環器救急患者の受け入れや救急隊との連携強化のために都道府県や地域のMC協議会における循環器医のかかわりについても含め、循環器救急搬送に関連する問題について幅広く討論したい。
Symposium 23日本語
2025年3月30日(日)13:20~14:50 第9会場(会議センター3F 315)
SY23
心不全の包括的疾病管理
Multidisciplinary Disease Management for Heart Failure
| 座長: | 北岡 裕章 | 高知大学 老年病・循環器内科学 |
|---|---|---|
| 眞茅 みゆき | 北里大学看護学部 看護システム学 | |
| 演者: | 大山 宗馬 | 東北大学病院 循環器内科学分野 |
| 髙林 健介 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 循環器内科 | |
| 伊藤 弘将 | 三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学 | |
| 衣笠 良治 | 鳥取大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 弓野 大 | 医療法人社団ゆみの |
心不全患者のQOLに大きく影響する増悪予防の観点から、multidisciplinary teamによる疾病管理は重要であり、ガイドラインで提唱されて以降、心不全医療の1つの核となっている。一方で、特に高齢心不全患者は,認知機能障害、フレイル、サルコペニア、低栄養、ポリファーマシー、抑うつ、独居などによる介護力不足など、医学的のみならず社会的にも複合的な問題を数多く抱えている。また、心不全患者の退院後の在宅療養時間を維持するために、在宅医療や地域連携の重要性は明白であるが、未だ発展途上の段階である。さらは、心不全の疾病管理の対象は全てのステージの心不全であり、患者、家族、さらには社会に対し心不全の予防啓発を推進することも求められる。一方、心不全療養指導士の誕生、心不全増悪の早期発見や地域の多職種連携におけるInternet of Things(loT)の活用、脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業など、心不全の疾病管理の普及、質向上が期待できる取り組みも進んでいる。本セッションでは、心不全患者が抱える複雑な問題や現在の医療、社会の課題に対応する疾病管理のあり方について、先駆的事例とエビデンスに基づく議論を期待したい。
Symposium 24日本語
2025年3月30日(日)13:20~14:50 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SY24
日本のDT治療は今後どうあるべきか
What should DT treatment in Japan look like?
| 座長: | 小野 稔 | 東京大学心臓外科 |
|---|---|---|
| 坂田 泰史 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 演者: | 絹川 弘一郎 | 富山大学附属病院 第二内科 |
| 岩永 光史 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 移植医療部 | |
| 兒玉 和久 | 済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科 | |
| 肥後 太基 | 医療法人社団 ゆみの | |
| 斎藤 俊輔 | 大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 |
日本における長期在宅補助人工心臓治療(Destination Therapy: DT)は、2021年4月に7施設で開始された。その後2023年7月に12施設が追加され、現在は19施設で行われている。装着症例も順調に増加しており、多くの患者が社会復帰を果たしている。日本における重症心不全治療として重要な役割を果たし始めている。
一方で、いくつかの課題も明らかになっている。まず、感染や血栓などの合併症の管理は長期使用になるほど難しくなる。また、長期にわたる右室機能や腎機能の悪化といった、左室補助以外の身体的要因も完全には予測できず、十分な生活の質を得られない症例も存在する。
さらに、装着や管理が可能な施設が全国で均等に整備されているわけではなく、その恩恵を受けられない地域も残っている。地域の特性に応じて、補助人工心臓を装着する患者やその家族のサポート体制、自宅でのケア、緊急時の対応体制を整える必要がある。また、補助人工心臓を装着した患者が社会にどのように受け入れられるかも定まっておらず、職場復帰などの社会的支援が求められている。
このように、DT医療には多くの医学的・社会的課題が残されているが、これは逆に言えば、さらに多くの患者に貢献できる可能性があるということである。本シンポジウムでは、どのようにすればもっと患者のためのDT医療を提供できるか、活発な議論を行いたい。
Symposium 25日本語
2025年3月30日(日)15:30~17:00 第6会場(会議センター3F 304)
SY25
循環器内科医師サブスペシャリティーとしての集中治療医学
-急性期治療に興味のある若手循環器内科医が学べる環境づくりの重要性-
Critical care cardiology as a subspeciality within cardiovascular medicine
-The importance of an effective training environment for young cardiologists-
| 座長: | 今村 浩 | 信州大学医学部 救急集中治療医学 |
|---|---|---|
| 竹内 一郎 | 横浜市立大学 救急医学/高度救命救急センター | |
| 演者: | 今村 浩 | 信州大学医学部 救急集中治療医学 |
| 川上 将司 | 飯塚病院 循環器内科 | |
| 真玉 英生 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 | |
| 嘉嶋 勇一郎 | 信州大学医学部救急集中治療医学 |
ディスカッサント:
| 山本 剛 | 日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 | |
| 新沼 廣幸 | 聖路加国際大学 聖路加国際病院 循環器内科 | |
| 澤村 匡史 | 済生会熊本病院 |
重症心血管疾患の治療において、原疾患の根本治療と質の高い集中治療は車の両輪であり、特に若手循環器医が集中治療を学ぶ意義は大きい。
本セッションは本学会と日本集中治療医学会との合同企画であり、まず導入として循環器集中治療の現状と課題を提示した後、実際の心血管症例を題材として、循環器医、集中治療医、循環器集中治療医等による症例検討を行う。以前に比べてより複雑な病態と多臓器の障害を有するようになった現代の重症患者管理のために、循環器集中治療医学の最新の知見をどのように活かしたらよいか考え、学ぶ場とする。若手循環器医が、循環器サブスペシャリティーとしてのCritical care cardiologyを学ぶ環境づくりについても議論したい。
本ジョイントシンポジウムが、今後の我が国における循環器集中治療の質の向上の一助になることを期待する。
Symposium 26日本語
2025年3月30日(日)15:30~17:00 第9会場(会議センター3F 315)
SY26
性差医療を再考する -啓蒙・実践への道標-
Gender-Specific Medicine Revisited: A Guide to Enlightenment and Practice
| 座長: | 阿古 潤哉 | 北里大学医学部 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 瀧原 圭子 | 大阪大学キャンパスライフ健康支援センター |
追加発言:
| 東條 美奈子 | 北里大学医療衛生学部 |
| 演者: | 安田 聡 | 東北大学大学病院 循環器内科学分野 |
|---|---|---|
| 塚田(哲翁) 弥生 | 日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科 | |
| 松島 将士 | 九州大学病院 循環器内科 | |
| 窪田 佳代子 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科 | |
| 副島 京子 | 杏林大学医学部付属病院 循環器内科 |
性差医療の始まりは、妊孕性を配慮したが故に除外された、1970年代の医学・薬学臨床研究への女性データの欠如という負の歴史に始まる。しかし、1980年代からは、むしろすべての年齢の女性において、女性特有の病態について研究されるべきという方針に従い、現在の性差医療、すなわち、生物学的性別の違いの影響により発症率や重症度、病状経過に差をみる疾患に関する学際領域として発展してきた。
日本では2010年に日本循環器学会が初めて「循環器領域における性差医療に関するガイドライン」を発表したが、時代の変遷の影響とエビデンス蓄積を考慮し、本年発表された「多様性に配慮した循環器診療ガイドライン」において、その内容が14年ぶりに改訂された。このように社会的な多様性への理解やムーブメントが時代と共に注目されるなか、性差医学についても改めてその必要性・重要性に注目があつまっているものの、同時に、未だ十分なエビデンスが不足している状況にある。この新たなガイドラインを含め、性差医療を実践的に診療に活かすためにはどう取り組むべきか、本セッションでは、これまでの経過、現状の問題点、さらに今後エビデンス構築にむけて、各エキスパートに話を伺い、日本の循環器診療における性差医療のあり方とその実践について議論する。
Symposium 27日本語
2025年3月30日(日)15:30~17:00 第16会場(会議センター5F 501)
SY27
循環器CT最前線
Frontiers in Cardiovascular CT
| 座長: | 陣崎 雅弘 | 慶應義塾大学 放射線科 |
|---|---|---|
| 三好 亨 | 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 | |
| 演者: | 中西 理子 | 東邦大学医学部、東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 |
| 三好 亨 | 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 | |
| 藤本 進一郎 | 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科 | |
| 山田 祥岳 | 慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 | |
| 小池 秀樹 | 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 | |
| 尾田 済太郎 | 熊本大学病院 画像診断・治療科 |
心臓CTは、近年急速に進化し、循環器領域における診断や治療において重要な役割を果たしている。非侵襲的かつ高い解像度を備え、心臓および冠動脈に関する詳細な情報を提供するため、患者の評価や治療計画において不可欠なツールとなっている。冠動脈CTでは、冠動脈の解剖学的評価や狭窄の程度、プラークの特徴など様々な情報が得られる。最近ではフォトンカウンティングCTの登場により、従来のCTに比べて高い空間分解能や低い被ばくを可能とし、より精緻な画像を提供することが期待されている。虚血評価には、侵襲的検査に代わりCT-FFRが臨床現場で活用されるようになり、近年の虚血性心疾患の診療ガイドラインでは、冠動脈CTの役割が強調され、治療方針決定に重要な位置づけとなっている。更には立位CTが登場し、静脈系の評価も可能な時代になりつつある。また、構造的心疾患に対する経カテーテル治療の発展に伴い、構造的心疾患におけるマルチモダリティイメージングの一つとして心臓CTは、その有用性を発揮している。このように、心臓CTの技術革新と研究の進展により、その応用範囲はますます広がっている。本シンポジウムでは、AIも含めた心臓CTの最新の技術や応用に焦点を当て、その現状と将来の展望について議論し、皆様と共に深く掘り下げたい。
Symposium 28日本語
2025年3月30日(日)15:30~17:00 第18会場(会議センター5F 503)
SY28
循環器領域における診療報酬の現状と課題
Current Status and Issues of Medical Reimbursement in the Cardiovascular Medicine
| 座長: | 的場 聖明 | 京都府立医科大学 大学院医学研究科 循環器内科 |
|---|---|---|
| 佐野 元昭 | 山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学 | |
| 演者: | 的場 聖明 | 京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科 |
| 横式 尚司 | 市立札幌病院 循環器内科 | |
| 内海 仁志 | 山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 | |
| 佐野 元昭 | 山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学講座 |
本シンポジウムでは、循環器医療従事者ならではの視点で、保険診療を目指す新しい医療、技術の発表をお待ちしています。
令和3年度の国民医療費は約45兆円で、主傷病による分類では、「循環器系の疾患」6兆1,116億円(構成 割合18.9%)が最も多く、次いで「新生物<腫瘍>」4兆8,428億円(同14.9%)、「筋骨格系及び結合組織の疾患」2兆6,076億円(同8.0%)と報告されています。
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/21/dl/kekka.pdf)
高齢化先進国の日本では、いかに持続可能で、安心安全な医療を迅速に届けるかが課題です。日本循環器学会の保険診療委員会では、循環器関連の学会と共同で新しい医療技術、医用機器、薬剤の診療報酬追加や修正に取り組んでいます。
今後の循環器医療の発展に向けて、必要な診療技術の開発、保険診療に向けての熱い議論を期待しています。
会長特別企画
会長特別企画 1日本語
2025年3月28日(金)8:00~9:30 第19会場(アネックスホール2F F201+F202)
SS01
心不全におけるGuideline Directed Medical Therapyを再考する
| 座長: | 井澤 英夫 | 藤田医科大学医学部 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 末永 祐哉 | 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学講座 | |
| 演者: | 近藤 徹 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
| 松川 龍一 | 福岡赤十字病院 循環器内科 | |
| 後岡 広太郎 | 東北大学病院 循環器内科 | |
| 大西 勝也 | 大西内科ハートクリニック |
会長特別企画 2日本語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
SS02
U40と一緒に考える今後の循環器医療
| 座長: | 奥村 貴裕 | 名古屋大学大学院医学系研究科 先進循環器治療学/循環器内科学 |
|---|---|---|
| 青山 里恵 | 船橋市立医療センター心臓血管センター循環器内科 | |
| 演者: | 末永 祐哉 | 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学講座 |
| 中澤 学 | 近畿大学 循環器内科 | |
| 楠瀬 賢也 | 琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学 | |
| 金岡 幸嗣朗 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 情報利用促進部 | |
| 木田 圭亮 | 聖マリアンナ医科大学 薬理学 |
会長特別企画 3日本語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
SS03
デジタル循環器学とモバイルヘルス・診療支援システム
| 座長: | 野村 章洋 | 金沢大学融合研究域/循環器内科 |
|---|---|---|
| 土肥 薫 | 三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学 | |
| 演者: | 永井 利幸 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 |
| 鍵山 暢之 | 順天堂大学 循環器内科 | |
| 網谷 英介 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 山田 純生 | 愛知医科大学 循環器内科 | |
| 田中 彰子 | 厚生労働省医政局 |
会長特別企画 4日本語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第5会場(会議センター3F 303)
SS04
CPC(Clinico-pathological conference)
~あらためて臨床ー病理連携の重要性を知る~
| 座長: | 柴田 剛徳 | 宮崎市郡医師会病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 畠山 金太 | 国立循環器病研究センター 病理部 | |
| 演者: | 新井 陸 | 日本大学医学部内科学系 循環器内科学分野 |
| 羽尾 裕之 | 日本大学医学部 病態病理学系人体病理学分野 | |
| 相川 裕彦 | 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 | |
| 雨宮 妃 | 国立循環器研究センター 病理部 | |
| 西平 賢作 | 宮崎市郡医師会病院 循環器内科 | |
| 浅田 祐士郎 | 宮崎市郡医師会病院 病理診断科 |
内科コメンテーター:
| 上野 高史 | 聖峰会マリン病院 | |
| 西垣 和彦 | 岐阜県立下呂温泉病院 内科:循環器内科 | |
| 児玉 隆秀 | 虎の門病院 循環器センター内科 |
会長特別企画 5日本語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第5会場(会議センター3F 303)
SS05
Brugada・J波症候群のメカニズムと治療
| 座長: | 清水 渉 | 日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 |
|---|---|---|
| 青沼 和隆 | 水戸済生会病院 | |
| 演者: | 森田 宏 | 岡山大学学術研究院先端循環器治療学講座 |
| 髙木 雅彦 | 関西医科大学総合医療センター 不整脈治療センター | |
| 因田 恭也 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科 | |
| 小松 雄樹 | 筑波大学附属病院 循環器内科 |
会長特別企画 6日本語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第17会場(会議センター5F 502)
SS06
新たなテクノロジーが切り拓く血管研究の最前線
| 座長: | 尾池 雄一 | 熊本大学 分子遺伝学講座 |
|---|---|---|
| 中岡 良和 | 国立循環器病研究センター研究所血管生理学部/病院心臓血管内科 | |
| 演者: | 清水 逸平 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心血管老化制御部 |
| 内藤 尚道 | 金沢大学 医薬保健研究域・血管分子生理 | |
| 坂上 倫久 | 愛媛大学 医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科学 | |
| 久保田 義顕 | 慶應義塾大学医学部 解剖学 | |
| 加藤 勝洋 | 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 |
会長特別企画 7日本語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
SS07
CJ、CRのIFをいかに上げるか
| 座長: | 安斉 俊久 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 |
|---|---|---|
| 萩原 誠久 | 医療法人社団 ゆみの | |
| 演者: | 安斉 俊久 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 |
| 辻田 賢一 | 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 | |
| 南野 徹 | 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科 |
会長特別企画 8日本語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
SS08
脂肪幹細胞を用いた基礎・臨床研究
| 座長: | 柴田 玲 | 中部電力株式会社 健康管理室 |
|---|---|---|
| 岩畔 英樹 | 医療法人再生会そばじまクリニック/金沢医科大学 再生医療センター | |
| 演者: | 清水 優樹 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
| 薄井 荘一郎 | 金沢大学附属病院 循環器内科 | |
| 佐々木 健一郎 | 久留米大学 医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門 | |
| 成田 伸伍 | 名古屋大学医学部医学系研究科 循環器内科学 |
会長特別企画 9日本語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第9会場(会議センター3F 315)
SS09
J4CS in JCS: 心原性ショックマネジメントプロトコル
| 座長: | 佐藤 直樹 | かわぐち心臓呼吸器病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 菊地 研 | 獨協医科大学 救命救急センター | |
| 演者: | 佐藤 直樹 | かわぐち心臓呼吸器病院 循環器内科 |
| 中島 啓裕 | 熊本大学 循環器内科 | |
| 近藤 徹 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 中田 淳 | 日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 | |
| 川上 将司 | 飯塚病院 循環器内科 |
会長特別企画 10日本語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第4会場(会議センター3F 302)
SS10
心不全の在宅診療と緩和ケア 現場と政策
| 座長: | 室原 豊明 | 名古屋大学大学院医学系研究科 病態内科学講座 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 安斉 俊久 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 | |
| 演者: | 樽見 英樹 | 日本年金機構 |
| 弓野 大 | 医療法人社団ゆみの | |
| 小笠原 文雄 | 小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニック |
会長特別企画 11日本語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第9会場(会議センター3F 315)
SS11
CAC(Clinico-anatomical conference)正常解剖を知ってますか?手技と解剖の関係
| 座長: | 井川 修 | 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 内科・循環器内科 |
|---|---|---|
| 國原 孝 | 東京慈恵会医科大学 心臓外科 | |
| 演者: | 芳村 直樹 | 国立大学法人富山大学医学部 第一外科 |
| 川田 典靖 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 心臓外科 | |
| 泉 佑樹 | 公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科 | |
| 國原 孝 | 東京慈恵会医科大学心臓外科 | |
| 井川 修 | 医療法人社団恵仁会 セントマーガレット病院 内科・循環器内科 |
会長特別企画(コメディカル)
数字で見抜く!次世代チーム医療 -QIで紐解く医療現場のブレイクスル-日本語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第8会場(会議センター3F 313+314)
CSS
| 座長: | 衣笠 良治 | 鳥取大学 循環器・内分泌代謝内科学分野 |
|---|---|---|
| 中島 菜穂子 | 久留米大学病院 看護部 | |
| 演者: | 水野 篤 | 聖路加国際病院 循環器内科 |
| 植村 祐介 | 安城更生病院 循環器センター | |
| 水川 真理子 | 神戸市看護大学 いちかんダイバーシティ看護開発センター | |
| 福勢 麻結子 | 東京医科大学病院 栄養管理科 | |
| 片野 唆敏 | 札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部 |
ミート・ザ・エキスパート
Meet the Expert 1英 語
2025年3月28日(金)9:35~11:05 第5会場(会議センター3F 303)
ME1
心不全基礎研究の最前線
Frontiers of Basic Research on Heart Failure
| 座長: | Stefan Offermanns | Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Germany |
|---|---|---|
| Junichi Sadoshima | Rutgers New Jersey Medical School, USA | |
| 演者: | 竹藤 幹人 | 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 |
| 川瀬 治哉 | マックスプランク研究所 | |
| 候 聡志 | 東京大学 大学院医学系研究科 先端循環器医科学講座 | |
| 的場 哲哉 | 九州大学病院 循環器内科 | |
| 木岡 秀隆 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
Meet the Expert 2日本語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第3会場(会議センター3F 301)
ME2
重症心不全患者における心室不整脈の管理
| 座長: | 絹川 弘一郎 | 富山大学附属病院 第二内科 |
|---|---|---|
| 野上 昭彦 | 東京心臓不整脈病院 難治性不整脈治療研究センター | |
| 演者: | 近藤 徹 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
| 中村 牧子 | 富山大学附属病院 第二内科 | |
| 山形 研一郎 | 東京大学医学部附属病院 | |
| 小松 雄樹 | 筑波大学附属病院 循環器内科 |
Meet the Expert 3日本語
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第9会場(会議センター3F 315)
ME3
核酸医薬 siRNA
| 座長: | 程 久美子 | 東京科学大学 総合研究院 核酸・ペプチド創薬治療研究(TIDE)センター |
|---|---|---|
| 斯波 真理子 | 大阪医科薬科大学 循環器センター | |
| 演者: | 程 久美子 | 東京科学大学 総合研究院 核酸・ペプチド創薬治療研究(TIDE)センター |
| 和田 猛 | 東京理科大学 薬学部 | |
| 斯波 真理子 | 大阪医科薬科大学 循環器センター | |
| 小倉 正恒 | 順天堂大学医療科学部臨床検査学科 |
Meet the Expert 4日本語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第5会場(会議センター3F 303)
ME4
重症心疾患と妊娠 ~Cardio-Obstericsの今を考える~
| 座長: | 窪田 佳代子 | 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科 |
|---|---|---|
| 牧 尚孝 | 自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科 | |
| 演者: | 神谷 千津子 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 産婦人科 |
| 相馬 桂 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 平川 今日子 | 熊本大学病院 循環器内科 |
ホットトピック
Hot Topic 1日本語
2025年3月28日(金)8:00~9:30 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
HT01
企業家セッション -アントレプレナーたちの夢と野望-
| 座長: | 室原 豊明 | 名古屋大学大学院医学系研究科 病態内科学講座 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 福田 恵一 | Heartseed株式会社 | |
| 演者: | 福田 恵一 | Heartseed株式会社 |
| 坪田 一男 | 株式会社坪田ラボ代表取締役CEO 慶應義塾大学名誉教授 | |
| 石見 陽 | メドピア株式会社 代表取締役社長 CEO (医師・医学博士) |
Hot Topic 2日本語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第4会場(会議センター3F 302)
HT02
ISHR World Congress 2025:日本の循環器基礎研究の将来
| 座長: | 小室 一成 | 国際医療福祉大学・東京大学 |
|---|---|---|
| 竹石 恭知 | 福島県立医科大学 循環器内科 | |
| 演者: | 斎藤 能彦 | 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター |
| 塩島 一朗 | 関西医科大学 内科学第二講座 | |
| 清水 逸平 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心血管老化制御部 | |
| 野村 征太郎 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 吉田 尚史 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター研究所 先端医療技術開発部 |
Hot Topic 3日本語
2025年3月29日(土)10:30~11:30 第22会場(展示ホール1F ホールB)
HT03
大阪万博 2025 の見どころ
| 座長: | 坂田 泰史 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 福田 大受 | 大阪公立大学 循環器内科 | |
| 演者: | 森下 竜一 | 大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学 |
| 更家 悠介 | サラヤ株式会社 代表取締役社長 |
Hot Topic 4英 語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第3会場(会議センター3F 301)
HT04
加齢の制御による心血管疾患治療へのアベニュー
Can aging research modify cardiovascular disease
| 座長: | Kenneth Walsh | University of Virginia, USA |
|---|---|---|
| 大内 乗有 | 名古屋大学大学院医学系研究科 分子循環器医学講座 | |
| 演者: | 南野 徹 | 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科 |
| 尾池 雄一 | 熊本大学大学院生命科学研究部 分子遺伝学 | |
| 高倉 伸幸 | 大阪大学・微生物病研究所 情報伝達分野 | |
| 由良 義充 | 名古屋大学 循環器内科 |
Hot Topic 5日本語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第17会場(会議センター5F 502)
HT05
臓器間ネットワークから紐解く心血管病
| 座長: | 武田 憲彦 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 佐野 元昭 | 山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学講座 | |
| 演者: | 大橋 浩二 | 名古屋大学大学院医学系研究科 分子循環器医学寄附講座 |
| 佐野 元昭 | 山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学講座 | |
| 絹川 真太郎 | 九州大学大学院医学研究院 循環器内科 | |
| 山下 智也 | 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科・先端医療学分野 | |
| 武田 憲彦 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 |
Hot Topic 6日本語
2025年3月30日(日)15:30~17:00 第8会場(会議センター3F 313+314)
HT06
PH-VTEガイドライン2025 を読み解く
| 座長: | 片岡 雅晴 | 産業医科大学医学部第2内科学 |
|---|---|---|
| 足立 史郎 | 名古屋大学 循環器内科 | |
| 演者: | 田村 雄一 | 国際医療福祉大学医学部 循環器内科学 |
| 福本 義弘 | 久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門 | |
| 大郷 剛 | 国立循環器病研究センター | |
| 山田 典一 | 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 循環器内科 | |
| 山下 侑吾 | 京都大学大学院医学研究科 循環器内科 |
ラウンドテーブルディスカッション
Round Table Discussion 1日本語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第5会場(会議センター3F 303)
RT1
Cardiopulmonary arrest(CPA)症例をどう治療するか?
| 座長: | 石見 拓 | 京都大学大学院医学研究科 予防医療学分野 |
|---|---|---|
| 菊地 研 | 獨協医科大学 救命救急センター | |
| 演者: | 風間 信吾 | 名古屋大学医学部附属病院 救急集中治療部・循環器内科 |
| 中島 啓裕 | 熊本大学病院 循環器内科 | |
| 中田 淳 | 日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 | |
| 川上 将司 | 飯塚病院 循環器内科 |
Round Table Discussion 2日本語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第18会場(会議センター5F 503)
RT2
心アミロイドーシス診療最前線
| 座長: | 猪又 孝元 | 新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 北岡 裕章 | 高知大学 老年病・循環器内科学 | |
| 演者: | 奥村 貴裕 | 名古屋大学大学院医学系研究科 先進循環器治療学/循環器内科学 |
| 久保 亨 | 高知大学医学部老年病・循環器内科学 | |
| 遠藤 仁 | 慶應義塾大学 循環器内科 | |
| 山野 哲弘 | 京都府立医科大学 感染制御・検査医学/循環器内科学 | |
| 泉家 康宏 | 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学 |
コントロバーシー
Controversy 1日本語
2025年3月29日(土)11:00~12:00 第23会場(展示ホール1F ホールC)
CV1
LDLコレステロールはどこまで下げるか?
| 座長: | 野出 孝一 | 佐賀大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 吉田 雅幸 | 東京科学大学先進倫理医科学分野・遺伝子診療科 | |
| 演者: | 大山 宗馬 | 東北大学病院循環器内科 |
| 梶波 康二 | 金沢医科大学 循環器内科学 |
Controversy 2日本語
2025年3月29日(土)13:30~14:30 第23会場(展示ホール1F ホールC)
CV2
高齢者の潜因性脳梗塞に対してどこまで行うか
-卵円孔開存閉鎖の適応、心房細動の検索-
| 座長: | 原 英彦 | 東邦大学医療センター大橋病院循環器内科 |
|---|---|---|
| 七里 守 | 公益財団法人榊原記念財団付属榊原記念病院 循環器内科 | |
| 演者: | 赤木 禎治 | 岡山大学 循環器内科 |
| 豊田 一則 | 国立循環器病研究センター 脳血管内科 |
JCS2025×JHRS(心電図検定)公認 心電図クイズ大会日本語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第23会場(展示ホール1F ホールC)
QA
司会進行:
| 柳澤 哲 | 名古屋大学 |
問題出題&登壇者:
| 原田 将英 | 藤田医科大学 | |
| 石川 真司 | 安城更生病院 | |
| 水谷 吉晶 | 市立四日市病院 | |
| 村瀬 陽介 | 小牧市民病院 | |
| 坂本 裕資 | 公立陶生病院 | |
| 須賀 一将 | 中京病院 | |
| 柳澤 哲 | 名古屋大学 |
特別ゲスト:
| 芦原 貴司 | 滋賀医科大学 |
日本心臓財団シンポジウム日本語
2025年3月30日(日)13:50~15:20 第5会場(会議センター3F 303)
HFSY
こうしたらええがね! 心臓突然死を減らすための市民教育
| 中澤 学 | 近畿大学 循環器内科学教室 | |
| 石見 拓 | 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 予防医療学分野 |
Keynote Lecture:
| 三田村 秀雄 | 公益財団 日本AED財団 |
| 演者: | 辻田 賢一 | 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 西山 知佳 | 京都大学医学研究科 人間健康科学系専攻 | |
| 吉村 聡志 | 京都大学医学研究科 社会健康医学系専攻 予防医療学分野、洛和会音羽病院救命救急センター・京都ER | |
| 佐藤 加代子 | 東京家政大学栄養学部 臨床病態学, 東京女子医科大学 循環器内科 |
JCS2025×HEPT企画セッション日本語
2025年3月30日(日)13:20~14:50 第19会場(アネックスホール2F F201+F202)
JCS2025-HEPT
| 座長: | 澤村 昭典 | 一宮市立市民病院 循環器内科 |
|---|
ANP発見40周年記念シンポジウム日本語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第6会場(会議センター3F 304)
ANP40
| 座長: | 中尾 一和 | 京都大学大学院医学研究科、メディカルイノベーションセンター |
|---|---|---|
| 伊藤 隆之 | 名城病院 | |
| 演者: | 中尾 一和 | 京都大学大学院医学研究科、メディカルイノベーションセンター |
| 斎藤 能彦 | 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター | |
| 吉村 道博 | 東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科 |
教育セッション日本語
2025年3月28日(金)16:05~17:05 第1会場(国立大ホール)
ESⅠ-1
心エコーが切り開く治療方針決定のポイント
| 座長: | 大倉 宏之 | 岐阜大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 瀬尾 由広 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 循環器内科学 | |
| 演者: | 平野 豊 | 近畿大学医学部医学教育センター |
| 福田 優子 | 兵庫県立がんセンター 腫瘍循環器科 | |
| 阿部 幸雄 | 大阪市立総合医療センター 循環器内科 |
2025年3月28日(金)17:05~18:05 第1会場(国立大ホール)
ESⅠ-2
循環器診療の医療面接・身体診察を究める
| 座長: | 野口 暉夫 | 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 |
|---|---|---|
| 山崎 直仁 | 高知大学医学部附属病院 老年病・循環器内科学 | |
| 演者: | 川崎 達也 | パナソニック健康保険組合 松下記念病院 循環器内科 |
| 阿部 幸雄 | 大阪市立総合医療センター 循環器内科 | |
| 三浦 弘之 | 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 |
2025年3月29日(土)14:30~15:30 第1会場(国立大ホール)
ESⅡ-1
感染性心内膜炎診療の最前線:2023ESCガイドライン・Duke診断基準の改訂を受けて
| 座長: | 大門 雅夫 | 国際医療福祉大学三田病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 大原 貴裕 | 東北医科薬科大学病院 老年・地域医療学教室/総合診療科 | |
| 演者: | 天野 雅史 | 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 |
| 光武 耕太郎 | 埼玉医大国際医療センター 感染症科・感染制御科 | |
| 北井 豪 | 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部 | |
| 三浦 崇 | 長崎大学 心臓血管外科 |
2025年3月29日(土)15:30~16:30 第1会場(国立大ホール)
ESⅡ-2
循環器ゲノム診療の実践
| 座長: | 吉田 雅幸 | 東京科学大学先進倫理医科学分野・遺伝子診療科 |
|---|---|---|
| 牧山 武 | 京都大学大学院医学研究科 地域医療システム学・循環器内科学 | |
| 演者: | 吉田 雅幸 | 東京科学大学先進倫理医科学分野・遺伝子診療科 |
| 多田 隼人 | 金沢大学附属病院 循環器内科/金沢大学大学院先進予防医学研究科 循環予防医学 | |
| 牧山 武 | 京都大学大学院医学研究科 地域医療システム学・循環器内科学 | |
| 大野 聖子 | 国立循環器病研究センターメディカルゲノムセンター |
2025年3月30日(日)10:00~11:00 第1会場(国立大ホール)
ESⅢ-1
循環器疾患における緩和ケア
| 座長: | 安斉 俊久 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 |
|---|---|---|
| 河野 隆志 | 杏林大学医学部付属病院 循環器内科 | |
| 演者: | 佐藤 琢真 | 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 移植医療部 |
| 河野 隆志 | 杏林大学医学部付属病院 循環器内科 |
2025年3月30日(日)11:00~12:00 第1会場(国立大ホール)
ESⅢ-2
循環器疾患における尿酸の意義を考える
| 座長: | 土橋 卓也 | 製鉄記念八幡病院 |
|---|---|---|
| 久留 一郎 | 国立病院機構 米子医療センター | |
| 演者: | 桑原 政成 | 自治医科大学 地域医療学センター公衆衛生学 兼 循環器内科学 |
| 荻野 和秀 | 鳥取赤十字病院 循環器内科 | |
| 小島 淳 | 桜十字八代リハビリテーション病院/熊本大学 |
チーム医療セッション 教育講演日本語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
CE1
チーム医療から考える心不全薬物治療
| 座長: | 木田 圭亮 | 聖マリアンナ医科大学 薬理学 |
|---|---|---|
| 鈴木 正論 | 帝京平成大学 薬学部/亀田総合病院 薬剤部 | |
| 演者: | 中島 菜穂子 | 久留米大学病院 看護部 |
| 西垣 賢 | 関西メディコ サン薬局 地域政策部 | |
| 阿部 隆宏 | 北海道医療大学 当別キャンパス リハビリテーション科学部 | |
| 宮島 功 | 社会医療法人近森会 近森病院 臨床栄養部 | |
| 宮崎 賢太郎 | 神鋼記念病院 |
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
CE2
多様性を活かすハートチームビルディング
| 座長: | 石津 智子 | 筑波大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 田嶋 明彦 | 新潟薬科大学 医療技術学部 | |
| 演者: | 会田 慶太 | 自治医科大学附属さいたま医療センター リハビリテーション部 |
| 保屋野 真 | 新潟大学医歯学総合病院 循環器内科 | |
| 齋藤 慶子 | 医療法人社団ゆみの 在宅診療部 | |
| 落合 亮太 | 筑波大学医学医療系 |
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
CE3
災害時医療と循環器疾患
| 座長: | 東條 美奈子 | 北里大学医療衛生学部 |
|---|---|---|
| 木村 祐也 | 埼玉県済生会加須病院 循環器内科 | |
| 演者: | 竹内 一郎 | 横浜市立大学 救急医学 高度救命救急センター |
| 由田 克士 | 大阪公立大学大学院 生活科学研究科 食栄養学分野 | |
| 河野 裕治 | 藤田医科大学病院 リハビリテーション部 | |
| 安藝 敬生 | 小倉記念病院 薬剤部 | |
| 赤星 昂己 | 厚生労働省 医政局地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室 |
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
CE4
冠動脈イメージングの再考-低侵襲imagingの現状-
| 座長: | 髙岡 浩之 | 千葉大学 医学部附属病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 梁川 範幸 | つくば国際大学 医療保健学部 診療放射線学科 | |
| 演者: | 小菅 寿徳 | 東京医科大学 循環器内科 |
| 青木 秀平 | 千葉大学大学院医学研究院 循環器内科 | |
| 望月 純二 | みなみ野循環器病院 放射線技術部 | |
| 北川 知郎 | 広島大学大学院医系科学研究科 循環器内科学 |
2025年3月30日(日)15:30~17:00 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
CE5
禁煙してはっぴぃ・はっぴぃ・はっぴぃ
| 座長: | 梅津 努 | 坂根Mクリニック(筑波大学附属病院 循環器内科) |
|---|---|---|
| 近藤 隆久 | 国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター | |
| 演者: | 水野 篤 | 聖路加国際病院 循環器内科 |
| 藤生 克仁 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| Ahmed Talib | ffiliation Kufa University College of Medicine, Iraq |
コメンテーター:
| 小川 孝二郎 | 筑波大学附属病院 循環器内科 |
ゲスト:
| すわん君 | 一般社団法人日本循環器学会 禁煙推進部会 |
チーム医療セッション シンポジウム
チーム医療セッション シンポジウム 1日本語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
CS1
循環器疾患患者の精神的問題に多職種チームでどう取り組むか
| 座長: | 西村 勝治 | 東京女子医科大学 神経精神科 |
|---|---|---|
| 志賀 剛 | 東京慈恵会医科大学 臨床薬理学 | |
| 演者: | 近藤 彩春 | 杏林大学医学部付属病院 看護部 |
| 乙部 知子 | 土浦協同病院 看護部 | |
| 福田 紘 | 洛和会音羽病院 看護部 | |
| 庵地 雄太 | 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 |
ディスカッサント:
| 河野 隆志 | 杏林大学医学部付属病院 循環器内科 |
循環器疾患患者が抱える精神・心理的問題は大きく、治療へのアドヒアランスのみならず、その予後に係わる重要な因子であることが認識されている。この問題に取り組むことは循環器疾患患者のQOL、治療へのアドヒアランスを改善させ、ひいては治療効果、さらに予後の改善にも繋がることが期待される。現在、循環器患者における精神・心理的問題とその課題を多職種が連携(チーム医療)して共有し、解決していくケアシステムを構築することが求められている。そのためには、まず循環器疾患患者に係わる医療スタッフが患者の抱える精神・心理的な問題に気付き、それらが適切な療養行動の妨げとなっていることを認識することから始まる。
本シンポジウムでは循環器診療において医療者が治療、療養指導を行うものの、適切な療養行動に至らない「あるある事例」をみなさんと検討したい。とくに今回は心不全患者にしばしば合併する「抑うつ」「不安」「軽度認知障害」を有する事例に焦点を当てる。本シンポジウムのゴールは、メンタルケアの観点からこれまでの療養指導における教育や支援の方法を少し変える糸口をつかむことである。循環器診療に携わるメディカルスタッフの方々がメンタルケアに関心を持つきっかけになれば幸いである。
チーム医療セッション シンポジウム 2日本語
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第21会場(アネックスホール2F F205+F206)
CS2
医師の働き方改革におけるタスクシェア・タスクシフト
| 座長: | 栗田 康生 | 国際医療福祉大学 大学院 |
|---|---|---|
| 伊東 紀揮 | 医療法人社団ゆみの 看護部 | |
| 演者: | 末冨 建 | 山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 |
| 木下 朋幸 | 横浜市立みなと赤十字病院 臨床検査部 | |
| 髙橋 佐枝子 | 医療法人徳洲会 湘南大磯病院 循環器科 | |
| 小川 浩司 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 臨床工学部 | |
| 前田 明子 | 杏林大学医学部循環器内科学 |
これまでの日本の医療は、医師の役割と業務の集中によって医師の長時間労働が常態化していた。少子高齢化や医療の高度化に伴い、患者が増加する一方で医療従事者の減少が進むことが予想され、医療提供体制をどのように維持していくのか極めて重要な課題となっている。医療の質と安全の確保、そして持続可能な医療提供体制を維持するためには、医師をはじめとする医療者が健康に働き続けられる環境を整備することが不可欠である。
このような考えのもと、2019年に「働き方改革関連法」が成立した。以降、厚生労働省や各職能団体で議論が重ねられ、法改正を含む準備が進められてきた。そして2024年4月より医師の働き方改革が施行となった。
この改革では、医師の適切な労務管理の推進とともに、他職種へのタスクシェア・タスクシフトの推進が図られている。これにより、各医療専門職がそれぞれの能力を活かし、能動的に対応できる医療体制を構築し、最終的には患者に対して質と安全が確保された持続可能な医療を提供することを目指している。
本セッションでは、循環器領域でタスクシェア・タスクシフトを実践している医療機関からの発表を通じて、その展望と課題について活発な議論を期待する。
チーム医療セッション シンポジウム 3日本語
2025年3月29日(土)16:30~18:00 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
CS3
腫瘍循環器診療における非侵襲検査の役割
| 座長: | 岩永 史郎 | 埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 |
|---|---|---|
| 小谷 敦志 | 近畿大学奈良病院 臨床検査部 | |
| 演者: | 守田 和憲 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 薬剤部 |
| 宮﨑 彩記子 | 順天堂大学循環器内科 | |
| 古島 早苗 | 長崎大学病院 超音波センター | |
| 相本 賢二 | 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター | |
| 渋谷 悠真 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 薬剤部 |
腫瘍性疾患や悪性血液疾患では様々な心臓合併症を生じるとともに、治療薬による心臓への悪影響も少なくない。腫瘍が心膜腔に浸潤する癌性心膜炎は、ステージの進んだ原発性・転移性肺癌に合併しやすい。また、腎癌の肝転移は下大静脈を通じて右房へ、血管浸潤性の高い肺癌は肺静脈を介して左房へ直接浸潤する。これらの治療には人工心肺を使用した心臓手術が必要となる場合がある。また、腺癌やリンパ腫では血液凝固能亢進によって、非細菌性血栓性疣贅、静脈血栓や肺血栓塞栓症、トルソー症候群と呼ばれる脳梗塞の発症率が増加する。心原性塞栓症では悪性疾患の検索が不可欠である。
アントラサイクリン系抗癌剤(ドキソルビシンなど)による用量依存性の不可逆性心筋障害は古くからよく知られた抗癌剤の心毒性であるが、シクロフォスファミドやドセタキセルでも心不全を来たしうる。近年、使用量が増加している分子標的薬でも心臓副作用を生じる。乳癌に使用されるトラスツズマブも心筋障害による心不全を来たすが、投与中止で左室機能が改善する症例が多い。免疫チェックポイント阻害薬による心筋炎などの免疫関連有害事象も多く報告されている。
腫瘍性疾患や悪性血液疾患や、その治療に伴う心血管疾患を非侵襲的に検査する方法について理解を深めるために本シンポジウムを企画した。
チーム医療セッション シンポジウム 4日本語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
CS4
心筋疾患のイメージング最前線
| 座長: | 北川 覚也 | 三重大学先進画像診断学講座 |
|---|---|---|
| 山口 隆義 | 華岡青洲記念病院 放射線技術部 | |
| 演者: | 中森 史朗 | 三重大学大学院 循環器・腎臓内科学 |
| 山口 隆義 | 華岡青洲記念病院 放射線技術部 | |
| 木下 ゆい | 熊本大学病院 中央検査部 | |
| 河窪 正照 | 九州大学大学院医学研究院保健学部門 医用量子線科学分野 | |
| 宿谷 篤 | 千葉西総合病院 放射線科 |
近年、様々なモダリティによる心筋イメージングが可能となり、虚血性のみならず非虚血性心筋疾患に対する非侵襲的画像診断の有用性が広く認識されてきた。国内外からのエビデンスの蓄積により、各種ガイドラインでもその重要性が強調されている。
心筋疾患を画像で評価するには、多角的なアプローチが必要である。スクリーニングとして施行される経胸壁心エコー検査では、壁運動や壁厚などを詳細に評価する。心臓MRIでは、それに加えて遅延造影の分布から各種疾患に対する診断の確信度を高めことができる。また、T1値やECV値によって、心筋性状を定量値として評価することも可能である。CTの主な役割は冠動脈CTによる虚血性心疾患の除外であるが、遅延相の撮影を追加することで、遅延造影の分布やECV値を評価でき、心筋疾患の検出機会を向上させるポテンシャルがある。一方、核医学では、FDGによる心サルコイドーシスの活動性評価やピロリン酸によるATTR心アミロイドーシスの診断など、代謝面から心筋疾患へアプローチする。核医学においてはその診断価値を高める上で、検査目的を明確化することが特に重要である。
我々は各種モダリティにおける画像の成り立ちを理解し、それぞれの特徴を活かした使い分けや組み合わせを緻密に考え、診断精度を高めていく必要がある。このシンポジウムでは、心筋イメージングの現状と技術的課題、そして今後の可能性について議論したい。
チーム医療セッション シンポジウム 5日本語
2025年3月30日(日)13:20~14:50 第20会場(アネックスホール2F F203+F204)
CS5
高齢心不全の入院生活をチームで見直す ~入院による悪影響を最小化するために~
| 座長: | 北井 豪 | 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部 |
|---|---|---|
| 神谷 健太郎 | 北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科 | |
| 演者: | 大森 基輝 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 看護部 |
| 辻内 美希 | 昭和大学藤が丘病院 循環器内科 | |
| 風間 寛子 | 群馬県立心臓血管センター リハビリテーション課 | |
| 野田 匠 | 国立循環器病研究センター 心血管リハビリテーション科 | |
| 岩田 健太郎 | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
高齢化が進む我が国では、心不全患者が高齢化・重症化し、多くの患者に急性期から、回復期、生活期までの切れ目のないリハビリテーション医療が必要となっている。また、医療に限らず、介護・福祉に係る居宅・通所・入所サービス間の連携や連続性、一体性の確保の必要性が強調されるようになってきた。令和6年度の診療報酬改定の議論の過程では、入院による安静臥床を原因とする歩行障害や機能障害が入院関連機能障害(Hospitalization-Associated Disability: HAD)として大きくクローズアップされた。高齢患者はもともと複数の疾患や重複した障害を有しており、入院を契機として日常生活動作能力が大きく損なわれ、自立した生活が送れなくなり、要介護状態となることが少なくない。これまでは「入院したから仕方がない」とすまされていたかもしれないが、高齢心不全患者がさらに増加することが予想される中、入院による悪影響を最小化するために高齢心不全の入院生活をチーム全体で見直していかなければならない。チーム医療セッションの本シンポジウムでは、チームでの入院関連機能障害予防の具体的な取り組みを共有し、今後の方法論を具体的に議論することで、現代医療の心不全マジョリティーに対する新たな心臓リハビリテーションを展望したい。
AHA-JCS Joint Symposium英 語
2025年3月30日(日)8:00~9:30 第7会場(会議センター3F 311+312)
AHA-JCS
Screening, Diagnosis, and Management of Anderson-Fabry Disease
| 座長: | 北岡 裕章 | 高知大学 老年病・循環器内科学 |
|---|---|---|
| Damodhar P. Suresh | St. Elizabeth’s Health Care / AHA (American Heart Association), USA | |
| 演者: | Gaetano Santulli | Albert Einstein College of Medicine, USA |
| Yuri Kim | Division of Cardiovascular Medicine, Brigham and Women's Hospital / Harvard Medical School, USA | |
| 久保 亨 | 高知大学医学部 老年病・循環器内科学 | |
| 本郷 賢一 | 東京慈恵会医科大学 循環器内科 |
KSC-JCS Joint Symposium英 語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第7会場(会議センター3F 311+312)
KSC-JCS
Heart Failure Management in Super-Aging Society
| 座長: | 猪又 孝元 | 新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| Seok-Min Kang | Yonsei University, Korea | |
| 演者: | 小幡 裕明 | 新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科 |
| 田中 秀和 | 神戸大学大学院 循環器内科学分野 | |
| Jin-Oh Choi | Sungkyunkwan University School of Medicine, Samsung Medical Center, Korea | |
| Jong-Chan Youn | Catholic University, Korea |
CSC-JCS Joint Symposium英 語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第7会場(会議センター3F 311+312)
CSC-JCS
Pulse Field Ablation for Atrial Fibrillation
| 座長: | 里見 和浩 | 東京医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| Yiwei Lai | Beijing Anzhen Hospital, China | |
| 演者: | 井上 耕一 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 循環器内科 |
| 舩迫 宴福 | Cardiology Department, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic | |
| Yiwei Lai | Beijing Anzhen Hospital, China | |
| Chenyang Jiang | Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China |
ESC-JCS Joint Symposium英 語
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第7会場(会議センター3F 311+312)
ESC-JCS
INOCA: Pathophysiology, Diagnosis and Management
| 座長: | 大倉 宏之 | 岐阜大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
|---|---|---|
| Franz Weidinger | Klinik Landstraße, Austria | |
| 演者: | 西 毅 | 千葉大学 循環器内科 |
| 田中 信大 | 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 | |
| Franz Weidinger | Klinik Landstraße, Austria | |
| Peter Ong | Department of Cardiology and Angiology, Robert Bosch Medical Centre, Bosch Health Campus, Germany |
APSC-JCS Joint Symposium英 語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第7会場(会議センター3F 311+312)
APSC-JCS
Current Status and Future of Structural Heart Disease Treatment in Asia
| 座長: | 出雲 昌樹 | 聖マリアンナ医科大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| Mao-Shin Lin | National Taiwan University Hospital, Taiwan | |
| 演者: | 奥野 泰史 | 聖マリアンナ医科大学 循環器内科 |
| 片岡 明久 | 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| Mao-Shin Lin | National Taiwan University Hospital, Taiwan | |
| Sai Satish | Apollo Hospital, India |
WHF-JCS Joint Symposium英 語
2025年3月28日(金)8:00~9:30 第6会場(会議センター3F 304)
WHF-JCS
Multimorbidity and Integrated Care
| 座長: | 塚田(哲翁) 弥生 | 日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科 |
|---|---|---|
| Dorairaj Prabhakaran | Centre for Chronic Disease Control, India | |
| 演者: | 塚田(哲翁) 弥生 | 日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科 |
| 岩﨑 雄樹 | 日本医科大学付属病院 循環器内科 | |
| Dorairaj Prabhakaran | Centre for Chronic Disease Control, India | |
| Eri Toda Kato | Kyoto University Hospital, Japan |
YIA審査講演会(Basic reseach)英 語
2025年3月28日(金)8:00~10:00 第10会場(会議センター4F 411+412)
YIA-B
| 座長: | 野出 孝一 | 佐賀大学 循環器内科 |
|---|
| 演者: | 梅井 智彦 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 |
|---|---|---|
| 高 聖淵 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 | |
| 後藤 耕策 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 髙橋 正起 | 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 |
YIA審査講演会(Clinical reseach)英 語
2025年3月28日(金)8:30~10:30 第11会場(会議センター4F 413)
YIA-C
| 座長: | 加藤 恵理 | 京都大学医学部附属病院 循環器内科 |
|---|
| 演者: | 池ノ内 孝 | 東京科学大学 循環制御内科学分野 |
|---|---|---|
| 川治 徹真 | 医療法人社団志高会 三菱京都病院 循環器内科 | |
| 鈴木 雄也 | 神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 | |
| 中島 夏奈 | 佐賀大学医学部 循環器内科 |
国際留学生YIA最終 審査講演会英 語
2025年3月29日(土)13:30~15:30 第10会場(会議センター4F 411+412)
OSYIA
| 座長: | 中野 由紀子 | 広島大学 循環器内科 |
|---|
| 演者: | Aga Krisnanda | 神戸薬科大学 医療薬剤学研究室 |
|---|---|---|
| Xueyuan Liu | 慶應義塾大学 循環器内科 | |
| Khan Md Mahbubur Rahman | 滋賀医科大学 分子病態生化学 | |
| Yiyi Yang | 東京大学 循環器内科 |
International Young Investigator’s Award
(Basic Research) Finalists Lectures英 語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第11会場(会議センター4F 413)
IYIA-B
| 座長: | 家田 真樹 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 |
|---|
| 演者: | Haihang Luo | Cardiology, Nagoya University |
|---|---|---|
| 仲野 晃司 | Department of Cardiology, Institute of Medicine, University of Tsukuba | |
| Man-Chen Hsu | College of Medicine, Graduate Institute of Physiology, National Taiwan University | |
| 三好 悠太郎 | Department of cardiovascular medicine, Kyoto University |
International Young Investigator’s Award
(Clinical Section) Finalists Lectures英 語
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第11会場(会議センター4F 413)
IYIA-C
| 座長: | 清水 渉 | 日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 |
|---|
| 演者: | 家城 博隆 | Genetics, Stanford University |
|---|---|---|
| 平井 健太 | Pediatrics, Okayama University Hospital | |
| 羽田 昌浩 | OLV Aalst, Belgium/Division of Cardiovascular Medicine, Tsuchiura Kyodo General Hospital | |
| 岸川 理紗 | Department of Cardiovascular Medicine, The University of Tokyo Hospital, The University of Tokyo |
Asian Pacific Grants for Innovative Research Plan Award(Basic/Clinical)英 語
2025年3月28日(金)16:05~18:05 第10会場(会議センター4F 411+412)
APA
| 座長: | 阿古 潤哉 | 北里大学医学部 循環器内科学 |
|---|
<Basic Research Plan>
| 演者: | Soo Yeon An | Seoul Asan Medical Center |
|---|---|---|
| Tzu-Yen Huang | Chang Gung Memorial Hospital | |
| Vu Diem My | University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City |
<Clinical Research Plan>
| 演者: | Chang, Chiao-Hsiang | Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taiwan |
|---|---|---|
| Jihye You | Jeonbuk National University Hospital, Korea | |
| Nabhat Noparatkailas | Chiang Mai University,Thailand |
APSC President Session英 語
2025年3月29日(土)16:00~18:00 第22会場(展示ホール1F ホールB)
APSC
Current Status and Challenges of ACS and AF Management in Asia
Opening Remarks:
| Yoshio Kobayashi | (JCS President, Japan) |
Session 1:ACS in APSC
| 座長: | Toshihisa Anzai | (Chairperson of JCS International Relations Committee, Japan) |
|---|---|---|
| Yi-Heng Li | (Taiwan) |
Current Antiplatelet Strategy for AMI in Taiwan
Keynote Lecture:
| Yi-Heng Li | (Taiwan) |
President Discussants:
| Mayanna Lund | (Australia,New Zealand) | |
| Yi-Heng Li | (Taiwan) | |
| Huynh Van Minh | (Vietnam) | |
| Ratna Mani Gajurel | (Nepal) | |
| Jawaid Akbar Sial | (Pakistan) | |
| Sampath Withanawasam | (Sri Lanka) |
Young Speakers:
| Yasushi Ueki | (Leader of JCS International Young Community (JIYC), Japan) | |
| Yong-Joon Lee | (Korea) | |
| Monghak SOK | (Cambodia) | |
| Thinnakrit Sasiprapha | (Thailand) | |
| Kaushik Manna | (India) | |
| Smriti Shakya | (Nepal) | |
| Mahesh Kumar | (Pakistan) | |
| Wanni Arachchige Ajith Prasanna | (Sri Lanka) |
Session 2:AF in APSCC
| 座長: | Yukiko Nakano | (JCS International Relations Committee, Japan) |
|---|---|---|
| Seok-Min Kang | (Korea) |
TBA
Keynote Lecture:
| Colin Yeo | (Singapore) |
President Discussants:
| Colin Yeo | (Singapore) | |
| Seok-Min Kang | (Korea) | |
| Mungun-Ulzii Khurelbaatar | (Mongol) | |
| Gary Lee Chin Keong | (Malaysia) | |
| Lourdes Ella Santos | (Philippine) | |
| Kasem Ratanasumawong | (Thailand) |
Young Speakers:
| Satoshi Higuchi | (Sub-Leader of JCS International Young Community (JIYC), Japan) | |
| Wei-Ting Liu | (Taiwan) | |
| Zorig Sanjdorj | (Mongol) | |
| Doan Pham Phuoc Long | (Vietnam) | |
| Ling Hwei Sung | (Malysia) | |
| Luigi Pierre Segundo | (Philippine) |
Observer:
| Ario Soeryo Kuncoro | (Indonesia) |
Closing Remarks:
| Seok-Min Kang | (Korea) |
日本心臓財団佐藤賞記念講演
Japan Heart Foundation Satoh Memorial Award Lecture英 語
2025年3月30日(日)15:30~16:30 第5会場(会議センター3F 303)
SATO
| 座長: | 室原 豊明 | 名古屋大学大学院医学系研究科 病態内科学講座 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | 野村 征太郎 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 |
日本循環器学会 委員会セッション(医療安全部会)
医療安全に関する講演会日本語
2025年3月30日(日)14:20~15:20 第1会場(国立大ホール)
SAFE
「患者・家族の願いに寄り添う医療安全
~求められるNon Technical Skill とPublic Commnication」
| 座長: | 井澤 英夫 | 藤田医科大学医学部 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | 後藤 克幸 | 中部日本放送(CBC) 論説委員 |
日本循環器学会 委員会セッション(倫理委員会)
倫理に関する講演会日本語
2025年3月30日(日)13:20~14:20 第1会場(国立大ホール)
ETHIC
研究公正、研究倫理の視点から考える臨床研究スキル
| 座長: | 植田 真一郎 | 琉球大学 臨床薬理学講座 |
|---|---|---|
| 演者: | 森本 剛 | 兵庫医科大学 臨床疫学 |
日本循環器学会 委員会セッション
(基本法・5ヵ年計画検討委員会)日本語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第19会場(アネックスホール2F F201+F202)
JSS
心血管疾患の患者支援を考える
| 座長: | 安田 聡 | 東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野 |
|---|---|---|
| 前村 浩二 | 長崎大学大学院医歯薬額総合研究科 循環器内科 | |
| 演者: | 安斉 俊久 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 |
| 辻田 賢一 | 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学 | |
| 塚田(哲翁) 弥生 | 日本医科大学武蔵小杉病院 救急・総合診療センター 総合診療科 | |
| 山岸 敬幸 | 東京都立小児総合医療センター | |
| 牧田 茂 | 川口きゅうぽらリハビリテーション病院 リハビリテーション科 | |
| 中山 敦子 | 公益財団法人 榊原記念財団 附属 榊原記念病院 循環器内科 |
日本循環器連合up-to-dateセミナー
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本小児循環器学会」日本語
2025年3月28日(金)8:00~9:00 第16会場(会議センター5F 501)
JCVA1
ファロー四徴症を斬る
| 座長: | 岩本 眞理 | まり こどもクリニック港南台 |
|---|---|---|
| 平松 祐司 | 筑波大学 心臓血管外科 | |
| 演者: | 塩野 淳子 | 茨城県立こども病院 小児科 |
| 藤井 隆成 | 昭和大学 小児循環器・成人先天性心疾患センター | |
| 小嶋 愛 | 長野県立こども病院 心臓血管外科 | |
| 五十嵐 都 | 筑波大学 循環器内科 | |
| 新川 武史 | 東京女子医科大学 心臓血管外科学 | |
| 佐地 真育 | 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 |
日本循環器連合up-to-dateセミナー
「日本心血管インターベンション治療学会」日本語
2025年3月28日(金)9:00~10:00 第16会場(会議センター5F 501)
JCVA2
インターベンション治療最前線
| 座長: | 上妻 謙 | 帝京大学医学部内科学講座・循環器内科 |
|---|---|---|
| 森野 禎浩 | 岩手医科大学医学部 内科学講座循環器内科分野 | |
| 演者: | 林田 健太郎 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 |
| 飯田 修 | 大阪警察病院 循環器内科 | |
| 伊苅 裕二 | 東海大学医学部 内科学系循環器内科学 |
日本循環器連合up-to-dateセミナー「一般社団法人日本心エコー図学会」日本語
2025年3月28日(金)10:00~11:00 第16会場(会議センター5F 501)
JCVA3
成人先天性心疾患の心エコー図プロトコールを学ぶ: ISACHD
| 座長: | 石津 智子 | 筑波大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 岩永 史郎 | 埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 | |
| 演者: | 石津 智子 | 筑波大学 循環器内科 |
| 瀧聞 浄宏 | 長野県立こども病院 循環器小児科 |
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本不整脈心電学会」日本語
2025年3月28日(金)16:35~17:35 第16会場(会議センター5F 501)
JCVA4
モバイル心電計を用いた不整脈診断の展望と課題
| 座長: | 清水 渉 | 日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 |
|---|---|---|
| 野出 孝一 | 佐賀大学 医学部 | |
| 演者: | 池田 隆徳 | 東邦大学大学院医学研究科 循環器内科学 |
| 髙橋 尚彦 | 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 | |
| 笹野 哲郎 | 東京科学大学 循環制御内科学 | |
| 髙月 誠司 | 慶應義塾大学医学部 循環器内科 | |
| 山形 研一郎 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 |
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心臓リハビリテーション学会」日本語
2025年3月29日(土)8:00~9:00 第16会場(会議センター5F 501)
JCVA5
変革が迫られる回復期の心臓リハビリテーション
| 座長: | 牧田 茂 | 川口きゅうぽらリハビリテーション病院 リハビリテーション科 |
|---|---|---|
| 三浦 伸一郎 | 福岡大学医学部 心臓・血管内科学 | |
| 演者: | 牧田 茂 | 川口きゅうぽらリハビリテーション病院 リハビリテーション科 |
| 高橋 哲也 | 順天堂大学 保健医療学部 | |
| 明石 嘉浩 | 聖マリアンナ医科大学 循環器内科 | |
| 網谷 英介 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 |
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心臓病学会」日本語
2025年3月29日(土)9:00~10:00 第16会場(会議センター5F 501)
JCVA6
心臓サルコイドーシス:診断と治療の最前線
| 座長: | 矢﨑 善一 | JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター 循環器内科 |
|---|---|---|
| 坂田 泰史 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 演者: | 田原 宣広 | 久留米大学内科学講座 心臓・血管内科部門 |
| 鍋田 健 | 北里大学 循環器内科学 | |
| 永井 利幸 | 北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 | |
| 中島 健三郎 | 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 |
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心不全学会」日本語
2025年3月30日(日)8:00~9:00 第16会場(会議センター5F 501)
JCVA7
「血中BNP/NT-proBNPを用いた心不全診療に関するステートメント
2023年改訂版」によって変わる日本の心不全診療
| 座長: | 絹川 弘一郎 | 富山大学附属病院 第二内科 |
|---|---|---|
| 瀬尾 由広 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 循環器内科学 | |
| 演者: | 桑原 宏一郎 | 信州大学医学部 循環器内科学教室 |
| 佐藤 直樹 | かわぐち心臓呼吸器病院 循環器内科 | |
| 猪又 孝元 | 新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学 | |
| 坂田 泰史 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
日本循環器連合up-to-dateセミナー「日本心臓血管外科学会」日本語
2025年3月30日(日)9:00~10:00 第16会場(会議センター5F 501)
JCVA8
B型急性大動脈解離に対するpreemptive TEVAR
| 座長: | 岡田 健次 | 神戸大学 心臓血管外科学 |
|---|---|---|
| 圷 宏一 | 日本医科大学付属病院 循環器内科 | |
| 演者: | 志村 信一郎 | 東邦大学医療センター大橋病院 心臓血管外科 |
| 田崎 淳一 | 日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科 | |
| 清家 愛幹 | 国立循環器病研究センター 血管外科 | |
| 内田 徹郎 | 山形大学医学部附属病院 第二外科 |
日本循環器学会・日本機械学会ジョイントシンポジウム日本語
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第14会場(会議センター4F 418)
JSME-JCS
医工連携の研究事例紹介:私たちは医工連携が好き
| 座長: | 高嶋 一登 | 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 |
|---|---|---|
| 朔 啓太 | 国立循環器病研究センター 循環動態制御部 | |
| 演者: | 片岡 則之 | 日本大学 工学部 |
| 伊藤 一陽 | 東京農工大学 工学研究院 | |
| 中村 太郎 | 中央大学 理工学部 |
日本循環器学会・日本脳卒中学会 ジョイントシンポジウム日本語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第6会場(会議センター3F 304)
JSTS-JCS
第三次5カ年計画に向けた課題 ~厚生労働省科研費研究者からの提案と提言~
| 座長: | 小林 欣夫 | 千葉大学 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 小笠原 邦昭 | 岩手医科大学 | |
| 演者: | 鶴田 真也 | 厚生労働省 健康・保健衛生局 がん・疾病対策課 |
| 宮本 享 | 京都大学医学部附属病院 脳卒中療養支援センター、もやもや病支援センター | |
| 猪原 匡史 | 国立循環器病研究センター 脳血管内科・脳神経内科 | |
| 辻田 賢一 | 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学 | |
| 絹川 弘一郎 | 富山大学附属病院 第二内科 |
国際名誉会員セッション
Special Lecture by International Honorary Members英 語
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第6会場(会議センター3F 304)
HM
| 座長: | 小室 一成 | 国際医療福祉大学・東京大学 |
|---|---|---|
| 演者: | Michael D. Schneider | National Heart and Lung Institute, Imperial College London, UK |
| Junbo Ge | Zhongshan Hospital, Fudan University, China |
JIYC オリジナルセッション英 語
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第12会場(会議センター4F 414+415)
JIYC
Knowledge gaps in PH: Future direction from 7th World Symposium on PH 2024
座長兼演者:
| 江尻 健太郎 | 岡山大学病院 循環器内科 | |
| Jurjan Aman | Amsterdam University Medical Center, Netherlands |
演者兼コメンテーター:
| 佐藤 大樹 | 東北大学病院 循環器内科 | |
| 吉田 賢明 | 九州大学病院 | |
| 西條 良仁 | 徳島大学病院 |
日本循環器学会 委員会セッション(ガイドライン部会)日本語
2025年3月28日(金)8:00~9:30 第2会場(会議センター1F メインホール)
GL1
ガイドラインに学ぶ 1
| 座長: | 北岡 裕章 | 高知大学医学部 老年病・循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | 北井 豪 | 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部 |
| 齋木 佳克 | 東北大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学分野 | |
| 重松 邦広 | 国際医療福祉大学三田病院 血管外科 |
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第2会場(会議センター1F メインホール)
GL2
ガイドラインに学ぶ 2
| 座長: | 北岡 裕章 | 高知大学医学部 老年病・循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | 田村 雄一 | 国際医療福祉大学医学部 循環器内科学 |
| 山岸 敬幸 | 東京都立小児総合医療センター | |
| 岩本 眞理 | まり こどもクリニック港南台 小児科・小児循環器内科 |
日本循環器学会 委員会セッション(学術集会プログラム部会)日本語
2025年3月28日(金)9:35~10:35 第2会場(会議センター1F メインホール)
GLS1
ガイドライン症例セッション 1
「2025年改訂版 心不全診療ガイドライン」
| 座長: | 加藤 貴雄 | 京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構 |
|---|---|---|
| 北井 豪 | 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部 | |
| 演者: | 那須 崇人 | 岩手医科大学 循環器内科 |
| 鈴木 翔 | 信州大学医学部附属病院 循環器内科 |
2025年3月28日(金)13:35~14:35 第2会場(会議センター1F メインホール)
GLS2
ガイドライン症例セッション 2
「2025年改訂版 心臓移植に関するガイドライン」
| 座長: | 齋木 佳克 | 東北大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学分野 |
|---|---|---|
| 演者: | 赤澤 康裕 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
| 三角 香世 | 九州大学病院 循環器内科 |
2025年3月28日(金)16:35~17:35 第2会場(会議センター1F メインホール)
GLS3
ガイドライン症例セッション 3
「2025年ガイドラインフォーカスアップデート版 末梢動脈疾患」
| 座長: | 重松 邦広 | 国際医療福祉大学三田病院 血管外科 |
|---|---|---|
| 演者: | 齋藤 佑一 | 千葉大学医学部附属病院 循環器内科 |
| 翁 佳輝 | 信州大学医学部附属病院 循環器内科 |
2025年3月29日(土)10:30~11:30 第2会場(会議センター1F メインホール)
GLS4
ガイドライン症例セッション 4
「2025年改訂版 成人先天性心疾患診療ガイドライン」
| 座長: | 山岸 敬幸 | 東京都立小児総合医療センター |
|---|---|---|
| 演者: | 齋藤 秀輝 | 総合病院 聖隷浜松病院 循環器科 |
| 石北 綾子 | 九州大学 循環器内科 |
2025年3月29日(土)13:30~14:30 第2会場(会議センター1F メインホール)
GLS5
ガイドライン症例セッション 5
「2025年ガイドラインフォーカスアップデート版 学校心臓検診」
| 座長: | 岩本 眞理 | まり こどもクリニック港南台 小児科・小児循環器科 |
|---|---|---|
| 演者: | 石田 秀和 | 大阪大学医学部附属病院 小児科 |
| 松尾 久実代 | 大阪母子医療センター 小児循環器 |
2025年3月29日(土)16:30~17:30 第2会場(会議センター1F メインホール)
GLS6
ガイドライン症例セッション 6
「2025年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症ガイドライン」
| 座長: | 田村 雄一 | 国際医療福祉大学医学部 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 演者: | 古賀 祐樹 | 久留米大学病院 心臓・血管内科 |
| 江尻 健太郎 | 岡山大学病院 循環器内科 |
海外留学ネットワーキングセミナー日本語
2025年3月28日(金)16:35~18:05 第22会場(展示ホール1F ホールB)
SAN
| 座長: | 佐藤 大樹 | 東北大学病院 循環器内科 |
|---|---|---|
| 吉田 賢明 | 九州大学病院 |
アドバイザー:
| 石口 博智 | 山口大学 大学院医学系研究科 器官病態内科学 | |
| 岡田 厚 | 国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 | |
| 安部 一太郎 | 大分大学医学部 循環器・臨床検査診断学講座 | |
| 田中 仁啓 | 静岡社会健康医学大学院大学 社会健康医学研究科 | |
| 小徳 のぞみ | 聖マリアンナ医科大学循環器内科/川崎市立多摩病院 循環器内科 | |
| 嘉澤 脩一郎 | 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 | |
| 小池 秀樹 | 東邦大学医学部 内科学講座循環器内科学分野 | |
| 網岡 尚史 | 岡山大学病院 循環器内科 | |
| 増山 潔 | 大阪大学 キャンパスライフ健康支援・相談センター・循環器内科学 | |
| 磯部 更紗 | 国際医療福祉大学 三田病院 | |
| 長坂 崇司 | 群馬大学大学院医学系研究科 内科学講座 循環器内科学 | |
| 河合 健志 | 兵庫医科大学 循環器・腎透析内科 | |
| 門脇 幸子 | 岡山大学病院 心臓血管外科 | |
| 山口 淑郎 | 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 樋口 諭 | 東京女子医科大学 循環器内科 先進電気的心臓制御研究部門 | |
| 近藤 徹 | 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 尾上 武志 | 産業医科大学医学部 第2内科学 | |
| 倉田 征昭 | 昭和大学 藤が丘病院 | |
| 木下 大資 | 山形大学医学部附属病院 | |
| 石北 綾子 | 九州大学 循環器内科 | |
| 山田 さつき | Mayo Clinic Rochester, USA | |
| 湊口 信吾 | 岐阜大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 大槻 尚男 | 東京女子医科大学病院 | |
| 山口 徹雄 | 虎の門病院 循環器センター内科 | |
| 前田 恵 | 東北大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 |
日本循環器学会 委員会セッション(教育研修/集中・救急委員会)
蘇生科学シンポジウム
Joint Session with AHA on Resuscitation Science -Cardiogenic Shock-英 語
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第4会場(会議センター3F 302)
RSY
Joint Session with AHA on Resuscitation Science -Cardiogenic Shock-
Chairperson:
| 田中 哲人 | 名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学 | |
| Damodhar P. Suresh | St. Elizabeth’s Health Care / AHA (American Heart Association), USA |
performer:
| Dhruv Kazi | Beth Israel Deaconess Medical Center, Israel | |
| 藤野 剛雄 | 九州大学大学院医学研究院重症心肺不全講座 | |
| 近藤 徹 | 名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学 |
日本循環器学会・日本循環器協会ジョイントシンポジウム日本語
2025年3月29日(土)10:30~12:00 第19会場(アネックスホール2F F201+202)
JCA-JCS1
医療・福祉・介護スタッフに対する心不全啓発の重要性
| 座長: | 高村 雅之 | 金沢大学 循環器内科 |
|---|---|---|
| 山本 一博 | 鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科 | |
| 演者: | 尾上 健児 | 奈良県立医科大学 循環器内科 |
| 衣笠 良治 | 鳥取大学 循環器・内分泌代謝内科学分野 | |
| 岡田 明子 | 北里大学 看護学部 | |
| 東田 雪絵 | 株式会社キープオン 訪問看護キープオン守山 | |
| 涌田 泰行 | 奈良県大和高田市立病院 薬剤部 | |
| 斎藤 慶子 | 医療法人社団ゆみの |
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第19会場(アネックスホール2F F201+202)
JCA-JCS2
地域心不全診療における病診連携・多職種連携の実態と展望
| 座長: | 辻田 賢一 | 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学 |
|---|---|---|
| 桑原 宏一郎 | 信州大学 循環器内科 | |
| 演者: | 肥後 友彰 | はくとホームケアクリニック |
| 國島 友之 | 医療法人慈念会 国島医院 | |
| 渡辺 德 | 社会医療法人抱生会 丸の内病院 | |
| 石津 智子 | 筑波大学 循環器内科 | |
| 笠嶋 智子 | グリーンメディック薬局 |
心不全療養指導士セッション
心不全療養指導士セッション日本語
2025年3月29日(土)8:00~9:30 第17会場(会議センター5F 502)
HFS1
心不全療養指導士がつなぐ地域連携
~今、私たち心不全療養指導士に求められていること~
| 座長: | 衣笠 良治 | 鳥取大学 循環器・内分泌代謝内科学分野 |
|---|---|---|
| 石原 真由美 | 岐阜県総合医療センター | |
| 演者: | 久家 由美 | 近森病院 |
| 涌田 泰行 | 大和高田市立病院 薬剤部 | |
| 掛川 ちさと | 済生会福岡総合病院 | |
| 二宮 隆史 | 九州医療センター |
2025年3月29日(土)13:30~15:00 第17会場(会議センター5F 502)
HFS2
心不全ステージ別の療養指導の最前線:診療報酬改定を受けて
| 座長: | 肥後 太基 | 医療法人社団ゆみの |
|---|---|---|
| 若林 留美 | 東京女子医科大学病院 看護部 | |
| 演者: | 仲村 直子 | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
| 澤田 和久 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 薬剤部 | |
| 中島 菜穂子 | 久留米大学病院 看護部 | |
| 上田 健太郎 | ゆみのハートクリニック渋谷 |
心不全療養指導士Café日本語
2025年3月29日(土)16:00~18:00 第19会場(アネックスホール2F F201+202)
CAFÉ
We❤心不全〜あなたの悩みはみんなの悩み!多職種で考えよう!〜
| 座長: | 青木 加奈 | 香川大学医学部附属病院 |
|---|---|---|
| 飯沼 優 | 筑波メディカルセンター病院 |
アドバイザー:
| 芦川 直也 | 豊橋ハートセンター |
基調講演:
| 若林 留美 | 東京女子医科大学病院 看護部 |
ファシリテータ―:
| 遠山 潤 | 熊本大学病院 | |
| 本間 美久子 | 日本海総合病院 | |
| 服部 和人 | 平成堂薬局 蒲池店 | |
| 澤田 和久 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 薬剤部 | |
| 阿部 隆宏 | 北海道医療大学 リハビリテーション科学部 | |
| 増田 桃子 | 杏林大学医学部付属病院 リハビリテーション室 | |
| 千葉 一幸 | 東北医科薬科大学病院 | |
| 和泉 真実 | 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 救命救急センター | |
| 白川 大樹 | 訪問看護ステーション立花畑 西宮店 | |
| 竹ノ山 優未子 | 井野病院 | |
| 西野 寛予 | 豊橋ハートセンター | |
| 島田 晶子 | 医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセンター 栄養科 | |
| 駒井 紅美 | 福寿会病院 |
日本循環器学会委員会セッション(専門医制度委員会)日本語
2025年3月30日(日)10:30~12:00 第7会場(会議センター3F 311+312)
JP
日本専門医機構認定専門医制度(新専門医制度)に関する現状
| 座長: | 上妻 謙 | 帝京大学医学部内科学講座・循環器内科 |
|---|---|---|
| 坂田 泰史 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 | |
| 演者: | 増谷 聡 | 埼玉医科大学 総合医療センター |
| 椎谷 紀彦 | 国立病院機構 函館医療センター 心臓血管外科 | |
| 池田 隆徳 | 東邦大学大学院医学研究科 循環器内科学 | |
| 岩永 善高 | 国立循環器病研究センター 循環器病統合情報センター 桜橋渡辺未来医療病院 |
日本循環器学会 Next Generation部会日本語
2025年3月29日(土)8:00~10:00 第22会場(展示ホール1F ホールB)
ECC
JCS EARLY CAREER CHAMPIONSHIP
| 座長: | 柴田 龍宏 | 久留米大学病院 心臓・血管内科 |
|---|---|---|
| 永田 春乃 | 琉球大学病院 |
演者(北海道):
| 佐藤 有沙 | 旭川医科大学 卒後臨床研修センター |
演者(東北):
| 川口 彪人 | 山形大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター |
演者(関東甲信越):
| 後藤 尚志 | 東海大学医学部付属病院 循環器内科 | |
| 高橋 慧 | 自治医科大学医学部医学科6年生 |
演者(東海):
| 飯田 卓 | 藤田医科大学病院 臨床研修センター |
演者(北陸):
| 松本 遼 | 石川県立中央病院 初期臨床研修医 |
演者(近畿):
| 住田 卓哉 | 大阪大学 医学部医学科6年次 |
演者(中国):
| 木原 帆香 | 岩国医療センター 初期臨床研修部 |
演者(四国):
| 藤原 崚太 | 愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター |
演者(九州):
| 大庭 悠貴 | 大分大学医学部附属病院 |
指導医(北海道):
| 木谷 祐也 | 旭川医科大学 内科学講座 循環器・腎臓内科学分野 |
指導医(東北):
| 須貝 孝幸 | 山形大学医学部 内科学第一講座 |
指導医(関東甲信越):
| 中村 則人 | 東海大学付属病院 循環器内科 | |
| 甲谷 友幸 | 自治医科大学内科学講座循環器内科学 成人先天性心疾患センター |
指導医(東海):
| 河合 秀樹 | 藤田医科大学 循環器内科 |
指導医(北陸):
| 本道 俊一郎 | 石川県立中央病院 循環器内科 |
指導医(近畿):
| 肥後 修一朗 | 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 |
指導医(中国):
| 今村 繭子 | 岩国医療センター 循環器内科 |
指導医(四国):
| 三好 徹 | 愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 |
指導医(九州):
| 御手洗 和毅 | 大分大学医学部附属病院 |
徹底討論:働き方改革から一年、私たちはどう生きるか日本語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第4会場(会議センター3F 302)
TD
| 座長: | 菅原 政貴 | 兵庫医科大学 ささやま医療センター |
|---|---|---|
| 永田 春乃 | 琉球大学病院 | |
| 演者: | 那須 崇人 | 岩手医科大学 循環器内科 |
| 本江 純子 | 医療法人五星会菊名記念病院 | |
| 秦 雅寿 | 大阪警察病院 心臓血管外科 | |
| 武井 黄太 | 長野県立こども病院 | |
| 菊池 祥平 | 名古屋市立大学医学部 |
第23回禁煙推進セミナー日本語
2025年3月28日(金)13:35~15:05 第17会場(会議センター5F 502)
NS
禁煙をもっと強く呼びかけるために~知っておきたい身近な病気とタバコの関係~
| 座長: | 石原 正治 | 兵庫医科大学 循環器科・腎透析内科学講座 |
|---|---|---|
| 中井 俊子 | 日本大学医学部 内科学系先端不整脈治療学部門 | |
| 演者: | 藤原 久義 | 兵庫県立尼崎総合医療センター 大隈病院 |
| 荒川 仁香 | 九州医療センター 臨床検査科 | |
| 植野 高章 | 大阪医科薬科大学医学部 口腔外科学教室 |
グループディスカッション:
| 石原 正治 | 兵庫医科大学 循環器科・腎透析内科学講座 | |
| 中井 俊子 | 日本大学医学部 内科学系先端不整脈治療学部門 | |
| 藤原 久義 | 兵庫県立尼崎総合医療センター 大隈病院 | |
| 荒川 仁香 | 九州医療センター 臨床検査科 | |
| 植野 高章 | 大阪医科薬科大学医学部 口腔外科学教室 | |
| 梅津 努 | 坂根Mクリニック/筑波大学医学医療エリア支援室 循環器内科 | |
| すわん君 | 一般社団法人日本循環器学会 禁煙推進部会 |
オンデマンド配信セッション(現地開催なし)
日本循環器学会 委員会セッション(学術委員会)日本語オンデマンド
GCR
2023年度医師臨床研究助成報告会
| 座長: | 岡村 智教 | 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 |
|---|---|---|
| 演者: | 那須 崇人 | 岩手医科大学 循環器内科 |
| 戴 哲皓 | 東京大学大学院医学系研究科 循環器内科 | |
| 金子 智洋 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科 |
日本循環器学会 委員会セッション(学術委員会)日本語オンデマンド
GMS
2023年度メディカルスタッフ研究助成報告会
| 座長: | 石田 万里 | 広島修道大学 健康科学部 健康栄養学科 |
|---|---|---|
| 演者: | 渋谷 悠真 | 国立がん研究センター東病院 薬剤部 |
| 杉本 望 | 産業医科大学病院 リハビリテーション部 | |
| 松尾 興志 | JA神奈川県厚生相模原協同病院 医療技術部 |
日本循環器学会 委員会セッション(学術委員会)日本語オンデマンド
RMF
未来開拓型医師臨床・基礎研究助成報告会
| 座長: | 的場 聖明 | 京都府立医科大学 大学院医学研究科 循環器内科 |
|---|---|---|
| 演者: | 清水 逸平 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 心血管老化制御部 |
| 野村 征太郎 | 東京大学医学部附属病院 循環器内科 | |
| 遠山 周吾 | 藤田医科大学東京 先端医療研究センター | |
| 多田 隼人 | 金沢大学附属病院 循環器内科 | |
| 中川 仁 | 奈良県立医科大学 循環器内科 |
日本循環器学会 委員会セッション(編集委員会)
JCS Editorial Commettee Session英 語オンデマンド
CJEHJ
CJ/EHJ Joint Session
| 座長: | 辻田 賢一 | 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 |
|---|---|---|
| Filippo Crea | Department of Cardiovascular and Pneumological Sciences, Catholic University of the Sacred Heart, Italy | |
| 演者: | 下川 宏明 | 国際医療福祉大学 |
| 石井 正将 | 熊本大学病院 医療情報経営企画部 | |
| 高橋 潤 | 東北大学病院 循環器内科 | |
| Colin Berry | School of Cardiovascular & Metabolic Health, College of Medical Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow, UK |
JCS Editorial Commettee Session英 語オンデマンド
CJAS
Circulation Journal Award Session
| 座長: | Kenichi Tsujita | Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Sciences, Kumamoto University, Japan |
|---|
<Clinical Investigation section>
| 演者: | Masataka Sato | Department of Cardiovascular Medicine, The University of Tokyo Hospital, Tokyo |
|---|---|---|
| Ichiro Mizushima | Department of Nephrology and Rheumatology, Kanazawa University Hospital, Kanazawa | |
| Hajime Yoshifuji | Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto | |
| Tadashi Murai | Cardiovascular Center, Yokosuka Kyosai Hospital, Kanagawa | |
| Ko Yamamoto | Department of Cardiology, Kokura Memorial Hospital, Fukuoka |
<Experimental Investigation section>
| 演者: | Hiroya Hayashi | Department of Cardiovascular Medicine, Osaka Metropolitan University Graduate School of Medicine, /Current Affiliation: Department of Cardiovascular Medicine, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka |
|---|
<Asian Award section>
| 演者: | Kuan-Yu Lai | Department of Internal Medicine, National Taiwan University Hospital, Taiwan |
|---|
日本循環器学会 委員会セッション(IT/DATABASE部会)日本語オンデマンド
J-ROAD
JROAD研究から創る循環器診療の未来
| 座長: | 福本 義弘 | 久留米大学医学部 内科学講座心臓・血管内科部門 |
|---|---|---|
| 的場 聖明 | 京都府立医科大学 大学院医学研究科 循環器内科 | |
| 演者: | 西 真宏 | 京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科 |
| 的場 哲哉 | 九州大学病院 循環器内科 | |
| 金岡 幸嗣朗 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 情報利用促進部 | |
| 坂東 泰子 | 三重大学大学院医学系研究科 基礎系講座分子生理学 | |
| 香坂 俊 | 慶応大学 循環器内科 |
日本循環器学会 委員会セッション(渉外委員会(国際))英 語オンデマンド
ESC-JCS
ESC-JCS Young Collaboration Session
座長兼演者:
| Vasiliki Tsampasian | Norwich Medical School, University of East Anglia, UK | |
| 藤野 剛雄 | 九州大学 重症心肺不全講座 |
| 演者: | Aleksandra Gasecka | Department of Cardiology, Medical University of Warsaw, Poland |
|---|---|---|
| 石田 秀和 | 大阪大学医学部附属病院 小児科 |